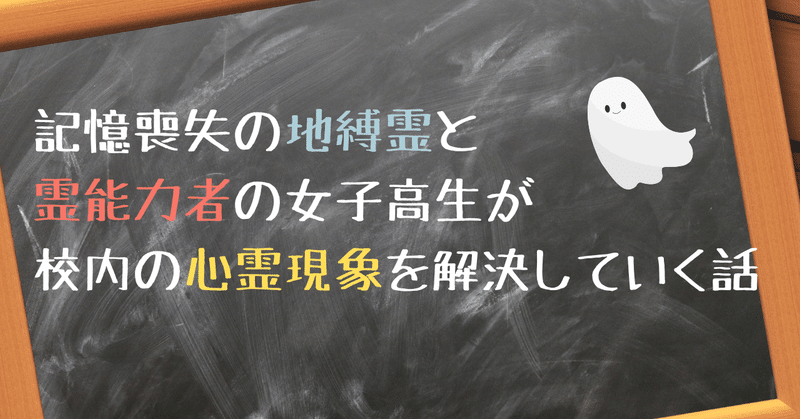
【長編小説】陽炎、稲妻、月の影 #29
第4話 天秤に掛けるもの――(10)
「なるほど、定期的にここの空気の澱みがえぐくなるのって、テストの所為だったんだ」
中庭での事件から二週間。
無事に期末テストも全日程が終了し、続々と結果が返ってきている。
アサカゲさんも例に漏れることなく、返ってきたテストの結果を確認済だが、何故か俺にはそれを教えてくれない。全教科出揃ったら教える、の一点張りである。とはいえ、彼女のクラスの時間割から鑑みるに、そろそろ全ての結果が出る頃ではあるはずだ。
アサカゲさんからテスト結果が告げられるのは、果たして今日か明日か。
そんな風にそわそわしながら、すっかり習慣と化した校内巡回をしていると、見覚えのある赤髪を発見した。そう、死神のイチギくんである。
せっかくだから少し話をしよう、という彼からの提案で、場所を屋上へと移し、死神と幽霊は、近況報告という名の世間話に花を咲かせていた。
最近のできごとの中でも、特に大事になった中庭の件を話したところ、イチギくんからは、先のようなさっぱりとした感想が返ってきたのだった。
「学校なんて大昔に行って以来だし、カリキュラムなんてすっかり抜け落ちてたわ。中間テストに期末テスト、いやあ、何年ぶりに聞いたかな、その単語。懐かしいねえ」
「死神って、学校に通うの?」
死者の魂が行き着く場所である冥界に、死神養成機関でもあるのだろうか。
そんなことを考えながら尋ねた俺に、イチギくんは、むっくんが考えてることを当ててあげようか、といたずらに微笑む。
「死神の学校なんてものはないよ。死神連中ってのは、元々は君らのような人間だったってだけ。そりゃあ俺だって、生前は学校に通ってたさ」
「……イチギくんは、ひとの心が読めるの?」
「むっくんの考えが表に出やすいだけだよ。目が見えていなくとも、気配でわかることは意外と多いんだぜ」
それで、とイチギくんは続ける。
「むっくん、なんか悩みごとでもあるんじゃないの? 顔色悪いぜ、たぶん。ああいや、死んでるんだから顔色なんて元から悪いか」
けらけらと笑いながら、イチギくんは的確に急所を突いてきた。
どうやら『気配でわかること』というのは、俺の想像を遥かに凌駕しているらしい。その辺りは、死者の魂を回収する死神ならではといったところか。
「悩みはあるけど、イチギくん、相談なんて乗ってくれるの?」
「なに言ってんのさ、俺は死者の魂を導く死神だぜ? むっくんが成仏できる手伝いになるなら、いくらでも相談に乗るさ」
放たれる言葉の全てが胡散臭く感じるようなことなんてあるんだなあ、と逆に感心しつつ、そろそろ解決策を練らなければならないと思っていたこともあり、俺はお言葉に甘えることにした。
「……アサカゲさんのことなんだけど」
そうして俺は、ここ一ヶ月ほどこね回していた悩みを、イチギくんに吐露した。
俺と一般生徒が話をしているとき、アサカゲさんに目配せをしても無視されてしまうこと。
その原因が、人間関係への諦観が起因しているようだが、どうにか状況を改善できないか、画策中であるということ。
それらをかいつまんで、イチギくんに説明した。
「むっくんは、ひーちゃんに人並みの交友関係を持ってほしいんだろうけどさ」
話を聞き終え、イチギくんは言う。
「無理じゃない?」
ばっさりと切り捨てる発言に、俺は肩を落とす。
それを知ってか知らずか、イチギくんは、だってさー、と言葉を続ける。
「元々クラスメイト側もひーちゃんを避ける傾向にあって、ひーちゃん自身も交流を避けてる。でもって、むっくんが間に入っても無理なら、絶望的だって」
それがどれだけ根深い問題なのかは、想像に難くない。
アサカゲさんは以前、地元は県外だけれど、八年前からこの近くにあるというお寺でお世話になってる、と言っていた。
八年前。
それなら当時のアサカゲさんは、六歳か七歳といったところだ。
この世のものではないものが視えることが原因で親元を離れ、学校では先生からでさえ『嘘を描いたら駄目』と言われてしまう始末。春先のユウキさんの件も、それ以降の校内の生徒の様子を見ていたら嫌でもわかってしまう、アサカゲさんへの忌避感。
中庭であれだけの拍手喝采を受けたと言っても、あのときの目撃者の大半は、あの辺りに自教室がある三年生だ。上級生からの露骨な忌避は減ったかもしれないが、一年生内の雰囲気までは、現状あまり変化が見られない。
「ううん、でも、あともうひと押しあれば、状況が変わる気もするんだよね。イチギくん、なにか良いアイディアはない?」
俺一人で考えを煮詰めていたところで、限界はある。ここで一度、全くの部外者からの意見を参考にさせてもらうつもりだったのだが。
「ないねえ」
と、ばっさり切り捨てられてしまった。
しかしイチギくんは、アイディアはないが、思うところはあるらしい。
というか、と話を続ける。
「むっくんの話を聞いた感じ、そのひと押しっていうのは、案外もう起きてるんじゃない? あんまりむっくんが気を揉む必要はないと思うけど」
「そうかなあ」
項垂れる俺に、イチギくんは皮肉げに笑って、言う。
「ひとつ忠告しておくぜ。本来、死人が生きてる人間にしてやれることなんて、ないはずだろ? 関わりを一切持つなとは言わないけど、干渉するのもほどほどにしておきなよ。じゃないと、痛い目に遭うだろうから」
「もちろん、それはわかってるよ」
死者と生者。
幽霊と人間。
世の理はわかっている。
それでもアサカゲさんの幸せを願うのは、間違っているのだろうか。
「……ま、死神から言えるのは、それくらいかな」
そう言うと、イチギくんは軽い足取りでフェンスを跨いだ。
「もう行くの?」
「うん。誰かが死んだ気配がしたから、仕事しに行かないと。またね、むっくん」
そうしてイチギくんは飛ぶように、或いは落ちるようにして、視界から姿を消した。なんとなく彼の行き先を目で追うが、あんなに目立つ赤髪も、あっという間に見えなくなる。
「……早く、思い出さなきゃなあ」
イチギくんの言うことは理解できる。
領分を間違ってはいけない。
俺はとうの昔に死んだ人間であり、生きている人間にどれだけ肩入れしたところで、その無念が晴れることはない。あくまでも俺が優先すべきは、生前の記憶を取り戻して成仏することであって、霊能力者への協力ではないのである。
わかっている。
頭では理解しているのだ。
しかし、中庭の一件で脳裏に過ぎった会話の断片も、結局あれきりで、前後の内容を全く思い出せないままでいる。
あの約束を果たせなかったことが、俺をこの世に留めている心残りなのだろうか。
であれば、果たせなかった約束を思い出したとして、成仏できるのだろうか。
不安がないわけではない。
これこそ、いの一番にイチギくんに相談すべきことだったのだろう。けれど、どうしてか俺にはそれができなかった。あの約束を口外すること自体を禁じられていたのかと思うほど、不思議と他人に言う気になれない。それだけ大切なもののはずなのに、あっさり忘れてしまっている自分が不甲斐なくて仕方なくなる。
そんな俺の考えを掻き消さんばかりに、一陣の風が屋上に吹きつけた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
