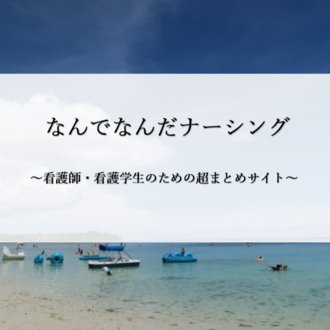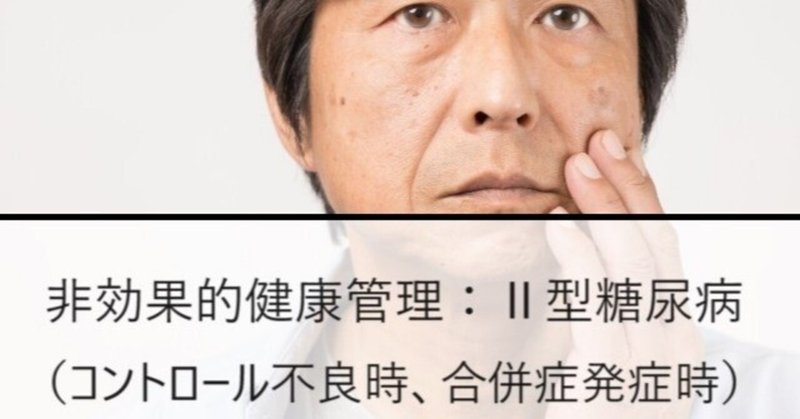
もっと楽々コピペで立案!非効果的健康管理:Ⅱ型糖尿病(コントロール不良時、合併症発症時)の看護計画
2024.6.2更新
非効果的健康管理:Ⅱ型糖尿病(コントロール不良時、合併症発症時)の看護計画
<定義>
非効果的健康管理とは、疾患によって医療処置・症状の管理・身体機能の維持などを必要とする患者やその家族が必要な処置やケアを行う事が困難あるいは不十分であり、望む生活ができない状態を言う。
<「非効果的健康維持」と「非効的健康管理」の使い方の違い>
「非効果的健康維持」は喫煙、運動不足や過食・偏食などの不健康な生活習慣を変えたいと願っている個人に用いられ、発病を予防するための1次予防の場合に使用する。
「非効的健康管理」は疾患や健康管理に関する教育が必要な患者に使用する。
<糖尿病の分類>
Ⅰ型糖尿病:主に自己免疫を基礎にした膵臓の膵β細胞の破壊によってインスリンが欠乏して生じる糖尿病。(インスリンの分泌不足)
Ⅱ型糖尿病:インスリンの分泌能低下や抵抗性の増大に加えて、不摂生な食事・運動不足・肥満などの環境因子によるインスリン抵抗性の増大によりイスリンの作用不足が生じる糖尿病。(インスリンの分泌不足、インスリン抵抗性の増大,、インスリンの作用不足)
その他の特定の機序、疾患によるもの:膵β細胞の遺伝子異常、インスリン作用の伝達機構にかかわる遺伝子異常や血糖を上昇させるホルモンの増加を引き起こす二次性糖尿病(疾患例:甲状腺機能亢進症、クッシング症候群、褐色細胞腫、膵炎、腫瘍、慢性肝炎、肝硬変、ステロイド、感染症など)。
妊娠糖尿病:妊娠中にはじめて発見または発症した糖尿病に至っていない糖代謝異常。
看護計画
疾患:
既往歴:
治療内容:
目標
問題点に気づき対処できる
自己管理に必要な知識や技術を習得できる
必要な支援を受けられる
O-P
1.検査データ
-耐糖能検査:75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)
-血液検査:血糖値、HbA1c、グルコアルブミン(GA)、インスリン、Cペプチド、1.5アンヒドログルシトール(1.5AG)、ケトン体、LDL-C、TG、HDL-C
-尿検査:尿糖、尿中アルブミン、尿中Ⅳ型コラーゲン、尿中ケトン、尿中Cベプチド
-腎機能検査
-眼底検査
-胸部レントゲン
-心電図
2.血糖値の変動
3.ADL・IADL
4.認知力、理解力
5.バイタルサイン
6.Ⅱ型糖尿病(コントロール不良時、合併症発症時)の症状
-高血糖症状
・口喝
・多飲
・多尿
・頻尿
・空腹感
・体重減少
・易疲労感
・イライラ感
・抑うつ感
・不眠
7.急性合併症の有無
-高血糖による脱水
-ケトーシス
・悪心、嘔吐
・腹痛
-ケトアシドーシス
・呼吸促拍
・意識障害
-高血糖高浸透圧昏睡(非ケトン性高浸透圧性昏睡)
・横紋筋融解
・精神神経症状
・腎不全
・血栓症
・脳浮腫
8.慢性合併症の有無(細小血管症)
-糖尿病網膜症
-糖尿病白内障
-糖尿病腎症
-神経障害
・末梢神経障害:下肢の痺れ、冷え、異常知覚、知覚低下による外傷(外傷、熱傷、皮膚潰瘍、靴擦れ)
・脳神経の単麻痺:表情筋の麻痺、眼球運動の障害
・自律神経障害:消化器の運動障害や消化液分泌障害に伴う食欲不振・便秘・下痢、膀胱直腸障害、起立性低血圧、発汗の減少に伴う皮膚の乾燥
9.慢性合併症の有無(動脈硬化症、大血管障害)
-脳梗塞
-狭心症
-心筋梗塞(末梢神経障害の知覚低下による無痛性心筋梗塞)
-下肢動脈硬化症(間欠性跛行)
-免疫能低下
・気道感染
・尿路感染
・皮膚感染
10.慢性合併症が及ぼしているADL・IADLへの影響
11.食事摂取量、内容、時間
12.間食の有無
13.嗜好、偏食の有無
14.水分摂取量
15.水分出納バランス
-IN(輸液量、水分摂取量)
-OUT(尿量、排液量)
16.体重、体重の変化(20歳の時の体重、現在までの体重の経過)
17.排尿状況、尿の性状
18.排便状況
19.安静度
20.活動量、運動習慣
21.睡眠状況
22.治療内容
-食事療法
-運動療法
-生活習慣改善に向けた糖尿病に対する教育
-薬物療法
・インスリン分泌促進薬:( )
・インスリン抵抗性改善薬:( )
・食後高血糖改善薬:( )
-GLP-1受容体作動薬
・使用しているGLP-1受容体作動薬:
・注射をしている部位、皮膚の状況
・悪心、嘔吐、便秘、便秘、下痢などの消化管障害の有無
-インスリン療法
・使用しているインスリン製剤:
・インスリン注射をしている部位、皮膚の状況
・低血糖症状の有無
・無自覚性低血糖の有無
・乳酸アシドーシスの有無(ビグアナイド系薬を飲んでいる場合)
23.服薬状況
24.服薬管理状況
25.疾患について誰にどの様に説明されているか
26.疾患、治療に対する受け止め方
27.増悪因子についての理解(不摂生な食事、運動不足、肥満、ストレス、喫煙、服薬管理ができないなど)
28.不安に思っていること
29.ストレスの有無、対処方法
30.セルフマネジメントの内容
-セルフマネジメントに対する理解度
-患者が行っている行動が正しいか
31.指導内容に対しての反応、理解
-食事療法( )
-運動療法( )
-薬物療法( )
32.生活状況
-1日の過ごし方
-食生活(回数、量、内容、時間など)
-喫煙の有無、程度
-飲酒の有無、程度
-自宅・地域の環境
-職業
-経済状況
33.家族のサポートの有無、状況
34.家族の知識、理解
35.ソーシャルサポート(社会的支援)の活用状況
-情緒的サポート:共感や愛情の提供
-道具的サポート:形のある物やサービスの提供
-情報的サポート:問題の解決に必要なアドバイスや情報の提供
-評価的サポート:肯定的な評価の提供
T-P
1.患者が糖尿病をどの様に認識しているか確認する
2.患者と一緒にこれまでの生活における問題点と今後改善できる具体的な行動について話し合う
※コピペでかんたん立案!非効果的健康維持の看護計画を参照する
3.水分出納バランスを確認し管理する
-水分管理を行う
・水分制限がある場合、水分量を守れる様に管理する
・水分制限がある場合、氷や含嗽などにより口喝を和らげる工夫を取り入れる
・水分が不足している場合は水分摂取を促す(介助する)
-排尿量を確認する
・水分出納バランスシートにチェックしてもらう(介助する)
4.すぐに排尿できる(排尿しやすい)様に環境整備する
5.安楽に過ごせる様に環境整備する
6.疲労感が強い場合は安静を促す
7.疲労感に応じて必要な動作を介助する
-できる事は自身で行う様に声掛けする
-できない事は介助する
8.患者の思いに寄り添い、尊重した態度で接する
9.患者の思い、不安に思っている事を傾聴する
10.患者の発言、表情や行動で気になった事は理由を確認する
11.イライラ感や抑うつ感が強い場合、専門科の受診を検討する(医師へ相談する)
12.医療者間で情報共有し、統一した態度で関わる
13.同じような体験を持つ患者と話ができる様に働きかける(ピアサポート)
14.不眠に対するケアを行う
※コピペでかんたん立案!不眠の看護計画を参照する
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?