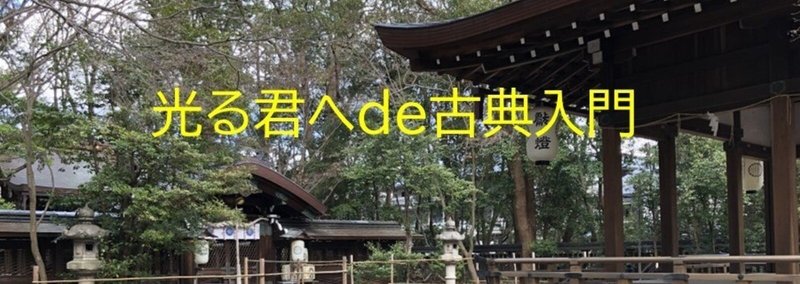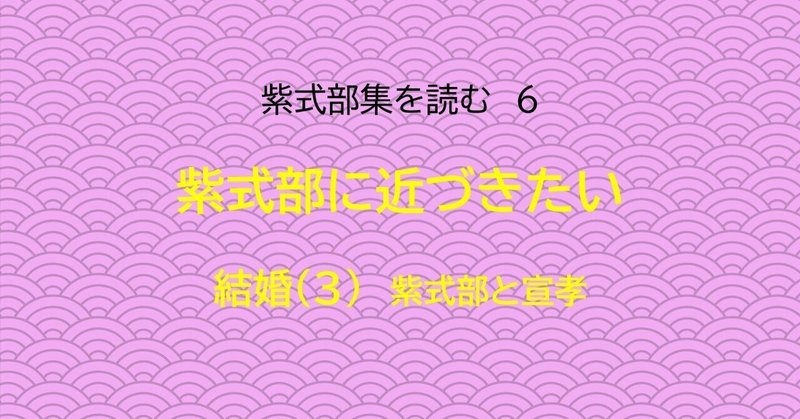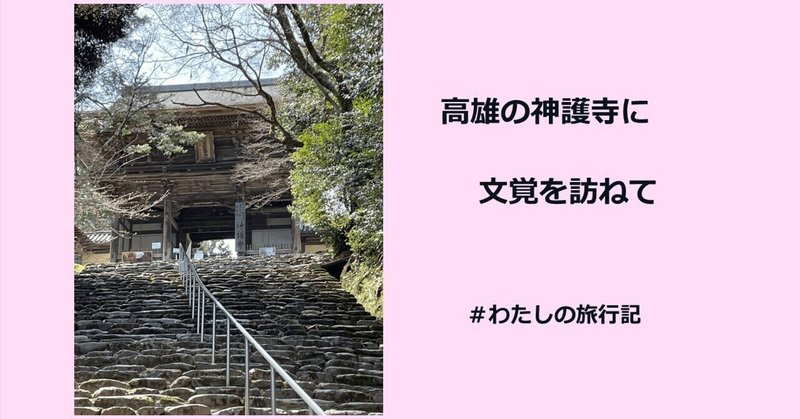のざわちかこ/古典を未来に
マガジン一覧
光る君へ de 古典入門
NHK大河ドラマ「光る君へ」で平安文学を好きになる人が増えてほしいなあ
紫式部に近づきたい
いろいろな方向から紫式部と『源氏物語』に近づいてみます。ぜひ、ご一緒に。
紫式部に近づきたい~紫式部集をよむ
紫式部集を読みやすく現代語訳し、歌にまつわるエピソードを紹介します。紫式部が読んだ歌にふれることで、紫式部に直に近づいてみましょう。
列車とバスで気ままな旅
列車とバスで旅をするのが好き、気ままなひとり旅が好き、突然古典について語り始める、わたしの旅の記録です。
『平家物語』は生きている
『平家物語』は群像劇。そこに描かれてるたくさんの人物からあふれだすエネルギー、感情をとりあげていきます。『平家物語』を原文で語る、俳優金子あいの仕事を応援しています。