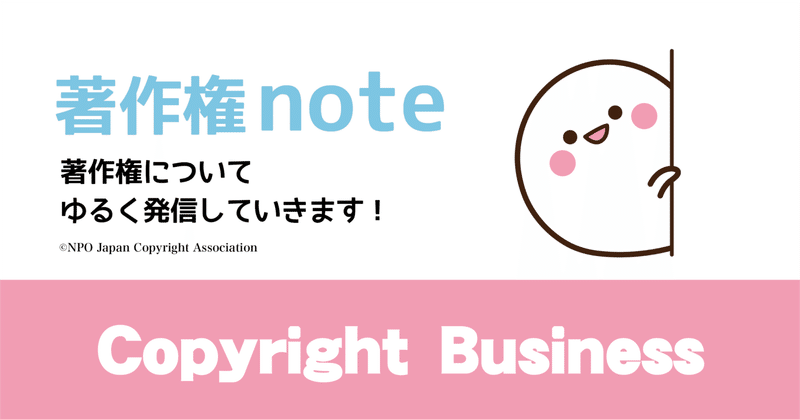
54.他人の創作物を自由に使ってみよう!
インターネット上で無料・無断で使うための著作権活用法
前回でもいいましたが、引用が一番該当するのは文章を中心とした活字関係です。しかし、ホームページ上となると少しむずかしくなります。
たとえば、絵や写真はどうなのでしょう。ホームページと一般印刷媒体(書籍や新聞、雑誌)の大きな違いは、一般印刷媒体は著作権や著作者人格権の複製物が基本となっているが、インターネット等のホームページは著作物の有線送信に当たるため、著作権の複製と有線送信の二つの規定があることを考えなければなりません。
まず、SNS投稿、ブログ、ホームページ等作成のための複製は私的利用の範囲には一切含まれない。つまり、個人的な趣味ということにはなりません。「個人的」とは私的という意味であり、ごく少数といわれる家庭内の使用といわれていますが、ネット上に掲載するということは不特定多数の人に情報を与えると考えられます。したがって、営利目的でなく非営利であっても著作権者の許諾が必要となります。
これは、著作物の有線送信について著作権法第三十条以下には規定がないため必ず許諾が必要となるということです。
では、絵や写真を引用するというときはどのような条件を満たせばよいのでしょうか。
引用という以上、
第一に引用の目的が社会慣行に適していなければなりません。
批評や研究の名を借りた盗用や借用ではなりません。つまり、正当な批評であり、研究であると社会的に見ても「引用」が必要だと考えられるような場合でなければならず、批評、研究の名を借りた鑑賞目的のものや、その物を売るためのものというのは一切認められません。
第二にその引用の範囲は「正当な範囲」でなければならない。
それは、「引用」の部分があくまでも従でなければならず、主は批評、研究でなければならないということです。また、絵画や写真はその一部分を切って利用すれば著作者人格権の中の同一性保持権の侵害行為になります。
では、その引用部分に関する主従関係の判断はどうなのでしょう。たとえば、主たる文章は自らが制作し、ネット上等の画像に小さくその写真や絵を掲載する。しかし極めて有名な作品や画家のものは、たとえどう扱ってもそれが主たるものになってしまうおそれもあります。このようにたとえ引用と思っていても、客観的に引用されない事がほとんどといわれているため著名な絵画の引用は要注意といえます。
引用のための出所明示の方法
(A)書物からの引用の場合(学術論文の出所明示)
①著者の姓名 ②著作の表題および副題 ③出版社名 ④出版年 ⑤頁
(B)雑誌論文からの引用の場合
①著者の姓名 ②論文もしくは章の表題 ③雑誌の表題 ④巻及び号数 ⑤年月 ⑥頁
出所明示は著作権法では義務とされ、これを怠ると三十万円以下の罰金(著作権法第三十二条)。引用にはこの著作権法上無断でできる「適法引用」と、他の著作物の抄録、要約、利用まで含めていわれる語向上の広義としての「引用」もあり、この「適法引用」の出所明示は法的に義務条件となっています。
この適法引用の表記は、文節の直後か、後か、章節の後。よく見かける「参考文献」などは、章の後か、巻末。許諾を受けた著作物は、扉裏ページか、巻末。日本では巻末が多くみられます。
(C)孫引き引用の場合(二次文献の引用)
学術論文の世界では原則として一次文献にあたるべきといわれていますが、すべての必要文献が一次文献にあるわけがなく、信頼できる二次文献資料があればそれをもとに引用できる場合もあります。その場合は、引用の個所の直後に一次文献の出所明示をして、そこに注の表記をします。そして、文節の後か章節の後の注に二次文献を明記するのが一般的です。
「実際に自分で裁判をやってみればすぐにわかることだが、裁判というものはとにかく長い。簡単な内容の裁判ならば決着も早いのだが、早いといっても一年はかかる。早い裁判というものはどのようなものかと言うと、それはたとえば、養親と養子の親子が、離縁届けを出して親子関係を解消したのに、後になってそれを争う場合である。……」
『裁判の秘密』山口宏・副島隆彦著、宝島社文庫 1999年5月10日 第1刷
これは一次文献の例としての引用個所。このように「 」をつけることによって、主たる文章と引用の部分を明確に区別し出所を明示します。また、引用部分の前後を一行ずつ空けるか、文字の大きさや書体を変えたりする方法もあります。このように区別してわかるようにしなければなりません。
そして最後に著作者人格権の同一性保持権を守る。つまり、原文、原画のままで勝手に手を加えたり、部分的に自分に都合の良い部分だけ引用し、他社に誤解を与えることもしてはなりません。
本章のおわりに
合法的に著作物を活用する。無料で無断で著作権を利用する。これらは著作権法第三十条の引用の定義を学ぶことで様々な分野で堂々と活用することができる。
著作権侵害を無用に恐れたり、他の著作物に触れることに不安を抱いたり、自分の著作物を他に無断で利用されてしまったと騒いだり、常に消極的にこの著作権問題を考えるのではなく、これからは誰もがすべての人が自由に簡単に創作者になる時代。
むしろ積極的に考え、自らの仕事や生活の中に取り入れ、戦略的に活用する時代でもある。
なぜならば、著作権は特定の専門家と呼ばれる人たちの特別な権利ではなく、素人であっても専門家でなくとも、技術や才能がなくとも、決して上手でなく下手であっても、新しいわたしたちの財産権となるものだから。
学ぶ価値のあるものだから。
生きていく上で必要性のあるものだから。
知る、学ぶ。
すると、わたしたちは誰もが身の回りにこんなにも自分の財産があったことに気づいてくる。知的財産権の中のこの著作権は、誰もが簡単にビジネス化、財産化できる権利ともいえる。
青い鳥の物語ではないが、わたしたちの身の回りに儲けという財産が深く眠っているのかもしれない。著作権という怪物は深く深くわたしたちの内部を侵食しはじめてきたようです。

※特非)著作権協会の電子書籍のご案内「~無料・無断で使用できる著作権活用法④~「無断OK!著作権」全4巻好評発売中!下記↓にて検索してください。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
