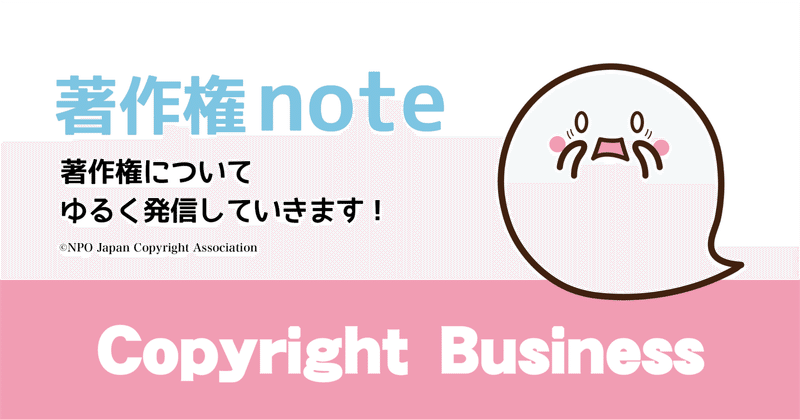
61.無料・無断・自由利用OK!
1.他人のモノを利用して怯える人たち
「著作権」「著作権侵害」と聞くとびくっとする人たちがいます。
権利のことは知らなくとも、人のモノを勝手に利用しているわけですから、結果びくびくしてしまうのでしょうね。
私たちのこのネット上の世界は知らず知らずして加害者となったり、被害者となる恐れのある世界です。
フェイスブック、インスタグラム、ツィッター等のSNS投稿などはまさに著作権侵害、肖像権侵害の宝庫といえるかもしれません。
現在私たちが利用しているnote記事の世界もそのような侵害行為が目立ちます。
ここで大切なことをいいます。
すべての著作物は許可がなければ著作権侵害行為となります。
しかし、著作権法の定義にあてはめた「引用の定義の範囲」であればだれもが自由に利用できます
。
さらに、安心して他人の著作物を利用したい場合は、「著作者」「著作権者」から使用許諾、つまり許可をいただければさらに自由度を増すことができます。
直接、著作者からイラストや写真を借りると費用が発生してしまう…。もちろん、それは当たり前の当然のこと。世の中にはなんでも無料で使えるとは限りません。
フリー素材、無料素材だって条件があります。
あくまでも「私的使用の範囲」であり、その素材を使い勝手に商品化して販売することはできません。
しかし、反対に考えてみましょう。勝手には使用して販売はできませんが、「許可」があればできるということです。
世の中すべての著作物は有料ではありません。大手の有名なキャラクターだってちゃんと許可をいただき条件を飲めば販売も可能ですし、販売目的でなくて非営利の場合は無償で貸し出してくれる大手企業やイラストレーター、デザイナー、写真家などもたくさんいます。
問題はその著作物の使用、利用の仕方にあります。
なぜ、恐れてしまうのか?
なぜ、怖いと思うのか?
それは勝手に許可なく利用または使用するからです。
ですからきちんと著作権法の定義に沿って利用することが一番安全なのです。
2.無料・無断・自由利用OK!
著作権というのは、著作者・著作権者というように特定の者の権利です。
よく、著作権は、独占的・排他的権利などといいますが、著作物の利用には必ず著作権者の「許諾」が必要になります。しかし、表現というものの公共性によって、無料・無断・無許可で著作物を利用してもよい場合もあり、自由利用OKの場合があります。それが著作権切れの著作物の活用です。
たとえば有名な美術家のピカソ(1973年没)とゴッホ(1890年没)の作品は、この著作権切れとの関係はどうなっているのでしょう。
それぞれに「没年」を記載しているように、ピカソの絵については、ピカソが亡くなってから70年以上経過していないため、たとえ亡くなっていようが勝手に使用はできないことがわかります。もちろんピカソ亡き後には、ピカソの相続人の代表者からの許諾が必要となります(現在は、フランスのピカソ絵画の著作権管理者はクロード・リュイズ・ピカソ)。
では、ゴッホの場合はどうでしょう。
著作権の保護期間は、著作者の死後70年間となっているため、この保護期間の起算は、著作者の死亡した年の翌年から始まり、これによれば、1960年の末日をもって、ゴッホの絵画の著作権は消滅していることがわかります。
ただし、サンフランシスコ平和条約に調印した旧連合国国民の著作物が日本国内で利用されるときには「戦時期間」(太平洋戦争が始まった日から、それぞれの国が平和条約を批准した日までの期間)が加算されます。これは日本は敗戦国として背負った第二次世界大戦の賠償ともいえるもので、たとえばオランダの場合は「戦時期間」は3844日(約10年)となり、この戦時期間を加えると、ゴッホの絵画の著作権保護期間の終了時は、1971年の6月頃とされています。
したがって、ゴッホの絵画の場合は、もうすでに著作権が消滅しているため、一切の許諾はいらず、自由に利用することができます。
さらに、世界中を調べればまだまだ著作権の切れた著作物は膨大に存在しています。たとえばゴッホ以外でも、ミレー、ゴーギャン、セザンヌ、ルノアールなども一切の許諾はいらず自由に利用できます。
フランス画家で注意しなければならないのは、ピカソを含め、ルオー、シャガール、ボナール、バン・ドンゲン、ブラマンク、クレー、ビュッフェ等はかなり使用条件が厳しいとされています。
さて、今日から百年前(1905年)。200年前(1805年)。もちろん死後70年ですが、1905年前に遡ればのぼるほど、安全な、自由に利用できる著作物と考えられています。
3.海外の著作物利用の注意点
著作権法第六条一号は、「日本国民の著作物についで、著作者の国籍に問わず、日本で発行された著作物(同条二号)、そして条約によって保護しなければならない海外の著作物(同条三号)」です。つまり、条約もなく、日本で最初に発行されていない著作物は保護されない、保護しなくてもよいということです。
この保護をしなくて済む国はかなり少なくなりましたが、中近東、南太平洋諸国などに多くあります。ヴェトナムなどはどの条件にも加盟していません。朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)は最近加盟しています。
ではどんな国際条約があるのかといえば、
一、ベルヌ条約
二、万国著作権条約
三、WTO協定TRIPS協定
四、WIPO著作権条約
この四つの条約は日本をはじめ先進諸国は、そのすべてに加入しています。
(1) ベルヌ条約
この条約(正式には「文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」という)は、フランスの文豪ビクトル・ユゴー(1802〜一1855)を名誉会長とする著作権法学会(ALAI)の提唱により始められた著作権保護に係る国際同盟の組織運動を背景として策定されたものです。具体的には、1886年9月9日、スイスのベルヌにヨーロッパ諸国(10か国)が参加して開催された国際会議において創設されました。ベルヌ創設条約の特色は、①内国民待遇の原則を確立したこと、②各同盟国に対し、国内法で最小限度に認むべき著作権の範囲を規定したことにあります。わが国は、1899(明治32)年3月4日に著作権法(明治32年法39)を公布し、同4月18日この条約に加入しています。
ベルヌ条約の最大の特徴は、1908年のベルリン改正条約で著作物の保護に関し、登録とか納本などの手続きを必要としないとする無方式主義を条約上の原則とした点にあります。ベルヌ条約には、1999年8月末現在、140か国が締結しています。
(2) 万国著作権条約
この条約(Universal Copyright Convention=UCC)は、著作権保護の条件として、登録・納入・著作権表示などの方式を要求していたパン・アメリカ条約に加入する南北両アメリカの諸国と、無方式で著作権を保護するベルヌ同盟条約に加入するヨーロッパ・アジア・アフリカの諸国と結ぶ懸橋条約として、1952(昭和27)年9月6日にジュネーブで成立しました。UCCは、ユネスコによって準備・所管されているため、ユネスコ条約とも称されています。この条約により、無方式国で最初に発行された著作物の複製物に、「マルシー表示」(Copyrightの頭文字である「©」の記号、「著作権者名」および「最初の発行年」を一体として表示すること)をしてあれば、方式国でも無方式国の国民の著作物が保護されることになりました。(万国3条1項)。
UCCには、1999年8月末現在、97か国が締結しています。わが国については1956(昭和31)年4月28日に発効していますが、無方式主義を採用しているので著作権法制上、マルシー表示には、直接の法的効果は定められていません。ベルヌ条約との関係については、両条約締結国相互間では、ベルヌ条約が優先的に適用されます。(万国17条)
(3) WIPOの設立条約
著作権を扱うベルヌ条約と工業所有権を扱うパリ条約の両条約の管理・機構上の問題を統一的に処理し、また全世界に知的所有権の保護を促進し、改善することを目的として(WIPO設立条約三条)、世界知的所有権機関(World Intellectual Proqerty Organization=WIPO)を設立する条約が成立し、1970年に発効されました。WIPO設立条約には1999年9月末現在、171か国が締結しています。わが国については1975(昭和50)年4月20日に発効しています。なおWIPOは、1974(昭和49)年に国連の一四番目の専門機関となりました。
(4) TRIPS協定
1990年代の国際社会における貿易のルールを定めるために設けられたGATT(関
税と貿易に関する一般協定)のウルグアイ・ラウンドは、一九八六年九月から開始され、知的財産権やサービスを含む多方面の貿易の分野で交渉が進められた結果、当初の予定に後れたが、1994年四月、モロッコのマラケシュで開催された閣僚会議において、世界貿易(World Trabe Organization=WTO)を設立するマラケシュ協定が成立するに至った。この協定は、本文のほかに四つの附属書から成っており、その「附属書一C」には「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights=TRIPS協定)が含まれています。
TRIPS協定のうち著作権関係規定は、①ベルヌ条約の規定する保護内容の導守、②コンピュータ・プログラムおよびデータ・ベースの著作権による保護、③コンピュータ・プログラム、映画およびレコードへの貸与権の付与、④実演家、レコード制作者および放送事業者の保護等を定めている。本協定は1995年1月1日に発効し、1999年8月末現在の受諸国数は134か国・地域である。わが国については、1996年1月1日に発効しています。
(5) WIPO新著作権関係条約
近年の情報化の進展による著作権を取り巻く状況の変化は、「デジタル化」から「ネットワーク化」の進展によってもたらされています。ここに、WIPOにおいても、1996年12月、「インターネット著作権条約」と称すべき新著作権条約として、著作者の権利を保護するため「WIPO著作権条約」が、実演家とレコード製作者の権利を保護するため「WIPO実演家・レコード条約」とともに、外交会議で採択されています。この二つの新条約には諸種の規定が盛り込まれていますが、最も重要なことは、著作物、実演、レコードをインターネットなどを用いた「インタラクティブ送信」によって公衆に伝達することについて、新しい権利を規定したことです。この両条約は、1999年8月末発効です。

特非)著作権協会です。みなさまいつも読んでくれて感謝します。
著作権の法律とか、専門用語ってつまらないですね。
ほとんどの人は条文や専門内容を見るだけで嫌になってしまいます。私もそうでした。
でもね、私たちの生活や仕事はすべてこの法律の中で生きているわけですから最低限度の知識や理論は必要になります。
私たち日本人はこの「防衛本能」が他国と比べると低い文化だといわれていますが、それだけ日本は平和な証拠でもありますね。
しかし、日夜問題やトラブル、事件は後を絶ちませんし、いつまでも「対岸の火」のようにただ眺めているだけではいつの間にか、加害者となったり、被害者になる恐れがあるからです。
ですから、すべてを暗記する必要はありませんが、ネットを利用する人たちnote記事やホームページ、ブログやSNS投稿をする人たちはいつでも犯罪に巻き込まれる恐れもありますし、加害者になる場合もあるからです。
ですから、注意することには越したことはありませんね。
本日もここまで、おつきあい感謝いたします。
※特非)著作権協会おすすめ電子書籍〈~著作権・肖像権に気をつけろ!~「著作権Q&A」①〉全4巻まで好評発売中!note記事には書ききれない物語満載。お時間がありましたらお読みくださいね。下記↓検索で目次内容等を検索して見てください。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
