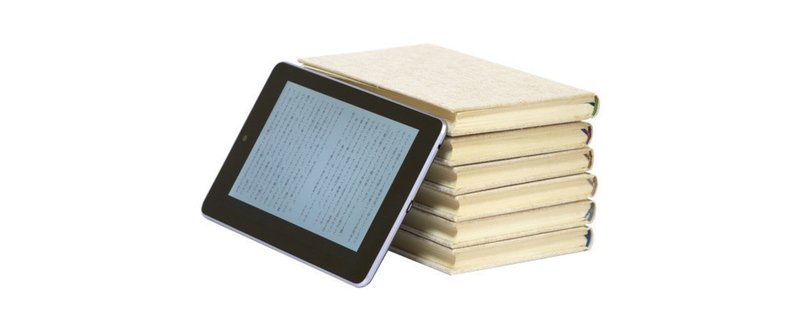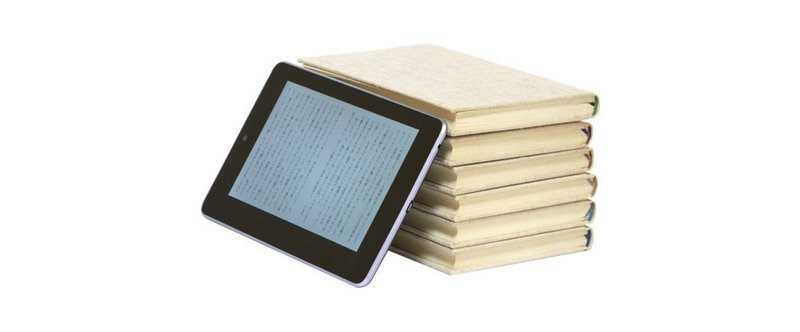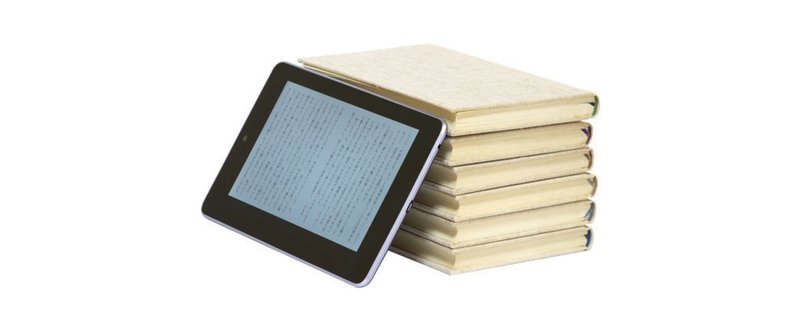- 運営しているクリエイター
2014年11月の記事一覧
成果主義がもたらすモラルハザードというもの、それに引きずられた日本の姿。過去から学ばねばならないことはまだまだあるのです──NHK取材班『日本人はなぜ戦争へと向かったのか』
「アメリカによる「愚行」であったイラク戦争。イラク攻撃にいたるブッシュ政権の意思決定過程をしらべると、それは真珠湾攻撃に至る日本の意思決定プロセスと非常によく似ていることがわかります。(略)どちらも理性ある人間と見られるメンバーがとんでもなく不合理な決定をしています。(略)異議を唱えるものには、「愛国心が欠落している」と糾弾する。「ちょっと待て。これは無茶苦茶だ」などといえばその人たちは排除さ
美しい日本はどこにある? 私たちの大きな勘違いを気づかせてくれる、ユーモアとジョークあふれる日本論なのです──アレックス・カー『ニッポン景観論』
この本は在日アメリカ人の日本文化研究者が今の日本にどのような素晴らしい景観があるのかを探索したレポート……ではありません! 私たちの景観・環境・風景がいかに浸食され(何によって?)、破壊され(誰によって?)放置され(私たちが?)続けているかを穏やかな、けれども怒りをこめたレポートです。アレックスさんのこの告発(といってもいいと思うのですが)にどのように応えればいいのか真摯に考える必要があるの
靖国を考えるなら、少なくともここに提起された問いに正面から答える必要があるのではないでしょうか──内田雅敏『靖国参拝の何が問題か』
「本来、追悼、慰霊は、故人の親族、故人と面識のあった友人たちなど、故人をよく知る者のみがなしうる、すぐれて個人的な営みである」
といった至極まっとうなことが、こと靖国神社が間に入るとひどく奇妙なことになる。それは戦死者だからなのでしょうか。
毎年必ず問題になる首相や閣僚の靖国神社参拝というものをどう考えればいいのか、この本はそのよい参考になるものだと思います。内田さんは、はっきりと首相や
音楽の魅力を追い、力一杯戦後を生きてきた湯川さんの心の底には音楽を超えた強い信念があったのです──和田靜香『音楽に恋をして♪ 評伝★湯川れい子
湯川れい子さんといえば、ある年代以上の人にとっては中村とうようさん、福田一郎さん、星加ルミ子さん、木崎義二さんと並んで洋楽(ロックというよりこういった方が適していると思います)を日本に根付かせた音楽評論家(音楽水先案内人?)の一人として思い浮かべるのではないかと思います。
また、ある年代以降は、売れっ子作詞家、音楽番組の審査員、近年では原発問題などに積極的に発言している人ということが、まず
小選挙区制がもたらしたものは政治への無関心が生んだアノミー状態と、あるいはその反面のポピュリズムへの傾斜ではないでしょうか──浅川博忠『小選挙区制は日本を滅ぼす 「失われた二十年」の政治抗争』
故・伊藤昌也さん(池田勇人元首相の首席秘書官をつとめた後、宏池会事務局長を経て政治評論家)の著書に『自民党戦国史』(現在は筑摩書房より刊行)というものがあります。佐藤栄作政権末期から田中角栄さん、三木武夫さん、福田赳夫さん、大平正芳さん、鈴木善幸さん、中曽根康弘さんの歴代各首相が政権を獲得するまでの権力闘争を描いた名著です。
この『小選挙区制は日本を滅ぼす』はその続編とも読めるものだと思い
自分たちの身体を縛っている規範から解放されて、体感をとりもどそう。実感の充実こそが自由をとりもどす要なのです──尹雄大『体の知性を取り戻す』
私たちの体はさまざまな観念や規範に縛られ、体が本来持っている自由さを失っているのではないか。本来、知性に結びつくものだったはずの、この体はどこへいってしまったのか……。尹さんは武術等の体験を通して、いかにその体を取り戻すかという試みを追っていきます。
尹さんは私たちが小さいときに「正しい姿勢」という名の下に、いかに体を見失ってきたかを詳細にわたって解き明かしています。「きちんと、正しく」
「しすぎ」「やりすぎ」をすることなく、もっともっとと追及をするのではなく、無理をせず、自分がある(いる)ということが肝心なのです──辻信一『 「しないこと」リストのすすめ』
忙しさに追われて自分を見失ったり、自分の時間がなくなっていく思いをしている人は多いのではないでしょうか。もちろん好きこのんで忙しくしているわけではないと思います。でも、時には立ち止まってその忙しさの正体を考えてみることも必要なのではないでしょうか。辻さんはこの本を通じてこのことをいっているのではないかと思います。
たとえば、私たちにおなじみの〈to do リスト〉ですが、それに追われる日
音楽の力は音を包んでいるジャケットにもあったことを思い出させてくれます──高地明『ブルース・ レコード・ジャケット』
「When music is over, it’s gone in the air. You can never capture it again.」
ジャズマン(サックス、フルート、クラリネット奏者)のエリック・ドルフィーが、死の直前に吹き込んだライブアルバム『ラスト・デイト』で演奏後に囁いた言葉です。
アルバム(CD)に収められたのですから、ドルフィーのいうように音楽が宙に消えたわけ
「無名にひとしい人たちへの紙碑」それは私たちが「忘れてはならない日本人」の姿なのです──宮本常一『忘れられた日本人』|レビュアー=野中幸宏
「土佐源氏」という章がありますが、これは源平合戦の源氏ではなく、源氏物語の源氏です。といっても「いとやむことなききはにはあらぬか」どころではなく、まったく無名の馬喰の激しいといってもいいような女性遍歴と放浪生活のさまがその本人から聞き取られているものです。
この本は日本中を旅してこの「土佐源氏」ように聞き取りを行ってきた民俗学者、宮本常一さんの代表作です。初めて発表されたのは1960年、もは
悲惨な現在に耐えられなくなったときに過去への旅が始まるのでしょうか。けれど過去をかえることで未来に幸福が待っているのでしょうか──横山光輝『時の行者』
タイムトラベルの物語は、小説ではH・G・ウェルズの『タイムマシン』を始め、映画では『バック・トゥー・ザ・フューチャー』 『ターミネーター』など私たちにおなじみのものが多いと思います。未来から来た人間が持っている知識(それは私たちにおなじみのものであったりするのですが)に驚く過去の人たちの姿、文化や生活などのギャップがもたらすユーモア(時にサスペンス)などがタイムトラベルものの魅力の典型だと思
書物はどのようにして私たちのもとへ届くのでしょうか。そして書物には歴史の影が刻まれていることもあるのです──和田敦彦『読書の歴史を問う』
読書というと、何を読むか、どう読むかということについて語られることが多いと思いますが、この本はそのような読書論とは一線を画すものです。和田さんは「読書のプロセス」を「書物が移動して読者にたどりつくプロセス」と「書物を読者が理解するプロセス」のふたつにわけ分析しています。
「書物が移動して読者にたどりつくプロセス」は普通、流通や教育の問題として読書とは別次元のものとして考えがちです。けれど確
「妙に行儀がいい」記者たちがそろっている取材現場、なぜそのようなことになったのか。ジャーナリズムは今どんな姿をしているのか!?──大鹿靖明他『ジャーナリズムの現場から』
「記者会見場(東日本大震災とそれに続く東電の福島第一原発爆発事故の会見)は、まるでそろばん教室のようだった。つめかけた記者たちは一斉に手持ちのパソコン画面に目を落とし、猛スピードでキーボードをたたいていく。未曾有の大地震が起き、原発が相次いで爆発したというのに、レクチャー担当者のほうに目をむけたがらない」
この取材現場で持った危機感、といっていいすぎならば違和感が大鹿さんにこの本を書かせる(
言葉が生きものであるということが持つおもしろさ、自在さ、そして怖さについて教えてくれる──小谷野敦『頭の悪い日本語』
そうそう、あるある……と小谷野敦さんの辛口のコメントやジョーク混じりの解説を笑って読んでいるうちにふと立ち止まって考えてみると……自分もだいぶ『頭の悪い日本語』使っているなあと反省させられることしきりでした。
この本は単に日本語の誤用や乱れをついたものではありません。言葉が生きものであるということが持つおもしろさ、自在さ、そして怖さについて教えてくれていると思います。ましてや、小谷野敦さ
“欠点を魅力に”どんな自己啓発本よりも優る自分磨きの方法がここにあります──滝沢充子『あなたのままで女優のように魅力的になる方法』
自分磨きに関心がない人はあまりいないと思います。けれど自分が実践している方法が本当に自分を磨いているのでしょうか、ということを考えさせるものでした。滝沢さんは数多くの女優さんを育ててきた人です。その実践法が15のレッスンで紹介されています。
例として紹介されている女優の人たちの魅力の分析に基づく実践法はとても強い説得力を感じさせます。
滝沢さんは次ぎの宣言からこの実践法(トレーニング)を