
成果主義がもたらすモラルハザードというもの、それに引きずられた日本の姿。過去から学ばねばならないことはまだまだあるのです──NHK取材班『日本人はなぜ戦争へと向かったのか』
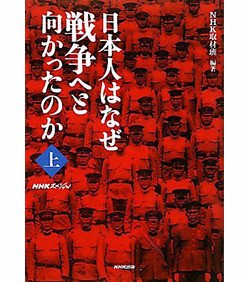
「アメリカによる「愚行」であったイラク戦争。イラク攻撃にいたるブッシュ政権の意思決定過程をしらべると、それは真珠湾攻撃に至る日本の意思決定プロセスと非常によく似ていることがわかります。(略)どちらも理性ある人間と見られるメンバーがとんでもなく不合理な決定をしています。(略)異議を唱えるものには、「愛国心が欠落している」と糾弾する。「ちょっと待て。これは無茶苦茶だ」などといえばその人たちは排除されてしまう。こうしたことが、ほとんどの社会の意思決定レベルで起きるのです」(ジョン・ダワーさん)
これが私たちがあの太平洋戦争を忘れることなく考え続けなければいけない理由のひとつだと思います。もちろん太平洋戦争だけでなく、戦争を起こさないためにも何度もさまざまな戦史は研究される必要があると思います。
この本は平成23年にNHKで放送された『日本人はなぜ戦争に向かったのか』をもとに、番組内では放送しきれなかったインタビュー部分を収録し、さらに新稿を加えて出版されました。通説を覆すものも含めわかりやすくあの戦争にいたるまでの日本と日本人の姿を追っています。(本書も放送時と同様に「外交」「陸軍」「メディア」「指導者」の4つの章で構成されています)
日本の戦前の(今でも?)外交の稚拙さはしばしば指摘されていますが、なぜそのようなことが起きてしまったのでしょうか。国際連盟脱退のいきさつでも政府は連盟にとどまることを望み、また全権代表だった松岡洋右も必ずしも脱退論者ではなかったようです。
「日本にとって有利な条件で妥結する道はあった。それを逃し、外交的に完全なる敗北を喫してしまった要因は、日本側当事者たちの甘い体質にほかならなかった。そこから浮かび上がってくるのは「希望的判断」に終始し、その幻想が破れると「急場しのぎ」の弥縫策に奔走する、国家としての根本的な戦略が欠如した日本の姿であった」
「希望的判断」とは、いってしまえば他者のいない(自分に都合のいい)判断だということです。そこには日本陸軍の勝手な思惑があったのです。
「最大五百五十万人にまで膨張した巨大組織・陸軍」の責任は以前からいわれているところですが、陸軍の暴走はなぜ起きたのでしょうか。菊澤研宗さんはそこにモラルハザードがあったと指摘しています。モラルハザードを引き起こしたものは何だったのでしょうか。それは「成果主義」というものだったのです
「成果主義の怖いところは、モラルハザードを引き起こすことです。本当は「やってはならない」といわれているのに、結果がよければゆるされるということがわかっていますから、隠れてこっそりやってしまう」
この成果主義が外交へ「希望的判断」を押しつけ(!)、「成果」を得るまで猪突猛進するということをもらたしたのです。たとえば、関東軍の現地独断による満州事変がその典型です。けれどそれは旧日本陸軍特有なものではありません。
このモラルハザードを増幅したのがメディアでした。メディアの責任を語る中で佐藤卓己さんは「自らが煽った世論に自らが縛られて動きがとれなくなって日米開戦に至った」と語っています。そのうえで、さらに佐藤さんは「輿論」=公的な意見(パブリック・オピニオン)と「世論」=より感情的な意見(ポピュラー・センチメンツ)と明確に区別し、「輿論の世論化」ということが起こったとして、戦前日本の大衆政治状況を分析しています。満州事変が国民に受け容れられた(成果主義ということもありますが)ことには「満州事変が日本にとっては日露戦争の戦後処理問題だと見なしていた」(佐藤さん)ゆえに、満州は国益論に結びつきやすく、メディアもそれを後押ししたのです。
佐藤さんはもうひとつ貴重な指摘をしています。
「戦争が非常に暗く貧しい状況を招くということが確実だとわかっていれば、もっと多くの人が戦争に反対したでしょう。つまり、少なくとも短期的には、開戦が明るく豊かな生活への高揚感をもたらしたという側面を無視してはいけないのです。まして、当時の日本人には敗戦の経験がありませんでした。そうした状況を正確に理解したうえで、それでもなお戦争に反対するべきだったということでなければ、歴史を教訓とすることにはなりません」
これはとても重要な指摘だと思います。暗く、統制され、戦火の下にあったのは確かですが、それだけのはずはありません。まして日本は「敗戦の経験」がなかったのです。世界不況下で各国がブロック経済化している中、閉塞感に包まれていた日本にとって戦争はなにかをこじ開ける鍵のように思われていたのかもしれません。
この「敗戦経験」の無さというのはきわめて重要なキーワードだと思います。「成果主義」への道だけでなく、第1次世界大戦の理解(分析)にも「敗戦経験」の無さからくる楽観主義があったのではないでしょうか。第1次世界大戦が国力を賭けた総力戦だという認識はごく一部の人にしかなかったことがこの本のいたるところで明らかにされています。
それでも開戦は起こった。この本を読むと「起こった」としかいいようのない実態が明らかにされています。「決定された」のではない、としか思えません。「決定」させたものはなにか。それを「負けるといえなかった空気」「異議を唱えられない雰囲気」だったといわれることが多いようです。事実、そのような言葉はしばしば、旧軍人の回顧談に出てきています。けれど、それはやはり責任の放棄だったのではないでしょうか。と同時に「輿論の世論化」の恐ろしさをも私たちは知っておく必要があると思います。
「タイトルが、なぜ「日本」でなく「日本人」なのか(略)「日本」とする場合、当時の天皇を中心とする政府・軍といった国家システムの責任を想起させますが、「日本人」とする場合、国家を形成する一人ひとり、責任が重い政治家や軍幹部の場合でも、運営の構成者としての個の主体性が浮き立ち、さらに、現在を生きる私たちにとっても、ある種の連続性を持って考えることができる印象になります。(略)太平洋戦争へ向かった原因を客観的に探る最新の研究は、「軍国主義に染まった日本国」というステレオタイプな主語では語りきれない広がりを持ってきています。「日本人」という主体のほうが広い視点で歴史を直視するにふさわしいと考えた理由です」
過去は捨てて(忘れて)いいものではありません、また、過去を恣意的に解釈してよいものではありません。過去を正当を学べるものにしか未来はやってこないのではないでしょうか。そのようなことを感じさせる一冊でした。
(「普天間基地や福島原発事故をめぐって迷走する現在の日本の政治状況が戦争前の日本とあまりに酷似している」というのも気にかかる一節でした)
書誌:
書 名 日本人はなぜ戦争へと向かったのか
編著者 NHK取材班
出版社 NHK出版
初 版 2011年2月25日
レビュアー近況:シーズンごとに仕事場のルームシューズだったりスリッパだったりを新調して気分を変えていますが、東京音羽も銀杏の色付きと共に気温が下がり、暖かいのを至急物色しなければならない事態に。麻のスリッパも気持ち良いのですが、流石に末端冷えてきました。
[初出]講談社プロジェクトアマテラス「ふくほん(福本)」2014.11.28
http://p-amateras.com/threadview/?pid=207&bbsid=3278
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
