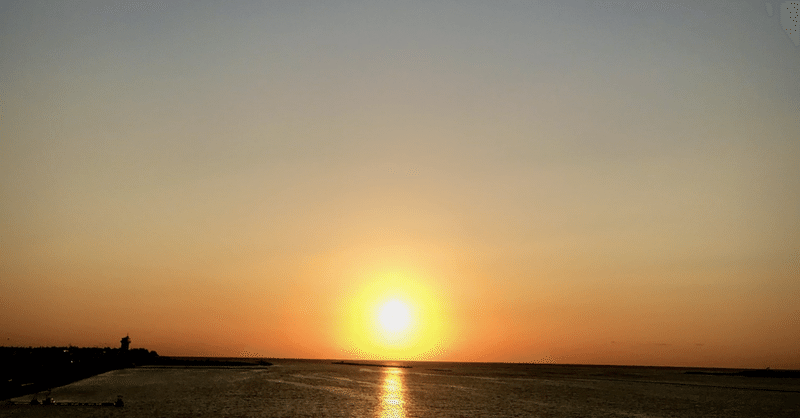
心理の本を読むことでうつ病から回復した話⑦(大学生編Ⅱ)
読んでくださってありがとうございます。
機能不全家族のもとで育ち、精神疾患(うつ病など)で苦しみ、そこから回復した自分の半生を書きたいと思います。
今回は大学生編Ⅱになります。
前回の話はこちら
1話はこちら
父親が少し変わり始める
大学に行かず、家に引きこもっていた自分はうつ病を再発してました。
家はゴミ屋敷になっており、問答無用で母親に実家に連れ戻されます。自分は「実家は父親がいるから嫌だなあ」と思っていました。
しかし実家に戻ると、ある変化に気付きます。
父親の様子が前と比べて、少し丸くなったように感じます。
母親に話を聞くと、どうやら取引先の仲が良かった社長が首つり自殺したとのことでした。ニュースにもなってました。
その社長は、父親から見て自殺するような人には見えなかったそうです。自殺する1週間前位に、その社長は父親に電話をかけてきました。その社長は仕事の話をすることはなく、「いつもと様子が違う」と父親は感じたそうですが、電話はすぐ終わってしまいました。
その後自殺したと聞いて、「あれはSOSだったのかも。自分はうまく対応できなかった」と父親は悔やんだようでした。
この出来事がきっかけとなり、息子の自分が自殺するのではないかということに父親は危機感を覚えたらしいです。「死にたいって言うやつは死なない」って本気で信じているような人間が少し変わり始めました。
自分は実家にいても以前よりは少しマシになりました。
悩んでいるのは自分だけじゃなかった
実家に戻り、自分は自堕落な毎日を過ごしていました。その時母親から「久しぶりにピアノでも習いに行ったら?音楽は癒しになるかもよ」と言われ、小学生の時、ピアノを習っていた先生に会いに行きます。
ピアノの先生は、自分のあまりの生気のなさに驚き、「何かあったの?」と話を聞いてくれました。「今自分はうつ病になって、苦しんでいる」と伝えると、先生は自分の辛さを受け止めてくれました。
自分の話を聞き終えた後、先生は「自分も昔パニック障害だった」と告白してくれました。先生も母親からの過干渉で苦しみ、学生の頃にパニック障害になったらしいです。
リアルで心を病んだ人の話を聞いたのはこの時が初めてでした。「悩んでいるのは自分だけじゃないんだなあ」と感じました。
先生は、父親よりも母親が、自分に悪影響を及ぼすのではないかと小さい頃から気にかけていたそうです。
自分の母親は、この先生が音大卒ということを知り、息子(自分)にピアノを教えてくれと無理やり頼みこんだそうです。その強引さに負け、先生はピアノ教室を開業したとのことでした。
自分は「父親もやべえ奴だけど、母親もなかなかにヤバい奴だな」と話を聞いて思いました。
話の最後に、先生はパニック障害を治したきっかけとなった心理センターを教えてくれました。自分はそこに行くようになります。
認知療法と出会う
先生に教えてもらった心理センターは今までとは少し違いました。そこでは、話を聞くだけではなく、「心は意識と無意識に分かれてて氷山によく例えられていて…」などの心理教育をしてくれました。
自分はそこで自律訓練法を学びます。
自律訓練法とは、催眠に似たリラクゼーション法です。自分に「右手が重い、温かい」などと自己暗示をかけることで、意識的にリラックス状態をつくり、自律神経のバランスを回復させる治療法です。
今でもパニック障害などの治療によく用いられています。(※禁忌症があります。自分でやる場合、禁忌に当てはまらないか確認し、自己責任で実行してください。)
自分はこの自律訓練法を習得し、リラックスした状態を少し思い出します。
治療開始して1ヵ月の頃、カウンセラーに「今私これ勉強してるんだ。君治療意欲高いから、もし良かったらやってみたらいいかも。」と、ある本のコピーを渡されます。
渡されたのは、認知療法の本のコピーでした。(※現在は認知療法と行動療法が合体し、認知行動療法と呼ばれています。)
認知行動療法は大学で学んでいたので、知ってはいました。というか、この頃は結構小馬鹿にしてました。
「今ここ」に焦点を当てるっていう考えが、当時自分の頭にはありませんでした。というのも自分の辛さは「過去」が原因で、怒りや悲しみなど抑圧された感情を吐き出すことが自分の改善に繋がると固く信じていました。
また、「精神疾患の人は認知が歪んでいるからそれを矯正しましょう」と言われているみたいで好きではありませんでした。
とはいえ、自分はこのカウンセラーが薦める位ならとりあえずやってみようと思い、800ページもある3800円もした分厚い本を買います。(当時はコンパクト版がなかった)
自分は「こんな分厚い本、急性期の自分なら絶対読めないわ」と思って最初はイライラしていましたが、この本を読んでいくうちに、段々とこの治療法に魅了されていきます。
ある程度読むと「これ自分ひとりで出来るやん」と気づき、自律訓練法ばかりするようになった心理センターをやめます。
この頃、大学2年生になり、大学にもう一度行くようになります。
頭の中で勝手に事故を起こしてる
「歪んだ認知」と言われているのは非常に癪に障りましたが、「自分が育った歪んだ環境に適応する為、自分の認知は歪んだんだ」と脳内で補完し、とりあえず治療法に取り組むことにしました。
(※認知行動療法では現在、「歪んだ認知」という言葉は避け、「非機能的認知」と修正しています。)
この本を読み、不快な感情は、出来事そのものから生み出されるのではなく、自分の考え方が今は適応的ではなく、その結果不快な感情を生み出していると学びます。
自分は、普段の生活で自分の思考を観察すること(セルフモニタリング)を行います。
セルフモニタリングの紹介はこちら
実はこのセルフモニタリング、少し馴染みがありました。そう、「自分いじめをやめる」ことをうつ病から回復した時に実行してました。(経験談の5話目参照。)
最初、自分の<認知>(考え)を自分の頭で把握するのは難しかったです。そこで、自分は、モヤっとした嫌な気分の時、その原因を探るようにしました。
「自分のこのモヤっとした感じはどこから来てるんだろう?あの時か?いや違う。じゃあ、あれか?これも違う。あ、そうだ!あの時だ!」
こんな感じで直近の出来事を頭の中で頑張って思い出しました。
大学ですれ違った友達に会釈をします。しかし、その友達は自分に話しかけてくれませんでした。
自分はその時「自分なんてどうせいらない存在。だから友達は無視したんだ」と頭の中で勝手に思っていたのでした。
頭の中で思っている<認知>は意識しないと過ぎ去ってしまう為、自分の中にはもやもやとした嫌な気持ちだけが残っていました。
自分はこのようにセルフモニタリングすることにより、色んな場面で頭の中では勝手に激突し不快な感情を生んでいることに気付きます。
自分の考えを現実とすり合わせてみる
自分は友達とすれ違った時、挨拶が返ってこなかったため「自分なんてどうせいらない存在。だから友達は無視したんだ」と思ってました。
自分は「友達は自分を無視をした」という考えに焦点を当て、この考えに代わる色んな考えを考えてみます。
「待てよ?今日の朝もこの友達と普通に話したよな?ってことは自分に気付かなかった可能性もあるよな。」
「そういえば、挨拶したのは授業と授業の合間の短い休みの間だった。もしかしたら友達は次の授業に遅れると思って、急いでたのかも。」
「てか、今日話してた奴がいきなり人のことを嫌うなんてことあるかな。それって現実的にはなさそうだ。」
「そもそもすれ違った友達は色んな人とも仲良くする奴だ。自分より性格悪いと思えるような友達もいっぱいいるぞ。」
「てか、人を無視するような人間って、そいつが嫌な奴なだけじゃん。もしそうなら友達と縁を切ればいいんだ」
こんな感じで代替的な思考を沢山生み出すと、最初の「友達は無視したに違いない」という考えは少し弱まりました。(完全になくなるわけではないです。)
思い直しをすることで、感じてた悲しみも少し和らぎました。
自分は本当に無視されたのかどうかが気になり、次の日「この友達になんであの時無視したの?」と聞きました。そしたら、友達は「え?そんなことあった?」と返答しました。
無視されていたわけではありませんでした。
このように、認知行動療法は『自分の考え』と『現実で起こっていること』、この双方のバランスが釣り合う考えを導き出すよう働きかける心理療法になります。
この思い直しは「認知再構成法」という認知行動療法の技法です。
気が向いたら、別の記事で書きます。
「今、ここ」で困っていることを改善する
自分は嫌な気持ちがあるとそれを【ネタ】にして「認知再構成法」を実行しました。そうすると、少しずつ気持ちが楽になっていきました。
また、この時は一人暮らしをしてたので、父親に縛られていた劣悪な環境からはある程度抜け出せていました。
昔学んだ「~~すべき」「~~出来ないやつはダメ人間だ」といった非機能的な認知を持っている必要はもうないんだなと段々と思えるようになっていきます。
「過去」を変えるのではなく、「過去に影響を受けた今」を変えることで自分の症状は段々と良くなりました。また、「今」を変えることは効果が早く出やすいんだなということも学びました。
今回はここまでとなります。次回は、大学生編後編に続きます。長い文章を読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
