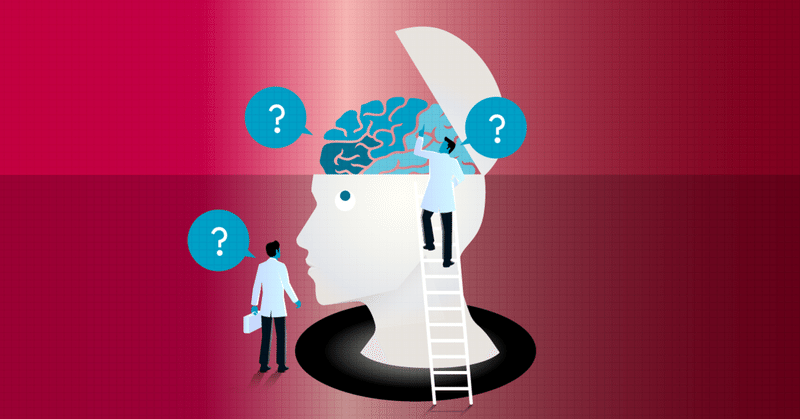
【思考訓練の場としての経済学入門】リスクマネジメントの基礎知識
(1)はじめに
昨年は、台風などの災害、今年に入ってからは新型コロナウイルスにより、私たちの社会は大きく揺らぎました。
私たちを取り巻くリスクは年々増えています。しかし、リスクとの付き合い方は、あまり知られていません。本稿では、この不確実な世界を生き抜くために必要なリスク管理の基本を解説し、これを身に付けていただくことを目標とします。
(2)リスクとは何か
「リスク」は面白い言葉です。一般的には、「危険」という意味で使われることが多いですが、実は他にも色々な意味を持つ言葉であり、掴みどころがありません。
語源は、「勇気」を表すラテン語です。「危険」以外に、金融の世界では、「期待するリターンに対するブレ幅」、リスクマネジメントの世界では、「目標達成までの間に起こりうる事象」を指します。
本稿での定義は、「目標達成までの間に起こりうる事象」とします。
組織にしろ個人にしろ、ある程度の目標を持っています。会社であれば、今年度の売上等の短期的な目標から、「こういう会社にしたい」という中長期的な目標まであります。個人であれば、将来の就きたい職業、健康で長生きするといった目標があるでしょう。100歳まで健康に生きたい人にとって、大病や事故はリスクです。また、人間らしい生活を送るうえで、金銭的な苦境に陥ることもリスクです。
(3)リスク管理の手順
全てが順風満帆なら苦労はないのですが、そうは問屋が卸さないのが世の常です。ゴールまでの道程には、必ず邪魔者(リスク)が現れます。この邪魔者の扱い方を知っているか否かが、ゴールに近づく要となります。では、この邪魔者との付き合い方を学びましょう。
❶ リスクを識別する
まずは、身の回りにあるリスクを洗い出します。想定できるリスクをどんどん書きだしましょう。このとき、「こんなことは起きないだろうな」と楽観的な先入観を抱かないことが大切です。「心配事の9割は起こらない」と言いますが、リスクの洗い出しにおいては、考えられる心配事はどんどん明らかにする方が良いのです。なぜなら、「起こらないだろうけど、万が一発生したら致命傷を負うリスク」(ブラックスワン)が存在するからです。
これは私の経験則ですが、確かに心配事の多くは杞憂に終わります。しかし、「大丈夫だろう」と高をくくったことは、不思議なくらいに実現します。根拠のない自信は、そっと隣に置いておきましょう。
❷ リスクを評価する
リスクを洗い出したら、各リスクの影響度合いを評価します。評価は「発生した場合のダメージの大きさ×発生確率」で評価します。「金額×確率」と考えても良いでしょう。
❸ リスク対策を講じる
最後に、リスク対策を講じます。
① フェーズごとのリスク対策
㋐ 予防
最も初期段階の策です。そもそも問題が起きないように予め対策することです。例えば、健康診断で生活指導したり、予防ワクチンを打ったりすることです。
㋑ 発見
発生した問題を、すぐに見つけ出すための策です。健康診断で病気を早期発見することなどが当てはまります。
㋒ 是正
発見された問題を解決することです。病気で言えば、治療にあたります。
優先順位は、予防>発見>是正です。対応は、早ければ早いほど手間がかからないからです。逆に、遅くなればなるほど、ダメージが深刻化し、手間やお金がかかります。
予防は、そもそも問題を起こさないためのものなので、有効に機能していれば、問題は発生しません。そのため、効果が目に見えないという難点があります。そのため、つい軽視されがちです。しかし、予防策こそローコストでリスク回避するためには最重要なのです。
(補足1:面倒くさがりなら、見つけたその場で処理せよ)
私もそうですが、ついつい問題を先送りにしがちです。しかし、何度も言いますが、問題への対応は早ければ早いほど労力がかかりませんので、逆説的ですが、見つけ次第その場で処理することが一番楽をする方法だと思います。例えば掃除も、まとめてやるのではなく、汚れを見つけたらその場でキレイにすれば、こびりつくこともありません。その場で掃除する習慣が身につけば、丸1日かけて掃除する必要もなくなるでしょう(貴重な休日をつぶさずに済みます)。
(補足2:あえて寝かせた方がいい問題もある)
補足1と矛盾するようですが、問題の中には、放置した方が良いものもあります。それは、時間が解決してくれる場合です。わざわざ自分が動かなくても、他人が対処してくれたりします。むしろ、こういうときに自分がしゃしゃり出ると、かえって問題を複雑化させる場合があります。ただ、こういう問題の見極めは、経験がないとなかなかできません。上に立つ人は、今までたくさんの問題解決をしてきたためか、この見極め力に長けていることが多いです。
② リスク対策手法
リスク対策には、主に受容、回避、低減、共有(移転)、活用の5つの方法があります。
㋐ 受容
何もしないことです。リスク対策もタダではありませんので、ダメージが小さいものであれば、あえて何もせず、受け入れることも有効です。
㋑ 回避
リスクが高いことをやめることです。企業であれば、高リスクの事業から撤退したり、そもそも参入しないことです。
㋒ 低減
大きなリスクを小さくすることです。災害による倒壊を防ぐために、自宅の耐震・耐火工事を施すことなどが当てはまります。
㋓ 共有(移転)
リスクを誰かと共有したり、誰かに移すことです。例えば保険は、少額の保険料で、万が一の場合は大きな保険金額が得られます。これは、大きなリスクに備えるため、たくさんの人がお金を出し合うことで、リスクをシェアするということです。また、企業が他社に外部委託することは、リスクを自社に抱え込まないようにする手段です。
㋔ 活用
以前は、リスクはできるだけ背負わないようにするものでしたが、リスクを取らなければ利益も得られないという考え方が広まり、許容範囲で積極的にリスクを取り、高いリターンを追究するというのが最近の潮流です。企業であれば、「これくらいのリスクなら背負っても大丈夫」という基準(リスクアペタイトフレームワーク)を設定するところがあります。また、個人なら寝かせているお金を、リスク許容度に応じて投資信託などに投資することがそうです。
(補足:無視できる小さなリスクと、無視できない小さなリスク)
すべての事故を生真面目に全力で解決にあたっていては、身も心も持ちません。チマチマした問題は、適当に処理すればよいのです。ただ、被害が小さいという理由で軽視すべきではありません。
優れた経営者は、小さな事故もチェックしています。そのうえで、うるさく言うものと、そうではないものを分別しているように思います。
チマチマした問題でも、重く受け止めるものと、適当にあしらうものがあり、この見極めは難しいですが、個人的には、「同じ発生原因で、大事故につながる恐れがある」問題は、重く受け止めるべきだと思います。
たとえば、「車で壁をこすってしまった」、「取引先に誤って、100円多く振り込んでしまった」という2つの事故があるとします。どちらの事故を重視すべきでしょうか?
今回のケースに限って言えば、被害の大きさは前者の方が大きいです(自動車保険への加入の有無は無視して、単純にこすってしまった壁と、自動車の修繕で、100円以上の費用はかかります)。しかし、前者の事故は、せいぜい運転者の不注意によるものであり、これ以上原因を追究しても意味がありません。一方、後者の事故は、たまたま今回の被害額が少額だったから良いものの、誤った金額で振り込みできてしまう仕組みがあること自体に大きな問題があります。チェック体制はどうなっていたのか?間違った振り込みが成立するシステムがあるのはなぜか?きちんと原因を追究し、再発防止策を講じないと、次は致命傷を与えることになるかもしれません。
(4)まとめ:リスク管理の要諦と新型コロナウイルス対策
リスク管理は、それを明確化し、それぞれに対策を打つことが基本です。
「根拠のない自信」は、モチベーションの維持には役立ちますが、リスク管理においては、リスクの洗い出しを阻害します。想像力を働かせて、最悪のケースを想定し、対策を講じることが何よりも重要です。リスク管理においては、心配性な方がよいのです。
「備えあれば憂いなし」という諺のとおり、様々なリスクに予め対策を講じていれば、いざ問題が起きても冷静に対処できます。逆に言えば、トラブルが発生してから慌てるようでは、リスク管理が不十分だということです。
新型コロナウイルスにより、想定外のことがたくさん発生しています。日頃から有事に備えていた方と、そうではない方で差が生じていることでしょう。今からできることは、予防に徹することだと思います。緊急事態宣言が発令され、外出自粛が要請されていますが、罰則を伴う諸外国と比べ、日本人の認識はまだまだ甘いと思います。
「自分は大丈夫」という根拠のない自信は、このような非常時には禁物です。万が一、感染し、重症化すれば、金銭的、身体的にどんどんコストがかかるでしょう。
また、政府は人との接触を最低でも7割、できれば8割と言っていますが、「7割減らせばよい」と考えるのではなく、「8割減らす」と捉えるのが正解です。未知のウイルスに対しては、とにかく保守的に見積もったシナリオを基に行動すべきだと思います。
慎重に行動する人に対し、「ビビっている」と揶揄する人がいますが、リスク管理がきちんとできる、賢明な人にようになるためには、是非「ビビる勇気」を持っていただきたいと思います。
【ドリル】
(1)リスクには、様々な意味があります。金融の世界では「①」、リスクマネジメントの世界では、「②」という意味です。
(2)リスク管理の手順は、リスクを(③)する→リスクを(④)する→(⑤)するです。
(3)フェーズごとのリスク対策について、優先順位は(⑥)>(⑦)>(⑧)です。
(4)リスク対策の手段は、(⑨)、(⑩)、(⑪)、(⑫)、(⑬)の5つがあります。
【解答】
①期待するリターンに対するブレ幅
②目標達成までの間に起こりうる事象
③識別
④評価
⑤リスク対策
⑥予防
⑦発見
⑧是正
⑨受容
⑩回避
⑪低減
⑫共有(移転)
⑬活用(⑨~⑬順不同)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
