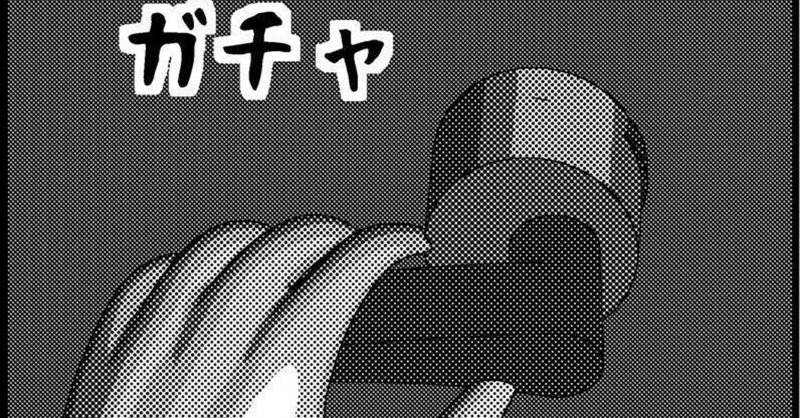
推敲(ゆるい解説 & 雑記)
科挙を受けるほどの秀才・賈島(かとう)はラッキー。
なんたって「推敲」の故事で、賈島は当時長安の知事であった韓愈(かんゆ)にぶつかっているんだから。どこか少女漫画の「食パン少女」を思い出す向きもあります。
韓愈は詩の大家でしたが、その韓愈も賈島の漢詩(=作文さくもん)の才能を認めていたとのこと。
推敲の意味は「詩や文章を、よりよく直すこと」。
文章のブラッシュアップを指します。
推敲は「推す=押す」と「敲く=叩く」で、どっちの方が詩にふさわしいか、賈島が悩んだ結果、韓愈がアドバイスをしたという故事からできた言葉。
韓愈曰く「敲く」のほうがいいよ、と。
理由は、音が出るから。
五感に訴えた表現って詩歌でも小説でも結構レベルの高い技なんだとばっかり思っていたんですが、唐の時代にもう意識してるってのはやっぱりできる人たちだったんだろうなと。
ちなみに「結局このとき賈島はどんな詩を作ったの?」っていう疑問は、塾講師時代にたまに聞かれました。
五言律詩(ごごん りっし)だったそうです。
覚えてますか、漢詩にまつわる専門用語を。
だいたい中2の教科書に出てくるんですが、漢詩の構成というのは……
・5文字(=五言) or 7文字(=七言)
・4行(=絶句) or 8行(=律詩)
の組み合わせで4パターン。五言絶句とか、七言律詩とか。
さらにいまでは詩のみならず小説などの構成の基本である起承転結は、「絶句」の4行それぞれの役割を説明したものです(「律詩」の場合には首頷頸尾しゅがんけいび)。
あるいは韻を踏む(押韻おういん)なんていう、いまではラップの世界でおなじみの技も、漢詩に由来します。対句(ついく)もバンバン出てきますし、解説材料としては使えるかな。
ただ、詩の出来の良し悪しは、わたしには正直さっぱりわかんないんです(高校のころ、現代文の先生が「『山月記』に出てくる漢詩の出来は天才が書いたものとは言いづらい」みたいなことを言っていましたが、わたしには判別がつきませんでした)。
以下は参考まで。「推敲」に出てくる賈島の作品を、以下にコピー&ペースト。一部太字に変更。
閑居少鄰竝 閑居隣並少なく
草径入荒園 草径荒園に入る
鳥宿池中樹 鳥は宿る 池中の樹
僧敲月下門 僧は敲く 月下の門
過橋分野色 橋を過ぎて野色を分かち
移石動雲根 石を移して雲根を動かす
暫去還来此 暫く去って還た此に来たる
幽期不負言 幽期 言に負(そむ)かず
横書きだと見づらいのはやむなし。
よく見れば、対句も押韻も盛りだくさんです。
お読みいただきまして、どうもありがとうございます! スキも、フォローも、シェアも、サポートも、めちゃくちゃ喜びます!
