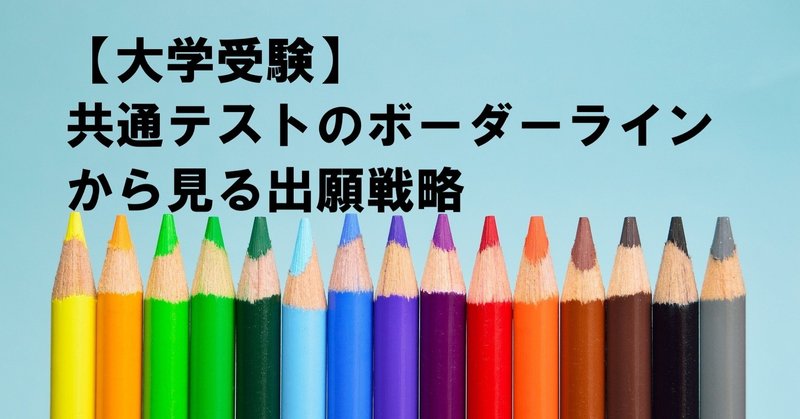
【大学受験】共通テストのボーダーラインから見る出願戦略
予備校で講師&学習アドバイザーをしている冒険者です。冒険者ブログを運営しています。
冒険者ブログは「幼児教育~大学入試」や「大人の学び」といった、生涯学び続ける人生偏差値を高くしたい人向けに記事を書いています。
さて、今回は「大学受験の共通テストボーダーラインから見る出願戦略」について解説していきます。
センター試験から共通テストに変わり、各大学の共通テストの得点率ボーダーラインが見えてきました。
そこを深堀しながら戦略を考えていきます!
今回もnoteは簡単に、詳細はブログで!という流れで行きます。
ではさっそくいってみましょう!
共通テスト ボーダーラインの変化
それでは、共通テストの得点率ボーダーラインの変化をみていきましょう。
国公立大学では共通テストの点数+2次試験の点数で合否が決まります。その共通テストで、どのくらいの点数を取れれば志望校に対して合格ラインになるのかが、発表されてきました。
センター試験よりも難しくなる共通テストですが、ザックリとどのくらいへんかするのかをまとめますと・・・
・難関国公立大→3~5%ダウン
・上位国公立大→5~7%ダウン
・地方国公立→5~10%ダウン
このように変化します。つまり、難しい大学はそこまで落ち込まず、偏差値が下がるほど、ボーダー得点率も下がっている傾向になるのですね。
ぶっちゃけ、難関大学にいこうとする学生にとって、センター試験も共通テストも大きな差がないのです。
それよりも2次試験勝負になることが多いですからね!
ただ、地方でも国公立大学に入りたい学生は、共通テストが大きな大きな壁となって立ちはだかることが予想されます。
思考力、表現力、判断力が試される共通テストですので、基礎学力がない学生には簡単に点数を取らせてくれないのです!しっかりと基礎を固めて対策をしてください。
共通テスト 英語の配点の変化
あまり話題になっていない感じがするのが、「英語の配点の変化」です。
けっこう変わっているのに、取り上げられていない事柄があります。それは・・・
・リーディング(筆記)とリスニングの得点比率
100点:100点
と、センター試験に比べてリスニングの比率が大きく上がりました。
大学ごとに比率は異なりますが、基本は1:1になります。つまり、筆記の勉強ばかりしていたセンター試験の英語の勉強の仕方では、共通テストは戦えません!
ちゃんとリスニング対策もやらないといけなくなったわけですね!
共通テスト 英語検定試験
では、英語の外部検定試験についての解説もします。
以前は「英検は必須!」「GTECやTEAPも受けた方がいい」という話がありましたが、公平に受験できる環境ではないとして、英語の外部試験導入も見送られました。
では、その後どうなったのでしょうか?これもザックリとまとめると・・・
・出願条件になっている大学がある
・加点する大学がある
・外部試験型受験がある
という感じです。つまり、そういう大学があって志望校に必要であれば受検する程度で良い、ということです。
結論を言うと「あまり深く考えなくてよい」ということですね。
最近面談した家庭で「英検は受けた方がいいのでしょうか?」と聞かれましたが、「志望している大学では必要ないので、大丈夫です」と答えています。
詳細は大学HPで確認してほしいのですが、そこまで取り上げている大学はほんの一握りに過ぎません。
今後の導入ではわかりませんが、2021年度入試においてはほぼ影響はないでしょう!
共通テスト ボーダーラインの変化 まとめ
いかがでしたでしょうか?
簡単に共通テストの変化を見てきましたが、難しくなることは間違いありません。
ただ、基本的な勉強を続けて、共通テストの傾向をつかみ対策をすれば戦えるようになります!
各大学のボーダーラインをご覧になりたい方はブログの方でご覧ください。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
合わせて読みたい記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
