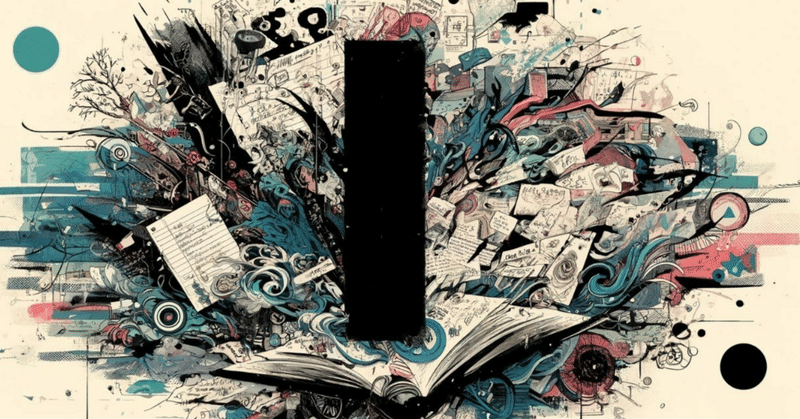
九州から上京したITエンジニアが起業し出版に至るまで
こんにちは!小野です。
出版について、様々な良い反響をいただいています。
ありがとうございます。
執筆を通じて、私自身の棚卸もできました。
今回は技術書という枠組みの中で多くは触れていない、私自身のこれまでの歩みについて振り返りたいと思います。
背景(生い立ちから学生時代)

出身は、九州の大分県です。
両親が公務員で共働きの家庭だったので、祖父母や親戚の方にも大変お世話になったことを覚えています。
その中で、両親が仕事に真摯に取り組む姿を見て育ったことが、当時の自立心の芽生えや、今の職業観に影響しているように思います。
また、祖父母が自営業をしていたことも、今の経営者としての働き方に繋がっていると感じています。
高校は「近いから」という理由で決定。徒歩3分なのに、自転車で通っていました(笑)
たまたまそこが進学校だったこともあり、周りと同じように勉強に注力し始め福岡の国立大学に進むことになりました。
大学の専攻は「地球惑星科学」。幼いころから考古学・恐竜・自然・宇宙などが好きだったことから選びました。
研究の面白さから大学院まで進み、南極周りの海を40日間航海したことは忘れられない思い出です。
大学院の修論は教授の薦めもあり、英語で書き上げて海外の専門誌に掲載されました。
ここまで見ると勉強熱心な学生ですが、実際は、部活(アイスホッケー)・バイト・麻雀に明け暮れた記憶が大部分を占めています(笑)
そして直面したのが、就職活動です。
大学院に進んだ理由の半分は研究の面白さですが、半分はやりたい仕事が見つからず2年先延ばししたかったからというのが本音でした。
しかし、無情にも院生1年目の秋には就活が始まります。
堅実な仕事をしていた両親や、研究で実験機器と向き合っていた経験から向き不向きで考え、大手企業かつ手に職がつくIT業界の企業を就職先に選びました。
東京への憧れがあったことも選択の要因になっています。
東京は危険だとか、人が冷たいだとか、だいぶ偏見をもっていたので(笑)、ドキドキの東京生活のスタートでもありました。
期待と不安は何事でもセットですね。
会社員時代

大手の電機メーカーに入社し、ITエンジニアとして働き始めました。
同期や職場の先輩方や、会社の教育制度に支えられながら、ITエンジニアとしてキャリアのスタートを切りました。
全体研修が終わり、「Java」というバックエンドの言語でシステム開発を行う部署で言語の習得を開始。
社内の研修制度や資格を取得するための自主学習にも励んでいましたが、一番は開発現場の中で優秀なITエンジニアの先輩方を真似ることが上達の道でした。
24時間365日停められないシステムの案件だったので、稼働時間含めてタフな経験でしたが、ITエンジニアとして成長に繋がる数年間でした。
人は環境の生き物なので、どういう環境で誰から学ぶのかは自分の成長や成果に直結するので大切です。
そんな中、将来を考えるきっかけになったのは、同期の独立でした。
彼と話す中で、「自分のゴールは何なのか?」「何のために働くのか?」ということに向き合いました。
振り返ると部活や勉強で努力していた時には、ゴールがありました。
しかし、その当時の自分は大手企業に入るまでがゴールになっていて、それ以降は会社から与えられた目標だけで仕事をしていたことに気付きました。一番直面したことは、自分のビジョンや目標も持たずに会社に依存していた自分自身に気付いたことでした。
会社の目標に向けて努力することが悪いわけではありません。ただ、その先の自分の人生について考えないことは別の話です。
残業が多く家と会社の往復の生活の中でインプット不足を感じていたので、まずはそこを打破しました。
稲盛和夫さんを始めたとした書籍や、異業種の先輩や経営者の方々とお話しする中で、自分の最初のキャリアビジョンが明確になっていきました。理想を描くための良質なインプット(書籍と人)が効果的でした。
著書の中でも「キャリアビジョン」の重要さには何度も触れています。
私の場合は、せっかくならITエンジニアという業種で制限をかけずに、大きく望んでみることにしました。
その結果、
「決められた時給の中で働くのではなく、自分で時間や仕事に付加価値を付けた分だけ収入を得てみたい」
「収入も時間も管理下において自分で働き方を決めたい」
「目標に挑戦し続ける自分でありたい」
という理想を最初に描きました。
そこから逆算して考えていくと、会社員やフリーランスのITエンジニアの延長線上には実現の道がなく、起業して経営者になる先に実現の可能性があることがわかったわけです。
創業期

そこからはご縁が合った経営者の方に教えを乞いました。スポーツや武道の道では良き師を持つことが重要だと言われますし、幼少期に空手や剣道を習っていたこともあり、経営という道に進む際も学ぶ人を決めることを最初に行いました。ITエンジニアが経験を積みながら上達していくのと同様に、経営者としての能力も起業して経験を積みながら磨くものだと考えています。ただし、起業前に事業を継続させていくための基本的な力に関しては、働きながら週末にトレーニングすることにしました。具体的には次のようなことを教わりながら習得してきました。
・ビジョンを描き方向性を示すこと
・目標設定能力(成果目標・行動目標)
・事業計画を立てること
・目標達成能力
・実践力
・形になるまで継続する一貫性
・自己管理能力
・キャッシュフロー管理
・営業力(新規開拓力)
・コミュニケーション能力
・組織作り
・マネージメント
・リスク管理
特別なことはなく、会社員・経営者問わずビジネスパーソンとして大切だと言われていることばかりだと思います。ただし、「知っている」と「実践できる」と「結果にできる」には違いがあります。
例えば、野球を「知っている」と「実践できる」と「結果にできる(プロとして稼げる)」には大きな違いがありますよね。野球を知っていて、授業や部活でやったことがある人と、プロとして野球で飯を食べている人には大きなギャップがあるわけです。
同様に、ビジネス書を読んで理解したことと、それを実践することにはギャップがあります。そして実践を継続し、その中で自分を磨き、求めている結果を作ることにも大きなギャップがあるのです。
私が学んできた過程では、時には模擬的に経営に携わるOJTのような形で、会社員を続けながら経営の実践経験を積むことがあり、それは実際に自分で経営する際の大きなアドバンテージになりました。そして能力に関しても、今でも自分が完璧であると感じることはなく、まだまだ仕事の中で自分を高めている過程です。

事業を起こし継続させていく中でボトルネックになるのが、「お金」と「人間関係」です。これは、企業が倒産するときの2大要因でもあります。そのため、後々必ず大事になる難しいポイントとして、この2点については起業する前にトレーニングを行いました。
一例を挙げると、イベントの企画運営でした。自分から手を挙げて小さな飲み会の幹事となって企画するところから始め、最終的には1000人以上を集める音楽イベントを成功させました。その中で、集客、価格設定、会場の手配、ミュージシャンとの出演交渉、スタッフへの報酬支払いなど、ビジネスで経験するお金の流れを体験できたのは、貴重な経験でした。人を集めて価値を提供し対価を得るという商売の基本を、実体験を通じて学ぶことができたわけです。収益を出せたこともあり、自己資金で起業することができました。
お金のトレーニングと並行して、起業した際に必要となる人脈形成も同時に進めていました。
前述のイベント企画は、人脈作りのトレーニングも兼ねていました。法人や自分の店舗がない段階だったため、自分の身一つで新しい人と新たな人間関係を構築し、集客につなげていかなくてはなりません。知り合った人の人脈から、また別の人を紹介してもらえるように、自分が信用してもらえるどうかにも心を砕いてきました。一度会って終わりではなく、ファンやリピーターとなってくれる人が増やせるかどうかも重視したポイントです。
インターネットやSNS上でどれだけ知り合いが増えても、事業を立ち上げることはできません。泥臭く汗をかくアナログ的な経験の中で、新規開拓や人脈を作る力を磨いてきたことが、今の私の土台になっています。
実際、起業する際の仲間や取引先は、そうやって育んできた人間関係の中から生まれています。このように事前準備から起業後のプロセスまで含め、先輩経営者から学ぶことができる場所を探して、その中に入っていくようなことにも時間を使いました。
「学ぶ人」と「学ぶ場所」を決め、実践形式で十分な準備を行ったこと。その準備が整ったときが、私にとっての起業のタイミングだったと考えています。
多角経営の現在

最初に事業基盤になったのは、イベント事業やそれに紐づく営業代行業です。人脈形成やイベント事業を続けていると、人との繋がりが緩やかなコミュニティの形を成してきます。コミュニティの構成要素は「人」です。今手掛けている不動産仲介支援やキャリア支援や小売業は、どれも人の生活やライフスタイルや働くということに密接にリンクしています。決して派手ではないですが、人に根差した事業は事業の生存率を上げることに繋がると考えています。
以前は音楽系のイベント運営でしたが、現在はIT関連事業やキャリア支援に関係するイベント運営を継続しています。
整体事業や関連する漢方系商品を取り扱うお店の運営も行っています。
コンセプトは、「からだ整う、こころ満ちる。」です。一緒に事業を行っている元薬剤師の妻の経験から、体調を崩して対症療法するのではなく、健康と病気の間でなんとなく不調を感じているひとが、心身ともに健康な状態を維持できるようになることに役立つ事業にしようと決めました。からだの外側からと内側からの両方からアプローチできるように、オーダーメイド整体と漢方系商品を組み合わせたサポートを提供しています。「からだ」の悩みを解消すれば、「こころ」が満ちて明日への活力が生まれます。
IT関連事業は、ITエンジニアのチーム作りからスタートしました。
Mission:「チームの力でITエンジニアの価値を最大化する」
Vision:「プロフェッショナル人材の輩出により、IT課題を解決し豊かな社会の実現に貢献する」
このMissionとVisionの元に、システム開発事業・キャリアアップ事業・プラットフォーム運営事業の3本柱で事業展開しています。
AIの登場や技術革新により、移り変わりが目まぐるしい時代です。
そのため、テクニカルスキルだけでなくプレゼンテーションやコミュニケーション、ヒューマンスキルを兼ね備えたITエンジニアをプロフェッショナル人材と、わたしたちは定義しています。
どんなに技術が進歩しても社会の課題を解決するのは、「人」です。
わたしたちは、ITエンジニアの価値を最大化することが、その課題解決の突破口になると考えています。
価値を最大化するとは何を指しているのか?
・テクニカルスキルとヒューマンスキルの両面を向上させ、自身の人的資本を高めること。
・その高めたスキルや能力に見合った対価を得ていること。
・個人の成果だけでなくチームの成果にも貢献し、相互依存関係を作れること。
そうやってITエンジニアとしての価値を高めたプロフェッショナル人材が、個人としても組織としても多くのIT課題を解決し、社会をより豊かにするビジョンを描いています。
詳しくはこちらをご覧ください。
まとめ
起業は「点」であり、経営は「線」であると教わってきました。今の時代、起業することは簡単ですが、それを継続し発展させていくことは別の話になります。何のために経営をするのか、仕事をするのか。その答えに繋がる自分のキャリビジョンを描き、それを実現するために線を引き行動していく。それを繰り返してきましたし、これからもステージアップを繰り返していくのだと思います。そうやって自分の可能性に挑戦し仕事に打ち込むことが、今の私の幸せの大部分を占めています。線を面にしながらご縁を大切にしコミュニティを広げていく中で、今回の出版に機会にも恵まれました。
振り返ると、いつも転機は「人との出会い」「仕事での大直面」「キャリアビジョンを描くこと・ブラッシュアップすること」でした。みなさんにとっても、良いきっかけになれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
