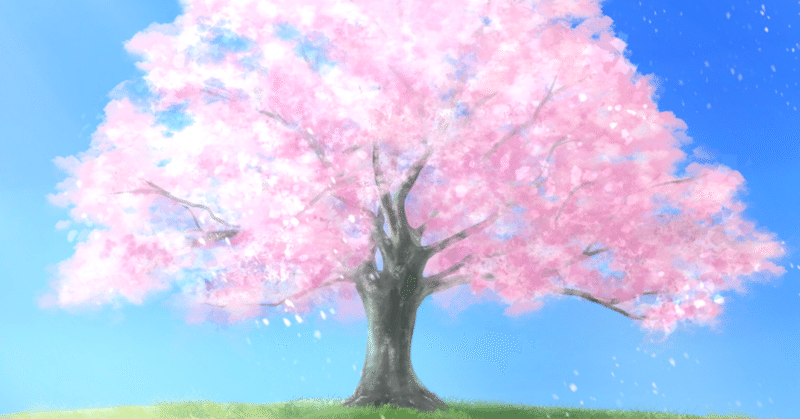
ハルタと桜色の夢。(2)
<3>
土手をもう少しのぼっていった先に、小さな古い家がありました。ぽつんと立っている家のまわりは、ひときわ強い風がふいていました。付近をとおる者はだれもいません。ガタガタと家のとびらがあき、中からおじいさんが出てきました。腰が少し曲がっていて、片手に杖をついています。ポストにたまった新聞を取り出し、家まで持ちかえろうとしたおじいさんは、地面にうずくまっている小さなアマガエルに気づきました。
「おや、こんな時期にまだいたのか」
おじいさんは、さむさでうごけなくなっているカエルを手のひらにのせると、家のとなりにある小屋へと向かいました。
ハルタが目を覚ました時、おじいさんは肘かけ椅子にすわって、たばこをふかしているところでした。ストーブにのせてあるやかんの口から、あつい湯気が出ています。部屋はあたたかく、窓ガラスは蒸気でくもっていました。
(あれ、ここはどこだ。おいら、まだ生きてるのかな?)
ハルタは目玉だけを左右にうごかして、まわりの様子をうかがいました。この人が、ピンク色のカエルに変えてくれる人なのか…。おじいさんは、髪の毛もひげも真っ白で、かおにはふかいしわが何本も刻まれています。こわそうな顔だちです。
(でも、せっかくここまで来たんだ、お願いしてみるしかない)
ハルタはお腹をふくらませると、なるべく大きな声で、おじいさんによびかけました。
「おねがいがあるんだ。どうか、おいらをピンク色のカエルにしてください」
おじいさんがちらりと、ハルタの方をみました。
「今、何かいったか?」
ひくい声でおじいさんが答えました。ハルタはもう一度、同じ言葉をくりかえしました。
「ことわる!」
おじいさんがぴしゃりと返事をしました。
「どうして?」
「どうしてもだ」
おじいさんは、目をつぶり、首をつよくふりました。これ以上ハルタの話に耳をかすつもりはないようです。ハルタはあたまの中が真っ白になりました。ドクン、ドクン、心臓が高まり、音がからだからあふれそうな気がしました。このままじゃ、ピンク色のカエルになれない、冬を越せない。お母さんとの約束が果たせないままになってしまう。
「それじゃあ、おいら、困るんだ」
ふるえる声で、ハルタはいいました。しどろもどろになっているハルタを、おじいさんがギロリとにらみつけました。ハルタはもう何も考えられなくなりました。もう一度思いっきりまわりの空気を吸いこむと、あらん限りの声でいいました。
「おいらには、どうしてもやらなきゃいけないことがあるんだ!」
お母さんが大好きだったさくらの花を自分もこの目で見たいんだ、しんでしまったお母さんの分まで、満開のさくらを見るんだ。大きなおじいさんに向かって、小さなハルタは必死にたのみつづけました。目からはボロボロと大つぶの涙がこぼれています。
「ああ、わかった、わかった」
おじいさんが、かんべんしてほしいというように、両手をあげていいました。
「もういい、もう泣かなくていい。ちゃんとおまえをピンク色にしてやるから」
ハルタが泣き止むまで、少し時間がかかりました。ヒックヒックとしゃくりあげるハルタの声と、シューシューとやかんの立てる音が、小屋の中を満たしていました。
おじいさんは、もう一本、新しいたばこに火をつけながら、昔、まだ元気だったおばあさんが、はじめて弱ったカエルをつれて帰ってきた日のことを思い出していました。
「あなたの腕のみせどころじゃないの!」
ふだんは温厚なおばあさんが、カエルを助けたい一心で、頬を真っ赤にしながらおじいさんにたのんだのです。
「おねがい、ピンク色のカエルにしてあげて。そしたらきっと、この子は幸せな夢を見られるはずよ」
その後も何度か同じように、カエルに色をぬってやったことがありました。でも、おばあさんがなくなると、おじいさんはそれをやめてしまいました。おばあさんを失った悲しみのせいで、だれかを助ける喜びを忘れていたのです。
「さあて、そろそろ始めるとするか」
たばこを吸いおわったおじいさんは立ち上がると、かべにかけてあったエプロンを身体にまきつけました。汚れたエプロンには、あか、きいろ、みどり、あお、ちゃいろ、いろいろな色がいたる所についています。
「何を始めるの?」
ハルタがたずねると、
「おまえのねがいをかなえてやるんだよ」
おじいさんが、ゆかいそうにわらいました。
「わしは絵かきなんだ。この小屋でもう何十年も絵をかいてきたんじゃ、絵かきのまほうを使えるというわけだよ」
おじいさんがひょいとハルタを持ち上げて、自分の手のひらにのせました。ゴツゴツした手のひらは、かたい岩のようです。おじいさんは作業台の上にハルタをつれていきました。
「ちょっとここでまってなさい」
そういってから、おじいさんはパレットといちばんほそい絵筆を何本か、たなから取り出しました。
「さあ、はじめるぞ。わしのいうとおりにからだをうごかすんじゃ」
おじいさんは、ハルタのせなかにそうっと絵筆をはしらせました。
「うわ、つめたい」
「うごいちゃいかん。いわれるまでじっとしておくように」
おじいさんはピンク色をハルタの肌に丁寧にのせていきました。筆にのせる絵の具の量と、ぬる部分の広さとを見比べながら、息をひそめて、おじいさんは筆の先に、気持ちを集中させました。背中がすむと、目をつぶらせてから、顔一面にうすく色をひろげます。顔がおわったら、今度は、右手、左手。後ろ足をのばした形にととのえてから、右足、左足と色づけの作業がすすんでいきます。
「ふふ、くすぐったい」
ハルタはときどき、こらえきれずにわらいました。なれてくると、絵筆でなでられる心地よさで、ねむたくなってしまいそうです。
「きもちいい」
「ようし、おわった。かわくまでそのままの姿勢でいろよ。くれぐれもうごかないように」
ピンク色になったハルタは、にっこりとわらって目をとじました。
「あとで鏡にうつして、おまえのからだをみせてあげよう」
おじいさんは、つかった絵筆やパレットを洗い場にはこびました。それから、本やものが山積みになっている机の引き出しをさぐり、奥の方からさびのついた手鏡を取り出しました。自分のすがたを見たら、ハルタはさぞびっくりすることでしょう。
(そろそろ、絵の具がかわいたころだ)
おじいさんはそっとハルタのそばに近づきました。ハルタは気持ちよさそうに寝息をたてています。小さなおなかがふくらんだり、へこんだりしています。かるく叩いても、もう目ざめる様子はないようです。
「さっそくねむってしまったのか」
ピンク色になったハルタは、さくらの花を夢みながら、長いねむりについていたのです。
あくる日、おじいさんは朝はやくに、土手にむかって坂をおりていきました。首にはえんじ色のマフラーをまいています。おばあさんがあんでくれた、思い出の品です。おじいさんの手のひらには、カエルがやさしくにぎられていました。
「この子を、どこかしずかな場所につれていってやらないとな」
ゆうべ、ねる前におじいさんは考えたのです。だれにもねむりをじゃまされない場所、目がさめたとき、春をいちばん感じられる場所はどこだろうかと。そして家からほど近い、おじいさんとおばあさんの思い出の場所にうめてやることにしたのです。
「さすがに、こんな季節にはだれもいないな」
広い土手の上には、大きなさくらの老木が一本、立っていました。木の下までやってくると、おじいさんは手のひらを木肌にあわせました。木の表面はおじいさんの手よりも、もっとかたく、もっとゴツゴツとかわいていました。でもその奥に、つよい生命の力がみなぎっていることを、おじいさんは感じました。
「ばあさんがいなくなって、もう何年になるかな」
おじいさんは、長い間さくらの木に近よろうとはしませんでした。二度と味わえないふたりの楽しい思い出が、あふれ出しそうでこわかったのです。
おじいさんは、手のひらの上でまるまっているピンク色のカエルを見つめました。
(この子もばあさんが、おれのところにつれてきたのかな)
おじいさんはさくらの木の下に、小さな穴をほりました。それからカエルを中にねかせ、上から茶色の枯れ葉を何枚もかけてやりました。これならほかの生き物に見つかることもないでしょう。
カエルが目を覚ましたところを、おじいさんは想像しました。ある日、その目にまぶしい陽の光がさしこみます。穴からおき出して空を見上げると、青い空いっぱいに、さくらの花たちがゆれているのです。
「来年の春は、わしもおまえといっしょに、さくらの花をみるとするか」
おじいさんはそういうと、家へとかえっていきました。
(完)
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。サポートしていただけるなら、執筆費用に充てさせていただきます。皆さまの応援が励みになります。宜しくお願いいたします。
