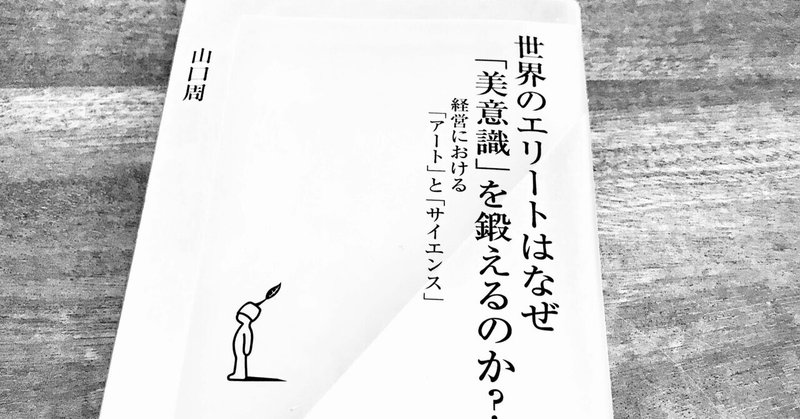
【読書】我が身に強い、芯を作れ〜アートの重要性〜
スキルを磨くのも大事だが、
クリエイティブとは新しい考え方を
提示することなのだ。
人工知能が進化する今後、
スキルだけで生き抜くのは
難しいと思うのだ。
佐藤可士和(日本経済新聞4/26~30
夕刊「こころの玉手箱」連載より)
人生を変えたと自ら気づける本に
出会うことは多くはないですが、
皆無でもありませんね。
先日、貴重な出会いがありました。
文学を読むのはビジネス書を読むより
ある意味において大切なことだ。
他人となって他人の生き方を
追体験出来るのだから。
それに、
すぐ役立つものは、すぐ役立たなくなる。
芸術は蔑ろにしてはいけない。
欧米ではリベラルアートとして
重んじられている。
こんな話は耳にタコが出来るほど
聞かされてきたことでしょう。
芸術が大切だと言われていることは
知っています。
でも、「どうして」の部分が
しっかり腑に落ちる説明をしてくれる人が
これまでいなかった。
どうしてビジネス書より
文学が大切なの?
娯楽色の強い文学より
ビジネスに役立つハウツー本の方が
優れているでしょう?
芸術は好きだけど
何に役立つの?
心の安定になる。癒しになる。
感動する。
それは分かるけど、
別のものでも良くない?
これを説明してくれる本が
こちらでした。
感銘を受けすぎて、
私の読書記録が長文になっています。
これをどうやって記事にしよう。
何日も悩みました。
うわ~ん😭タルイさ~ん😭
※タルイタケシさんは
良書の記事を分かりやすく、かつ
魅力的に書かれる
スペシャリストです。
ファーストリテイリングは
アートをないがしろにしないために、
クリエイティブディレクター佐藤可士和氏
などに権限移譲して
アートのガバナンスを形成している。
無印良品はプロダクトデザイナーの
深澤直人氏が外部アドバイザーとして
関わっている。
ソフトバンクの外部アドバイザーは
広告で知られる大貫卓也氏。
この本によると、
日本を代表する企業がこぞって
アートを重用していることが分かります。
ウィンストン・チャーチルと
アドルフ・ヒトラーは
本格的な絵描きだった。
ノーベル賞受賞者は、一般人と比較した場合、
2.8倍も芸術的趣味を保有している
確率が高い。
アートって、大切なんですね。
じゃあ、どうして?
もっと具体的に、知りたい。
今は、豊かな時代ですね。
教育も、特に日本では
誰もが受けている。
その中で、論理的、理性的な
学び(つまりビジネス書など)というのは、
コモディティ化する(みんな同じになる)
そうです。
これは、私がマーケティングを学んでいても
気づいたことです。
マーケティングは今や
ビジネスマンにとっての常識です。
だから、マーケティングを学んだ者は
皆、同じように考える。
マーケティングの基本は
「差別化」なのに、
皆同じ、つまり「コモディディ化」
してしまうんです。
なんというパラドックスでしょう。
論理と理性に軸足をおいて経営をすれば、
必ず他社と同じ結論に至る。
論理的、理性的な学び、
これは、無くてはならないです。
でも、これだけだとコモディティ化する。
経営の意思決定のクオリティは
アート(なんとなく=天才性)、
サイエンス(事実と論理)、
クラフト(過去の実績に基づいた主張)の
バランスが必要だ。
ビジネス書で学ぶサイエンスは必須です。
過去の実績や伝統を重視するクラフトも
大切です。
でも、アートつまり、なんとなく。
これがないと、現代においては
コモディティ化してしまう。
また、現在は
時代の流れがとても速いです。
法が出来るより先に、
システムが変化する。
例えば車の自動運転。
SDGsのための水素の開発。
これに法律が、制度が追いつかない。
じゃあ、法が追いつく前に
法の穴をくぐって悪行をしても
悪ではないのでしょうか。
これは、遡って悪になる。
画期的なイノベーションが起こる過程では、
論理と理性を超越するような意思決定が
行われている。
法律がまだ存在しない時、
誰も何が善で何が悪か分からない時に、
善悪の判断を正しく出来る
高度な意思決定の能力が必要です。
だから、内在的に真善美を判断するための
美意識が求められる。
トップにアート、
両翼にサイエンスとクラフトが理想的。
スティーブ・ジョブズとジョン・スカリー。
ビジョンのウォルトと財政&リーガルのロイ(ディズニー)。
本田宗一郎と藤沢武夫のホンダ。
かつて地下鉄サリン事件を起こした
オウム真理教の信者は
高学歴の者が多いことで有名でした。
彼らを調べたところ、
偏差値は高いけれども、
文学を読んでいない者が
圧倒的に多かったそうです。
サティアンは殺風景で美意識など無く、
彼らの曼荼羅は稚拙すぎたそうです。
つまり、
オウム真理教にはアートが無かった。
その内部は、受験のような
言われた通りに修行すれば
高みへ行ける、誰にでも明確な
階層があったそうです。
学生までは、他人の指示通りに
勉強すれば良い。
しかしながら、社会に出たら現実は
不条理、理不尽に溢れている。
どれが正解かなんて、
誰にも分からない。
その中で「清濁併せ呑むバランス感覚」を
どうやって身につけるか。
アートです。
何が正しいのか分からない
不安定な時代に、我が身に、
オリジナルの強い芯を作る。
それでアート?
ちょっと軽率すぎない?
と思いますか。
もっと科学的に説明しましょうか。
脳内で美を感じる役割を担っているのは
前頭前野です。
高度な意思決定も前頭前野で行っています。
つまり、前頭前野を美しい絵画や音楽、
詩や文章で鍛えると、
意思決定の能力もついてくるのです。
人に言われなくても
法律が存在しなくても
善悪を間違えない、高度な意思決定能力。
主観的な内部のモノサシを鍛えるために
美意識を鍛える。
じゃあどうするか。
1つには、美術鑑賞。
1つの絵を見て何が描かれているか、
これから何をするところかなどを観察し、
話し合う。
そうすると、
皆が違う視点を持っていることに気づく。
1つには、哲学を読むこと。
時代を反逆的に見ていたのが哲学者です。
その時代背景でその哲学者が
どうやってこの思考に至ったのかを
考えながら、読む。
1つには、文学を読むこと。
自分なりの真善美の感覚に照らして、
誰の生き様や考え方に
共鳴するかを考えることで、
自分のアンテナの感度を磨く。
1つには、詩を読むこと。
詩には比喩が多用されているが、
人を引きつける魅力あるスピーチは
大抵比喩が使われている。
比喩が持つ、人を酔わせる力をつける。
冒頭で紹介した佐藤可士和さんは
Tポイントカード、ユニクロ、
セブン&iホールディングス、
くら寿司などのロゴをデザインした
時代の寵児とも言われる方です。
折しも、この本と同じことを
言っていますね。
私は学生の頃から
芸術ばかりが好きで、
科学的なもの
この本でいえばサイエンスに
あまり興味を抱かない自分に
後ろめたさを感じていました。
この本によれば、
確かにサイエンスも重要ですが
アートも決して
蔑ろには出来ないので
嬉しく思っています。
ありがとうございます!頂いたサポートは美しい日本語啓蒙活動の原動力(くまか薔薇か落雁)に使うかも?しれません。
