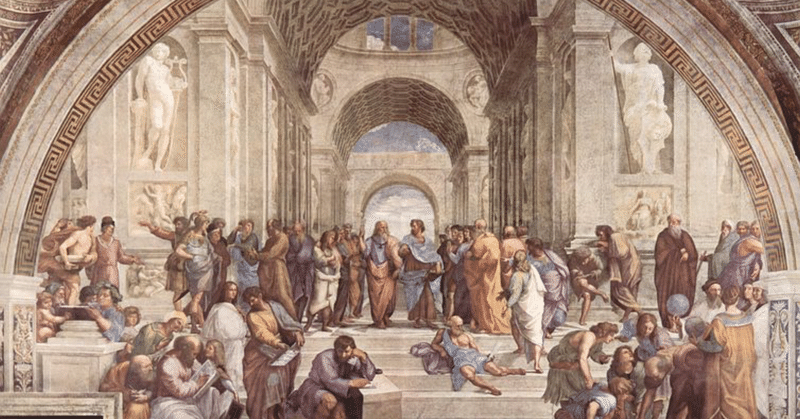
今日も、読書。 |今の私にできる、暇と退屈との戦い方
なんとなく暇だ。理由は分からないが、なぜか満たされない。
誰しも、そんな感覚を抱いたことがあるだろう。日常の中で、ふとした瞬間に押し寄せる「暇」と「退屈」の波。はっきりとした原因も、解決するための対策もわからない……。
今回ご紹介する國分功一郎さんの『暇と退屈の倫理学』は、そもそも「暇」「退屈」とは何か?という根本的な問いから、「暇」「退屈」とどう向き合うべきかという実践的な問いまで、「暇」と「退屈」について、これでもかと深く哲学する本である。
著者の國分さんは、偉大な先人哲学者たちの著書を引用・考察しながら、新たな「暇」と「退屈」の概念の創造を試みている。
國分功一郎|暇と退屈の倫理学

「暇」とは何か。人間はいつから「退屈」しているのだろうか。答えに辿り着けない人生の問いと対峙するとき、哲学は大きな助けとなる。著者の導きでスピノザ、ルソー、ニーチェ、ハイデッガーなど先人たちの叡智を読み解けば、知の樹海で思索する喜びを発見するだろう—―現代の消費社会において気晴らしと退屈が抱える問題点を鋭く指摘したベストセラー、あとがきを加えて待望の文庫化。
「哲学」と聞くと堅苦しいイメージを抱くかもしれない。かくいう私もそうだった。
今年の春頃に永井玲衣さんの『水中の哲学者たち』という哲学エッセイを読み、なんとなく「哲学って面白そう」とは感じていたが、ニーチェとかハイデッガーとか哲学者の名前が登場してくると、「すみませんでした」と謝りながら退散せざるを得なかった。
本書は、本格的な哲学の議論が、非常にくだけた文体で書かれており、読みやすい。
國分さんは東大の准教授というすごい方だが、「まえがき」での一人称が「私」とかではなく「俺」だったり、偉大な哲学者にガンガン突っ込みを入れていったりと、ユーモアに満ち溢れている。
親しみやすい文章で、難解になりがちな哲学の議論を、初心者にも分かりやすく論じてくれている。
この本は俺が自分の悩みに答えを出すために書いたものである。自分が考えてきた道がいかなるものであるかを示し、自分が出した答えをいわば一枚の画として描き、読者のみなさんに判断してもらってその意見を知りたいのである。
上記引用は、冒頭部分に書かれた本書の目的である。著者の、読者に寄り添ってくれる優しい姿勢が伺える。
退屈の起源について
ぜひ実際に読んでみていただきたいのだが、ここでは私が印象に残ったことを書き連ねてみる。
まず、退屈の起源。そもそも退屈に起源があるのかというところから新鮮だったが、本書によれば、「定住化」の革命が人類に退屈をもたらしたのだという。
遊動生活から定住生活に移行したことで、人類は文化という営みを発展させていくのだが、それと同時に、退屈との戦いを強いられることにもなったという。
そして資本主義が発達した近代、それまでは上流階級の特権だった暇が、一般人にも「余暇」という形でもたらされ、ひとつの権利となった。
長い歴史を経て、突然暇の中に投げ込まれた近代人たちは、自分たちが何を求めているのか、どう対処すべきなのかが分からなかった。
突然もたらされた「退屈」に、私たちは太刀打ちする術を知らなかったのである。
休めない余暇
レジャー産業の役割とは、何をしたらよいか分からない人たちに「したいこと」を与えることだ。レジャー産業は人々の要求や欲望に応えるのではない。人々の欲望そのものを作り出す。
消費社会は私たちを浪費ではなくて消費へと駆り立てる。消費社会としては浪費されては困るのだ。なぜなら浪費は満足をもたらしてしまうからだ。消費社会は、私たちが浪費家ではなくて消費者になって、絶えざる観念の消費のゲームを続けることをもとめるのである。消費社会とは、人々が浪費するのを妨げる社会である。
余暇はいまや、「俺は好きなことをしているんだぞ」と全力で周囲にアピールしなければならない時間である。逆説的だが、何かをしなければならないのが余暇という時間なのだ。
近代社会に突如としてもたらされた暇と退屈を、うまく操って稼ぎを生み出すのがレジャー産業だ。
このあたりの主張は、自分自身の行いを振り返ってみると、納得せざるを得ない。
たとえば、読みたい本を選ぶとき。
自分の嗜好や感性に基づいて本を選んでいるつもりでも、実はSNSの広告で目にした本を手に取っていたり、芸能人や書店員の評価を参考にして本を選択していたりする。
自分の欲望は、知らず知らずのうちに操作され、作り出されている。
そして、本を読み終えたらSNSで読了報告をし、感想を周囲に発信する。やがて、「本を読んだからTwitterを更新しなくては」という思考になる。
私が今まさに書いているこのnoteだって、同じかもしれない。何かをしなければならない、周囲に知らせなければならない、という思いに縛られてしまうのが、現代社会の余暇である。
暇と退屈との戦い方
暇や退屈に、どう向き合うべきか。『暇と退屈の倫理学』は、3つの結論を導き出して、幕を閉じている。
読者はそれらの結論と、そこに至るまでの議論のプロセスを読み、自分なりの暇と退屈への処方箋を考える。
本書の結論が絶対的な正解ではないし、本書を読んで私たちがどのように感じるのかを知りたいというのが、國分さんの想いだ。ここから先の暇と退屈の哲学は、自分たちで突き詰めていくしかない。
私は、毎日何かひとつでも、自分の心がほんの少し沸き立つような、ちょっとした「変化」を取り入れたいと思っている。
私は、同じような時間が繰り返されると、強い退屈を感じる。単調で刺激の少ない生活が何日も何日も続くと、どうしようもない虚無感に苛まれる。
だから毎日、最低1つ、前日と異なる要素を生活に取り入れる。その変化が、昨日でも明日でもない「今日を過ごした意味」となってくれる。
しかし、私は基本的に「変化」が苦手である。
身の回りの環境が大きく変化すると、それに適応するのに膨大な時間を要するし、ストレスで疲れてしまう。そのため、取り入れる変化は本当に些細なものでいい。
たとえば、仕事に向かう電車の中で、普段は全く読まない物理学の本を読んでみる。理系の世界に触れることで、前日とは少しだけ違う通勤になる。
週末に通っているカフェの、ほんの少し先にある別のカフェを訪れる。友達と電話する。ちょっと豪華な食事をテイクアウトする。そんな些細なことでいい。
等身大の生活の中で、身の丈に合った変化を取り入れる。もしこれでも退屈してきたら、ちょっと遠出して、気分転換してみてもいい。
過剰な変化に疲れたら、あえて部屋に籠もって、本を読み続けるだけの日々を過ごしてもいい。現代社会の余暇のように、何かに縛られてしまうのが最も怖い。
「今日は昨日と違う1日だった」、そう感じられる日々を過ごすことが、今の私にできる、暇と退屈との戦い方である。
◇「今日も、読書。」のイチオシnoteはこちら◇
◇「今日も、読書。」の他のnoteはこちらから◇
◇本に関するおすすめnote◇
◇読書会Podcast「本の海を泳ぐ」配信中◇
◇マシュマロでご意見、ご質問を募集しています◇
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
