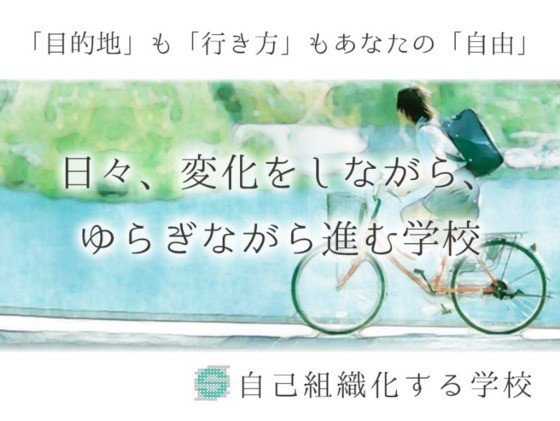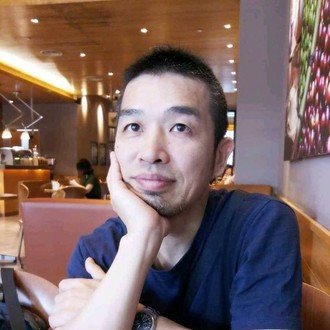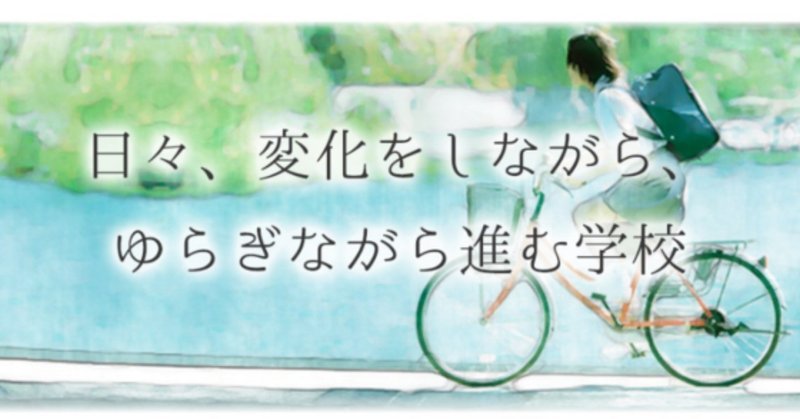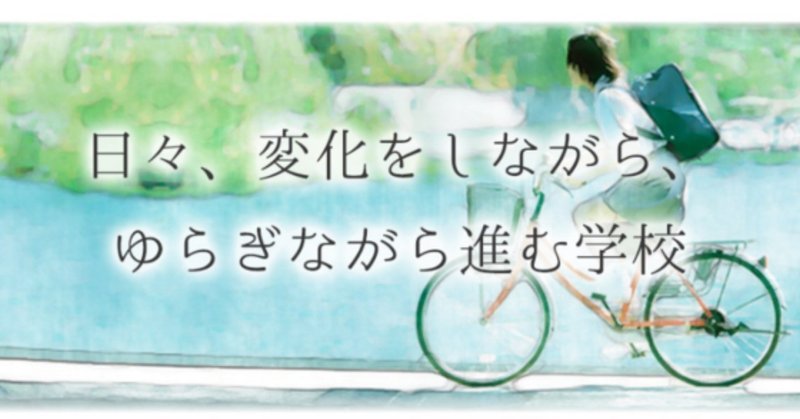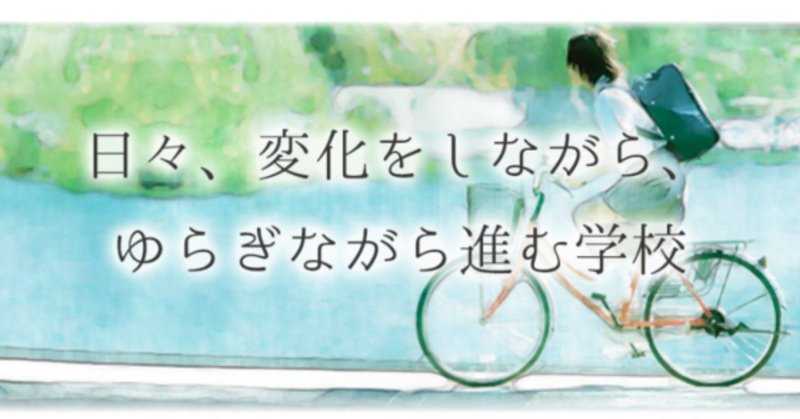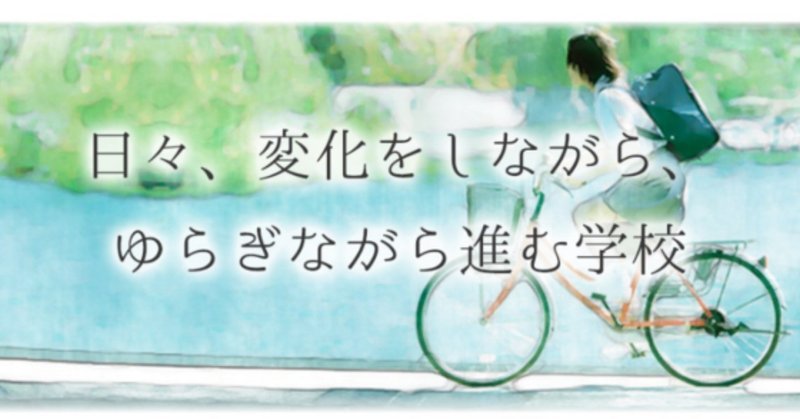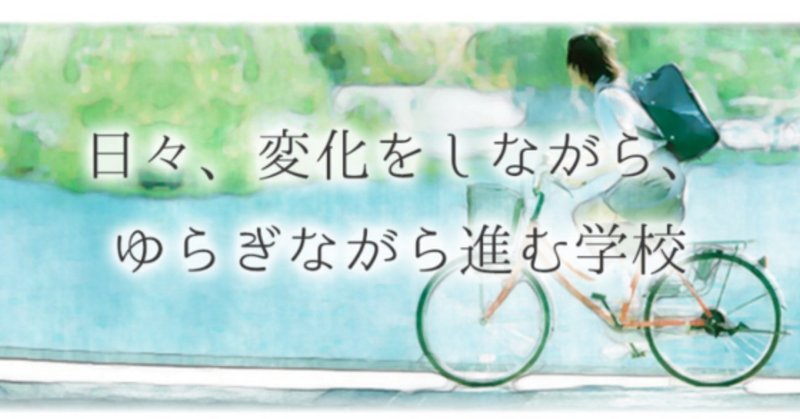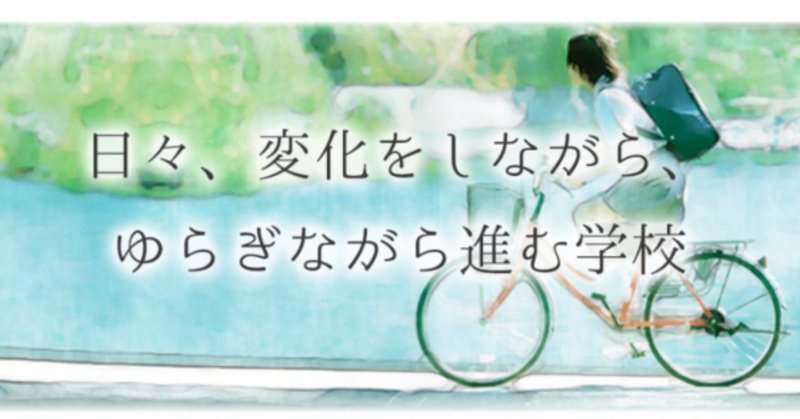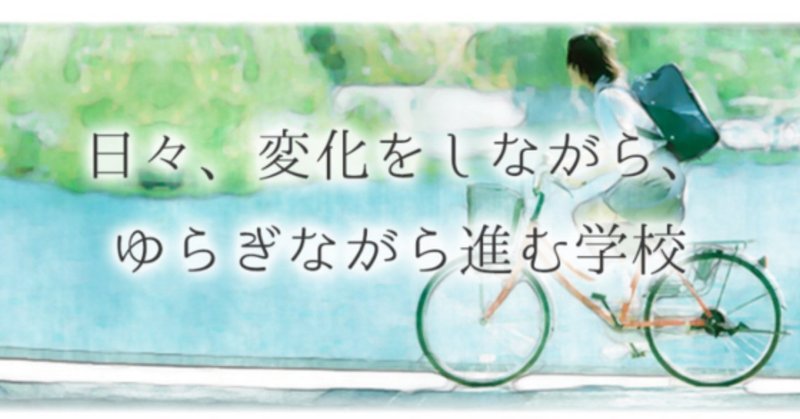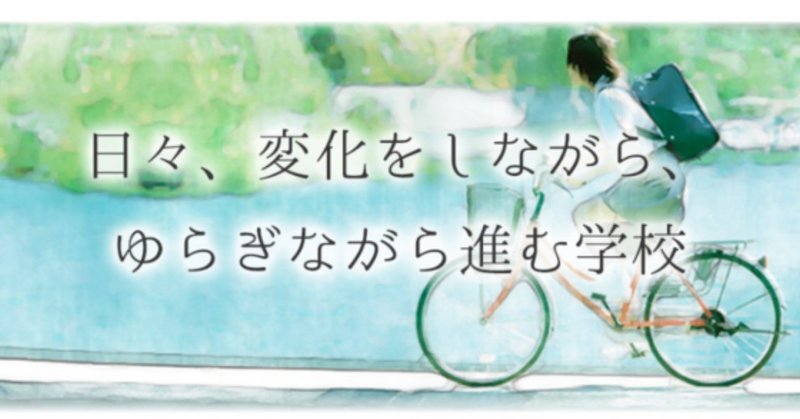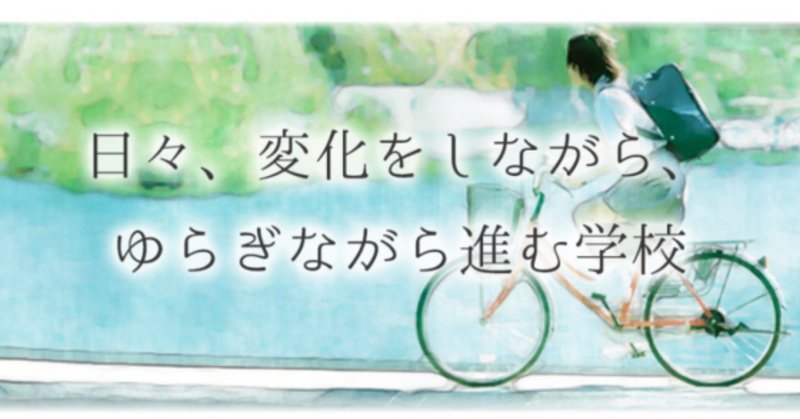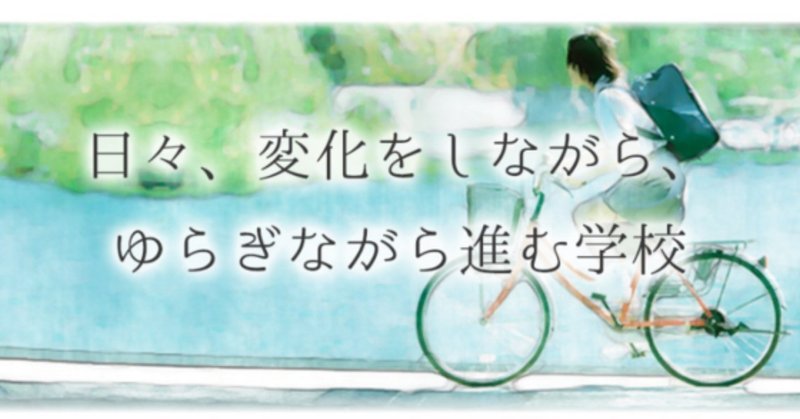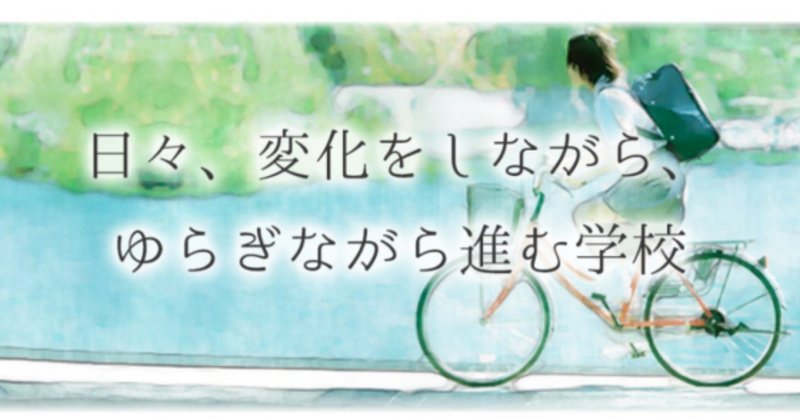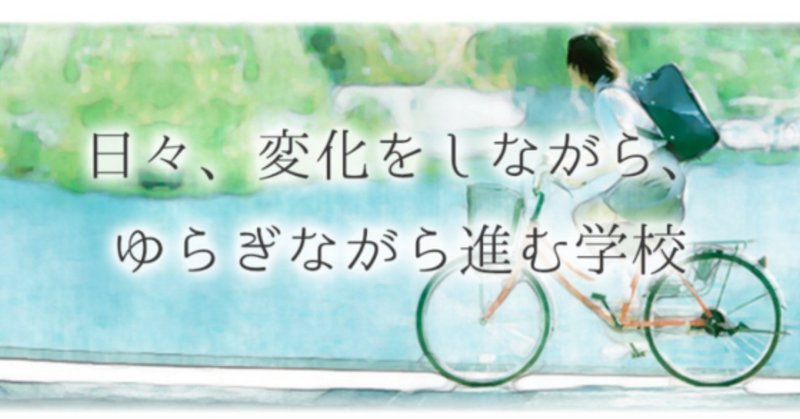#アクティブラーニング
学校が自己組織化する #12 ジコヨビ
フリースクールを経営している江川和弥さんと話をしていて、高校には行かずに大学進学を目指す生徒向けに学習サポートをすることができる場所を作ろうという話になりました。
僕自身は、物理ネット予備校(フィズヨビ)というものを2005年からやっていて、2015年からは、オンライン反転授業という形で対話型の学びに挑戦し、参加者のやる気に火がついて、自ら動き出す場創りに手応えを感じていたので、それを土台にして
学校が自己組織化する #11 子どもの創造性
オンラインの対話を重ねる中でいくつかの企画が立ち上がりました。
最初に始まったのは、「多様な学びプロジェクト」を主宰している生駒知里さんを中心とした小学生向けのSDGs講座。
「オンラインで水をテーマにSDGsを学ぼう!」は、平日の11時からという時間帯に実施したこともあり、フリースクールに通っている子や、ホームスクーリングしている子、海外在住の子などを中心に、13人の小学生が参加してくれまし
学校が自己組織化する #10 パワー&ラブ
3月に毎日対話を重ねているうちに、参加者も200名を超えてきました。
200人でどうやって合意形成をしながら、学校を作っていけばいいのか?
学校を自己組織化するというのは、どういうことなのか?
そのヒントになったのは、ホラクラシー組織やティール組織の考え方でした。
ティール組織では、1)自主経営 2)全体性 3)進化する目的 の3つが柱になります。
自己組織化する学校では、各曜日のグルー
学校が自己組織化する #9 対話の土壌生態系
Facebookの投稿に反応してくれて最初に集まった180人が、次々に自己紹介を始めました。
一人一人の自己紹介が長文で、そこにそれぞれの想いが込められているのを感じました。
様々な人の想いが実現するには、どんな感じだったらよいのだろうと思い、多くの人の声に耳を澄まして全体像を描いてみました。
2月は、それぞれがやりたいことに耳を傾けるかたちで、ミーティングを重ねました。何しろ、お互いに知ら
学校が自己組織化する #8 すべての違いを学びの源にする
311の後に僕が体験したのは、「同じ」で表面的に繋がっているだけの関係性は、「違い」が表面化したときに、あっという間に壊れていくのだということでした。
それは、なぜなのか?
じゃあ、どうすればいいのか?
それを、7年間、ずっと考えてきました。
「違い」が表面化すると関係性が崩壊するから、学校でも、会社でも、表面的に「同じ」を装い、仮面をかぶり続けてしまう。
仮面の下で、表現できない本当の
学校が自己組織化する #7 自己組織化コミュニティ
「反転授業の研究」の体験を通して、オンラインコミュニティの自己組織化の大きな可能性を感じていた2015年、1冊の本に出会いました。
ボブ・スティルガー著『未来が見えなくなったとき、僕たちは何を語ればいいのだろう』
これは、社会変革ファシリテーターのボブさんが、311の後の福島で行ったラーニングジャーニーについて綴ってある本でした。この本に書いてあることの中で、僕の心を打ったのは、次の考えでした
学校を自己組織化する #6 ネット果樹園
2013年に始まった「反転授業の研究」は、主体的な学びに関心のある教師や、教師以外の教育関係者が半分で、それ以外が半分で、多様性のあるコミュニティでした。
「ここに多様性に満ちた森を創ろう」と呼びかけ、お互いが与え合うことで集合知が生まれ、循環が生まれるはずだと思って運営を始めました。
毎月、無料のオンライン勉強会をやり、一歩踏み出した人にスポットライトをあて、インタビュー記事を書いて、実践の
学校が自己組織化する #5 コネクティングドッツ
グループで集まって学ぶと、どんなふうに学べるんだろう?
そのような問いを抱えて、「反転授業の研究」で、いろんな人とやり取りしているうちに、集合知という言葉と出会い、集合知を生み出すワークショップの手法としてワールドカフェというものと出会いました。
ワールドカフェというのは、グループのメンバーを2-3回、交代しながら、ファシリテーターが出す問いについてグループで話し合うという手法です。
テーブ
学校が自己組織化する #4 小林昭文さん
2005年から動画を使った学びに取り組んできて、その効果について自分なりに理解しているつもりでした。
僕の受講生は、動画を倍速再生で視聴して全体像をつかみ、その後、最初から再生して、今度は、必要なところで一時停止して問題演習し、理解を深め、分からないところは画面キャプチャして質問を送ってくるという方法で学んでいました。
予備校での生講義は臨場感という点では動画に勝りますが、理解から定着までのプ
学校が自己組織化する #3 反転授業との出会い
日本人として、ずっと日本に住んできたけれど、そこで身につけた考えを根底から見直したいという気持ちと、自分の娘を日本の教育システムに乗せて大丈夫なのか?という疑問に突き動かされ、2011年の8月に日本を旅立ってしまったわけですが、海外生活は初めてだし、英語が得意なわけじゃないし、勢いに任せての決断でした。
10年以上やっていた河合塾の物理講師を辞め、ネット予備校の収入だけが頼りになったんですが、海
学校が自己組織化する #2 オンライン教育をはじめたきっかけ
大学院生をやっていた5年間に中高一貫の私立学校で数学を教え、大学院を中退後、予備校講師になった私は、その頃から数えると、教育にかかわるようになって24年になります。
教育にかかわるようになった最初の頃は、自分が教わった経験を元にして、授業をしていました。分かりやすく教えるということに意識が向いていました。
予備校講師になると、「分かりやすい教え方」が自分の商品になるので、どれだけ分かりやすく、
学校が自己組織化する #1 311から始まった
僕が学校教育について問題意識を持ち始めたきっかけは311でした。
当時、仙台に住んでいた僕は、東日本大震災と原発事故が起こり、どうやって捉えたらいいかも分からないような混乱の中で、毎日、海外の情報と日本の情報とを見比べながら、僕と家族は、どうしたらいいのか、不眠不休で考える日々でした。
海外の報道と見比べると、日本の報道は、情報を小さく伝えて収束させようとしているように見えました。「実は。