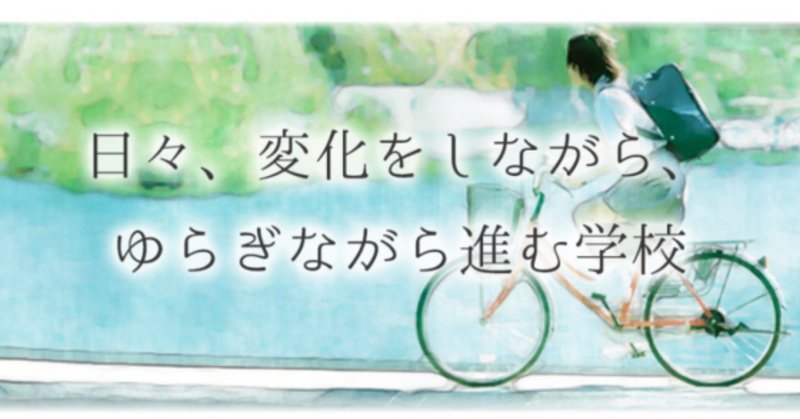
学校が自己組織化する #4 小林昭文さん
2005年から動画を使った学びに取り組んできて、その効果について自分なりに理解しているつもりでした。
僕の受講生は、動画を倍速再生で視聴して全体像をつかみ、その後、最初から再生して、今度は、必要なところで一時停止して問題演習し、理解を深め、分からないところは画面キャプチャして質問を送ってくるという方法で学んでいました。
予備校での生講義は臨場感という点では動画に勝りますが、理解から定着までのプロセスを考えたときは、動画講義は学習ツールとして優れていると感じていました。
そして、一度作ってしまえば、何度再生してもコストがかからないので、生講義よりも圧倒的にコストパフォーマンスがよいのです。教師が、単に「教える人」であれば、その仕事は動画に置き換わっていくということが、自分自身が動画講義を作ってきたからこそ、実感として理解することができたのです。
じゃあ、生身の自分は何をする?と考えたときに、そのヒントが「反転授業」にありました。
反転授業とは、旧来の授業における教室と家庭学習との役割(教室で知識を獲得し、家庭学習で定着させる)を反転し、家庭学習で動画などを使って知識を獲得し、教室でグループ対話などを通して定着するというものです。
はじめて「反転授業」のことを聞いたとき、教壇に立って大勢の生徒の前で授業をする一斉講義型の授業しか経験がなかったので、グループ対話の部分が、全く想像できませんでした。
グループで話すことが、どのように学びに繋がるのか?
僕自身に体験がなかったので、ぴんと来なかったのです。
「反転授業の研究」で、アクティブ・ラーニングを実践している人から話を聴く勉強会を重ねていくうちに、少しずつイメージが明確になってきました。
僕にとって幸運だったのは、アクティブ・ラーニングの伝道師の一人である小林昭文さんが、物理教師だったため、小林さんのやり方をたたき台にして授業をしてみるという取り組みがしやすかったことです。
小林さんが教室でやっているアクティブ・ラーニングを、オンラインでやるためにはどうしたらよいかを考え、WizIQというWeb教室システムを使って、オンラインのアクティブ・ラーニングを始めました。
その中で、僕自身の言葉よりも、受講者同士のやりとりによって、彼らがモチベーションを高め、心を動かし、学び合う姿を目の当たりにしました。
その体験を通して、自分の授業を根底から変えてみようという気持ちが生まれました。
「自己組織化する学校」クラウドファンディング実施中
現在33% 残り24日
https://readyfor.jp/projects/17284
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
