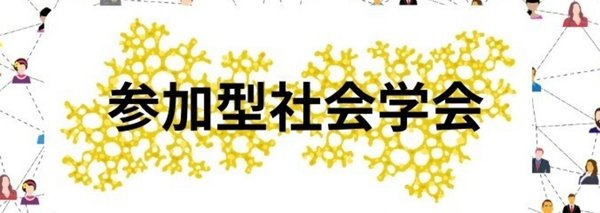田原真人
生命体の可能性が花開くことに喜びを感じるデジタルファシリテータ。非暴力アナキスト。20…
最近の記事

「ハブの原理」が作動するアジール空間では、「ハコの原理」で傷ついた心が癒される:ワールドアジールネットワークに流通する雑誌で世界を癒したい
フランスの思想家ミシェル・フーコーやアラン・バディウは、アジールを社会の支配構造から逃れるための空間や、支配的な権力から独立した行動が可能な場所として捉えました。この文脈では、アジールは単なる避難所ではなく、社会の中で自由や独立性を維持するための象徴的な空間と考えられます。 今から思えば、僕がZoomを使って作ってきたオンラインコミュニティは、アジール的な空間でした。リアルのしがらみから離れ、役職の仮面を外して個人として集まった多様な人たちが、日常では語れないことを語ってい
マガジン
記事

文明の時代が「ハコの原理」なら、文化の時代は「ハブの原理」:新しい文化が生まれているハブを相互に繋いで、次の時代を創造する雑誌を作りたい。
人口波動論を提唱する古田隆彦先生の「人口が増加するときに文明が生まれ、人口が減少するときに文化が生まれる」という言葉が、コロナ後の数年間、ずっと頭の中にあります。 橘川幸夫さんは、かつて書籍で「ビジネスの原理は、コピペとピンハネだ」と書いていました。成功事例をマニュアル化して、コピー&ペーストするように横展開していき、フランチャイズから上納金を受け取るというのが、大きな利益を上げる常套手段だというのです。 産業革命などの技術革新が起こると、新しい方法論による新しい文明が生