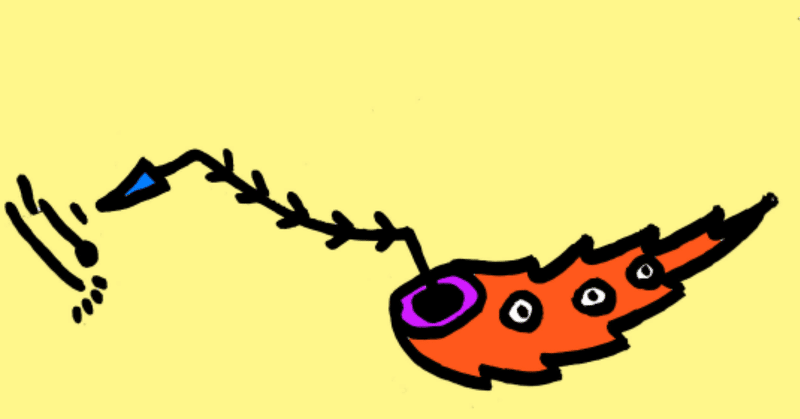
発達障害に対する、いまの私のスタンス〜「発達障害」と診断された人のための「発達障害」の説明書②〜
一緒に作るマガジン
前回から、【「発達障害」と診断された人のための発達障害の説明書】と題して、マガジンの作成を始めた。
このマガジンは、『一緒に作るマガジン』という設定にしている。
「受け身ではない、主体的な学びの機会を作りたい」
という思いからの『一緒に作るマガジン』。
マガジンの作成に読者が参加してもらうことで、きっと、受け身ではない、主体的な学びの機会が作れる。
このマガジンで扱う内容は、「今まで誰も言ったことのないことを言う」とか、「段違いにわかりやすい」とか、そんなことはおそらくないのだけれど、参加型で、一緒に作っていくという点だけは、チャレンジングで価値ある試みであるように感じている。
たとえば、もし何か質問が出たら、次回はその質問について取りあげた記事を書きたいし、もし発達障害について書いた記事を紹介されたら、次回はそれについて一緒に考えたい。
そんな風に、発達障害のことについて一緒に考え、理解を深めていきたい。
そんな風にして行う皆さんとのやりとりこそ、リアルな「発達障害」の説明書になり得ると考えている。
「発達障害」の説明書、よかったら、一緒に作りましょう。
発達障害に対する、いまの私のスタンス
これから「発達障害」について考えていくにあたって、まずは、現時点での私の「発達障害」に対するスタンスを表すところから始めてみたいと思う。
ただ、あくまでこれは現時点での私のスタンスであり、変わっていく可能性を十分に含んでいるものである。
むしろ、私としては、ここで、いろいろな人たちと交流したり議論したりしながら一緒にマガジンを作ることを通して、今の自分の考えやスタンスが少しでも変わっていくことを望んでいる。
そして同様に、マガジン作成に関わってくれた人たちの考えやスタンスにも、何らかの変化が起きることを期待している。
何かに触れて、自分の中に動きが生じ、その結果自分に何かしらの変化が起きる。
それが、主体的に学ぶということだと思うからである。
この「一緒に作るマガジン」は、主体的な学びの機会を作るマガジンでありたい。
発達障害とは?~本マガジンで取り上げたい発達障害~
それでは本論に入る。
まず、発達障害の定義と、本マガジンで取り上げたい発達障害について、簡単にまとめてみようと思う。
発達障害とは何か。
発達障害を医学的に見ると、『神経発達症群』に属する疾患群と言える。
『神経発達症群』は、神経発達を原因として、発達の偏りや遅れを示す症候群である。
神経発達症群には、自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害(LD)などが含まれ、知的障害も含まれる。
一方、日本の発達障害者支援法における発達障害の概念は、医学的な『神経発達症群』とは少し異なっている。
発達障害者支援法(2004年施行)第2条
この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう
大きな違いは、知的障害が発達障害に入るか否かというところであるが、発達障害者支援法に知的障害が含まれないのには理由がある。
発達障害者支援法は、これまで福祉サービスの対象となっていなかった発達障害者にきちんとサービスを届けようということで動き始めたものである。
日本において知的障害者は「知的障害者福祉法(1960年施行)」によって従来から福祉サービスの対象となっていたため、発達障害のカテゴリーに含めないことが多いということである。
少し話が逸れたが、発達障害の定義としてよく引用されるのはこのあたりだろうと思う。
そして、本マガジンで考えていく発達障害の対象としては、医学的な『神経発達症群』の中から、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、限局性学習障害(LD)、知的障害、発達性協調運動障害(DCD)について取り上げたいと思う。
発達特性がある人≠発達障害
次に、発達特性と発達障害の捉え方について、私のスタンスを示そうと思う。
発達特性とは、もともと「誰もが持つ発達上の特徴や性質」という意味があるが、最近は、「発達の偏りや遅れ」を指して「発達特性」と表現されることが多い。
本マガジンでも、便宜上、「発達の偏りや遅れ」のことを「発達特性」として話を進めていきたい。
発達障害と発達特性を考える上で、私は、
『発達特性がある人≠発達障害』
という立ち位置をとっている。
以下で詳しく説明したい。
発達障害の診断はどのようになされている?
そもそも発達障害というのは、どのように診断されているのか。
現在、精神科領域の診断のほとんどは、アメリカの精神医学会が出版しているDSM-5という手引きを用いてなされている。
そのDSM-5の診断基準は、たとえば自閉スペクトラム症(ASD)であれば以下のようになっている。
以下のA、B、C、Dを満たすこと
A:社会的コミュニケーション及び相互関係における持続的障害
B:限定された反復する様式の行動、興味、活動
C:症状は発達早期の段階で必ず出現するが、後になって明らかになる物もある
D:症状は社会や職業その他の重要な機能に重大な障害を引き起こしている
これらA、B、C、Dをすべてを満たせば、自閉スペクトラム症(ASD)と診断することができる、ということである。
ここでのAとBは、ASDの発達特性に関する記載である。
Aは、ASDの空気の読めなさやコミュニケーションの苦手さに関する部分。
Bは、ASDのこだわりに関する部分。
Cは、生まれつきのものですよ、という記載。いわゆる神経発達症群に含まれますよという前提の部分。
そしてD、ここに注目したい。
D:症状は社会や職業その他の重要な機能に重大な障害を引き起こしている
他の発達障害の診断でも、このDと似たような記載がある。
つまり、発達特性があることで、社会にうまく適応できない状態にある、というような記載。
ここから言えることは、AとBを満たしていたとしても、Dを満たしていなければ、発達障害とは診断されないということである。
言いかえるなら、発達特性があっても、社会や職業その他の重要な機能に重大な障害を引き起こしていなければ、発達障害ではないということである。
発達特性は、発達障害者の個性や強みとなり得る部分でもある。
発達特性を持ちながら、発達特性を活かしながら、社会で活躍する人たちがいる。
ASDのこだわりという発達特性を活かして研究者として活躍する人がいる。
ASDの人は他者の気持ちがわかりづらいとか感情表現が苦手とか言われることも多いが、ASDの人に学術論文や説明文を書かせたら右に出るものはいない。
感情や個人的な思いなどの余計なものが入っていない、横道に逸れることのないスッキリとした文章は、何かを説明するための文章として大変優れている。
ADHDの多動と注意の移りやすさという発達特性を活かして起業家として活躍する人がいる。
ADHDの人は、色々なものにアンテナが向いていて、アイデアが次々と思いつく。思いついたらすぐ行動、そんなADHDの特性を活かして様々な事業を興し、成功を収める人は多い。
知的障害の特性と直接的な関連があるかはわからないが、知的障害の人は色彩感覚が豊かであり、芸術家として活躍する人も多い。
LDとDCDは…どうだろう。
でも、発達特性を何が何でもプラスに転換させようと無理をする必要もないような気がしている。
ある発達特性があって、それをプラスに活かせそうであればプラスに転換させてもいいし、支援を受けたり、別のやり方をすることで社会に適応できるのであれば、それでいい。
発達特性なんて、その子を構成するほんの一部であって、きっと発達特性に関連しない部分でも、その子の良さというのはあるだろうし、全体としてその子がその子らしく生きることができればいい。
つまり、支援者としては、発達特性があっても、その子がその子らしく社会の中で生きることができるように支援をするということである。
支援の結果、その子がその子らしく社会の中で生きられるようになり、もしDの項目にチェックがつかないようになれば、その子はもう発達障害ではない。
伝えたいことは、自分の発達特性を理解し、自分のことを理解し、自分らしく生きられるようになって、発達障害から卒業、という道もあるということ。
発達障害という診断があった方が、受けられるサポートや資源もあったりするので、必ずしも発達障害から卒業することを推奨するものでもないけれど、考え方としてはそのような考え方もあるということを伝えたかったし、私は、発達特性と発達障害は分けて考えたいというスタンスで、支援を行っている。
読者の皆さんはどうだろうか。
次回予告(仮)
これから数回に分けて、私の発達障害に対するスタンスについて書いていくつもりである。
その後、自閉スペクトラム症、ADHD、LD、知的障害、DCDをひとつずつ、それぞれピックアップして取り上げていきたいと思う。
ただ、これはあくまで現時点での私の見通しである。
もし仮に、このマガジンが様々な質問や意見で溢れて、私の見通し通りにいかない、なんてことがあれば、それは素晴らしいことだと思う。
「一緒に作るマガジン」
主体的な学びのために。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
