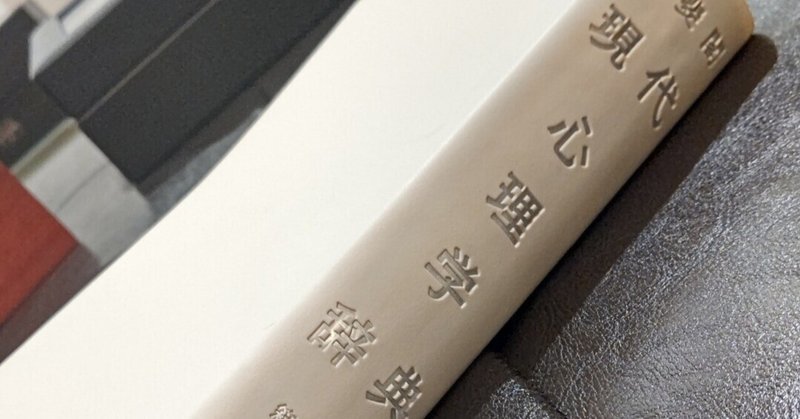
他者の視線や脅威から、自己の姿を知るということ。
今日も比較的のんびりと楽しく一日を過ごせました。楽しみにしていたSchottのレザーカーコートも無事に届きました。茶芯のカウハイドなので、着こむほどに芯の茶色が出てくるという渋さ。たまりません。。
まだまだ暑いので全く着られませんが(試着してポーズを取っていたら汗だくになりました…)、秋冬は毎日着てやろうと思っています。
今回も、思ったことを徒然と書いてみます。
お付き合いいただければ幸いです。
※※※※※※※※※※
外部から視線を向けられたとき、若しくは外部からの脅威に晒されたときに、初めて「私」や「我々」という概念が発生してくる。それまではボンヤリとしていた「内部」がいきなり「私」や「我々」として具体的に立ち現れる。
「これは、内村(鑑三)だけに限るのではありません。ネーションを生み出したのは『国家』に敵対するグループ、あらゆる伝統を一度切断するような人たちです。これは、広い意味で自由民権運動に属するような人たちです。たとえば、自由民権派のグループは、多くの新聞を発行し、『政治小説』と呼ばれる小説を書き、これが広範に読まれたのです。ナショナリズムが高揚するのは、日清戦争(一八九四年)においてですが、その場合、最も熱烈なナショナリストは、もと自由民権派だった人たちであり、彼らの多くはそれ以後国家主義者に転向していったのです。しかし、ナショナリズムは、『国家』に敵対する者の側で実現されたといっていいのです。」
(「〈戦前〉の思考」柄谷行人、講談社学術文庫 p.30)
自由民権派の人々が攻撃しているもの、断固反対しているもの、それそこが「国家」だった。それを知って市民は、「ああ、これが『国家』というものなのか」と知る。こう書くと実に牧歌的だが、その間も自由民権派の人々は「国家」への攻撃をやめない。そうするとますます「国家」(の在り方)に深くコミットしていくことになる。「国家」の良いところも悪いところも熟知するようになる。この時点で既に、自由民権派の人々の中では「想像の共同体」ができあがっている。そうなると、彼らの「国家」に対するファナティックな情念は、ナショナリズムへと変貌を遂げていくことになる。
「岡倉(天心)がいう『アジアは一つ』という観念に対しては、それは現実に根ざしていないのではないか、あるいは、ヨーロッパのような歴史的背景をもっていないのではないかという疑問が投げかけられてきました。もちろん、岡倉のいうアジアのonenessは、『想像のトランスナショナル共同体』以外のものではありません。しかし、それは、ヨーロッパのonenessについても、同じことなのです。こうした同一性は、いつも外部からの脅威によってもたらされるのです。」
(前掲書 p.39)
「外部」からの脅威、それによって初めて「内部」が意識され、形成される。これは心理学における、「内集団」「外集団」の形成、そしてそれによる「内集団ひいき」に繋がっていく問題とも関連している。自由民権派の人々は、「国家」に対する外集団だった。しかしその外集団自体が、上記のようなプロセスを経て、対立する集団(「国家」)をファナティックに支持するようになったのだ。これはそれほど意外なことではないと思う。とにかく、バラバラに存在していた市民が「国家」としての「oneness」を得たのは、「国家」に敵対していた人々の側から実現された事態なのだ。
物事を考える際には、例外から見ていくべきだと柄谷行人はいう。経済について考えるときに、マルクスが、例外的な状態、つまり恐慌から見ていったように。
因みに、意外ではないことと、例外的な状態であるということとは、矛盾しない。経済においても、恐慌が起こることは例外的な状態だが、決して意外なことではないだろう。
これまで書いてきたような仕組みは、個人が自己を知るための方法としても使えるだろう。外部からの視線や脅威、それによって、自己の姿をよく知ることができるだろう。外部と対峙すること。そこから始まる何かが、きっとあるような気がしている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
