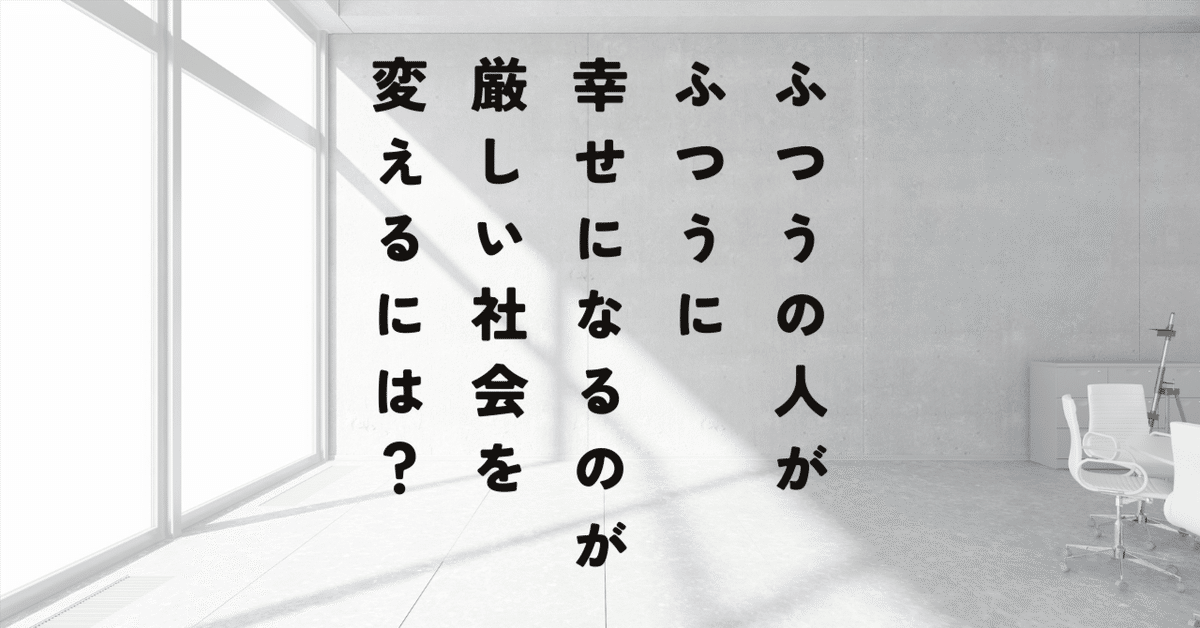
ふつうの人が、ふつうに幸せになるのが厳しい社会を、変えるには?
こんにちは、Loohcs代表の嶺井です。
僕は、これから、日本社会は、ふつうの人々が、ふつうに幸せになることが、どんどん厳しくなっていくなと思っています。
僕がLoohcsに参画し、また雨ニモマケズ風ニモマケズLoohcsに参画し続けている理由が、この問題意識にあります。20代前半の頃に、考えたことで、割とその問題意識を抱えたまま走ってきました。
(この話、Loohcsと自分の関わりについてまとめる、わたしの物語で書くフォーマットで書こうとしていたんですが、言いたいことが収まらなかったので別記事になりました)
なぜ、ふつうの人が幸せになりづらくなって、いきそうなのか。
まず、なぜそう思うのか?という話を、3つに分けて、順をおって説明させてください。解決策を求める前に、浅学ながら(僕中卒なんで)、問題構造の理解を進めたいと思っています。
※なお、ここでいう「ふつうの人」は特定の誰かでなく(おそらく、普通ど真ん中は存在しない人間である)、「一般的なセグメントの人たち」みたいに捉えてください。
①幸せになるにも「才能や技術」が必要で、みなにできるわけではない。
まず第一に、「幸福度が高い人」になるために必要な「態度・振る舞い」は、現代社会でふつうに身につけられるかというと微妙だからということがあります。お金やモノなどが不十分な時代でしたら、「態度・振る舞い」以上に、経済的・物質的豊かさを追い求めるプロセスにより、幸せ度を上げることができたと思います。しかし、物質的・経済的には一定程度(みんな充足しているわけではない)、充足された現代では、「態度・振る舞い」の習得状況が幸福度合いに直結します。
ここで、「態度・振る舞い」についても説明を入れます。
「幸せになるためにはどうしたらいいだろうか?」という問いを心の中に描いたことのある人はそれなりに居ると思いますが、統計的に結論に近い話が世の中にはあるので、以下、慶應大の前野教授が整理した「幸福になるための因子(統計的に、どんな要素を持っていると、幸福度が高い傾向があるか)」を示します。
1.「やってみよう」因子(自己実現と成長)
夢や目標を見つけ、それに向かって努力したり、成長したりしていくとき、幸福度は増します。逆に、「やらされている感」を持っている人や、やりたくない、やる気がないのに行動している人は幸福度が低いです。
2.「ありがとう」因子(つながりと感謝)
周囲にいるさまざまな人とのつながりを大切にする人、感謝の気持ちを持っている人や、思いやりがあり、親切な人は幸せです。逆に、孤独感や孤立は幸福度を下げます。
3.「なんとかなる」因子(前向きと楽観)
どんなことも楽観的に捉えることができ、常にチャレンジ精神をもって取り組んでいる人は幸せです。
4.「ありのままに」因子(独立と自分らしさ)
他人と比較することなく、自分らしく生きている人は幸福度が高く、人と自分を比べ過ぎる人は幸福度が低い傾向があります。
(前野先生は僕も個人的に大変尊敬しておりまして、某Loohcsの元学長がやらかす以前には、Loohcsにもお招きし特別授業をしていただいておりました)
確かに、見るからに、前向きに(3)、自分らしく(4)、成長しながら(1)、まわりに感謝して(2)生きている人は幸せそうですね。Loohcsでうまくいっている人に、何人か注目してみると、この4つをちゃんと満たしているなぁ、と感じることもよくあります。
ただ、あなたはどうですか?幸福になるために、どんな「態度・振る舞い」が必要かは、すでに結論が出ていても、生まれもって、自然に、ナチュラルボーンでこれらの態度・振る舞いができている人はどのくらいいるでしょうか?(誰かナチュラルボーンハッピー勢の比率を研究してませんかね)
少なくとも100%ではないことは確かです。なぜなら、僕がそうではないので。ちなみに、僕自身は2と4がちょっと弱いかなぁ、と自分で感じまして、感謝することもひとつの技術だと思って、感謝力が高まるよう意識したんですが、そうすると共に会社も成長するようになりました。
これらの態度振る舞いは、時と場合によって発揮できたりできなかったりするものだと思います。もしかすると、ナチュラルボーンでできる人は、「幸せとは」に悩んだりさえしないのかもしれません。とはいえ、僕はよく悩んできましたし、幸せそうにしていた人が揺らいだり、お金はあるのにアンハッピーで不安定な人がいろいろなきっかけで変わったり、という瞬間も多々みてきました。
世の中に悩んでいる人が多々いるから、幸せをテーマにした本もよく出ているのだと思います。前野さんの本です。幸せについて悩んだことがある人はぜひ読んでください。これできっと幸せに近づけます。マジで悩んでいる人は、この記事よりこの本ですね。
さて、①の内容を読んで、あるいは本を読み、「なんだ、案外簡単に幸せになれそうじゃん」と思った方もいるやもしれません。はい、確かに幸せ度を上げること自体は、そこまで難しくないと思います。
しかしながら、ところがどっこい、これらの幸せのメカニズムは学校で教えてくれるのでしょうか。もしくは、先生や親、家庭でしっかり、文化として継承されているでしょうか。
僕が前野さんの話を見つけることができたのは(この記事を読んでいる諸兄は当然に把握していたのかも知れませんが)、僕が当時よくみていたNewspicksで前野さんが出てきたり、あるいは自分で幸せについて本を探したりするリテラシーが僕にあったりしたからです。
ということで、ここで第二のポイントです。
②幸福度を高める方法を、社会的に学ぶシステムは脆弱である。
これは僕の現状認識であって、「厳しい理由」にはなっていても、さらに「厳しくなっていく」というには不十分ではありますが、理解を進める上では重要なポイントだと思います。
たしかに、「ウェルビーイング」という単語が社会のいろいろなところで使われるようになって、あるいは教育目標に「態度や振る舞い」が入り、主体的で探究的な学習プロセスを愛する派閥が日本社会にも誕生したことで、「幸せになる方法論を知る機会」は増え、少しはよくなってきていると思います。
しかしながら、先に書いた4つの因子を「実践知」として育むには、最先端のプログラムを以てしても「対応できることもあれば、対応できないこともある」というのが正直なところでしょう。さらには、そうしたプログラムは属人性が高かったりもしますから、なかなか全国に同じように展開するというわけにはいきません。
これまでの社会システムに注目しても、いわんや、日本の学校システムは課題が指摘されて久しく、場合によっては教員がそもそも幸せでないということもありますから(過労とかね)、既存の社会システムの中で上手に学ぶのは難しいと言わざるを得ません。幸せになる技術は、うまく良い先生や、良いコミュニティや、良い機会に恵まれた人"だけが"、身につけることができる技術になっているのだと思います。
さらに困ったことには、類は友を呼ぶという言葉もありますから、「幸福度が高いグループ」と「幸福度が低いグループ」が生まれたりもします。ありがとうを言い合ってどんどん幸せになるグループと、恨み憎しみあい足を引っ張りあってどんどん幸せから遠のくグループがあるのだとしたら、かなり悲しい話ですね。
さらに、最近(2023年)の研究では、所得と幸福度の相関性について、「幸福度が低いグループでは途中で頭打ち」で「幸福度が高いグループでは所得と比例して伸び続ける」という話も示されました。
幸福4因子が不十分な人はお金を稼いでも途中から幸せを感じられなくなるし、十分な人は稼ぐほど幸せになるということで、社会の理不尽さを僕はここで感じます。
*
③物質的な豊かさも依然として幸福度に影響を与えるが、、、
幸せになるために1番大事なことは①で述べましたが、マインドセットの問題なので、簡単な人は簡単ですし、そうでない人はなかなか幸せになれないこともあるでしょう。
そこで、「年収7.5万ドルまでは、所得の増加と幸福度の増加は比例する(お金があるほど幸福度が高いが、頭打ちする)」という話はみなさん聞いたことありますでしょうか。たしかノーベル経済学賞とか取った著名な学者の研究です。先ほどの文献でも触れられていました。この話は「なんだ、世の中お金だけじゃないじゃん」「いや7.5万ドルは必要なんだからそれ目指そうせ」みたいな議論によく使われていますね。
そういう意味では、幸福4因子が不十分な人は、一旦お金を稼げばある程度は幸せになれます。資本主義社会としての道を歩み始めた日本に住む私たちとしては、一種の逃げ道として機能するかもしれません。日本の平均年収や中央値を見ると、全然足りないですし。

*
2024年の円ドル相場当てはめると、頭打ちラインを超えている人は1割強です。円安になる前まで基準下げても、「日本人の7割はお金を稼ぐほど幸せになれる」ということになります。いま、ポジティブに書きましたが、「日本人の7割は幸せ頭打ちラインを超えるだけの所得を持ってない」という解釈もできます。
さらには、そんなに簡単にお金って稼げますかね? 僕も20代前後のWeb系のコンサルをやっている頃は、Loohcsよりはラクして稼いでたのと、世の中には資本家階級が存在することも知っているのでは、様々な苦労が別途あろうとも、何らかの方法はあると思います。
しかしながら、以下の記事にある通り、
日本は先進諸国でも珍しく実質賃金が下がり続けている国ですし、
世界トップの高齢化率で、社会保険料負担は増え続けてますし、
今後も負担が増え続けることは不可避なように見えますし、
グローバルに見れば世界経済が発展してるとしても、日本の中間層って、まさに経済成長から取り残されがちの先進国中間層の代表みたいなもんですし、、、
ということで、ちょっとデータを洗うのが面倒になって、リンク集になりましたが、普通に日本社会の基本的な数字や立ち位置を見ていく、あんまり良い未来が見えませんね!!
というか、このままで大丈夫なんですかね?
*
そんな社会を変えるには?
僕は一人一人が豊かな「社会関係資本(平たく言うのであれば「ご縁」と言い換えても良いかもしれません)」を持つことが、解決策になると思っています。社会システムの方に限界が来る可能性は全然ありそうですが、その前に、自分の力で生きていけるだけのスキルやリテラシーを身につけていれば何とかなるよね、という考え方です。幸福の4因子と、貨幣経済下で飯を食っていけるだけのテクニカルスキルを、みなが持てれば良いし、それをもたらすのは、②で触れたように、良いXX(先生、機会、etc)との出会いであり、それは「社会関係資本」です。
そのための社会システムを構築しようという壮大な試みがLoohcsです。
社会を変えるには?というタイトルにしちゃいましたが、おそらく、社会は変えるより「付け足す」「作り足す」方が勝ち目があると思います。
Loohcsのミッションは「Good Commons for ALL」としていますが、コモンズは幅の広い概念で、この「社会関係資本」も含まれます。(むしろど真ん中?)教育は、対処療法的な自衛手段の提供ですが、それが「コモンズ」になれば、刹那の奇跡が人々のウェルビーイングを支える社会から、もう一歩前に進めるのではないでしょうか。
最後足早でしたが、ギリギリ一応次のアポイントまでに結論に辿り着けました。自己紹介にちょっと書き足すつもりがほとんど書き下ろしになってしまった、、、「ご縁」に関する話はまたいつかしたいと思うのと、会社で何をやってて今後どうするつもりかについても、もう少し書きたいなと思っています。
、、、僕の自己紹介記事はいつ終わるんだろうか。
ちょっとでもこの記事が学びになった人は「スキ」を押したりシェアしたりしてくださいね・・・!お願いします!!
[今回の記事担当]嶺井 祐輝
1991年生まれ。沖縄工業高専・慶應義塾大学総合政策学部を中退。在学中からFintech系上場企業子会社の事業責任者、ITベンチャーの立ち上げ等を経験した後、”ふつうの人がふつうに幸せになれる社会づくり”を目指し、Loohcsへ。10年以上高校生の指導に関わりつつ、現在は社長。
関連記事/おすすめ記事
◇ルークスとは?
今足りていない教育を問い直し、補完し続けるような存在。
「新しい方式の入試対策(AO推薦入試・総合型選抜)」や「探究学習」など“OECD Education 2030”を先取りしながら、高い難関大学合格実績を誇る、教育サービスを運営中です。
◇運営サービス
◇公式SNS
リリース発信やサイト更新など、Loohcsの「今」をお知らせ中!
フォローよろしくお願いします!
Loohcs株式会社【X】【Facebook】
Loohcs志塾【X】【Instagram】
Loohcs高等学院【X】【Instagram】
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
