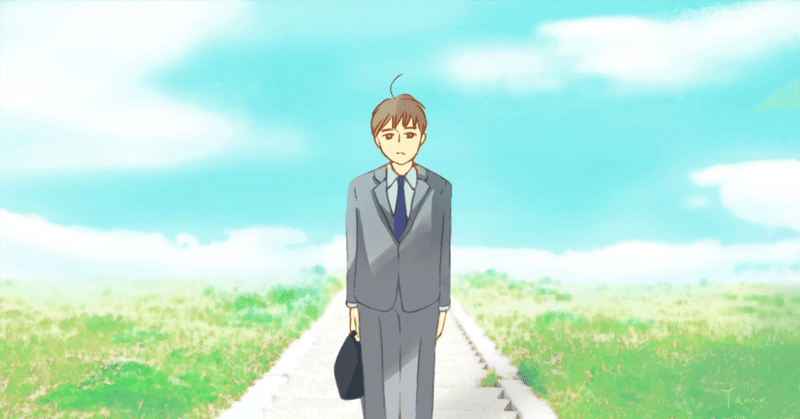
53.【読書と私】⑫なぜ働いていると本が読めなくなるのか/三宅香帆
最近テレ東の“あの本、読みました?”という番組をTVerで見ています。
読書好きの鈴木保奈美さんが司会で、テーマを元にいろんな本が紹介され、作家当人や担当編集者さんなどが出て話している。見る度に読んでみたいと思う本が増えてくる。番組に合わせてかパンツスタイルにスニーカーとちょっとカジュアルな保奈美さん。芸能人の方は拘束時間多そうだし、その中で仕事に関したものも含め、読書されている方多く素敵な発信もされていて、まさにタレント(才能)ですね。
「新書」がテーマの回で出ていた本が気になって読んでみました。
ちなみに、オープニングの曲よく耳にしたことのある曲のタイトルが、出そうで出てきません。どなたかわかりますか?
『なぜ働いていると本が読めなくなるか』
わたし的には、読書は最近ポツポツ出来るようにはなってきたので、今はもう必要はないかな?と思いながら中身が気になります。久々の新書。小説よりもペースアップでどんどん読み進められました。
どんな切り口かと言えば、明治以降~現代に至るまでの、労働と時代を代表する本の歴史が語られていますが、興味深くまとめられていて、歴史が若干苦手な私でも、ずっと興味を持って読むすすめることができました。
大きくは労働の立場から「教養」としての読書か「修養」としての読書かの視点。そこは時代の中で変遷があるところですが、「修養」としての読書は、速読法につながるところもあり、「読書とはノイズである」のタイトルにかかれた文章より、速読に対してのスロー・リーディングを提唱していた平野啓一郎氏の『本の読み方』が自ずから思い出されてきました。また、後半に進むにつれて、好きな系統ばかりでなく、いろんなジャンルのもの読もうか…という思いが出てきました。雑学さえ修養本としてある昨今ですが。
以前に、単行本について考えたことがあり、「単行本」は「全集」に対してのものということを知りましたが、この本の中で全集が普及した流れについての話があったのも興味深かったです。テレビに載っていたフランス人形(ありませんでした?)もふと思い出しました。
それにしても、カッパブックスというのも何か家にあったか覚えがあるし、『サラダ記念日』『窓ぎわのトットちゃん』『ノルウェイの森』
『キッチン』『超「勉強法」』自己啓発書、片付け本…『13歳のハローワーク』『コンビニ人間』『舟を編む』と、挙げられている本に「あー読んだことある…」が続き、流行りものにとびついていたからというのはあるでしょうが、選んで読んでいたようで、出版の歴史の流れに見事に翻弄されていた自分を感じました。
そして、後半に提唱されている「半身で働くこと」著者自身は「本が読めなかったから会社をやめました」として、もう仕事として本を読んでいらっしゃいますが、そう、結局は時間、余裕(余暇)ですよね。仕事に忙殺されて頭がパンパンな中では、ぼーっとしての休養を求めるしかなく、つい気軽なコンテンツに向かいますが、それはどこか虚しさはあり。脳もあまり活動してないという話も聞いたような。読書(または違う能動的な余暇でもいいと思うのですが)できる余裕があると、アドレナリン?のようなものも出て、また翌日の仕事にいい循環も生まれそうなのに。
「アフターファイブ」なんて言葉のあった頃が懐かしい。逆に労働が詰まってくる日々に、半身とはいかなくても、せめて1時間早く退勤できると余力があるのにとか、読書も可能になる休憩時間がしっかりあるといいなと思います。
最近読んだ『本心』では、母がリアル・アバターとして働いている主人公のことを心配するようなところがありました。一人の作家を慕って読書していた母からすると、それは読書する機会もなく、自由意思のないものとして労働する息子を案じる気持ちだったかとも思いました。
(突然、ここで違う本の読書感想文)
また、全編通して挙げられる、『花束みたいな恋をした』のエピソードが、若い著者の色合いを感じさせてくれます。そのイメージで見出し画像も選んでみました。
三宅香帆さんの他の本もタイトルを見ると興味深いので、今後読んでみたいと思います。
三宅香帆(1994ー )
『なぜ働いていると本が読めなくなるか』
(2024)
追記:
長文って、どれくらいの長さから?(多分、文字数抜きにも内容がダルイとなったら長文扱いですかね) ついつい、読書感想長くなってきました。自分が読んだ時の思いの備忘録にもなってきてるので、ノイズというより、ムダが多いかもしれませんが、お付き合いありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

