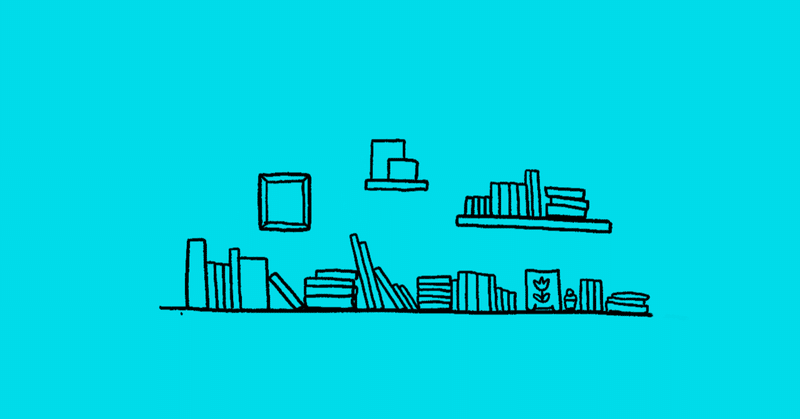
雑感記録(70)
【小栗風葉について覚書】
以前の記録で小栗風葉について書こうと思っていると書いた。それについては以下の記録を参照されたし。
小栗風葉については大学時代、近代文学演習なるもので僕が題材にして論じた作家である。僕は彼の作品が面白いとか正直思わなかったのだけれども、「文体」という点に関して非常に面白い変遷をしている作家である。今日は大学時代に書いたレポートを再度読み直し、適宜修正を加えたものを書き残したいと思う。
実はこのレポートがある意味で僕の1つの転換点でもあるのだ。それは今まで作品内容そのものからの考察から離れて、テクストから考察するという所謂テクスト論に興味を持ち始めたキッカケでもあるからだ。僕の今年のテーマの1つとして言葉について考えるということを掲げている。その原点的な部分として別の媒体、そうこのnoteを利用して再考しようという試みである。稚拙な文章が蔓延るかもしれないが自身のための記録である。自分自身が理解できれば良いとの心持で記す。
1.小栗風葉とは何者
さて、唐突に僕はこれから小栗風葉について書こうとしている訳だが、果たして小栗風葉を知っている人はどれくらいいるだろうか。先に彼のプロフィール的なところをササっと見ていこう。

小栗風葉は愛知県生まれの作家である。彼の中で大きなポイントとなるのは尾崎紅葉の硯友社に所属していたというところだろう。有名な話で言えば、尾崎紅葉が『金色夜叉』を未完のまま死に、その後風葉が『続金色夜叉』を書いたというところだろう。ここで結構知られているんじゃないかなと思われる。
まあ、細かい経歴などはウィキ先生で検索して見てくれればそれで充分なのだろう。先にも書いた通り、特筆すべきは①尾崎紅葉の門下であったこと、そして②田山花袋と親交があったこと。この2点で良いだろう。ここが文体に非常に大きな影響を与えた一端と言っても良いからだ。ぶっちゃけそれ以外はあまり気にせず進む。風葉がどんな生活を送っていたかはテクストから考えればいいことだ。
彼の主な代表作は、『寝白粉』『下士官』『青春』『戀ざめ』などである。特に『寝白粉』なんかは面白くて、内容的には近親相姦のことがツラツラと書かれており、発禁処分になったぐらいの作品である。風葉はこれ以外にも発禁処分をくらった作品を持っている。『姉の妹』という作品なのだが、僕も大学時代に読みたかったのだが探しても見つからなかったのが今でも悔やまれる所である。
2.『世間師』という作品について
僕は大学当時、『世間師』について論じた。これは今だと岩波文庫から出ている『日本近代短編小説選 明治篇2』で読める。ぜひお時間があれば読んでみて欲しい。『世間師』以外にも面白い作品があるので、結構オススメ出来る。こうしてサクサクっと読めるのはありがたい限りである。
『世間師』の内容としては簡単に説明すると、風葉自身が自分の出郷から出世作を出すまでの道のりを描いた作品である。これについては風葉自身が語っているのでそれを引用した方がいいだろう。
かれこれして、ある年漸く高等學校の入學試験を受けてみた。成蹟のわかるのを樂みにしてゐると…見事に落第!それからは學校へも出ずに、長い放浪生活を續けた。そして終に紅葉先生に拾いあげられたのだが、先生の所へ來てからのことは、屡ゝ人に話したことがあるから、今度は一つ放浪時代の珍生活を打明けるとしよう。(中略)
東京から九州へ行つたことがある。歸りに、門司から馬關へ渡ると、こゝで財布が空になつて了つた。(中略)
さすがの私も我を折つて、町端の木賃宿へ辿り着いた、併し二銭の屋根代をと云はれて、先づ困つた。事實、嚢中無一文、大に當惑して、穿いてゐた駒下駄を屋根代の代りにぬいで、やツと泊めて貰つた。
1909年6月発行P.68、69
引用箇所の最後の部分については、実際に作中でも同様な形で語られており、物語のスタート地点はこの宿から始まる。ここで様々な人との出会いがあり、作品を書くに至るまでの様子を描く。感想を言うと、結構こざっぱりしていて読み易いというのが1番だろう。
ところで、この『世間師』という作品について正宗白鳥がこんなことを言っている。
風葉の「世間師」を今度改めて読んでみたが、これは自然主義的作品で、これを花袋の作品中に入れたなら傑作の部に属するのである。
P.44
さて、これを読んで皆さんが何を思うかは知ったことじゃないが、しかしこの表現は些かの引っ掛かりを僕は覚えるのだ。なぜ正宗白鳥は「自然主義文学」と断定せずに、「自然主義的文学」と「的」と表現したのだろうか?花袋の作品に属するとすれば、それは自然主義文学でいいのではないか?なぜ敢えて「的」などという言葉を使用したのだろうか。まあ、今回の書きたいこととはズレる内容なのだが…。
3.自然主義文学についておさらい
話をズラすついでに、ここで自然主義文学というものについて簡単におさらいしておこう。基本的な姿勢を僕の考えるところで挙げるとすれば以下の4点。
(ⅰ)対象をありのままに描く(田山花袋『露骨なる描写』)
(ⅱ)内容は物事の真理を描く(田山花袋『露骨なる描写』)
(ⅲ)文章の背後にある人生の理想およびそれの読取可能性(片上天弦『平凡醜悪なる事實の價値』)
(ⅳ)作者の主観は不要(島村抱月『文藝上の自然主義』)
自分は明治の文壇が久しい間、所謂文章、所謂技巧なるものに支配せられて、十分なる發達をなす能はざることを甚だ遺憾に思うた一人である。文士がいづれも文章に苦心し、文體に煩悶した結果、果ては篁村調とか、紅葉調とか、露伴調とか、鷗外調とかいふ、一種特別なる形式に陥り、自から自己の筆を束縛して、新しき思想を有しながら、しかしその一端をも其筆に上すこと能はず、空しく文章の奴隷となつて居るもの多いのを見もし、試験も爲て、尠なからず遺憾に思つたのである。
1904年2月P.160
まあ、これは言わずもがなというか…。説明するまでもないので引用だけしておくことにする。以下も同様に引用しておけば十分であるように思う。
自然主義の藝術は、平凡醜惡なる人生の事實を表とし、裏に不可測の人生の理想を藏して、その中に何者かを探り索めしめんとするものである。
1907年4月P.5

島村抱月に関しては図を拝借し、尚且つ僕の解釈で図を作成したものである。
正直あんまりここは関係ないっちゃ関係ない。まあ、おまけみたいなところだと考えて貰えればいい。大学の時にはこれで論じていたが、今回書きたいこととはかけ離れており、さして重要ではない。『世間師』という作品だけを考えるにあたっては関係してくるが、ここから記録しようとしていることが実は僕のターニングポイントである訳で、ここまで書いといて何だがあんまりここは重要ではないし面白いところではない。次からが僕の書きたいことの中心である。
4.文体の変遷を辿る
さて、ここからが僕の書きたいことであり、テクスト論について興味関心を持つようになったキッカケである。ここから矢鱈引用が続く。
留湯一切御斷申候、小町湯の夕暮の門を忙しげに出行く女あり。艶やかなる髪の濃く見事なるを、小さき島田髷の密に娘裝、紫紺の半襟に縞繻子の帶、良古りたる縮緬の帶揚の飛々ながら紅の入りたる、疎き三本格子の黄も濁れる八丈の書生羽織を裾長に着たる、年に比べていづれか若やかならぬはなし。見たる所二十五六の秋も稍深く、水涸に闌れし朝顔も有繋し麗しきは暁の濡色、長湯に熱せし顔の瑩々と露の滴る如く、目鼻立揃いて、生際良亂れたれども、畫きたるやうの三日月の眉も捨てたものならぬ容貌。藝者にては固より無く、茶屋女にしても野夫なり。矢場女か、月縛の妾か、この年齒にして此扮裝、よもや堅氣にはあるまじ。
1896年9月P.1
小母と謂つても、格別血縁のあるのでも何でも無い。唯自分の形式的の保證人、學校の届書に印を捺してもらつた其人の細君なるのに止まるので、お茂と謂つて今年四十三とかである。生際と唇の薄い、稍小肥の、餘り品の好い細君では無い。が、然し、風采の活潑とした、氣の若い、女には似合はぬ決斷の可い、淸潔好きの、先男勝と謂ふ方で、亭主が死んでも、見事後家で行り通さうと謂ふ側の女である。早口に能く喋つて、侃々諤々した調子の、慍輙い、左もすれば亭主に抗つて懸りかねぬので。奥様でもあるまい、と謂つて、苟もお勤人御内賓を、お神様と呼ぶのも不躾であらうし、又自分のお母程の者を捕へて單にお茂様と名を呼ぶのも異なるものと思ふ所から、自分は小児が一般の女性の代名詞に使ふと同じ意味で、小母様と呼んでいるのである。
1897年8月P.9
美しき八字髯を蓄ふれど、小官吏などの物々しき容體もあらず、英吉利ネルの洋服を着て、瓦斯四二子の綿入に鼠縮緬の兵児帯、秋田織の縫紋の羽織を紙捻に留め、鼠の中古の中折を戴きたるものあり。其が妹と覺しき年の程の、前髪を截り下げの束髪に薔薇の一輪も臈たく、變縞の山糸織の上に珍客の節糸織を合せて、小柳繻子の帶幅稍狭く、伊勢崎織菱綛の書生羽織を着たるを前に擁ひて、柱を小楯に木戸の罅くをこそ待ちしか。來合わせけるは黒の眞岡の五紋の長羽織に手織布子の裾短く、大幅の金巾を臍の下に巻き着け、時計の紐に外國貨幣と賞牌とを下げて、圓心のやうなる白の胸紐を膝の邊まで垂れつゝ、紀州ネルの窄袴下を段袋の如く膨ませたる、日頃教えを受くる書生なるらし。然るは二人の下足札を受取りて、直ちに己が薩摩下駄と與に持ち來れるが、打見の粗けきにも似氣無く、娘を偸み見る目の怪うも可笑かりけり。
欽哉は今年二十五、背は並で、肉付も餘り豊かで無く、惡くすると骨細な華奢形に見られさうな格服であるが、その狹からぬ腹膈と、屹と張つた肩幅とに男らしい嚴つさを補つて居る。男前が好いのでは無いが、緊つた活々した顔立ちで、截の長い目に濕り光を持つて、癖のある濃い髪毛は廣い額に直り張付いて、少し色澤の惡いのは、此節神經衰弱の氣味だと云ふその所爲でもあらう―其癖ビイルを平氣で飲んで居る―文科大學の一年で身飭のカラア白く、襟に光つたL字の新しい割合に、金釦の餘り光らぬ中古の制服を窮屈さうに掛合わせて、ヅボンは縞物を穿いて居る。
『日本現代文學全集十一 山田美妙・廣津柳浪・川上眉山・小栗風葉集』
(講談社1968年P.200)
私は寐床の中から見ると薄暗くて顔は分からぬが、若い脊の高い男で、裾の短い着物を着て、白い兵児帯を幅廣に緊めて居るのが目に立つ。手に塗柄の附いた馬上提燈を下げて、その提燈に何やら書いてあるらしいが、火を消して居るので分からなかった。
『明治文學全集六十五 小杉天外・小栗風葉・後藤宙外集』
(筑摩書房1968年)P.302
さてここまで非常に長い引用が続く。これは一応時系列順に並んでいる。なお、これは僕の不手際なのだが、まさか文学全集から引用してくるとは…。我ながら恥ずかしい…。時系列を整理しよう。
『寝白粉』(1896年)→『十七八』(1897年)→『鬘下地』(1899年)→『青春』(1905年)→『世間師』(1908年)
というような順番になる。ここで作品を僕は恣意的に選んでいる訳だが、なぜこれらの作品を抽出したかについて説明する必要があるだろう。(『鬘下地』と『青春』の間の大きな隔たりに自分自身でも違和感があるのだ。)
『寝白粉』は風葉にとってのデビュー作であり、所謂硯友社文学の影響を大いに受けていることがよく分かる。文章を如何に煌びやかに装飾して魅せるか。これが非常に顕著に現れている。彼が会得した文体の最初はとにかく装飾する文体であること。これが出発点となることをまずは確認したかった。
『十七八』に関しては風葉が初めて言文一致体で書いた小説とされている。この言文一致運動に関しては非常に難しいところがある。今回は本当にササっと触れただけなので、もし詳細を知りたいという人が居れば柄谷行人の名著『日本近代文学の起源』を読んでもらうと良いだろう。
『鬘下地』に関しては風葉自身が上田敏を真似て擬古体で書いた唯一の作品である。擬古体とは辞書的な説明になるのだが、俗語をわざと古めかしい言葉に変換し文章を組み立てるというようなものである。ちなみにこの『鬘下地』前後は基本的には『十七八』と同じ文体であることは確認済みである。
『青春』については風葉の出世作であり、風葉の名が知れ渡るようになった作品なのである。これは着目したいという、何だろうな…これは完璧なる僕の独断と偏見であるのだ。出世した作品だから何か仕掛けがあると思うのは僕だけなのだろうか。
さて、ここまで長ったらしく書いてきたが次には実際に引用を利用し文体について検討してみようと思う。大学時の思考と、現在の考え得る僕の思考をミックスして少し考えてみようと思う。(と言ってまともなこと書けそうにないのだが…そこはご愛敬ということで…)
5.文体の分析
さて上記の引用を使用しながら順を追って検討してみたい。
まず以てここで着目して欲しいのが、これらの引用は僕が恣意的に選んだとは言え、人物の描写に関しての部分を引っ張ってきている。人物描写をする際にどれ程の言葉を費やしているか。ここが非常に重要になってくる。細密描写の問題点が風葉の文体から見ることが出来る。ここで1つ森鷗外の作品から1つ、そして補完として斎藤緑雨の作品から1つ引用してみようと思う。
日本にせよ、西洋にせよ、衣服容貌を精く書く必要を認めたる小説家決して少からず。卽ち衣服は其人物を能く著はすものなればなり。西鶴京傳三馬等は殊に意を注ぎたり。(中略)衣服容貌を精く書く必要は、洵に東西詩家の認めたる所なり。されど餘りに詳に書く弊害も亦東西詩家の認めたる所なり。(中略)詩は固より畫に非ず。一目して悉すべきことも、之を文に筆して帽より襟に及び、襟より帶に及び、帶より襪に及ぶうちには、遂に帽のいかなりしかを忘るゝが如きことなきにあらず。
(岩波書店1973年)P.100、101
台がオロシヤゆゑ緻密々々と滅法緻密がるをよしとす「煙管を持た煙草を丸めた雁首へ入れた火をつけた吸つた煙を吹いた」と斯く言ふべし吸附煙草の形容に五六分位費ること雑作もなし其間に煙草は大概燃切る者なり緻密が主にて本尊に向ひ下に居らうと声を懸るときあれど敢て問はぬなり唯緻密の算段に全力を尽すべし算段は二葉より芳しと評判されること請合なり折々翻訳するもよし但し緻密を忘れさへせねば成るべく首も尾もないものを択ぶべし
(筑摩書房2002年)P.195、196
さて、この2つで述べられていることは細密描写の弊害である。鷗外の場合はレッシングの『ラオコーン』から影響を受けていると思われるのだが、斎藤緑雨に関しては鷗外以前のものとなるので、斎藤緑雨の方が先見性があったとも言えなくはないのだが、そこは置いておくこととしよう。斎藤緑雨に関しては二葉亭四迷の『浮雲』を引き合いに出してこのようなことを論じている。
細密描写をする際、要はその人物像が崩壊していくことに問題点がある。とある人物を描写する際に身に着けているもの、その人物の風体、その人物の性格等々を順繰りに描写していくと最初に書いたことを読んでいる読者、つまり我々が忘れてしまうということになる。
『寝白粉』の場合、あの引用箇所全てが人物描写である。最初の1文「留湯一切御斷申候、小町湯の夕暮の門を忙しげに出行く女」についての描写をしている訳だが、如何に続くのはその女がどういう恰好をしており、年齢はどのくらいで、どんな表情をしており…といったように事細かに表現されている。正直僕らからしたら「女」であることが分かれば十分であり、背後関係などは読んでいけば分かることだ。しかし、その外装ばかりがのべつまくなしに語られることによりその「女」の正体が不明瞭になる。
風葉の場合、それは『青春』まで続くように思われる。厳密に言えば、『青春』のあたりでは大分緩和されているような気がしなくもないが、やはり外装に関するものが多い気がする。
これを更に考えるのであれば、リカルドゥの『叙述の時間と虚構の時間』を参照するともっと深められるだろう。
しかし、たまたま速度の減少がひどくなって、停止状態にまで立ち至ることもある。つまり、描写を読んでいるときがそれである。それは、対象が一種の恒久的な不動状態の中で生みだされていくためなのだ。いまここで問題にしているような、少なくとも基本的な段階においては、言葉は直線的に進むものなので、描写が生みだされていくのは、行動の時間的な流れの犠牲の上になのである。また、同様にそこで注意されるのは、描写の行なわれる便宜のために、作中人物もしばしば不動状態におかれてしまいがちになるということである。
(紀伊国屋書店1969年)P.243、244
本当ならここで図示が示されていて、凄く分かりやすいんだけれども今の僕にはそれを作成する気力は残っていない。もし興味があれば実際に『言葉と小説』を読んでみて欲しい。
しかし、『世間師』になってみると何故か急にこざっぱりした文体になっている。人物の描写もそこまで多い訳ではない。そのお陰もあってか、僕等読者にとっても非常にすんなり入ってきやすいものとなっている。加えて言うのであれば、この『世間師』が描かれた時代的には自然主義文学が文壇を席巻していた時代でもある。泉鏡花などは硯友社文学の唯一の血統を引きながら作品を描いてきた訳だが、自然主義文学の隆盛により自身の作品が売れなくなったと文句を言っている。
泉鏡花が出たついでに、上記に関連させて特徴を言うのなら、泉鏡花はこの叙述の時間を利用して不思議な世界観を見事に作り上げている。泉鏡花の作品には必ずと言っていいほど「女の幽霊」が姿を現す。しかし、その「女の幽霊」はどこか魅力的であり正体が掴みにくい。それは畢竟するにこの細密描写による人物像(「女の幽霊」)の崩壊が起きるからこそ読者には謎のままで魅力を感じるのではないだろうか。得体の知れない美しい女性。正しく叙述によって生み出されたものである。
陰のある女性に惹かれる。これはまあ、谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』を読んでもらえればいいだろう。
さて、話は少し脱線してしまった訳だが、結局のところ風葉はかなりの頻度で文体を変えている、ある意味挑戦的な作家であったと言えるのではないだろうか。ただ、結局のところ風葉自身はどこを目指していたのだろうかとも思われる。そこで最後に彼のエッセーを引用して締めよう。
6.風葉が目指したところ
ここまで長ったらしくかいた訳だけれども、結局のところ風葉が目指していた書き方とはどんなものだったのだろうか。
藝術上の主義は無論従来の寫實派では飽足らない、是非自然派のあヽいふ傾向に進まねばならないといふ考は「涼番」なぞ書いた頃からあつた。(中略)感じてさて其れを書かうとなると、どうも其儘では飽足らなくなる、一番こいつを面白いものに爲やうと云ふ當氣が出る、儚い空想で以て色々に細工をやる、其所でどうしても造り物拵へ物になる、人物が類性に陥つたり、作物全體が馬鹿に變化のある、辻褄の合つた、お芝居になつて了ふ、それへ又文章上の技巧でコテヽヽ白粉を塗する、どうも惡い弊だと思ひながら止められない。
1907年4月P.156、157
風葉的にはコテコテした文章よりもさっぱりした文章を書きたいと思っていたらしい。そのように考えると、自然主義文学云々は置いておくとして、成功したっちゃ成功したんじゃないのかなとも思える。
何と言うか紆余曲折を経て、自身が様々な文体で描いて見せることで、最終的に自身の目指していたものに辿り着くことが出来たのならば作者冥利に尽きるというものだろう。
7.最後に
はてさて、ここまで本当に長く書いた訳だ。風葉について考えてみるとやはり「ああ、この時代って本気で文学に向き合っていたんだな」ということがよく分かる。あと小説もある種の技術で描かれていることもよく分かる。
「大衆文学も読もうキャンペーン」中の僕は読んでいく中で、詰まらないと感じる理由が少し分かった気がする。それは言葉に対する何かというよりも、内容に対する何かを掴むのに必死であり、終始説明的な文章であることなのだろうと思う。
風葉は内容云々よりもまずは「文体」に着目して、「文体」から変えていこうとした訳だ。僕もこうして文章を書いていて思うが、自分がどのように書くかという、所謂クセみたいなものを変えるというのは至難の業である。要は今までの自分を捨てることになるからだ。
しかし、それを風葉はあっさりとやってしまった訳だ。1番簡単な内容ではなく文体を変えたのだ。だからこそこうして後年に渡っても読みうる作家なのだろうと思う。
言葉への跳躍。これは僕も大事にしたい。
よしなに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
