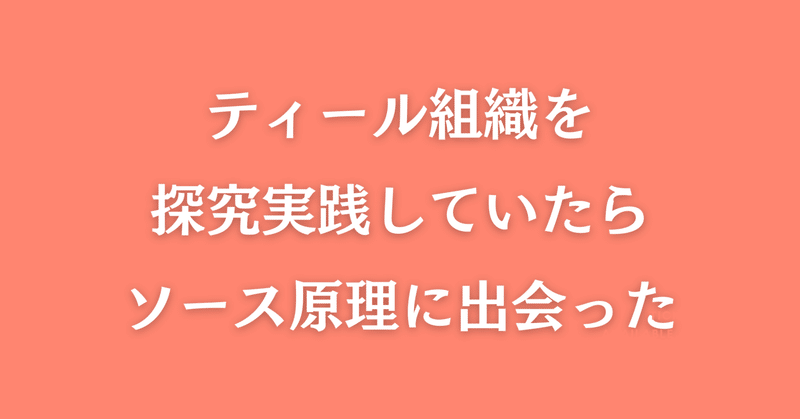
「ティール組織」を探究実践していたら「ソースプリンシプル」に出会った
はじめに
2018年3月頃に書籍「ティール組織」に出会ってから、それまでのビジネスのテーマとして「個人の内面」や「人間関係」にフォーカスしてきた中である種の限界を感じていたこともあり、「個人から組織(その中でも仕組みや構造)」へと興味関心が移りました。
今回の記事では、そのJourney(旅路)の中で「ソース・プリンシプル」とはどのように出会ったのかについて書きます。
2018年〜2021年にわたるJourney
まずプロジェクトで試してみた
書籍「ティール組織」にビビっときてから、まずはそのタイミングで関わるようになった事業再生的なプロジェクトでメンバーが「自主的に動ける場づくり」をするために活かせるのではないか?せっかくなら積極的に活用したい!と思いました。
そこで3、4回ほど読み、自分なりにエッセンスを抽出しプロジェクトリーダーと話しながら進めていったのです。
しかし、その狙いは失敗しました。プロジェクトを進めていく中で気づいたことはこちら。
・ティールになれば儲かるのではない。
儲かるビジネスモデルづくりは別の話。ということでした。冷静に考えれば当たり前ですよね 汗
・短期的に売り上げを作ることと、自主的に動けるようになる環境づくりや働きかけを両立するのは困難。
こちらも振り返ると当たり前なのですが、この2つを同時にしようとしていました。過去に短期的な売上を作った経験があるメンバーであれば環境を整えれば、ワークしたと思いますが、その点について未経験のメンバーでした。そんな中で自主的に動けるように組織を整えようと試みても、どう動いたらいいのか分からないのが当たり前ですよね。
・ティール的なことがワークするための前提条件がある。
短期的に売上を作る必要があるときに、その経験がないメンバーに対して主体性を発揮できる環境づくりを心がけたとしてもお互いにストレスが溜まる。むしろトップダウンで引っ張っていって一気に成功体験を共有するところまで走れた方がwin-winになる。
会社の中から取り組んでみよう
上記の反省と、組織の外側から関わることって「しっくりこないな」「実際に内側でやってみないと何も分からないよな」と感じ、環境を探したところ、「ティール組織を標榜」&「事業領域も関心がある」スタートアップに入ることができました。
そこは創業者がエンジニアであったこともあり、様々なデジタルツールが活用された「情報の透明性が非常に高い環境」でした。あえてティール組織の3大特徴に当てはめていうなら「自主経営(セルフマネジメント)」にまつわる経験を積めたと言えるでしょう。
働いていく中で組織づくりにもいよいよこれから本格的に関わっていけると思っていた矢先、病気→入院。半強制的に色々省みる機会となり、発覚から約1年後に会社を辞める決断に至りました。
参加型・自律分散型の組織で活動しよう
会社を辞めたあとにたまたま出会った参加型・自律分散志向の組織が2つありました。
これらの組織では最終的に経営・全体運営チームメンバーとなり、活動を通じて、ティール的・自己組織化的組織の知見に触れる⇄実践するのサイクルをぐるぐる回すことができましたし、件のスタートアップ同様、情報の透明性が高い×ほぼフルリモートで活動できる環境だったので、オンライン×自律分散化にまつわる色々な経験を積むことができました。
このように主には組織の一員として、時には外部からの支援者としてクライアントのティール的組織へと進化していくプロセス(意図的に個々人への直接的アプローチは脇に置いた上で、仕組み・構造面に集中)に伴走することで、気づいたことがあります。
それは、組織の仕組み・構造が実態としてどのようにワークするかは個々人に依存している、ということでした。
心の声(「いや、当たり前すぎる気づきじゃん 汗」)
冒頭で書いたように「個人→組織(その中でも仕組みや構造)」という集中テーマのシフトの通りに、探究実践を続けてきていましたが「やっぱり個人の内面、関係性への直接的なアプローチも大事だよなぁ」と思うようになったわけです。笑。
「ソース・プリンシプル」に出会った
「ソース・プリンシプル」を知ったのは上記の思いが浮かぶようになってから数ヶ月後のことでした。
ちなみに今、日本において「ソース・プリンシプル」は和訳された本のテーマ上、組織論の文脈で扱われる・捉えられがちです。本来は「ソース・プリンシプル」とは個人にまつわるものです。(むしろ、ソース・プリンシプルというレンズにおいては組織のことを固まりとして捉えず、流れ・プロセスとして捉えています)
※上記の補足
「Source Principle」の提唱者であるピーター・カーニックの言葉
『ソース・プリンシプルの最も重要な考えとは、”私達の誰もが生まれながらにしてのソースであり、自分たちの人生をソースとして生きていく素質が生まれながらにして備わっている”という個人への視点があるんだ。
つまり、組織の前に、個人として、誰もが、”自分の人生を愛してやまないことに注ぐ素質があり”、自分の人生のソースであるということが最初にある考えなんだ。このことがソース・プリンシプルの根幹にある。そのため、ソースワークに優先して、個人のマネーワークを日常的に行い、個人のソースとしての素質を取り戻そうと意図しているんだ』
『次に、そもそも、ソース・プリンシプルでは、組織のパーパスが、組織ではなく、その組織を始めたソース(特定の個人)から生まれてきたものと捉えている。
つまり、組織パーパスや組織ビジョンという概念は無く、ソース個人のパーパスやビジョンとして捉えているんだ。
だから、メンバーは、もし組織のソースのパーパスがフィットしなければ、対話の上、組織の外で自分にとって愛してやまない活動に取り組めばよいという考えがある。組織のソースに束縛されることはないんだ。(ソース自身もソースとしての相応しい振る舞い方に日々改善し続ける必要がある)』
『以上の見解から、”組織のパーパス”という表現を使う場合、「人が生まれながらにして備えているソースとしての素質がぼやけてしまう」と考えている。
なぜなら、一般的に個人は組織のパーパスに合わせて振舞ってしまうものだから。なので、ソース・プリンシプルでは、組織のパーパスという表現は使っていないんだ。
加えると、僕は組織という言葉自体も使っていない。エンタープライズ、プロジェクト、イニシアティブという表現を時間軸等によって使い分けている』
2021年の冬頃につながったJUNKANグローバル探究コミュニティ(※)で、仲間たちと原著を読み進めていく企画に参加することで、約4年振りに探究テーマとして個人にフォーカスが当たることとなりました。
※JUNKANグローバル探究コミュニティとは?
2021年秋に、吉原史郎氏がソースとなって立ち上がりました。JUNKAN(循環畑や、循環プランター、土中環境の実践等)を日々の暮らしの中で実践し、JUNKANの感覚を体に宿しながら、経営やマネーについても探究していくコミュニティです。多様な分野で活躍する仲間達が集っています。
しかし、以前のそれと違うのは個人と集団と構造が同時に存在しているという手触り感を持てていること。それぞれのレンズを使い分けられるようになってきていること。その上での個人に関する探究となったということです。
振り返って思うことは、書籍「ティール組織」と出会ってからの4年間のジャーニーは「組織におけるすべての側面を(ちゃんと在ることとして)鑑みながら支援していきたい」という自分の”ありたいスタンス”に出会うためのプロセスだったのだなぁとも思っています。
さいごに
ソース・プリンシプルを知り、学んでいく中でどう感じたのか等についてはまた別に書きます。
最後、個人的に今気になっていて探究したいな〜と感じている問いについて載せて終わります。
それは『「ソース・プリンシプル」という叡智は、会社組織におけるHR領域にまつわるこれまでの変遷という文脈において、どんな意味を持ちうるのか?』という問いです。
なかなかに大きな問いですが、好きなことなので資料や書籍なども辿りながら楽しく探っていきたいと思います〜♪
オススメの紹介
「ソース・プリンシプル」は想いある起業家・経営者・組織の代表者の方や、個人や組織の伴走・支援者の方に強くオススメしたいものですので気になった方はぜひ書籍や関連記事等を見てみてくださいね。
現在日本で出ている関連本はこちら。
上記の書籍で扱われているメインテーマ(ソース・プリンシプル×イベント・プロジェクト・事業)も含んだ「ソース・プリンシプル」の全体像についてイメージ・理解が深まる記事はこちら。
ソース・プリンシプル提唱者初来日イベント開催決定!
ソースプリンプシプル提唱者であるピーター・カーニックの初来日が決定!イベントが開催されることになりました!ピーターの年齢(70代)もあるので、最初で最後の機会だと思います。気になる方はぜひ!
続きはこちらから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
