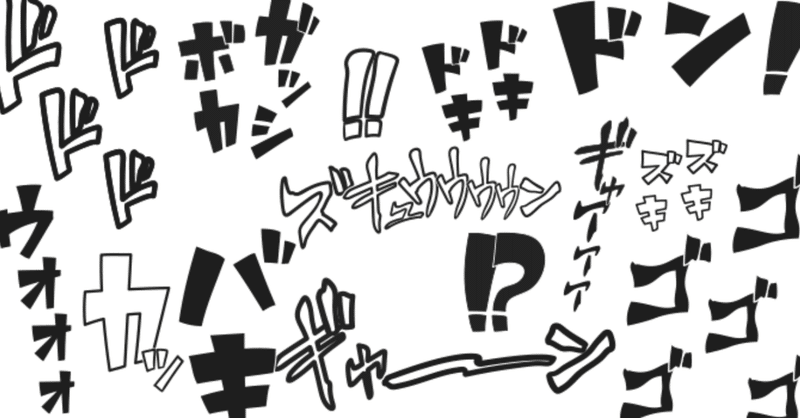
「永遠に終わらないものなんてあるのか?」ということが永遠である(ウサギノヴィッチ)
どうも、ウサギノヴィッチです。
今日は最後の「N.G.T」のレビューです。
作者は遠藤ヒツジさん。お題となった曲は、MANGA SICK です。
タイトルは『CRIMSON GIRL YUGURE」です。
僕はあんまりというか、全然マンガを読まない。この作品には、たくさんのマンガのタイトルが出てくる。タイトルの通りなのだけれども。
小説を書くに当たって必要なものがある、そして、それが武器になるのだとしたら、それは知識だ。読者も思わず唸ってしまうようなほどの知識量があると読んでいて、「この人はこの小説を書くためにたくさん勉強したんだ」or「知識があるんだ」という判断をくだす。それは作者に対して当然ながら優位に働く。また、小説の世界を構築することが容易くなる。
この小説は、二人の女子高生の友情の話だ。もともとヒツジさんの色が出ていて非常に読みやすい。
また、男性が女性を書いていても違和感はまったくなかった。あんまり、作家でたとえたくないのだけれども、たとえると舞城王太郎のような文体と物語の運び方だと感じた。
僕はそれに憧れてしまう。
そして、物語に度々出てくるマンガのタイトル。僕は、「凄い」と感じた。
また、最後が好きだ。それはここで書いてしまうともったいないないので、是非とも読んでみて欲しいと思った。
そもそも、僕はマンガを読まない。先にも書いたが。理由は、画を見て物事を感じ取ることができないからだ。だったら、アニメの方が画が動いてて、声と動きで感情の動きが分かるし、ドラマを見た方が、役者の表情や仕草など細かいところまで見れる。
僕が知りたいのは、実はそんなところではない。
この物語がどう進むかという事だ。
じゃあ、マンガでもいいじゃないかと思うかもしれない。しかし、マンガにはそれを読み取ろうとする能力が働かない。ジャンプやマガジン、サンデー、その他は一週間で進む量が限られている。その先のさらに先を考えることが、なんとなくだが、面倒くさくなってしまうし、思考が停止してしまう。単行本を読んで初めてこの作品はこの先どこに進んでいくのだろうと思うのだった。
ただ、こんな自分でも読んでいたマンガがある。それは、「アカギ」だった。毎月一日と十五日に発売される近代麻雀の、一日の方だけに載っている「アカギ」は毎月読んでいた。
なぜ、読んでいたかというと、もうこの物語、アカギが死なないことはわかっているので、じゃあ、どうやってアカギが勝つのが気になっていたし、いつまで鷲巣麻雀は続くのだろうかと、その興味だけで読んでいた。
それは作品に飲み込まれていたといって過言ではない。配牌だけで一ヶ月使っまたりしたときはある種笑った。そんなバカなことがあっていいのかと思った。
ふと、思ったので、ここで内容にちょっと触れたいと思うことができたのでする。
少女同士の友情ものは尊いと思う。
なに、馬鹿なことを言っているんだと思っているんだと思うかもしれない。だが、それが壊れる瞬間、それがなんとも言えないように思った。二人が永遠だと思っていたものがそうでなくなるとき、二人は静かに絶望する。もちろん、話が長くなれば、そこが回復する物語が出てくる。でも、そこまで至らない場合、話は最悪の方向へと進みかねない。つまり、「死」だ。それがさらに尊く感じる。二人の行き違い永遠のまま、修復したいまま、話は終わってしまう。本当にばっどえだ。なにも出来ずに終わってしまう、残された女の子は絶望の淵に立たされる。でも、それでも生きていかなくてはならない。その儚さが妙に心をくすぐられる。
リアルな人間関係では、ここまでのことは起こりかねないと思いたい。フィクションだから、ここまでのことが起こせるのだ。そして、リアルの人間関係に永遠を期待しているからこそ、小説の中にもそれを求めてしまうのかもしれない。
もしかしたら、その逆で、人間関係がずっと続くことなんてないからここ、小説内の作りものの永く続いて欲しいものを期待しているのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
