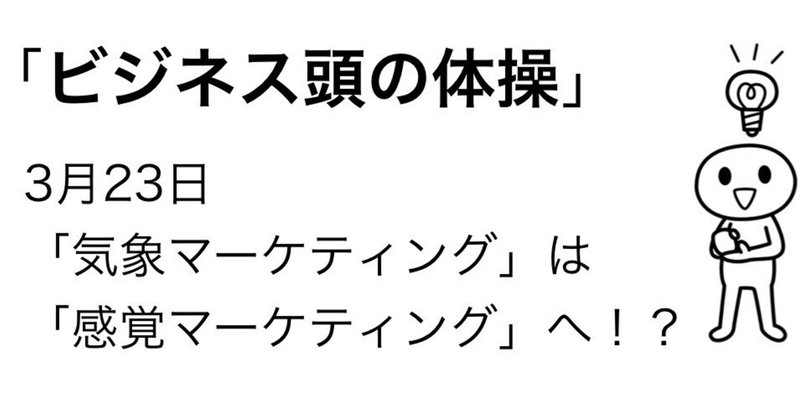
3月23日 「気象マーケティング」は「感覚マーケティング」へ!?
はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例はこちら。
→気象はさまざまなビジネスチャンスがある。今後どのようなサービスが普及すると考えられるだろうか?
世界気象機関(WMO)が、発足10周年を記念して1960(昭和35)年に制定した「世界気象デー」です。
1950(昭和25)年のこの日、世界気象機関条約が発効し、WMOが発足しました。
WMOは、加盟諸国の気象観測通報の調整、気象観測や気象資料の交換を行っている世界組織で、日本は1953(昭和28)年に加盟しました。
気象。
実は2月16日が「天気図記念日」ということで、気象庁と気象協会、ウェザーニューズという「天気予報会社」についてご紹介しました(下リンク)。
天気は人々の生活に大きく影響するものです。
近年では、この天気をさまざまなサービスやマーケティングに活用しようとする動きが活発です。
そこで今回は「気象ビジネス」について調べてみました。
国土交通省の交通政策審議会第30回気象分科会(令和2年4月)の資料(36枚ありますが、気象に関する規制緩和から体制、民間での活用状況まで非常によく纏まった資料です)から、気象データの活用の広がりがわかるデータをご紹介します。
その前提として、日本の気象に関する規制は平成5年の気象業務法改正により大きく転換したことを押さえる必要があります(下図)。

従来、自治体や関係機関(主に日本気象協会ですね)、報道機関が独占していた気象庁の観測データに、民間気象業務支援センターを通じて民間事業者がさまざまなサービスに活用することができる体制になりました。
この気象データを活用する事業者の数ですが、増加傾向にあることが分かります(下図)。

自らの事業に気象庁のデータを活用している事業者が増えていることが伺えます。
気象庁のデータを、事業に活用って?と思われるかもしれませんが、以下のようなことに活用されているそうです(同資料より)。

実際、IBMは2017年3月から企業向け気象予報サービスに参入しています。
また、この分野での起業も目立ちます。一例として2016年に設立されたClimaCellは「気象テクノロジープラットフォームのリーダー」を目指す、としていて、2019年4月にはソフトバンクグループであるSBエナジーが出資をしています。顧客にはウーバーやユナイテッド航空、フォード、全米オープンテニス、などが名を連ねています。
この企業は、気象情報の提供ではなく、それをどう解釈し、どうアクションすべきか、までを提供するところを差別化としているそうです。
また、報道などでも、食材のロスを減らすために気象データを活用して弁当や食品の需要を予測し、生産をコントロールする技術のことが紹介されることがありますが、日本気象協会と全国小売店のデータを持つインテージとが「気象データによる商品需要予測」サービスを提供していたりします。
こうした動きは、当然マーケティングにも活用され、三井物産が作成した「気象データを活用したビジネスの現状と可能性」という資料によると、「気象マーケティング」から「感覚マーケティング」へ展開していくと予想されています(下図)。

→気象はさまざまなビジネスチャンスがあるようだ。身の回りでどのようなサービスがあるだろうか?また、今後どのようなサービスがあれば普及すると考えられるだろうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
頭の体操になれば嬉しいです。
昨年7月から同様の投稿をしています。かなり溜まってきました。
へぇ〜というものがあると思いますのでご興味があれば過去分もご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
