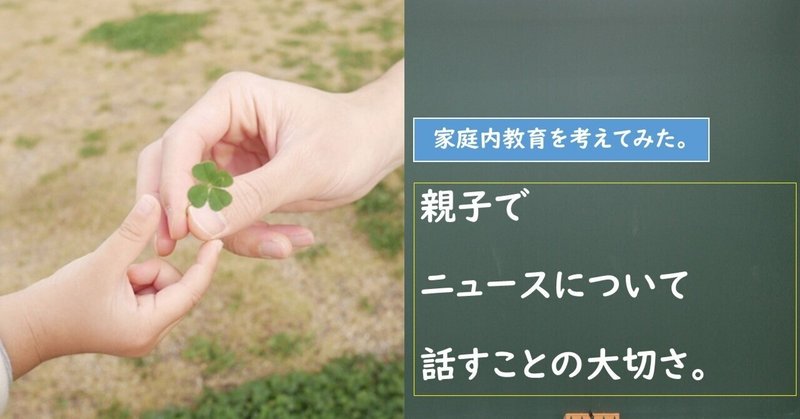
親子でニュースについて話すことの大切さ。
先週、ロシアによるウクライナ侵攻の授業を、高校1年生の「現代社会」という科目で行いました。
連日ニュースになっていたこともあり、生徒の関心が高く、集中して聞いていました。
授業の感想を聞いてみると、断片的な報道が多かったため、
全体像を分かりやすく教えてもらえて良かった、とのことでした。
また、こういうニュースの話題を人と話したことがないので、周りの人と対話ができて良かったという声もありました。
おそらくニュースについて家族で話し合うことは少ないのではないかな…と思います。
私が担当しているクラスは40人中約4人ほどしか、政治をはじめとしたニュースの話を家庭内で行っていませんでした。(^_^;)
私は中学生くらいからニュースを見て、
母から政治の内容を教えてもらったり、
新聞を毎朝隅々まで読む父の姿を見たりしていました。
そのためか、ニュースに対するアンテナは人より高い方だと思っています。
おかげで今の授業づくりに活きており、
世の中の流れが分かることで、
・今自分に何が必要なのか
・これからの社会で何が求められるのか
を自分の頭で考える習慣が出来ました。
そして、「自分だけに利益があればいい」という考え方ではなく、
「社会に貢献するためには何が必要か」という公益性が身に付いたような気がします。
思えば、そこが自分の原点になっているのかもしれないなと思いました。

学校現場では現在、主権者教育という名で「政治の関心を高めるための教育」を行っています。
模擬投票や討論会などを行い、政治参加への意識を高めるような授業を企画し、実施しています。
しかし、、、それも3か月に1回程度です(笑)。
高校によっては、もっとやっている学校もあるかもしれませんが、効果が充分にあるかと言えば、断言は出来ません。
実際、10~20代の投票率は約30%台です。
やはり家庭や友人間で政治の話を頻繁にする方が、より世の中に関心を持ちます。
高い投票率を出しているスウェーデンでは、親子間で政治の話をすることが日常であるという話を聞きました。

最近、熊本大学法学部の小論文の添削を行っていて、「個人主義による分断」というキーワードをよく目にします。
対話が少なくなってきていることへの危機感を伝えるような課題文が多く、私自身とても考えさせられています。
分断と格差が社会に如実に現れている中で、
世の中に目を向けてもらい、公益性を高めることがより重要になっているような気がしました。
私はまだ親になっていないので、もしその機会を与えてもらうことができたたなら、
親子でニュースについて語り合ってみたいなと思います(^^)。

教育のこと、授業をしている倫理や政治経済のこと、熊本の良いところ…。 記事の幅が多岐に渡りますが、それはシンプルに「多くの人の人生を豊かにしたい!」という想いから!。参考となる記事になるようコツコツ書いていきます(^^)/
