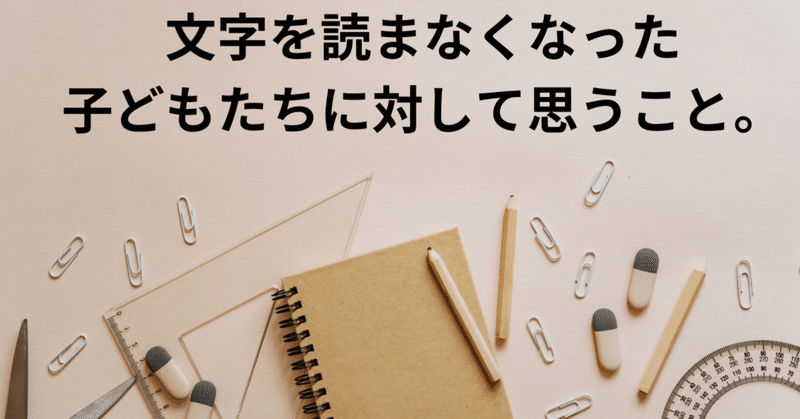
文字を読まなくなった子どもたちに対して思うこと。
お疲れ様です、よっしー先生です!
今日は学校現場で感じたことを思いのままにつぶやきます。
今回のテーマは「文字を読まなくなった子どもたち」。
授業をしながら、生徒たちが年々文字を読まなくなっていることを感じています。。。
その現状や原因、今後の見通し等々お伝えします。
文字を読まない子どもたちの現状
具体的にどういう場面で感じるか、というと、「資料集のこの部分に書いてあるから読んでみて」という指示を出した時です。
考え方を説明するときには必ず教科書や資料集の記述から説明します。
そのため、長い文章を提示して解説をしていかなくてはなりません。
出来るだけわかりやすく、コンパクトに伝えようとしているのですが、
生徒が引いていくのを感じます、、。
文字アレルギーというんですかね。。
そこでやる気が削がれている感覚を受けます。
そのため、授業スライドに文字をずらっと並べることはやめて、
出来るだけイラストや写真で説明するようにしています。
もしくは一気に出てくる文字をアニメーションを使って少しずつ出す、等の工夫をしています。
「読めば分かるのに、、、」と思ったことは一度や二度ではありません。。。
でも読もうとしない現実があります。
やっぱり配慮は必要だなと感じているところです。
そもそもなぜ、こんなに文章を読まなくなったのか
やはりスマホの影響がかなり大きいのではないでしょうか。
YouTubeショートやInstagram、TikTokに親しんだ彼らにとって、
教科書や資料集は無味乾燥なものに映るのではないかと思います。
動画はやはり刺激が強いですから、、。
長い文章を読み込んで、そこから学びとるという学習の仕方はハードルが高いのかもしれません。
図書館の先生に聞くと、貸し出し冊数はここ数年で激減したと言われていました。
学校現場にChromebookが入った影響もかなり大きいです。
文章が読めないとどうなるか
まず知識の絶対量が減ります。
動画を見るよりも文章を読んだ方が早いからです。
AIがあるから知識なんて要らないという意見もありますが、
考える力は育たないのでは、、と個人的には思います。
自分の頭の中で考えるということは、知識と知識をつなげて新しいアイデアを模索するということ。
その前提となる知識がある程度ないと、考えることが出来ません、、。
授業中に生徒に話し合わせる活動をさせていますが、
知識がある子とない子の対話の質は雲泥の差です。。
今の学習指導要領は、知識よりも学び方の方に焦点が当たっているため、
知識が軽視される傾向があります。
しかし、偏り過ぎてもいけないのかなと思っています。
文章を読ませるために工夫していること
私は以下の工夫をしています。
・ペアで教科書や資料集のある部分を丸読みさせる。
・ワークシートの穴埋めを、教科書や資料集から抜き出して記述させる。
・新聞記事をペアで丸読みさせる。
ペアでの丸読みは結構楽しんでやってくれています(笑)。
大学入試共通テストもかなり文章量が多いので、少しでも読む習慣がつけばな、、と思っているところです。
かくいう私もスマホばかり見てるので読書する事を心がけたいところです💦
教育のこと、授業をしている倫理や政治経済のこと、熊本の良いところ…。 記事の幅が多岐に渡りますが、それはシンプルに「多くの人の人生を豊かにしたい!」という想いから!。参考となる記事になるようコツコツ書いていきます(^^)/
