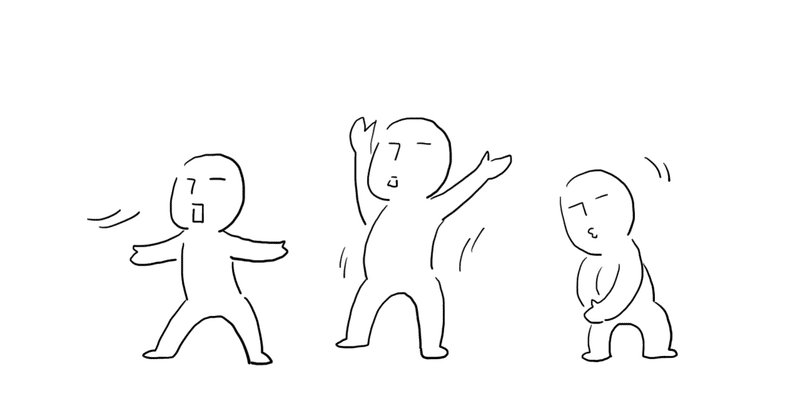
ヨガ、気功、呼吸法について。瞑想との関係
瞑想について調べると、その関連としてヨガや気功、呼吸法などに触れらていることも多いです。
瞑想関連としても あわせて検索されることがあるようです。
様々な考え方がありますが、今回は「瞑想する人」noteでの位置づけです。
ヨガ、気功、呼吸法はどれも瞑想と同じようにアロマテラピー(精油)との相性が良いように感じています。
フランキンセンスや樹木(森林浴、フィトンチッド)系が合うと思うのですが、ハーブ系なども含め好みのものを使用すると良いでしょう。
呼吸法ではユーカリ、ローズマリーなどシネオール系の精油やティートリーなども合うと思います。
アロマテラピー、精油の利用においては禁忌、使用量、換気などに気を付けて下さい。
香りが微かに感じられる程度の控えめの使用が良いと思います。
楽天ROOM:精油・フィトンチッド・ハーブなど
ヨガ(ヨーガ)
ヨガはインド発祥ですが、ホットヨガ他 現代においてアレンジされたものも人気があります。
エアリアルヨガ(ハンモックヨガ)なんてものもあります、笑。
インドの伝統ではヨガ(ヨーガ)は宗教・哲学・信仰と密接な関係があり、知識のヨガ、バクティヨガ、カルマヨガなどがあります。
本来は瞑想はもちろん思想、哲学、信仰も含めた体系がヨガであると言えるでしょう。
ここでは瞑想の実践に関連したもののみを考えます。
・体操(アーサナ)のヨガ
体操のヨガの中では、このnote記事ではリラクゼーションを目的とした静的ストレッチとしてのヨガに触れます。
各アーサナのポーズを維持する時間を長めにすると副交感神経が活発になり、筋肉、筋膜も緩み、精神的にもリラックスが得られます。
瞑想前にも適しています。
リラクゼーション効果によって瞑想状態へのスムーズな移行を助けます。また瞑想中の肩や背中、腰のコリや痛みの予防にも良いと思います。
もちろん就寝前にも適しているでしょう。
重要なコツとしては、慌てずに丁寧にポーズを維持すること、シャバアーサナを重視することです。
丁寧なアーサナ(ポーズの維持)とシャバアーサナによって得られるリラクゼーション、いわば「ヨガ的な休息」が醍醐味の一つです。
これに関して逸話があります。
有名な音楽家ユーディ(イェフディ、Yehudi)・メニューイン(1916-1999)は戦後1950年頃の一時期、ストレス、疲労感、神経の緊張など心身の問題に悩まされていました。
この状態はメニューインの音楽家としてのキャリアに深刻な影響を及ぼすほど酷いものだったようです。
この危機から彼を救ったのがヨガの実践だといわれています。
1952年にアイアンガーヨガの創始者のB.K.S.アイアンガーに出会い指導を受けました。
この時に指導されたのがヨガによるリラクゼーションの方法だといわれています。
急速に心身の状態が改善したメニューインは感動し、ヨガを賞賛するようになり、西洋でのヨガの広まりを手助けし、アイアンガーの著書に推薦文を寄せることまでしました。
メニューインの著書『ヴァイオリンを愛する友へ』(クリストファー・ホープ 編 岸本完司 訳 音楽之友社)にもヨガへの言及があります。
一連のアーサナ、シャバアーサナの後に後述するプラーナヤーマもするとさらに良いのではないでしょうか。
またシャバアーサナを、もっとじっくりと行うとヨガ ニドラというものになります。
ここでの体操のヨガは事実上は静的ストレッチなので、筋トレや運動などの前には適していません。その場合には動的ストレッチのほうが良いです。
消費カロリーもたいしたことないので、ダイエット(痩身)としても効率的ではありません。
ちなみに、体操のポーズ(アーサナ)には近現代になってヨガのアーサナとして考案されたものも多いようです。
有名な「太陽礼拝」も、西洋体育の理論・効果に感銘を受けたインド人のボディービルダーが考案して、それがヨガに組み込まれたようです。
注意事項としてはネットで調べると多く見つかりますが、アーサナによる事故、怪我もありますので、そういったリスクにも気を付けましょう。
このヨガは、要は静的ストレッチを用いたリラクゼーション法もしくはリフレッシュ法であり、リスクをおかしてまで難しいポーズに挑戦する必要は全くないと思います。
・密教的なヨーガ
体操のヨガとは毛色が違ったマニアックなヨーガがあります。
プラーナ、シャクティ、クンダリニー(クンダリーニ)といった「生命エネルギー」を扱うようなヨーガです。
これは特に宗教性、神秘性のあるものです。
このヨーガにおいては、それほど体操(アーサナ)は重視されない傾向があります。
呼吸法や瞑想が重視されます。
呼吸法も、健康目的とは違って、気を付けないと健康を害するようなものも含まれます。
主にバンダやクンバカといったものが用いられるムドラーといった呼吸法が重視されます。
(ここで言うムドラーとは手の印のことではありません。呼吸法のことです)
このような特殊な呼吸法などで「生命エネルギー」を活性化、目覚めさせて特有の意識状態を体験しようとするものです。
実践には健康被害も含めて様々な種類の危険がともなうことがあり、決して万人向けではありません。
クンダリニー(クンダリーニ)をテーマに扱っているとする書籍、ヨガ教室、ネット情報がありますが、実際には、具体的な実践方法や体験の過程に関する詳細な情報、体系的な理解に役立つものは出回っていません。
呼吸法(ムドラー)などの断片的な情報が見つかることもあるのですが、しかし周辺知識もなくて、そういったものを軽々しくやると健康を害することもあります。
視力、聴力の低下といったことから、失明、脳や心臓などの血管系の急性の症状など重篤なものも含まれます。
気功
気功には非常に多くの種類があります。流派、分類法も様々です。
武術気功、健康養生気功、内気功。仏家・儒家・医家・道家気功などなど。
歴史は非常に古いと言われ、たしかに諸説はあるのですが、紀元前の遺跡からも気功に関して記されたものが発見されているようです。
またこれについても諸説があるのですが、紀元前から、後に内丹(仙道)につながっていくような高度な瞑想の実践が既になされていたという主張もあります。
ちなみに「気功」という言葉は現代になって指定されました。大昔から統一的に用いられていたわけではありません。
吐納、導引、行気などと言われていたようです。
実践的には、動きをともなった気功である動功と、動かない気功である静功に大別できるでしょう。
・動功と静功
動功は健康体操のような要素があります。経絡・経穴や「気」の循環に関する中国伝統医学(中医学)の理論が背景にあって、動作が組み立てられていることが多いです。
有名なのは太極拳などの中国武術の動作を取り入れた気功や八段錦、五禽戯、大雁気功、易筋経(易筋洗髄経)などなどです。
禅密気功といった「背骨ゆらゆら体操」のある面白いものもあります。
これにはチベット密教(蔵密)の影響があるのかなぁ。この気功は瞑想も重視されるようです。
静功に関してはこれも様々なものがあるのですが、瞑想といっても良いと思っています。内功、静坐などとも呼ばれています。
立って行うものとしては站樁功(タントウ功、立禅)が有名です。
站樁功 ↓↓
この站樁功を重視する気功に少林内勁一指禅という非常に高名なものがあります。
これには動功の要素もあります。
小周天で有名な内丹(仙道)といった奥深い実践においては、特にこの静功が重視されます。
特に内丹においては、瞑想に関して返観、内視、内景といった用語も使用されます。
・経絡、経穴についての逸話
中医学においては経絡・経穴が説かれています。
これは科学的なエビデンスに乏しく、エセ医学、迷信だという批判もある一方で、これを用いた処置が有効なこともあると言われたりしていて知見・情報が錯綜とはしています。

この経絡・経穴がどのようにして発見されたのかということも不思議です。
武術修行の時や、石にぶつかったり矢に刺さったりして、偶然に見つかったのではなどの意見があります。
「経絡敏感人」といって、経絡の感知能力の高い人が存在すると言われることもあります。
気功においては、おそらくは後に特に内丹(仙道)の体系に結びついていくような修行において、発見されていったという説が主張されることもあります。
つまり気功の修行者によって、実際に「気の活動」を体験して発見されてきたという主張です。
古代中国においては医業にたずさわる人の中には、気功の修行者も多かったようです。
“ 中医学のもっとも基礎で、代表的な経絡論と気化論は、すべて内景の能力と密接な関係がある。 昔から医と道は相通じてきた。医学を学ぶ者の大多数は修道者であり、修道者のほとんどが医学に通じていたのもうなずけることである。” 『気功の真髄 丹道・峨眉気功の扉を開く』(張 明亮 著 KADOKAWA/角川学芸出版)p.223
“ 数百年前の中国の偉大な医家である李時珍はその著書『奇経八脈考』のなかで、「人体内景隧道、惟返観内視者能照察之(人体内景の隧道〈トンネル〉は、ただ返観内視する者のみが、それを見て理解するのだ)」としみじみと語っている。” 同上
瞑想によって生じる意識-脳・神経生理には、まだまだよく分かっていないことが多く、こういったこともあるのかもしれませんね。
関連note:奇経八脈(任脈、督脈、衝脈...)について。経絡と気功、瞑想
呼吸法
リラクゼーションや健康法として呼吸法を実践する人も多いです。
腹式(丹田)呼吸法、ヨガのプラーナヤーマなどがあります。
・健康目的の呼吸法
健康目的で行われる腹式呼吸(丹田呼吸)などです。様々な人が様々な呼吸法を提唱しています。
それなりに支持者がいるものとしては西野流呼吸法が有名なのではないでしょうか。
この西野流呼吸法には気功の要素もあります。( ⇒ 足芯呼吸)
他には藤田霊斎による調和道丹田呼吸法というのもあります。
個性が強いものとしてはヴィム・ホフ・メソッドの呼吸法があります。
これは健康目的でされているようですが、この呼吸法には後述する「密教的な呼吸法」に通じる性質があります。
ヴィム・ホフの呼吸法は、ハイパーベンチレーションによるブラックアウトが生じるリスクがあるので、寒冷訓練として水風呂とあわせて実践する場合には他に人がいる中でした方が良いと思われます。
フッと意識を失って深刻な低体温症や溺死といったリスクがあります。
・ヨガのプラーナヤーマ(ナディショーダナ、クンバカなどについて)
ヨガの呼吸法であるプラーナヤーマ(調気法)も健康目的で行われることもあります。
また瞑想前にするものとしても適していると思います。
この場合のコツはリラックスして、特に呼気を丁寧に静かに長くすることです。
プラーナヤーマではクンバカ(息止め)をすることがありますが、これをする場合には無理をして長くするのはダメです。力むのもダメです。
クンバカの効果としては神経の強壮、調整などと言われますが、実際的には過大評価するようなものでもないと思います。
数秒程度の短めのクンバカなら神経の安定、自律神経の調整などがあるようです。瞑想前にやると、その集中状態を助けたりするようです。
しかし無理をした長めのクンバカは必要ないと思います。
長い息止めで、血液が脳に向かい脳細胞の活性化に役立つという意見を目にしたことがあるのですが、これはトンデモ似非健康情報じゃないでしょうか?
これによって得られるメリットよりも、血圧・眼圧上昇、心臓・血管系疾患リスク上昇などによるデメリットの方が大きいように思います。
おそらく医学部の学生レベル以上の医学知識がある人で、長時間のクンバカが健康に良いと主張する人は、いないのではないでしょうか?
ヨガにおいては「クンバカによって身体にプラーナ(気)が補充される」など説かれることがあります。
こういった精神論は、お好きなら勝手にどうぞ、なのですが、こういったスピ系の世迷いごとを有り難がる前に大切にすべきことがあるように思います。
ちなみに今日では吸気後(プーラカ)のクンバカ(アンタラ・クンバカ)の時には、腹部のバンダ(ウディヤーナバンダ)はすべきではないとされることが多いです。健康に良くないからです。
プラーナヤーマで最も有名なものの一つにナディショーダナというものがあります。片鼻呼吸法とも言われています。
片鼻を交互におさえながら呼吸をします。クンバカを入れることがあります。
熟練を目指す場合には、吸気:クンバカ:吐気の時間の比率はまずは1:1:1から1:1:2へ、そして慣れるにしたがい1:2:2、さらに1:4:2が良いなどといわれます(私はここまでは全く関心ありませんが)。
この片鼻呼吸は、ひょっとするとネイザルサイクル(nasal cycle)と呼ばれる生理現象と何か関連があるのかもしれません。
交代性鼻閉などともいわれていて、要は右左の鼻の穴が交互に閉じたり開いたりする生理現象です。
このネイザルサイクルは片方の鼻を休ませたり、鼻の中の粘膜、神経の機能の維持のためにあるのではないか、などと言われています。
またこのサイクルには脳の視床下部が関わっていて自律神経支配とされます。(副交感神経支配であるという見解を聞いたことがあります。副交感神経の障害によってネイザルサイクルも見られなくなるという見解を聞いたことがあります)
しかしまだよく分かっていないことも多いようです。
とにかく、ヨガのプラーナヤーマによって、自己制御や感情、自律神経のコントロールなどに関わる脳部位が活性化するという知見があります。
特に熟練者ほど、それらの脳部位が活性化するようです。
あと、右鼻の穴が交感神経につながり、左鼻の穴が副交感神経につながるといった意見がヨガの実践者の中で述べられることがありますが、私は探してもそういった意見の神経生理的な根拠を発見できませんでした。
そういった意見、主張はエセ科学なのではないでしょうか?今後、根拠が発見されるかもしれませんが。
関連note:【ヨガの呼吸法】プラーナヤーマ、クンバカ、バンダ、ムドラーの簡単な整理
・密教的な呼吸法
人体において生命エネルギーの活動を生じさせることを目的とする呼吸法もあります。
前述のヨーガのムドラーもそうです。
主に高藤聡一郎氏によって有名になった仙道にも「武息」という呼吸法があります。クンバカをともなった呼吸法です。
この武息によって主に下丹田に気(陽気、真気などとも)を発生させて、小周天をするとされます。
この武息とほとんど同じものがチベット密教にもあります。
「ナーローの六法」などの「ツンモ(霊的な火)」を生じさせる呼吸法です。
特殊な呼吸法などによって人体にあるとされる「チャクラ」、生命エネルギーを活性化させるといったことが言われます。
チャクラに関連するnote↓↓
長時間のクンバカは、このような実践で行われることが多いです。
健康目的とは違います。
長めのクンバカは準備、やり方、手順があるので、それらをすっぽかしてやると健康被害などが生じます。
前述しましたが、ヨーガであれ呼吸法であれ、生命エネルギーといったものに関わる密教的な方法は万人向けでは決してなく、リスクがあるので、気軽に実践しないほうが良いと思われます。
瞑想との関係
ヨガ、気功、呼吸法は単独でなされることもありますが、どれもが瞑想前にも適したものだと思います。
ヨガはそのリラクゼーション効果によって瞑想への移行を助けます。
リラクゼーション法としてのヨガのアーサナとシャバアーサナ。その後にプラーナヤーマ。それらによって心身を整えて瞑想。
こういったヨガのプログラムは健康にもとても良いのではないでしょうか。
気功の伝統においては、子どもや初級者はまず動功を重視して静功(瞑想)へという段階が説かれることが多いです。
仏家(仏教系気功)においては、座って瞑想ばかりして健康を害した修行者のために動功が考案された経緯もあったようです。
西野流呼吸法や、ヨガのプラーナヤーマも瞑想への移行を助けると思います。
特に瞑想に慣れていない人は、ナディショーダナなどのプラーナヤーマを丁寧に長めにしてから瞑想すると良いかもしれません。
瞑想前のプラーナヤーマのコツはリラックスと丁寧な呼吸です。特に呼気の時に静かに丁寧に。
クンバカはしてもしなくても。する場合には2、3秒~10秒以下で。
クンバカをする時には無理をしないことです。
クンバカ中は力むのではなくて、心を鎮め安定させることの方がはるかに重要です。
プラーナヤーマを続けて心身が安定したら瞑想に移ります。
楽天ROOM:【本】瞑想・ヨガ・気功・呼吸法・密教・思想など
