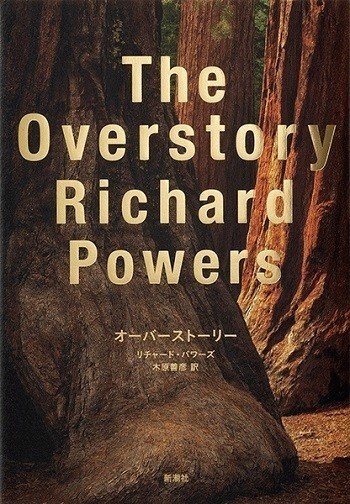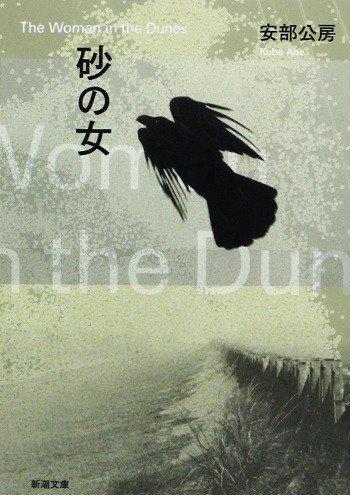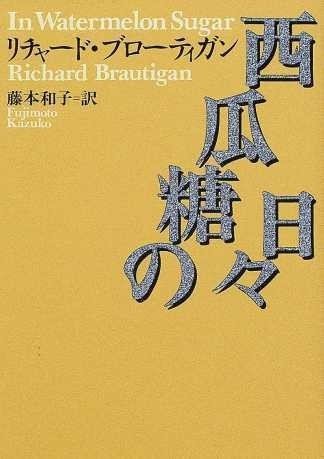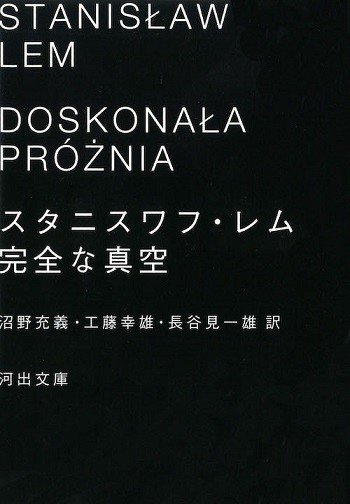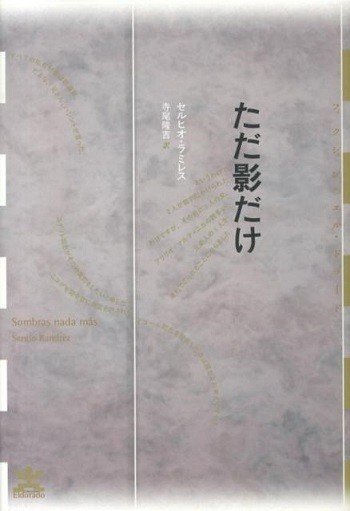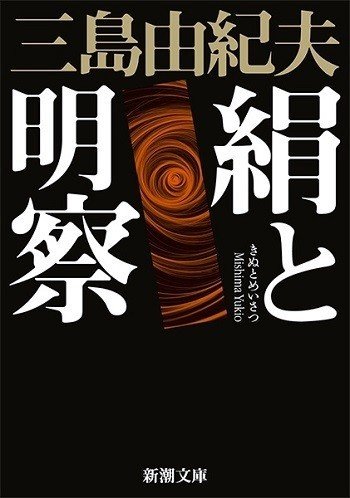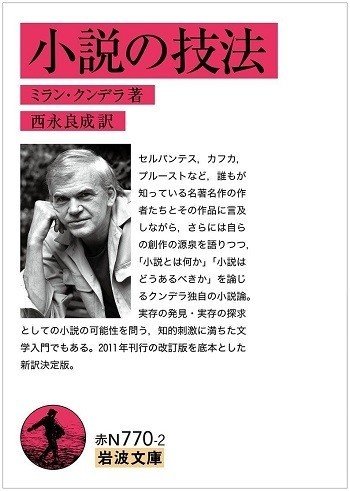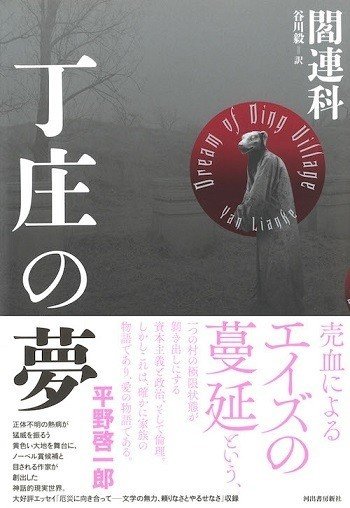【読書備忘録】オーバーストーリーから丁庄の夢まで
本文とは関係ないのですが、最近ものがよく壊れます。それも長期間現役生活を続けてきた長寿の家具類が次々と。夏の終り頃には10歳を超えるエアコンが壊れ、秋口には長兄のおさがりで30歳を超える学習机(作業用)が壊れ、先日40歳を超える電灯の照明カバーが壊れました。寝ていたら突然照明カバーが落ちてきたので心臓が口から出そうになりました。その前にも電気スタンドの傘が粉々になって買い替えましたし、明日は何が壊れるのだろうと戦々兢々する日々を送っています。学習机も棚の雑誌類を全部おろしたため置き場所に困っているのですよね。ただでさえ書物に部屋を追いだされそうな状況なのに、未解決状態のままさらに圧迫されてしまうとは。悩ましい状況ではありますが、身体まで壊すことのないよう気を付けます(この文章を書いてから約10時間後に嘔吐と下痢のコンボで四苦八苦しました。皆さまも体調管理には充分ご注意ください)。
前書きがただの近況報告になりました。29回目となる今回も紙から電子まで、昔から最近までの良書をご紹介します。皆さまの読書のお役に立てれば幸いです。
* * * * *
オーバーストーリー
*新潮社(2019)
*リチャード・パワーズ(著)
*木原善彦(訳)
木が酸素を排出しなければ人間は生きていけない。すなわち人間は木に生かされているといえる。ところが人間は日常生活を充実させる方法として森林を材料に変える道を選択した。自然保護を唱えるのは容易ではあるが、木材のない生活を想像することは非常に難しい。自分の日常を振り返る。部屋には木を原材料とする家具が所狭しと並んでいる。木製の机で作業し、木製の箸を使い、木製のタンスに衣類をしまい、木製の本棚に収納している本を読む。こんなありさまだから環境問題に踏み込み、生命の源たる森林を象徴的に表現した『オーバーストーリー』はなおさら胸に迫った。本作品は群像劇の形式で書かれている。家庭環境も性格もまったく異なる九人の主役。けれども主役たちは何らかのかたちで木との関わりを持っており、その記憶と絶滅の危機に瀕するアメリカ大陸最後の原始林が呼応するように、森林伐採という難題に向かっていく。栗の木を写真におさめてきた一族の末裔、ベンガルボダイジュに命を救われた帰還兵、感電死するも光の精霊の導きで息を吹き返した女子大生、聴覚障碍を抱えながら植物研究に従事する学者など。成長する大木の枝葉のように縦横無尽に広がり、森林の息吹を具現化する彼/彼女たちの物語は自然界の危機を伝える痛切なメッセージである。
われら
*光文社古典新訳文庫(2019)
*エヴゲーニイ・ザミャーチン(著)
*松下隆志(訳)
近現代ディストピア小説の先駆的作品。宇宙船の建造技師Д-503の日記という体裁で、癖のある文体と断章形式で展開する。舞台は約一〇〇〇年後。絶対的支配者である「恩人」の統治下で、人民は「単一国」という緑の壁に覆われた管理社会で生活していた。プライバシーは存在しない。名前は番号に替わり、住居はガラス製の集合住宅。日常の言動は監視・盗聴対象で、性行為も予約制で当局にピンク・クーポンを申請する必要がある。けれども管理社会下で教育を受けてきた人々は統制に不満を覚えることはなく、Д-503を始め現体制を賞賛し、統治以前の社会を下等なものと見くだしている。すでに「恩人」による支配は、人間の思考まで行き届いている。その中、古代の文化を尊ぶI-330が宇宙船インテグラルの建造技師であるД-503を誘惑し、国家転覆を企てるのであった。エヴゲーニイ・ザミャーチンが『われら』の執筆を開始したのは一九二〇年。もっとも全体主義を風刺する内容故ソ連で発表できず、一九二七年チェコにて出版。ロシアで出版されたのは一九八八年だった。後にジョージ・オーウェルに影響を与えることになった問題作の鮮度は、一世紀を経ても薄れていない。
砂の女
*新潮文庫(1981)
*安部公房(著)
二〇数箇国語に翻訳された『砂の女』は、不条理の表現者安部公房の名を世界文学史に刻み付けた名作として、初版刊行後半世紀以上経た今も愛読されている。本作品は安部公房作品を知る契機となったもので個人的に思い入れが深く、懐古的な気持ちで手にとった。しかし、読み返したら閉鎖的な砂の世界に立ち込める圧倒的な虚無に、新鮮な感動を覚えてしまった。主人公は仁木順平という教師。彼は歪な夫婦関係と憂鬱な教職に辟易し、空虚な日常から逃れ、昆虫採集に没頭するため休暇を利用して海岸沿いの部落を訪れる。ところが男は砂穴の底にある民家に閉じ込められて、住人の寡婦と砂掻きをさせられることになる。ここから始まる男の悪戦苦闘は壮絶である。脱出を阻む砂丘は蟻地獄を連想させる。砂はまるで生きもののように蠢き、部落を飲み込む勢いで休まず流動する。愛郷精神を旨とする住民は監視を怠らず、同居している寡婦は居場所を守るため男を引きとめる。友好的な態度を崩さないまま核心には触れさせない狡猾な住民たちは不気味極まりなく、脅迫めいた言動をしてもいないのに強固な抑止力を働かせる。そして、部落にも男にも従順な寡婦は逃走を妨げる蟻地獄の主であり、砂穴での監禁生活を日常に変えていく存在として象徴的に描かれる。作中ではたびたび砂の流動性が語られるけれども、日常的に砂穴で生活するようになる男を観察していると、彼もまた流動する砂の一粒に見えてくる。
西瓜糖の日々
*河出文庫(2004)
*リチャード・ブローティガン(著)
*藤本和子(訳)
詩人にして小説家であるリチャード・ブローティガン。このビートニク思想を継承するヒッピー文化の象徴でありながら、流行の終焉とともに存在感を喪失した表現者は、ある意味では時流の犠牲者だったのかも知れない。少なくともヒッピー誕生以前に発表した『西瓜糖の日々』に社会的運動との縁はうかがえないし、俗世間を断絶したような作法には日本でいう隠者文学に通ずるものを感じる。不思議な空間を舞台としており、アイデスと呼ばれる共同体の地と、忘れられた世界と呼ばれる場所が共存している。小屋や橋は西瓜糖で作られていて、西瓜鱒油でランタンに火を灯す。人々は単調ながら平穏な日常を営んでいる。あるとき、主人公は知人の勧めで一七一年間で二四冊目である本の執筆に着手することになるが、本作品はその記述内容である。西瓜工場、野球公園、送水管、鱒の孵化場。断章形式で淡々と描きだされる風景はお伽噺に出そうな奇妙なものばかりで、どこか死後の世界を連想させる。特にマーガレットという女が足繁く通う「忘れられた世界」は生死の境界線を現しているようであり、その入口に居座るインボイルを筆頭とする荒れくれ者たちは門番のようである。
完全な真空
*河出文庫(2020)
*スタニスワフ・レム(著)
*沼野充義(訳)
工藤幸雄(訳)
長谷川一雄(訳)
長編小説『エデン』『ソラリス』『砂漠の惑星』などでSF文学界の重鎮に君臨したポーランドの作家スタニスワフ・レム。けれども『完全な真空』はSFではないし、そもそも小説なのかもわからない。勿論小説なのは間違いないのだけれども、本作品は架空の書物を論じる書評集という特殊な内容なのだ。架空の書評自体はボルヘスやラブレーを始めとする先駆者がいるのでスタニスワフ・レムの発明ではないと冒頭で語られる。ただしこの冒頭も『完全な真空』の書評として書かれている点には充分留意しなければならない。とりあげられている書物は一六を数える。前半部の『ロビンソン物語』『ギガメシュ』などに見られる風刺的な論評、それから小説の草案に言及する『親衛隊少将ルイ十六世』『白痴』などを経て、ノーベル賞受賞者アルフレッド・テスタ教授の講演を書き起こした『新しい宇宙創造説』に至る。各作品と各作者に言及する語り口はそれぞれ独創的な癖を覗かせており、複数の書評家を想像させる作りになっている点もフィクションに対する批評性を高める要因になっている。メタフィクションの一言で片付けるのは語弊がありそうだが、メタフィクションの基本であるフィクションにおける自己言及という条件を支柱とする本作品は、メタフィクションの極北にあるといえるのではないだろうか。
拷問人の息子
*インゲン書房(2020)
*松代守弘(著)
本作品はnoteで連載中『拷問人の息子』の電子書籍版である。舞台は「黄衣の王」を信仰する組織の支配下にある「帝国」という異世界で、主人公は管区の筆頭拷問人と呼ばれる役職に就いているエル・イーホという人物。あるとき彼は機械化異端審問官にして「非神子」という不老の奇跡術者であるメルガールの依頼により、パブロス司祭の拷問を請け負う。このパブロスは聖職者にあるまじき不埒者で、醜聞が絶えないばかりか、調査の末に貴重な「蜂蜜酒」の横流しにも手を染めていたことが発覚する。そうして拷問人の息子たるエル・イーホの「蜂蜜酒」探しは幕をあけるのであった。本作品はクトゥルフ神話の骨組みに、少女を素体とする「非神子」などのライトな要素と、マカロニウエスタンの渋味を混合することで独創的な映像性を生みだす点が特徴で、その個性を支える設定資料は制作ノートで確認することができる。また、グルメとエロスを日常的に溶け込ませる表現を持ち味とする松代守弘氏の筆致も見どころ。さりげなく描かれる食事風景には唾を飲み、濃厚な性表現には息を呑む。この類の陶酔感は併録されている外伝『聖なる処女のうんちは紫とうもろこしの味』で溺れるほど味わえるので、これから読まれる方は心して。
ただ影だけ
*水声社(2013)
*セルヒオ・ラミレス(著)
*寺尾隆吉(訳)
ニカラグアを支配してきたソモサ政権と、サンディニスタ民族解放戦線の激突を主題とする長編小説。セルヒオ・ラミレス自身反ソモサ派の筆頭としてサンディニスタ民族解放戦線を支援した後、副大統領を務めた経歴の持ち主だけあって、革命の背景に切り込む筆致は鋭利である。それでいて説教臭いわけではなく、写実的な物語という認識を与えておきながら、史実の合間に虚構を織り交ぜることで読者を混乱させるといった、小憎らしい演出を凝らすことで物語性を強めたりもしている。また、私設秘書官アリリオ・マルティニカも虚実の境界線に砂をかける要素としてあげられる。モデルはソモサの側近として独裁政権を支えたコルネリオ・ヒュック。物語は彼に関する尋問・証言・調書といった複眼的な文章で構成されており、作中にはアリリオ・マルティニカの元妻ロレナ・ロペスの作者宛書簡に一章を費やすところもある。架空人物の元妻と著者自身の対話。何という紛らわしさ。この奇妙な章のおかげで、すっかりアリリオ・マルティニカを実在人物と勘違いしてしまった。こうした現実と架空の倒錯現象が意図的になされているのはいうまでもなく、物語の力、フィクションの効力に対する小説家セルヒオ・ラミレスの信念を読み取ることができる。
絹と明察
*新潮文庫(1987)
*三島由紀夫
近江絹糸における労働争議をモデルに、旧態依然とした経営法で業績を伸ばしてきた紡績会社社長の栄枯盛衰を描き、日本古来の精神と父性の問題に言及した三島由紀夫後期の名作。紡績会社を営む駒沢善次郎は日本的家族を旨として、社長である自分を「父」、従業員を「子」に見立てる家父長経営に終始していた。その実情は従業員の私生活に干渉するばかりか、父親の権威で抑圧的な管理体制を敷くものであった。駒沢の古臭さはアメリカ流の経営学を取り入れている同業者の失笑を買いながらも、その成長ぶりに危機感を覚えさせることにもなり、経営破綻を画策する動きが出始める。そこで抜擢されたのは政財界に通ずる岡野という人物。岡野は知り合いの芸者菊乃を諜報員として工場に送り込み、血気盛んな若者大槻を扇動するなど、駒沢紡績に不満を抱く従業員に反逆のきっかけを与えていく。この小説は複数の対立を骨子にしている。そこには日本的な家族における父と子があり、経営者と労働者があり、欧米の近代主義と日本の精神風土がある。駒沢善次郎という哀れな道化によって構築される対立構造。日本主義を表す「絹」と、輸入された合理的思想である「明察」を追究することは、本作品における対立構造を理解する上で要となる。
小説の技法
*岩波文庫(2016)
*ミラン・クンデラ(著)
*西永良成(訳)
世界文学の筆頭格に数えられる小説家ミラン・クンデラ氏が一九七九年から一九八五年までの六年間に発表したテクストをまとめ、実作者としての小説観を展開する評論集。小説技法に音楽理論を組み込むクンデラ氏の、ポリフォニックな七部構成に対するこだわりは評論集『小説の技法』でも認められる。セルバンテスに関する講演原稿の書き改め、分割されている対談、ブロッホ『夢遊の人々』を題材とする小説論、カフカ作品で表現されるカフカ的なる世界の解説、六九語に及ぶ小説の辞書、エルサレムでの講演。異なるアプローチで小説の根幹に迫る手法がポリフォニーを形成する。まるで小説を読んでいるような気持ちになる。もっとも執筆時期は受難の連続だった。この六年間は政治的抑圧の影響で創作活動を制限され、客員教授に招かれてフランスに出国後チェコの国籍を剥奪されてしまい、フランスの市民権を取得することになった頃とかさなる。また、同時期のフランス文学界も揺れ動いており、新たな価値観の萌芽とともに小説の終焉を唱える潮流が生まれていた。この状況下でヨーロッパにおける小説史観をよりどころに、小説の可能性を主題とする評論を多数寄稿したことを踏まえると、その並々ならぬ覚悟が輪郭をなしていく。
丁庄の夢
*河出書房新社(2020)
*閻連科(著)
*谷川毅(訳)
この物語は毒入りトマトで殺された少年「丁小強」の独白である。河南省東部の村「丁庄」は、脱貧致富を目指す中国政府による売血政策に乗じ、結果的に多数のエイズ感染者を生むことに。少年の魂は売血運動に加担した祖父と父、あるいは売血したために感染した叔父の苦悩と混乱の日々を語っていく。エイズ蔓延が原因で丁家と村民は一触即発の状態だった。しかし、父は積極的に売血を推し進めながらも悠然たる態度を取り、罪の意識に責めさいなまれる祖父とは対立を深める。それから祖父は患者を学校に隔離してその終活を見守り始めることになるが、皮肉にもこの移住は幾度にもわたり騒動の引き金を引いてしまう。死を間近に控えても人間とは欲に駆られる生きもので、次々語られる患者のエピソードは権威や見栄に対する憧憬で彩られている。そこには生々しい人間臭さが立ち込めていて、愚かしく悲しい愛憎劇を何度も何度も目撃することになる。けれども村民が滑稽にも映る愛憎劇を演じる背景には、豊かな日常を求めざるを得ず、豊かさを求める故に破滅に至る社会の構造が控えており、丁家も村民も、誰もが被害者である事実を物語っているのだ。
〈読書備忘録〉とは?
読書備忘録はお気に入りの本をピックアップし、短評を添えてご紹介するコラムです。翻訳書籍・小説の割合が多いのは国内外を問わず良書を読みたいという筆者の気持ち、物語が好きで自分自身も書いている筆者の趣味嗜好の表れです。読書家を自称できるほどの読書量ではありませんし、また、そうした肩書きにも興味はなく、とにかく「面白い本をたくさん読みたい」の一心で本探しの旅を続けています。その旅の中で出会った良書を少しでも広められたい、一人でも多くの人と共有したい、という願望をこめてマガジンを作成しました。
このマガジンはひたすら好きな書籍をあげていくというテーマで書いています。小さな書評とでも申しましょうか。短評や推薦と称するのはおこがましいですが、一〇〇~五〇〇字を目安に紹介文を記述しています。これでももしも当記事で興味を覚え、紹介した書籍をご購入し、関係者の皆さまにお力添えできれば望外の喜びです。
お読みいただき、ありがとうございます。 今後も小説を始め、さまざまな読みものを公開します。もしもお気に召したらサポートしてくださると大変助かります。サポートとはいわゆる投げ銭で、アカウントをお持ちでなくてもできます。