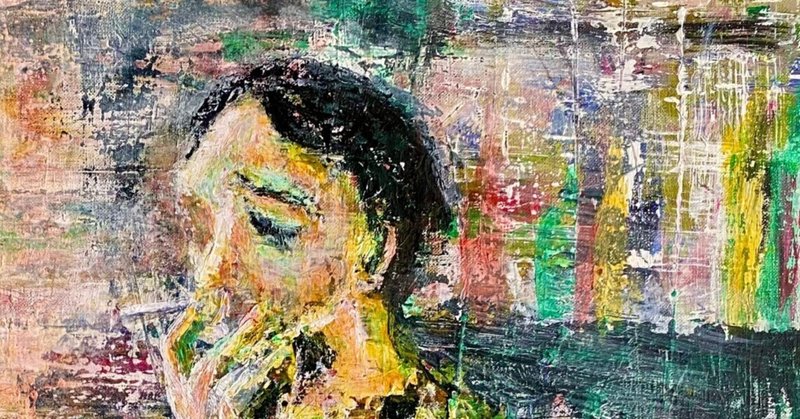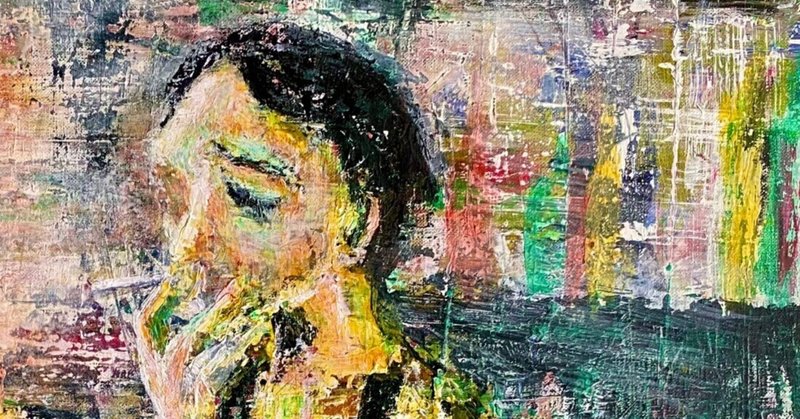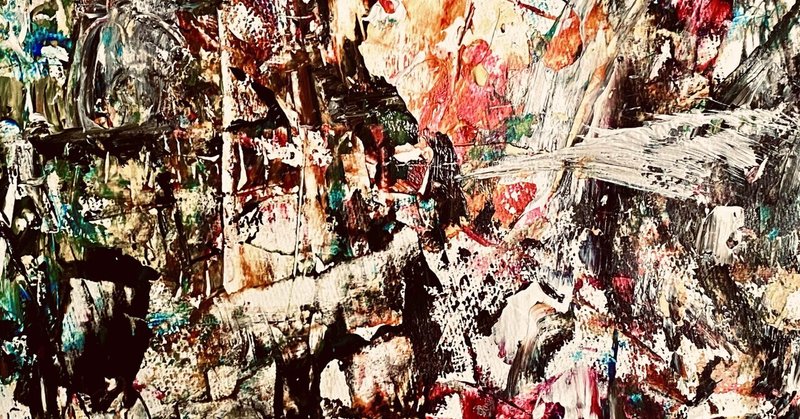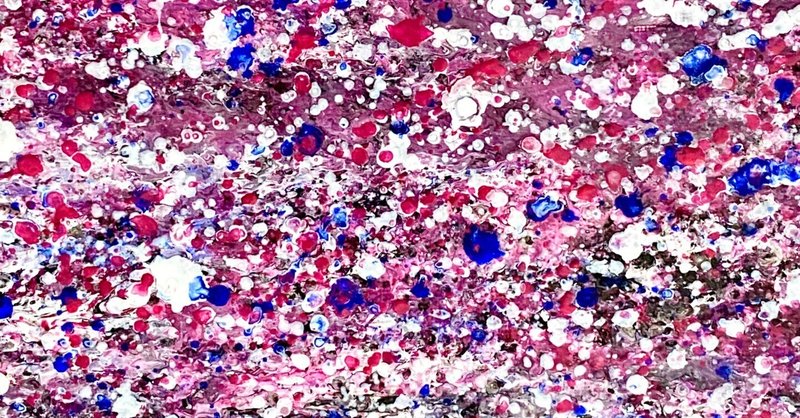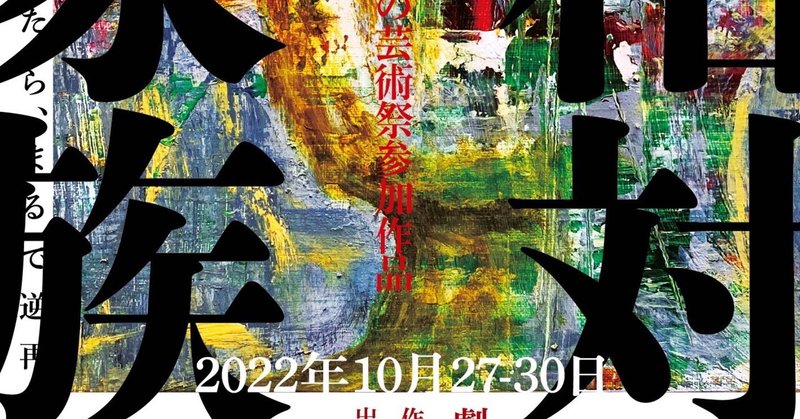記事一覧
【聞き流す募集要項】演技を学問し実践する短期コミュニティ「ソマティック映像演技研究コモンズ」第二期 参加者募集
前回の記事『演技を学問し実践する短期コミュニティ「ソマティック映像演技研究コモンズ」第二期 参加者募集』ですが、ワークショップの募集要項としては長すぎる!難しくてわからない!というご指摘をいただきました!!
そこで、【聞き流す募集要項】を作成しました!
募集要項の内容を音声で読み上げ、解説しております!
お散歩やランニング、筋トレや料理に掃除のお供に、聞き流しながら募集要項の内容をご確認いただ
演技を学問し実践する短期コミュニティ「ソマティック映像演技研究コモンズ」第二期 参加者募集
この度、「ソマティック映像演技研究コモンズ」第二期の参加者を募集します。役者だけでなく演出家・プロデューサー・脚本家・その他技術職の方など、映画制作やコモンズに関心のある方は是非ご検討ください。
週一回のワークショップを活動の中心としながら集まったメンバーの特性を元に映画制作の新しい可能性について考え実践していきます。
以下、「ソマティック映像演技研究コモンズ」について説明していきます。
※
『演技と身体』Vol.53 世阿弥『能作書(三道)』を読み解く
世阿弥『能作書(三道)』を読み解く『能作書』(あるいは『三道』)は、世阿弥の中期の書で、風姿花伝の第六 花修で述べられていた書き手の心得をさらに具体的に書き記したものである。(花修の内容はVol.27世阿弥『風姿花伝』を読み解く② 実用編を参照)
主に書き手向けのものと思われるが、書き手だけでなく役者が留意すべきことも読み取れるのではないかと思う。基本的には能の場面展開を前提とした内容ではあるが一
『演技と身体』Vol.52 反応と応答
反応と応答反応の鮮度
最近、ふと考えたことを忘れないうちに書き留めておこうと思い書くものである。
演技の中で上手く反応することが大事なのは言うまでもない。よく反応するためには、相手をよく聴くこと、相手に十分な注意を払うこと。当然このようなことが思い浮かぶのだが、何かそれだけでは十分ではないような気もする。
というのも、相手に注意を払っている時、初めから自分が何に反応をするかを決め込んでしまってい
『演技と身体』Vol.51 サブテキストの活用とクオリア
サブテキストの活用とクオリア『世界は時間でできている: ベルクソン時間哲学入門』(著:平井靖史)を読んでいるのだが、すこぶる面白い。まだ読み途中なのだが、演技に敷衍できそうな重要な示唆があったので、思いついたままに書こうと思った次第である。
サブテキストの有効性と弊害
〈役の設定〉について僕は従来から、脚本に書かれていない設定は不要であるという立場を取ってきた。物語とは明らかに人生や生活の抜粋
『演技と身体』Vol.50 内臓一元論③ 内臓と身体意識
内臓一元論③内臓と身体意識前々回の記事では内臓感覚と感情の結びつきを確認した上で内臓が無意識の領域に属することを説明した。
また前回の記事では、内臓感覚を活性化させるための身体の使い方などについてお話した。
今回はより積極的な内臓への働きかけを考える。
内臓反応をいかに方向づけするか
内臓感覚が無意識の感覚なのだとすると、そこを意識的に動かすことは難しいし、狙った感情に簡単になれちゃうのもちょ
『演技と身体』Vol.49 内臓一元論② 内臓でみんなうまくいく
内臓一元論② 内臓でみんなうまくいく前回の記事では改めて感情表現における内臓感覚の重要性を確認した上で、無意識や呼吸と内臓の関係を考察した。
今回はもう少し具体的に内臓感覚を研ぎ澄ます方法をまとめてみよう。
内臓中心に姿勢を考える
内臓の感受性が感情の豊かさと深く関連するならば、望ましい状態は物理的に余計な負荷や制限が内臓にかかっていないような状態である。一言にしてしまえば、姿勢正しく力みのな
『演技と身体』Vol.48 内臓一元論① 内臓・無意識・共感・呼吸
内臓一元論① 内臓・無意識・共感・呼吸この連載は今年の1月から始めて毎週欠かさずに更新してきた。
続けることが一つの目的ではあったものの、案外書く内容に困ることもなく続けてくることができた。しかし、もう1年やれるかと聞かれたら「めんどくさい!」という言葉が反射的に出てくる。それくらい面倒なのだ(まあ、好きでやってるんだけどね)。
まだ世阿弥の芸論など紹介しきれていないものもあるので、不定期に更新は
『演技と身体』Vol.47 身体意識のサイズと粒度
身体意識のサイズと粒度断片的な身体意識と統合された身体意識
普段私たちが生活の中で自分の身体を意識する時間は案外少ないかもしれない。身体が平常運転をしているうちは特に身体を意識する必要はないからだ。しかし、全く意識していないとも言い切れないように思う。
例えば今ここに書く言葉を頭で整理していざタイプしようと右手を上げたほんの一瞬、意識は右手にあったように思う。0.5秒にも満たない短い時間であった
『演技と身体』Vol.46 世阿弥『至花道』を読み解く②
世阿弥『至花道』を読み解く②前回に引き続き世阿弥、中期の伝書『至花道』を読み解いていきたい。
世阿弥の伝書では前期の作『風姿花伝』が最も有名だが、『風姿花伝』は父・観阿弥の教えを書いたものとも言われているので、世阿弥の独自性が出てくるのは中期の作以降とも言える。そして、世阿弥の特徴はその抽象性にあると思う。能の演目でも、世阿弥が作った作品は人物の想いが非常に抽象化されたイメージを纏っている感じがす
『演技と身体』Vol.45 世阿弥『至花道』を読み解く①
世阿弥『至花道』を読み解く①今回は世阿弥の中期の伝書『至花道(しかどう)』を読み解いていく。
前回紹介した『音曲声出口伝』と比べると概念的なところも多いが、それだけに汎用性が高い。世阿弥が57歳の時の作で、世阿弥の中でのテーマが“花”から“幽玄”へと移ってゆく時期である。
花から幽玄へ
“花”から“幽玄”へ。というのはどのような変化なのだろうか。
それが最もよく表れているのが『至花道』の中の「
『演技と身体』Vol.44 世阿弥『音曲声出口伝』を読み解く
世阿弥『音曲声出口伝』を読み解く今回は世阿弥の中期の伝書『音曲声出口伝(おんぎょくこわだしくでん)』の要点を書こうと思う。書名からもわかる通り、主に発声や謡について書かれたものであるが、読んでみると非常に細かい点にまで言及されていてすごい。
「風姿花伝」と比べても細かな技術書という感じがする。能の発声は特殊すぎるようにも感じるがそれは表面的な部分に過ぎず、あくまで全身で発声すること、演技の面白さを
『演技と身体』Vol.43 観客の身体性
観客の身体性演技における身体性といえば普通、役者の身体性を思い浮かべるだろう。だが、役者や作り手は最終的には観客の身体性にも責任を持たなければならない。つまり、作品を受け取る側の身体に何が起こるのかについてまで考える必要があるのだ。
観客の身体性の変遷
観客の身体性はメディアの歴史に応じて変化してきた。というか失われてきた。
スポーツ観戦を例に考えてみよう。スポーツを観戦する本質的な気持ちよさ