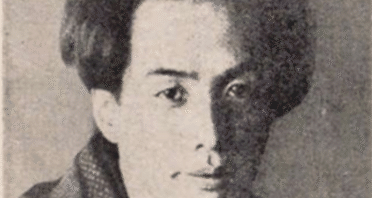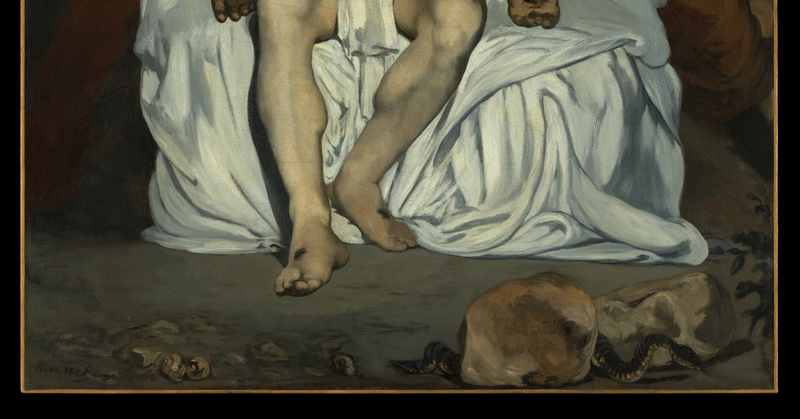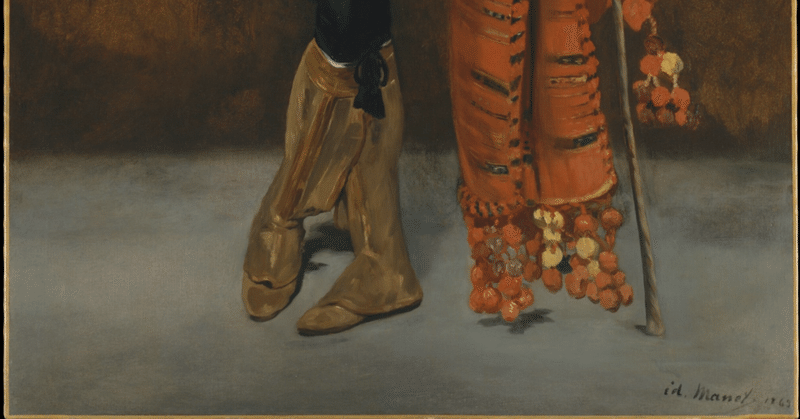2023年9月の記事一覧
芥川龍之介の『鼠小僧次郎吉』をどう読むか① 東方の遊び人
三島由紀夫は『大鏡』の「顕証にこそありけれ。いかがすべからむ」とある「顕証」の文字をはっきり覚えていて、この字を現代小説に使おうとする。
つまり三島由紀夫は『夜の寝覚』に三か所、『栄花物語』に一か所、『更級日記』に一か所、『枕草子』に七か所、『蜻蛉日記』に「顯證」として一か所、や『紫式部日記』に三か所、『源氏物語』に八か所、『竹取物語』に一か所、『落窪物語』に一か所、「顕証」の文字があること
芥川龍之介の『点心』をどう読むか⑪ もうやり直しは出来ない
ここまで『点心』は作家芥川龍之介が大正十年の正月から二月にかけて、もの思うことというていで書かれてきた。随分難しい理屈もこねられた。博識も披露した。
その中に最後にポツンと極めて短い小説のような「蕗」が置かれている。勿論小説と呼びうるほどの長さではない。しかし構えとしては『蜜柑』や『トロッコ』と変わりない。回顧の形式の中に詩的関興が込められている。現在の作家芥川龍之介とも連絡をもち、何をかの
芥川龍之介の『点心』をどう読むか⑩ そんな事を言われても違うものは違う
「数日後に明らかになるように、芥川龍之介は徹底的に調べ尽くす作家である。『点心』ではこの後芥川が時代考証に賭ける意地のようなものを見せつける」と、先日書いた通り、ここは芥川が時代考証に賭ける意地のようなものを見せつけているように思えなくもないところではある。
問題の「虫の垂衣」はここに現れる。
ところで同じ名前でも時代によって同じものを指すとは限らず、多く鎌倉時代の女の旅の衣装として描
芥川龍之介の『点心』をどう読むか⑨兼『文芸的な、余りに文芸的な』をどう読むのか② 何かが仕掛けられている
Ambroso Bierceは Ambrose Gwinnett Bierceの誤りのようだ。というより『悪魔の辞典』のビアスと言えば、今では多くの人が「ああ何となく知っている」と思うのではなかろうか。
そうだ。なにが面倒くさいのかよく分からないが、Ambroseは「A」と略されていた。Bierceで「ビアス」と読むのかとは今、初めて知った。
で何故アムブロオズ・ビイアスが語られているか
芥川龍之介の『点心』をどう読むか⑧ 文意が捻じれている
https://academic-accelerator.com/Manuscript-Generator/jp/Alberto-Blest
※アルベルト・ブレスト・ガナ
漱石のようにその作品に於いて英吉利臭さというものをほとんど見せない芥川だが(漱石作品ではしばしば地の文が翻訳調となる。)、こうしたものを読む限り、広く海外文学に触れてはいたようだ。
しかしこの話は細かく見ると少し
芥川龍之介の『文芸的な、余りに文芸的な』をどう読むか① 一人だに聞くことを願はぬ詞を歌はしめよ。
昨日、この記事で、
この言葉に引っかかった。これまでにも何度となく読んできたはずの所だが、改めて眺めると解らないところだ。
まずこの『文芸的な、余りに文芸的な』は極めて事務的に、当該喫緊の課題としての谷崎潤一郎との論争に整理をつけようというのか、「話」らしい話のない小説、谷崎潤一郎氏に答ふ、として始まる。
最近はこんな真剣な論争があるのかないのか知らないが、——あれば少しは文芸誌の売
芥川龍之介の『点心』をどう読むか⑦ KDPなら七割だ
こちらとは別人。
当時の一フランを現在の日本円に換算するといくらになるのかという値は様々に言われている。基準にするものによって計算上かなり開きが出るようで、諸説あり、余りに幅が広いので、ここではその数字を挙げない。ここで言われているのはあくまでも「一割という取り分が百年経っても変わらないので日本は遅れているのではないか」ということだ。
これを読んだ現代の作家なら、現在の印税は一割貰えない
芥川龍之介の『点心』をどう読むか⑥ 芥川はどこまで知っていたのか?
※「渦福の鉢」……高台の銘が渦を巻いたような「福」の鉢。ただし明治十八年以降は柿右衛門窯の鉢という意味になる。
※「白銅」……大正六年発行の大型五銭白銅貨のことか、あるいは大正九年発行の小型五銭白銅貨のことか。どちらとも判断しかねる。
※「剞劂に付した」……上梓した。
さて、この話の肝はどこにあるのだろうか。
私は「香港上海の支那人の中には、偶然この本を読んだ為めに、生涯托氏を師と仰いだ
前田雀郎『芥川龍之介と川柳』 その日は涼しかった
芥川龍之介氏と川柳
—私をして語らしめよ—
「唯僕に對する社會的條件。···僕の上に影を投げた封建時代のことだけは故意にその中にも書かなかつた。なぜ又故意に書かなかつたかと云へば、我々人間は今日でも多少は封建時代の影の中にゐるからである」これは芥川龍之介氏の遺書「或舊友へ送る手記」の一節である。が、私はこの短い文章の中に何か芥川氏らしい—東京人としての芥川氏らしいある姿を感じない譯にはいかない
芥川龍之介の『点心』をどう読むか⑤ 少しはあれも必要だ
この話の面白いところは、「夏雄の事」で「香取秀真氏の話によると」としてまさに「私の友人のなにがしがかう云ふ話をして聞かせた」式の話を入れているところではなかろう。むしろ「もし年をとると共に、嘲魔のみが力を加へれば」と書きながら、二年後には正岡子規に喧嘩を売る『芭蕉雑記』を書くところにあるのではなかろうか。『芭蕉雑記』には冷酷な、観察的なところがないとは言えない。いや、ある。
ともかくも「嘲魔
飯田蛇笏『俳人芥川龍之介』
重患のはげしい痛苦で、泣きわめきながら文稿をつゞつた不敵な魂の持主である正岡子規と、どうした因緣か齡を同じうして現世を去つていつたのは芥川龍之介であつた。子規と龍之介といふ人物との對照は、又別に相當興味ある問題を構成し得べきものでもあるのだが、それはそれとして、一脈相通ふところのものが看破されるのは、その不敵なたましひの有りやうである。
龍之介も子規といふ人物のそのたましひに次第にひかれてゆ
芥川龍之介の『点心』をどう読むか④ そりゃあんただろう
惝怳
普通に読めばまず「そりゃあんただろう」と言いたくなる。誰が、ではなく、その大任はあなたがひきうけるべきなのではないかと。漱石門下からは何人か作家が現れたものの、現代でも名前が残るのは内田百閒と芥川くらいなもの。後は探せば出てくる程度で、この二人には遠く及ばない。だからやはり芥川が書くべきなのではなかったのかと思ってしまう。現に書いたそばから誰かがそういうのではなかろうか。
しかし「少
芥川龍之介の『点心』をどう読むか② 本当に彼は困ったものです
困ったものだ。
どう読むも何も「千葉勝が紙幣を愛したやうに」の「千葉勝」がもう解らない。
香取秀真は近所の彫金師。
香取秀真が加納夏雄の話をしてきて「千葉勝が紙幣を愛したやうに」とあるので、どうも紙幣の図案にかかる絵師ではないかと想像するが、あれこれ調べても名前が出てこない。
これではどう読むのかもないものだ。
しかしここはそう難しい話にしなくとも良いだろう。「点心」とはせい
芥川龍之介の『点心』をどう読むか① 正々堂々と隠されている
鶉居はどこからきたの?
御降り
この話の面白いところは、鴨居にぶら下がった少年が落ちたかどうなのか解らないところ、その顛末を曖昧に、「して見れば御降りの記憶の中にも、幼いながら嫉妬となぞと云ふ娑婆界の苦労はあつたのである」といじめられた方の「娑婆界の苦労」を見ないところにある。
つまり落ちがなく賺している。
その程度の話だ。
というわけでもない。
いきなりタイトルが「点心