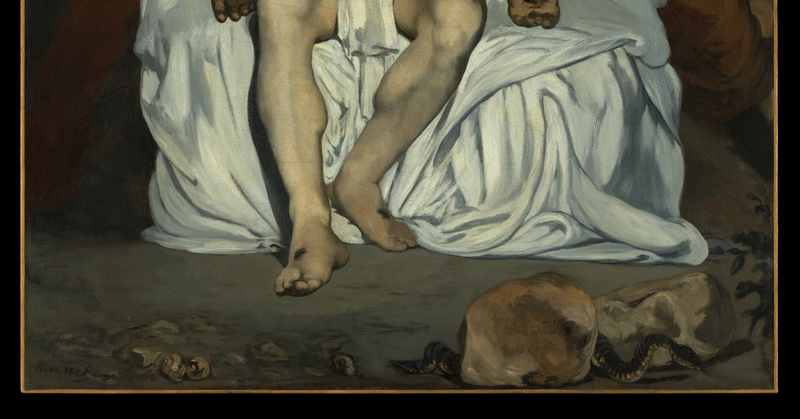
芥川龍之介の『点心』をどう読むか⑨兼『文芸的な、余りに文芸的な』をどう読むのか② 何かが仕掛けられている
Ambroso Bierce
日米関係を論じた次手に、亜米利加の作家を一人挙げよう。アムブロオズ・ビイアスは毛色の変つた作家である。(一)短篇小説を組み立てさせれば、彼程鋭い技巧家は少い。評論がポオの再来と云ふのは、確かにこの点でも当つてゐる。その上彼が好んで描くのは、やはりポオと同じやうに、無気味みな超自然の世界である。この方面の小説家では、英吉利に Algernon Blackwood があるが、到底ビイアスの敵ではない。(二)彼は又批評や諷刺詩を書くと、辛辣無双な皮肉家である。現にレジンスキイと云ふ、確か波蘭土系の詩人の如きは、彼の毒舌に翻弄された結果自殺を遂げたと云はれてゐる。が、彼の批評を読めば、精到の妙はないにしても、犀利の快には富んでゐると思ふ。(三)彼は同時代の作家の中では、最もコスモポリタンだつた。南北戦争に従軍した事もある。桑港の雑誌の主筆をした事もある。倫敦に文を売つてゐた事もある。しかも彼は生きたか死んだか、未だに行方が判然しない。中には彼の悪口が、余りに人を傷けた為め暗殺されたのだと云ふものもある。(四)彼の著書には十二巻の全集がある。短篇小説のみ読みたい人は In the Midst of Life 及び Can Such Things Be ? の二巻に就くが好い。私はこの二巻の中に、特に前者を推したいのである。後者には佳作は一二しか見えぬ。(五)彼の評伝は一冊もない。オウ・ヘンリイ等らに比べると、此処でも彼は薄倖である。彼の事を多少知りたい人は、ケムブリツヂ版の History of American Literature 第二版の三八六―七頁、或は Cooper 著 Some American Story Tellers のビイアス論を見るが好い。前に書くのを忘れたが、年代は一八三八―一九一四? である。日本訳は一つも見えない。紹介もこれが最初であらう。(二月二日)
Ambroso Bierceは Ambrose Gwinnett Bierceの誤りのようだ。というより『悪魔の辞典』のビアスと言えば、今では多くの人が「ああ何となく知っている」と思うのではなかろうか。

そうだ。なにが面倒くさいのかよく分からないが、Ambroseは「A」と略されていた。Bierceで「ビアス」と読むのかとは今、初めて知った。
で何故アムブロオズ・ビイアスが語られているかと言えば、宣伝のためである。

へ、編集者?

うん、編集者だ。


Algernon Blackwoodの作品もちゃんと入っている。
この点芥川も抜け目がない。
厳密には大正十年に書いた『点心』によって、知り合いの書肆が声をかけてきて、それで芥川が編集というよりは選者という形で「これとこれとこれ」という形でセレクトして、興文社は日本語に訳しませんかと一応芥川に打診したところ何らかの理由できっぱり断られて、仕方なくそのまま印刷したということなのだろう。
これらの本が出た時期ではまだ芥川に自殺の明確な覚悟はなかった筈なので、「僕にはもう時間がない」という訳ではなかったのではないかと思われる。つまり「何らかの理由」とは何としても翻訳を拒むような何かであり、結果として翻訳ものを一切書かなかった芥川という作家にとってかなり本質的なことなのではなかろうか。
ところで当時の著作権の考え方や、「しかも彼は生きたか死んだか、未だに行方が判然しない」などとあることから、Algernon BlackwoodやAmbrose Bierceに印税が渡ったかどうかは謎である。(極めて疑わしい。今でいう海賊版という可能性はないだろうか?)
これで、バルザックの印税の話がまた訳の分からないややこしいところへ持っていかれるような不思議な感覚がある。そもそも当時の翻訳ものの印税はちゃんと支払われていたのだろうか?
しかしあらためて考えると、日本の出版社から出すなら芥川でないにしても、金に困っている文士の誰かが翻訳しても良さそうなものだが、そうはならなかった。そもそも芥川作品にこうした編集物があることは、菊池寛とのもの以外はほとんど知られていないのは何故だろう?
そう取りとめもなく考えているうちに、やはり問題は芥川の翻訳というところにあるように思えて来た。
ここでわざわざAlgernon BlackwoodやAmbrose Bierceを紹介するのは、芥川程の教養があるからだ。どうも芥川は英語がスラスラ読める。それにも関わらず、翻訳がないのは何故だろう。むしろここでわざわざAlgernon BlackwoodやAmbrose Bierceを紹介するのは、確かに師・漱石にも翻訳作品らしきものは見当たらないが……と余計なことを考えさせる仕掛けではなかろうか。
例えば今自分の文芸との関りを総括したような『文芸的な、余りに文芸的な』を確認してみても「自分と翻訳の関り」「自分が翻訳作品を書かない理由」は真正面からは論じられていない。
正宗白鳥氏のダンテ論は前人のダンテ論を圧倒してゐる。少くとも独特な点ではクロオチエのダンテ論にも劣らないかも知れない。僕はあの議論を愛読した。正宗氏はダンテの「美しさ」には殆ど目をつぶつてゐる。それは或は故意にしたのであらう。或は又自然にしたのかも知れない。故上田敏博士もダンテの研究家の一人だつた。しかも「神曲」を飜訳しようとしてゐた。が、博士の遺稿を見れば、イタリア語の原文によつたものではない。あの書き入れの示すやうにケエリイの英吉利訳によつたのである。ケエリイの英吉利訳によりながら、ダンテの「美しさ」を云々するのは或は滑稽に堕ちるのであらう。(僕も亦ケエリイの外は読んだことはない。)しかしダンテの「美しさ」はたとひケエリイの英吉利訳だけ読んでも、幾分か感ぜられるのは確かである。……
このように翻訳に関して「重訳では滑稽」などという意見は漏れるもの、余技にせよ趣味にせよ、自身に翻訳作品のないことに関する弁明はない。しかし本当にAmbrose BierceやAlgernon Blackwoodを日本人にも紹介したければ、翻訳するのが筋というものではなかろうか。
何なら遅筆の芥川でも翻訳は早いので稼ぎにもなったのではないか。翻訳で稼いでいる作家がいることを知らなかったわけでもあるまいし、このことは案外突き詰めて考えるべき問題かもしれない。
またトルストイ問題、や日米関係の話も絡んでくる。
トルストイもドストエフスキーもニーチェも芥川は英語で読んでいる筈だ。ロマン・ロランはフランス語で読んだだろうか。
ではハイネは?
ゲーテはどうだろう?
僕はこの不可思議なギリシアこそ最も西洋的な文芸上の作品を僕等の日本語に飜訳することを遮げてゐるのではないかと思つてゐる。
例えば芥川がAmbrose BierceやAlgernon Blackwoodを日本語に訳さなかったのは、「英語くらいわかるだろう」という気取りではなく、英語さえわからない者にはいくら翻訳ものを読んでもAmbrose BierceやAlgernon Blackwoodなど解るわけはないのだと、冷たく突き放したような表向きでありながら、英語さえ解れば、ギリシャを根に持つ西洋の呼び声に届くが、紅毛人には漢詩が理解できないように、西洋と東洋の間には翻訳の壁が存在するのだと言っていないだろうか。
ハイネやゲーテを理解するためにも英語が必要なのだということか?
つまり、ABCも解らぬものはハイネもゲーテも解らないのだと……?
Ambrose Bierce
Algernon Blackwood
どちらもA.B.だ。これはたまたま? 遊んだ?
なかなか複雑な話にはなるが、色々なことが『点心』と『文芸的な、余りに文芸的な』では繋がっている。
ポオは詩の上にこの事実に依つた彼の原則を主張した。それからビイアス(Ambrose Bierce)は散文の上にもやはりこの事実に依つた彼の原則を主張した。
ここでは綴りが直っている。
なんでや。と言えば『モダン・ゴースト・ストーリーズ』を編集したからだ。あるいはこの綴り間違えにさえ気が付いていない人は少なくない。
この『モダン・ゴースト・ストーリーズ』の寸止めのような「セレクト」「でも英語のまま出版」といういささか無責任なふるまいには、やはり何か已むに已まれぬもの、むしろ「訳すべきではない」という強い意思のようなものが感じられないだろうか。
あるいは英語くらい読めないと自分の作品を理解することもできないだろうよと読者に喧嘩を売っていないだろうか?
実際芥川作品は正しく読まれていないので、そのくらいのことは言われても仕方ない。
芥川の翻訳問題に関しては、まずその作品中に英語の仕掛けがないかどうか、総点検することが必要だろうか。
なかなか気が遠くなるような話だ。
私にはもう無理かもしれない。
物価高には困ります
— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) September 26, 2023
⇒ https://t.co/0zyTgotBvX #アメブロ @ameba_officialより
ほんまやで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
