
芥川龍之介の『鼠小僧次郎吉』をどう読むか① 東方の遊び人
三島由紀夫は『大鏡』の「顕証にこそありけれ。いかがすべからむ」とある「顕証」の文字をはっきり覚えていて、この字を現代小説に使おうとする。
つまり三島由紀夫は『夜の寝覚』に三か所、『栄花物語』に一か所、『更級日記』に一か所、『枕草子』に七か所、『蜻蛉日記』に「顯證」として一か所、や『紫式部日記』に三か所、『源氏物語』に八か所、『竹取物語』に一か所、『落窪物語』に一か所、「顕証」の文字があることははっきり覚えていないのだ。覚えていれば『枕草子』か『源氏物語』、あるいは『竹取物語』を引き合いに出すべきであろう。
何の話か、と言えば三島由紀夫は平安時代以前の語彙を現代小説に用いた。それに対して芥川は『鼠小僧次郎吉』においては、なかなか使用例の確認できない江戸言葉を駆使して、器用に江戸時代のファンタジーに仕上げているということである。
例えば「剳青」の文字は青空文庫では泉鏡花と芥川しか使っていない。「八反の平ぐけ」は芥川の他は長谷川時雨、三上於菟吉だけだ。「何時になつてもひつてんだ」の「ひってん」(貧乏)は泉鏡花だけ。間違いないという意味の「噓は無え」も尾崎紅葉だけ。「おそれべ」はさすがに芥川だけだ。(西鶴は使っている。)

固有名詞となるとこれはもう意味が解らない。「改代町の裸松」が「改代町の八百屋松五郎」であるかないか、

それがこの、「木村鶴平御代官所 武州葛飾郡須田村百姓 八百屋松五郞」なのかどうか。
そんなことどもがぼんやりしたまま、大方こんなものであろうという江戸時代風俗が綴られていく。
丁度今から三年前、おれが盆茣蓙の上の達て引きから、江戸を売つた時の事だ。
こんな一行は中学生でなくても現代語訳が欲しいと思わないではいられないところ。盆茣蓙はサイコロ賭博の壺を伏せるところに敷く茣蓙、その意味が転じて賭場、達て引きは意地の張り合いや金の貸し借りから、やはり意味が転じてそうしたところから生じる争い、江戸を売ったは江戸を引き払ったという程度の意味なので「賭場のトラブルで江戸を引き払った時のことだ」とでも読めばいいのだろうか。しかしまさにそう書かないで「盆茣蓙の上の達て引きから」と書くことで江戸のファンタジーが生まれる。
東海道にやちつと差しがあつて、路は悪いが甲州街道を身延まで出にやなら無えから、忘れもし無え、極月の十一日、四谷の荒木町を振り出しに、とうとう旅鴉に身をやつしたが、なりは手前も知つてた通り、結城紬の二枚重ねに一本独銛の博多の帯、道中差しをぶつこんでの、革色の半合羽に菅笠をかぶつてゐたと思ひねえ。
この落語のような講談のような滑らかな語りは、短い文節になれた現代人にとってはやはり時代の味わいを感じさせるものだ。この「思ひねえ」でさえ、漱石、鏡花、安吾くらいしか使っていない。いや「思いねえ」の表記では吉川英治他ちらほらと引っかかるが、やはりこれは江戸言葉なのだ。
「酒に恨みが数々ござるつてね、私なんぞも旦那の前だが、茶屋酒のちいつとまはり過ぎたのが、飛んだ身の仇になりやした。あ、あだな潮来で迷はせるつ。」
とふるへ声で唄ひ始めやがる。
これなんぞも式亭三馬の、ここから採ったのだろう。

はてな、何だか可笑しな容子だぞと、かう思ふか思は無え内に、今度はおれの夜具の中へ、人間の手が這入つて来やがつた。それもがたがたふるへながら、胴巻の結び目を探しやがるのよ。成程。人は見かけにやよら無えものだ。あのでれ助が胡麻の蠅とは、こいつはちいつと出来すぎたわい。
この「胡麻の蠅」もほぼ死語だろう。
ごま‐の‐はい【護摩の灰・×胡麻の×蠅】‐はひ 昔、旅人の姿をして、道中で、旅客の持ち物を盗み取ったどろぼう。高野聖(こうやひじり)のなりをして、弘法大師の護摩の灰だといって押し売りして歩いた者があったところからの名という。
つまりもともと押し売りの護摩の灰だったものが、すり、巾着切り、コソ泥のような胡麻の蠅に転じている。さらに古い言葉で泥棒を意味する言葉に「じら」があるが、むしろ「胡麻の蠅」隠語の生々しさが江戸の景色になっている。

烏骨鶏を「をこつけい」と読ませるのも味である。いちいち芸が細かい。これを量り売りでやっているのだから大したものだ。というより、これを量り売りで買い叩いた書肆が頭がおかしかったと言わざるを得ない。

「ほんによ、こんな胡麻の蠅も、今に劫羅(こふら)を経て見さつし、鼠小僧なんぞはそこのけの大泥坊になるかも知れ無え。ほんによ、さうなつた日にやこいつの御蔭で、街道筋の旅籠屋が、みんな暖簾に瑕がつくわな。その事を思や今の内に、ぶつ殺した方が人助けよ。」
この『鼠小僧次郎吉』はこうした江戸言葉に飾られて江戸の景色を作り出し、ほとんど落語のように落ちている。胡麻の蠅が鼠小僧を名乗り、色の浅黒い、小肥りに肥つた男、苦みばしつた男ぶりを、一層いなせに見せてゐる語り手が、
「はて、このおれが云ふのだから、本望に違え無えぢや無えか。手前にやまだ明さなかつたが、三年前に鼠小僧と江戸で噂が高かつたのは――」
と云ふと、猪口を控へた儘、鋭くあたりへ眼をくばつて、
「この和泉屋の次郎吉の事だ。」
と、また鼠小僧を名乗る。ほとんど落語と書いたが、その言い残した根拠となる筈のわずかな「近代文学たる要素」がどこにあるのか、今の私には明確に言語化は出来ない。小太りでは鼠小僧ではなく、豚小僧ではないかという話でもなさそうだ。
しかし前途悠々たるべきこの大正八年という時期に「こんなもの」を書いたからには、芥川にはそれなりの意匠というものがあった筈なのだ。
盛んに言われているように『鼠小僧次郎吉』はアイルランドの劇作家、ジョン・ミリントン・シングの『西の国のプレイボーイ』と鼠小僧の講談本、あるいは落語を組み合わせたような由来を持っている。
つまり昨日書いたように、
昨日?
一昨日?
兎に角前に書いたように、「あるいは英語くらい読めないと自分の作品を理解することもできないだろうよと読者に喧嘩を売っていないだろうか?」という作品の類であると考えられなくもないのだ。
しかしどうも考えられない。『鼻』や『地獄変』、あるいは『羅生門』で見てきたように、元ネタそのものは大したことはないのだ。それは『杜子春』や『蜘蛛の糸』に関しても言えることで、こう言っては何だが、元ネタとの比較にはあまり意味がないように思えるのだ。
CHRISTY.
twisting round on her with a sharp cry of horror.—Don’t strike me. I killed my poor father, Tuesday was a week, for doing the like of that.
PEGEEN.
with blank amazement.—Is it killed your father?
CHRISTY.
subsiding.—With the help of God I did surely, and that the Holy Immaculate Mother may intercede for his soul.
PHILLY.
retreating with Jimmy.—There’s a daring fellow.
JIMMY.
Oh, glory be to God!
MICHAEL.
with great respect.—That was a hanging crime, mister honey. You should have had good reason for doing the like of that.
CHRISTY.
in a very reasonable tone.—He was a dirty man, God forgive him, and he getting old and crusty, the way I couldn’t put up with him at all.
恐らくこの芝居の肝はこの「with great respect.」と「in a very reasonable tone.」というさして知的ではないひねりにあるのだろう。reasonable toneとはここでは「理性的な口調」という程度の意味になろうか。なんでそうなるの? と思わないではないが、これを芥川が気に入って、
「お前さんと云ふ人は、何たる又悪党だんべい。」
と唸るやうな声を出した時にや、おれは可笑しさがこみ上げての、あぶなく吹き出す所だつた。ましてあの胡麻の蠅が、もう酔もさめたのだらう、如何にも寒さうな顔色で、歯の根も合は無え程ふるへながら、口先ばかりや勢よく、
「何と、ちつとは性根がついたか。だがおれの官禄は、まだまだそんな事ぢや無え。今度江戸をずらかつたのは、臍繰金が欲しいばかりに二人と無え御袋を、おれの手にかけて絞め殺した、その化の皮が剥げたからよ。」
と大きな見得を切つた時にや、三人ともあつと息を引いての、千両役者でも出て来はしめえし、小鬢から脹れ上つたあいつの面を、難有さうに見つめやがつた。
こう茶化したのだろう。
それでもあえてジョン・ミリントン・シングの『西の国のプレイボーイ』から拾うものがあるとするならば、『鼠小僧次郎吉』は「東方の遊び人」の話だということだけだ。
父親の頭に鍬を突き立て殺したという自慢話で人気者になり女に惚れられるという元ネタに対して、『鼠小僧次郎吉』は臍繰り欲しさに母親を絞め殺したという自慢話で英雄視されるも女が出てこない。そして簡単に小肥りに肥つた男にやり込められてしまう。
此処にゐる馬子や若え衆が、丁度御前おめえにや好い相手だ。
こんな言葉で親殺しを英雄にしてしまうアイルランド国民を馬鹿にしている訳でもあるまい。しかし芥川が江戸の「馬子や若え衆」という無教養な人たちを馬鹿にして、そうではない聞き手を相手に語っていたことは間違いない。その一方で胡麻の蠅を軽蔑し、なお鼠小僧の伝説を我が物にしようという遊び人の「つい話が大きくなりすぎてしまう」庶民性を揶揄っていることも確かだ。
鼠小僧の伝説そのものに、「えらいことをしでかす悪党に対する庶民の憧れ」や「つい話が大きくなりすぎてしまう庶民性」というものが加担していよう。しかし芥川の筆はそこをとことん馬鹿にするでも批判するでもなく、あえてそういうものとして愛しみ、楽しんでいるように思える。
これ以上書くことはもう何もない。
しかしこういう所は困る。「劫羅(こふら)を経て」は、
劫﨟を経る、劫量経る、とは言うが、



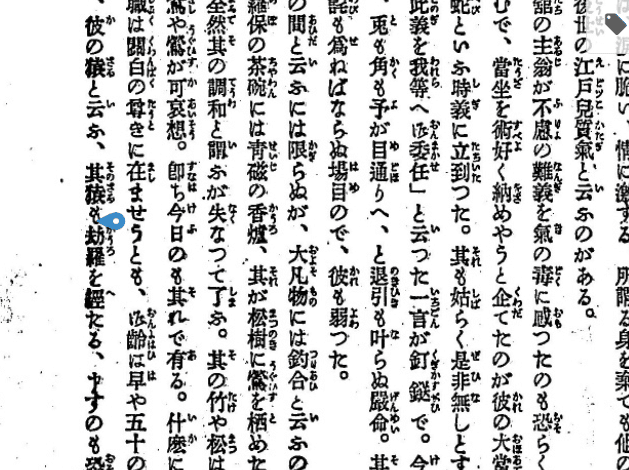


これなど劫羅(かうろ)を経て」になっている。

これは……。

あえて読めば「劫羅(ごふら)」になる。
まあ、「劫羅(こふら)を経て」も使われていないことはないので、これでいいか。
しかし一度「劫羅」で検索してみて欲しい。この言葉はもう汚れていて使えない。そもそも英語だけの問題でもないのだ。「劫羅(こふら)を経て」がぱっと解るという人は、当時もどれくらいいたものか。
ごっぽう‐にん【業報人】 (業報をうける人の意から)人をののしっていう語。浮世風呂前「なんだ此の―め」
これも「青空文庫」では芥川ひとり。
よい‐よい 手足が麻痺し歩行が不自由で、口・舌などのよく回らない病気の俗称。また、それにかかっている人。
これは直木三十五も使っているが、
が‐もの【が物】 (助詞「が」に名詞「もの」が付いたもの)…分。…だけ。…の値に相当するもの。滑稽本、続膝栗毛「礼金二分―はあるだろう」
やはり言い回しとしては古い。
すすど・い【鋭い】 〔形〕[文]すすど・し(ク) ①敏捷である。すばやい。宇治拾遺物語11「―・く歩みて過るを」。平家物語11「九郎は―・き男にてさぶらふなれば、大風大浪をもきらはず」 ②こすい。わるがしこい。世間胸算用5「若年の時より―・く無用の欲心なり」
竹久夢二と吉川英治だ。しかし広辞苑の用例にあるように相当に古い言葉だ。これ等の語彙を全部受け止めてaudibleで聞き流す猛者は大正八年には存在しなかっただろう。
むしろ今は?
[余談]
この元ネタは何々という以外の、芥川作品の英語との関係性はこの作品には見いだせなかった。無論現代性も。
明日何かわかるだろうか?
どのようなお店でも、利用した時は「サンキウ」とお礼を言っておきたい。 pic.twitter.com/AzlZrzYeFB
— Watanabe (@nabe1975) October 4, 2023
で、みなさんは?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
