
芥川龍之介の『点心』をどう読むか⑩ そんな事を言われても違うものは違う
むし
私は「龍」と云ふ小説を書いた時、「虫の垂衣をした女が一人、建札の前に立つてゐる」と書いた。その後或人の注意によると、虫の垂衣が行はれたのは、鎌倉時代以後ださうである。その証拠には源氏の初瀬詣の条にも、虫の垂衣の事は見えぬさうである。私はその人の注意に感謝した。が、私が虫の垂衣云々の事を書いたのは、「信貴山縁起」「粉河寺縁起」なぞの画巻物によつてゐたのである。だからさう云ふ注意を受けても、剛情に自説を改めなかつた。その後のち何かの次手から、宮本勢助氏にこの事を話すと、虫の垂衣は今昔物語にも出てゐると云ふ事を教へられた。それから早速今昔を見ると、本朝の部巻六、従鎮西上人依観音助遁賊難持命語の中に、「転て思すらむ。然れども昼牟子を風の吹き開きたりつるより見奉るに、更に物もの不思えず罪免し給へ云々」とある。私は心の舒びるのを感じた。同時に自説は曲げずにゐても、矢張やはり文献に証拠のないのが、今までは多少寂しかつたのを知つた。(二月三日)
「数日後に明らかになるように、芥川龍之介は徹底的に調べ尽くす作家である。『点心』ではこの後芥川が時代考証に賭ける意地のようなものを見せつける」と、先日書いた通り、ここは芥川が時代考証に賭ける意地のようなものを見せつけているように思えなくもないところではある。
実はあの発頭人の得業恵印、諢名は鼻蔵が、もう昨夜建てた高札にひっかかった鳥がありそうだくらいな、はなはだ怪しからん量見で、容子を見ながら、池のほとりを、歩いて居ったのでございますから。が、婆さんの行った後には、もう早立ちの旅人と見えて、伴の下人に荷を負わせた虫の垂衣の女が一人、市女笠の下から建札を読んで居るのでございます。そこで恵印は大事をとって、一生懸命笑を噛み殺しながら、自分も建札の前に立って一応読むようなふりをすると、あの大鼻の赤鼻をさも不思議そうに鳴らして見せて、それからのそのそ興福寺の方へ引返して参りました。
問題の「虫の垂衣」はここに現れる。
室町時代女子の旅姿室町時代の婦人の旅姿として行はれた特趣な姿は、市女笠に白帛と白紐を垂れた所謂蟲の垂衣をつけて冠ることであつた。

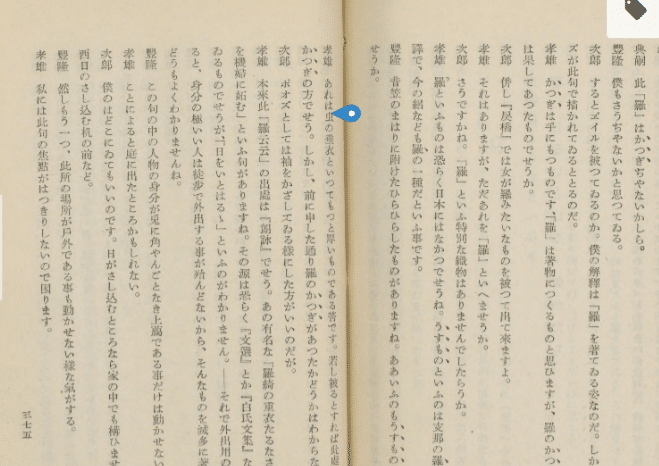
ところで同じ名前でも時代によって同じものを指すとは限らず、多く鎌倉時代の女の旅の衣装として描かれる市女笠に虫の垂衣が平安時代のものと同じだったかどうかは不明である。ちなみに契沖、真淵、宣長以来の国学の伝統に連なる最後の国学者・山田孝雄は虫の垂衣が「うすもの」ではないと唱えており、そういうものが芥川のイメージと同じなのかどうかも解らない。
もともとは「白帛と白紐を垂れた」とあることから、かなりがっしりしたものであったようである。
しかしここで改めて問わねばならないのは、『素戔嗚尊』の「針金雀花」のことであろう。
芥川も谷崎潤一郎もしばしば「ないこと」を書いてくる。「億兆の国民」やら、
「紂王の寵妃、末喜」
「五段目の勘平が切腹して」などと、
無いものを書いてきた。他にも、「二宮尊徳は十六の歳に自分の家を再興した」「源頼朝は十三歳の歳に平治の乱で武勇の誉れを擧げた」などわざと出鱈目を書いてくる。
これは「意味のない悪戯」なのではないかと考えてもきたが、昨日の英語の話と合わせて考えると、やはり読者を試す、読者を選ぶふるまいでもあるのではなかろうか。
例えば、
Achilles ergrimmt, und ohne ein Wort zu versetzen, schlägt er ihn so unsanft zwischen Back' und Ohr, daß ihm Zähne, und Blut und Seele mit eins aus dem Halse stürzen. Zu grausam! Der jachzornige mörderische Achilles wird mir verhaßter, als der tückische knurrende Thersites; das Freudengeschrei, welches die Griechen über diese Tat erheben, beleidiget mich; ich trete auf die Seite des Diomedes, der schon das Schwert zucket, seinen Anverwandten an dem Mörder zu rächen: denn ich empfinde es, daß Thersites auch mein Anverwandter ist, ein Mensch.
谷崎はレッシングの『ラオコーン』の原文を二度も長尺で引用する。
こんなものは誰が読むのだと思わなくもない。しかしそもそも芥川や谷崎は漱石や永井荷風、そして帝国大学の同人らという怖ろしく教養の高い連中をまず念頭に置いて、彼らを「大向こう」として「大向こうを唸らせる」つもりで書いているようなところがあったのではなかろうか。
そうでなければそもそも「In the Midst of Life 及び Can Such Things Be ? の二巻に就くが好い」とか「ケムブリツヂ版の History of American Literature 第二版の三八六―七頁、或は Cooper 著 Some American Story Tellers のビイアス論を見るが好い」などという話にはなる筈がないのだ。
少なくとも芥川や谷崎は頭の悪い中高生(それは勿論年齢だけの問題ではなく、教養レベルが頭の悪い中高生レベルの人の事を言うのだ。あるいはおねだりやさんなど)に読んで貰おうとは思ってもいまい。それは漱石なども同じで、例えば英語すらわからない奴に読ませても仕方ないと書くと横柄にとられかねないが、漱石は実際漢籍が読めないと解らないようなことを書いていたわけである。
そういう頑固な師がいたからこそ芥川は、「なかなかついてこれる奴が現れないな」と感じていたのではないだろうか。
だからと言って同じ比喩を二回使ってよいかというとこれは別の話のようでもあるが、そのくらい読者は嘗められていた、あるいは時々はひねくれたくなるほど芥川は孤独だったのではなかろうか。
「虫の垂衣」は一つのたとえに過ぎない。
芥川生存中に誰か一人でも「津波に攫われた鎌倉の景色を書いたから、阿蘭陀の風俗画なんですね」とファンレターを書いただろうか? そういうものがなくても仕方がないと思いながら書いていて、後で「今までは多少寂しかつたのを知」ることになつたのではなかろうか。
それでも何かを隠すことが肝になる作品を思いつけば、何かを隠して書かねばならない。隠されたものが永遠に気が付かれないかもしれないとしても、隠さざるを得ない。
そうして芥川は「ああ、そうか!」と思わせたかったのだ。
つまり「転て思すらむ。然れども昼牟子を風の吹き開きたりつるより見奉るに、更に物もの不思えず罪免し給へ云々」とわざわざ書いたのは、この年の四月、
牟子をしたる旅の女 私はちと足が痛うなつた。あの乞食の足でも借りたいものぢや。
皮子を負へる下人 もうこの橋を越えさへすれば、すぐに町でございます。
釣をする下衆 牟子の中が一目見てやりたい。
こんなことを書き、いちばん神経症の辛い暮れ、『藪の中』で、
わたしは昨日の午少し過ぎ、あの夫婦に出会いました。その時風の吹いた拍子に、牟子の垂絹が上ったものですから、ちらりと女の顔が見えたのです。ちらりと、――見えたと思う瞬間には、もう見えなくなったのですが、一つにはそのためもあったのでしょう、わたしにはあの女の顔が、女菩薩のように見えたのです。わたしはその咄嗟の間に、たとい男は殺しても、女は奪おうと決心しました。
こんなことを書く準備になっている。しかし『今昔物語』は、
和ら板敷の下に入て聞けば、法師、我が妻の許に来て云ふなる様、「転(うたてし)と思すらむ。然れども、昼牟子(むし)を風の吹き開たりつるより見奉つるに、更に物思えず。罪免し給へ」とて、打寝て臥しぬ。

なので「転て思すらむ」は「て」と「と」の写し誤りである。「て」と「と」は違う。誰が何と言おうと違う。
これがわざとかどうかは判断しかねる。かなりの確率で「わざとではない」のではなかろうか。しかしどうも芥川の「虫の垂衣」は『今昔物語』で確証を以てうすものの「垂絹」に転じ、山田孝雄の見解とは別の「虫の垂衣」になったようだ。このファンタジーはもう覆りそうもないが、違うものは違うと書き残しておく。
荷田春満の見解はどうだろう?
櫛まつり
— 青華 (@aoironosirabe) September 25, 2023
衣装の中では平安時代の白拍子、鎌倉時代の市女笠、虫の垂れ衣、壺装束が推し⸜ ෆ ⸝
虫の垂れ衣、厚い生地だと外から顔が見えにくくなるんだなぁ。
一度で良いから着てみたい。
#京都 #櫛まつり pic.twitter.com/7ztVIK25XP
石山寺縁起絵巻より。衣を引き上げた上から市女笠をかぶったりもしていたようです。 pic.twitter.com/sHkBBTrisJ
— 逆名🌈🕊️🏳️🌈🏳️⚧️ (@sakana6634) September 19, 2023
ひとまず市女笠醜女衆はこれで完成で pic.twitter.com/TAI9XGJ1ew
— だいあち (@daiachi_FG) September 24, 2023
[余談]
いわゆるアカデミックなところで発表されている芥川作品に関する論文をまたいくつか読んでみたが、
①芥川作品に関する研究はされ尽くしている
②この件に関してはすでにいくつもの先行研究がある
……という何のためか分からない言い訳のような前置きが冒頭に添えられていて、作品の「読み」に関しては疎かになっているという共通点が確認できた。
それならば『あばばばば』に関するひつじ書房の失態はなんなのかと呆れてしまう。
研究というのが因縁探しに集中しているのもどうかと思う。それにしても『素戔嗚尊』や『芭蕉雑記』の出鱈目に気が付いている人がいたのかね?
芥川はまだ誰にも読まれていないと思う。読まれるまでに最低あと一年くらいはかかると思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
