
征服と料理:じゃがいもの語源等
(カバー写真はシンガポール隔離生活中に出てきた配給食のマッシュポテトです。)
学校の教科書では、料理の歴史を習うことはまず無いと思います。なので、先祖が何を食べていたかとか、自分たちが食べているものがいつごろ日本に来たのかについてはあまり学びません。歴史家である私も、日々驚くことがあります。
今回は主にじゃがいもの話をしようと思います。じゃがいもの歴史について調べていたら、語源に世界史や東南アジア史が感じられてぐっと来ました。
前回、シンガポールの上海ラーメン店(なのにオススメは視線担々麺)を紹介したのだけれど、シンガポールでは実に多様な料理が食されています。そもそもマレー半島の南端に小さく存在しているこの島に上海ラーメン、四川料理、海南料理、インド料理、インド系ムスリム料理等々が持ち込まれた背景には、1819年のラッフルズ到着以降のイギリスの植民地化の過程があります。
シンガポールもマレー半島も、もともとは大まかに言ってマレー系文化の範疇に入る人たちが大半を占める地域でした。19世紀以降、中華系や一部のインド系を「働き者の人種」と見なしたオランダやイギリスの植民地政府は、積極的に中華系やインド系の移民たちを雇用し、移民を奨励しました。これがシンガポールでマレー料理、西洋料理、中華料理、インド料理などの多様なバリエーションが食されるようになったきっかけです。
シンガポールで「西洋料理」というと、ほとんどの場合、じゃがいもを使った料理が出てきます。マッシュポテトやフライドポテトなど。
じゃがいもという食品の歴史は非常におもしろいんですが、西洋の食べ物になった背景にも植民地主義があります。そもそもの原産地は、中南米です。15世紀末以降に中南米を占領し、植民地化したスペイン人たちが16世紀頃にイベリアに持ち帰ります。
そして、西洋人として最初にじゃがいもの栽培を普及させたのが、イギリス帝国支配下のアイルランド。領主たちが地代として麦を取っていたこともあり、収奪されないじゃがいもが生産されたのです。
ここから先は
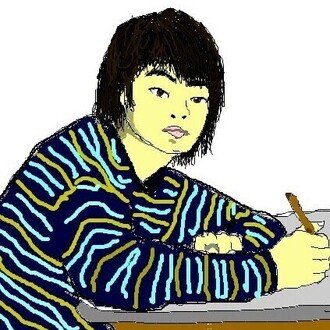
グローバル・アジア研究マガジン
土屋喜生(シンガポール国立大研究員・歴史学博士・東南アジア学修士、法政大学国際政治学学士)がグローバル・アジア研究について報告していきます。
この記事が参加している募集
よろしければサポートお願いします。活動費にします。困窮したらうちの子供達の生活費になります。
