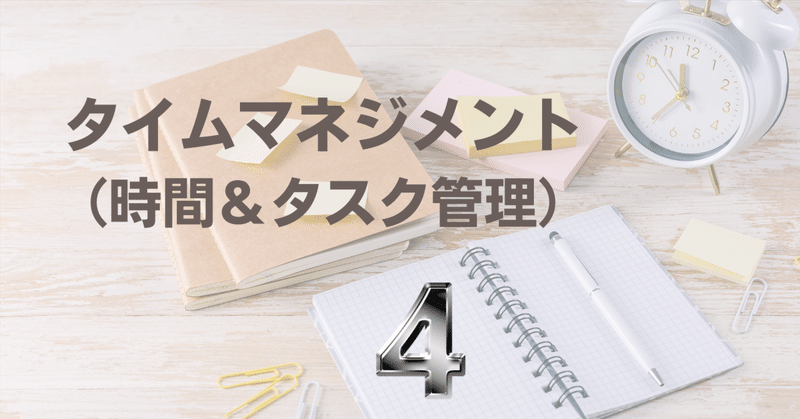
タイムマネジメント④ やるべきことは何?:本当にやる必要があるか?
前回記事では、やるべきことを全部洗い出すことについてお伝えしました。
これらは、自分で「やるべき」だと思って書き出したはずのものですが、本当にすべてやる必要があるタスクなんでしょうか。
今回は、洗い出したタスクについて、「本当にやる必要があるのか」「ひょっとしたらやらなくてもいいかも?」を検証することについて書いていきます。
■本当にやる必要があるか?
🎯洗い出したタスクはすべて本当にやる必要ある?
やるべきことが多すぎて時間が足りない、と感じていたとして、そのやるべきことの中に本当はやらなくていいことが混じっていたらどうでしょう。
それをやめてしまえば、それに費やすはずだった時間が浮く、ということになりますよね。
「やめる」という選択は、タイムマネジメント的に一番効果の高い手法です。
日々やっている業務は、大きなもの・小さなもの、重要度の高いもの・低いもの、急ぐもの・急がないものなど様々ありますよね。全部が同じ程度にやらなきゃいけないわけではありません。
・パレートの法則
「パレートの法則」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが19世紀後半に提唱した「全体の成果の80%は、全体の20%から生み出される」という主旨の法則です。
彼は、イタリア国内の富の分配について研究する中で、イタリアの土地の80%は20%の富裕層によって所有されていることを発見しました。
「80対20の法則」とも言われますが、ご存じの方も多いと思います。
これをビジネスにあてはめると、例えば、「ある企業の売上の80%は、その企業の20%の主要商品が生みだしている」といったことですね。
この20%のものは、全体の8割もの成果を生み出すものなので絶対にやめない方がいいですよね。逆に残りの80%は、やめたとしてもそこまでの影響がないということ。
洗い出した全部のタスクのうち、この重要な20%とそれ以外を見極めることができると、時間の使い方にも反映できますよね。その見極めは、それはそれで簡単なことではなさそうですが。
でも、こういった視点をもって、ご自身のそれぞれのタスクについて考えてみるといいのではと思います。
この辺りの考え方を理解するには、以下の本がおすすめです!
🎯やっている目的・根拠は?
重要な仕事かどうか(=やめられる可能性があるか)判断するには、洗い出したタスクについて、なんでやっているのかを考えてみるのが役に立ちます。
「なんでやっているのか」とは、そのタスクの目的(=なんのために)と根拠(=何が元になって)のことです。
・目的=なんのためにやっているのか
例えば、「議事録を作成する」というタスクの目的は、「会議のポイントや決定事項を明確にし、組織内で共有するため」。
この目的は、組織で仕事を回していくには必要なステップですよね。そしてその目的を果たすには、今のところ、議事録を作成することが一番適していると判断できるから、やる。
でも、「業務の進捗状況確認」の目的のために、「毎日ミーティング」をしているとしたらどうでしょうか。
その目的自体は大事かもしれないけど、そのためなら、例えば、「業務の進捗管理システムの導入」や、「チャットでの情報共有」の方がより効率的かもしれません。
業務によっては、そんな目的のためだったら、今それは必要ないよね、という判断もあり得るわけです。
・根拠=何が元になっているのか
例えば、「ある補助金の実績報告書の作成」という業務の根拠が、「補助金を出している〇〇市の〇〇補助金交付要綱において定められているから」、という場合。
これは、自分の会社の規定ではなく、補助金を出す側の組織の規定で定められているので、やらないわけにはいきませんよね。その〇〇市も、法律や条例などが根拠になって定めたものでしょうからなおさらです。
逆に、「自分の会社の内規で定められている」という根拠なら、そこは社内の手続きを踏んで改正すればやめられる可能性があるということ。担当部署の運用方針として決めているだけなら、その部署の責任者がよしと言えば変えられます。
業務の必要性を考える際には、ぜひ、目的と根拠を確認してみてくださいね。
🎯「以前からやってるから」やってない?
目的と根拠を考えた時に、「以前からずっとやってるから」という理由が出ること、ありませんか?
実はこういう仕事、結構多いですよね。前任者から引き継いだから、あまり疑問を持たずに忠実にやってきた、とか。
そんな仕事こそ、ぜひ、目的と根拠をよく確認してみてください。ひょっとしたら、やめることができたり、他の手段が見つかったりするかもしれません。
🎯手段が目的になっていない?
そして、目的や根拠を考えることをしないと、目的のための「手段」がいつの間にか目的化していることがあります。
例えば、「必要な議論を行い方針を決定すること」が会議の目的であるはずなのに、会議を開くこと自体が目的化されてしまい、特段の議題がないのに無理やり情報共有のネタを出して会議を開催している、とか。年間スケジュールで予定組んでるからやらなきゃ、みたいなこと、ないでしょうか。
ぜひ、この記事を読んだのをきっかけに、ご自身のタスクの目的と根拠をよく考えてみていただければと思います!
「本当にやる必要があるか?」について書いてきましたが、だいぶ長くなってしまったので、一旦ここまでにします。
このテーマについてはまだ書きたいことが残っているので、この続きは次回にしますね。ぜひ、次回も読んでいただけますと幸いです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

