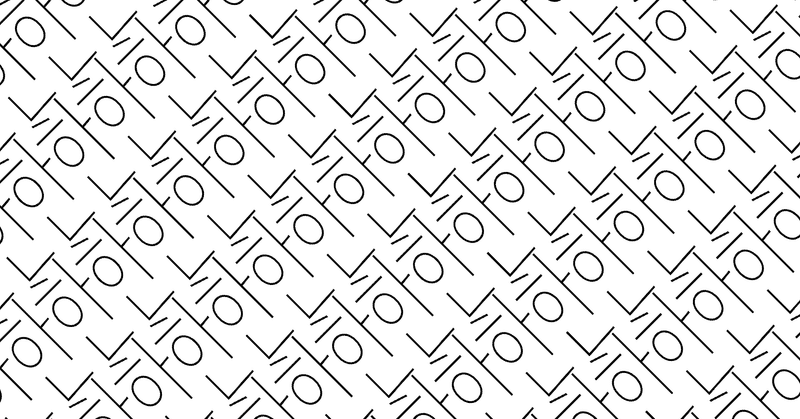
December 19, 2020, 6:39 PM
私は先月、11月最後の週、47歳になった。
シングルマザーである。娘は高校生。外も中も美しく利口で立派な娘。
娘には将来がある。きちんとしてやりたいと思う一方で、きちんとしてやれる自身はまるでない。私は年が明けたら真剣に就活でもしないとヤバイ。就活?今更?このコロナ渦で?
世間の常識的な見地で現在の私の金銭状況や将来性を検証すると、現状はかなりひどい。
でも、修復してみせる。2021年の間に。必ず。
12月に入って、この根拠のない自信。
唯一私を前向きに生かさせているのは、数日前29年ぶりに聞いたあの声のせいというか、あの声のおかげである。世界で一番あったかい声。生きててよかった。彼が。私もだけれど。
29年前、季節は全く覚えていない。春だったか夏だったか。
彼を見た最後の風景はこうだった。
下を向いて花を持っていた。
花も下を向いていた。
小雨の肌寒い、薄暗い日だった。マサチューセッツ州の雨空はやたらと広くて重い。
ともかく、女子寮のドアの前で17歳の少年が絶望感を背中に立っている。
彼が泣いていたかはわからない。
顔を見たいとは思わなかった。
無感情に歩き去った自分を覚えている。
傷つけないと、気が済まない感じがした。
勝手に来たんだから、勝手に帰ればいいじゃないって思った。
どのくらいの期間つきあっていた?
一体どこでどのくらい会って、何をどのくらい話していた?
私は色々なことをよく覚えていない。
覚えていないのは、それからひどく長い年月が経ったからではない。
その時点でも、幼い頃からずっと私の記憶は常に適当であやふやだった。
全てのことに対して記憶に留めておく価値を感じていなかった。毎日が死なずに済めば上出来とでもいうかのように、まるで戦士になったかのような気分で、日々何かと戦っていた。そんな必要はないのに。
本当の世間の過酷さを全く知らない小娘だったが、一生懸命それなりにつっぱったり、いきがったりして。
大人にも子供にもバブルだった90年代前半。北米東海岸、全寮制お嬢様学校。うちは母子家庭だったけれど、母が事業で成功していた。
彼はソウルの起業家の長男で、隣町の、やはりお金持ちの子供しかいない名門全寮制の共学校に入っていた。
毎週水曜日だったか木曜日だったか、地域の私学がバスで乗り入れるゲレンデで、スキーの課外授業があった。
私達日本人のグループは滑る気なんてまるでなく、常習犯的にサボるのだが、ロッジでは同じくサボっている韓国人の男子グループをよく見かけた。彼らは白人の不良とは根本的に違っていて、その中でもアレックスのグループは一際輝いていた。同じ学校の女子なんかには全く興味がないと言った感じで、毎週ロッジの同じテーブルを陣取る私達の事を熱い目で見ているのは知っていたが、あの可愛い顔をした体の大きな男の子が私の所へ真っ直ぐに歩いてきた時は、かなり焦った。手を引かれて、森に行った。木の下に座った。
「君、なんていう名前なの?」と聞かれ時には、すでに私は彼の膝に乗っかって、じゃれあっていた。
韓国の男の子達はどの子も育ちがいいのは明らかで、渡米まもない子もどういう訳だか英語が堪能であるのがとってもカッコよく見えた。彼も例外ではなく英語が流暢だったが、それだけでなくちょっと特別の雰囲気を持っていた。アカラサマに強烈な品があった。加えて少年特有の無邪気なふざけ方でキラキラと笑顔を振りまくのだが、ふとした瞬間、まるで成熟しきった父親かのような安定感ある物言いで、目から鱗的な事をちょいちょい。何とも言えないオーラを放っていた。
何ヶ月なのか、何年なのか、どのくらい会って、どのくらい話したか。
色々なことをよく覚えていない。
私は適当に身勝手に生きていたから。
つっぱった、冷たい女の子だったと思う。
心には、幼い頃からズドーンと氷山を抱えていた。
家にいくらか金銀はあっても、基本、人生は苦と孤独に満ちていると決めていた。
なのに、アレックスは私の心の中の氷山にはお構いなしだった。
いつでも無邪気にキラキラした目で私に戯れていた。
鬱陶しいと思ったり、めんどくさいと思ったりもしたけれど、
ただ一つ確実なのは、その時間はいつも確実に暖かくて、
一度諦めて身を委ねてしまうと、ずっとそこにいたかった。
共有した時間の全てが暖かかった。
共有ではないかもしれない。彼が一方的に提供してくれていたという印象が正しいかも。
すれっからしの私は、ずっとそこにいたいと思いつつも、十代の恋なんてどうせ続かないから、早く大人になりたい、だからここは早いところ壊して次に行ってしまいたい、とも思っていた。
そして、ぶち壊した。わざと。
その節は相当傷つけたに違いないし、29年の間に私はおばさんになってしまったのに、彼はそんな事にはお構いなしで今日もキラキラした目で私を見つめている。「君を見つける事ができて、本当に嬉しいよ」って。
8800キロ離れているけれど、今、モニター越しに確実にそこにいて、疲れた私の、こんなノーメイクの顔を受け止めてくれている。愛情たっぷりの笑顔で。
心の奥底から、涙がこぼれた。
Don't cry, Doushite?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
