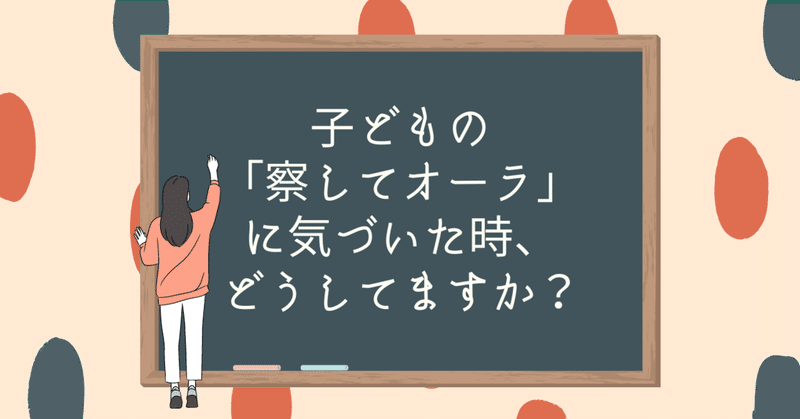
子どもの「察してオーラ」に気づいた時、どうしてますか?
今日は、先生の生徒指導シリーズ「子どもの自立をサポートするための声かけ」についての悩みをお話ししていきます。
この記事を書いている人:
現職教員としてはたらく20代。教育改革や職場改革に奔走するも、心身不調により休職経験あり。教育についての自分の経験や科学的情報、心身安定に関する情報を発信しています。
「察してオーラ」に気づきがち、先回りしがち問題
私がずっと生徒指導として迷っていることがあります。
それは、子どもが発する「察してオーラ」の反応の仕方に困ってしまうということです。
察してオーラとは・・・
職員室前にいた生徒2人
「はじめての先生だから名前の読み方が分からないよね〜。先生いるかなぁ?」(ちらっ)
「え〜でも名前間違ったら恥ずかしいし、どうする〜?」(ちらっ)
その場にたまたま居合わせた元担任の私「あ、なんか困っててこっちの方チラチラみてんな〜〜たぶんその先生を呼んでほしいんだろうな〜でも私には直接こないな〜」
みたいな状況のことです。
特に中学生でよく遭遇します。
なぜ対応に悩むのかというと
はっきりと子どもから聞いてくれれば、「ほらやってごらん」と背中を押すことができるのですが、先回りして声をかけてしまうと、その子達の自立を妨げてしまうのではないか、といつも迷うのです。
また、クラス担任だった時に一度そういう子に声かけをしたら、それに味をしめたのか、毎日のように私の近くで「察してちゃん」になる、なんて経験もありました。
クラス単位でみているときは、その子だけでなく、他の子にも目を配りたいもの。その時間のバランスがうまく取れずに悩んでしまうのです。
では、「言ってこないんだから、無理に声をかけなくてもよくない?」なのか。
確かに、アドラー的「課題の分離」理論で言えば、その行為に最終的に責任を取る主体の行動を干渉して変えようとすることはできない、なので、子どもたちに働きかけても・・・という論理になってしまいます。
その子の主体的行動を待てばいいのでは?とも考えられます。
しかし、それでは私たち教員は待つことしかできないのか。
私は、その子が行動するための「勇気づけ」をすること、そして自分たちでどうすればいいか気づかせることができるのではないか、と感気ました。
そのためには、
できたところまでは認めた上で、質問する
という対応が今はベストなのかな、なんて思いました。
自分の職場の先輩方は「どうしたの?」「何かあった?」など話しかけることが多いです。こういう時、先輩がたはどうやって対応しているのか、すごく気になります。
🖋あとがき
ここまで記事を読んでくださった方、ありがとうございました😊
よかったら、ほかのエッセイや読書ノートも目を通してもらえたら嬉しいです!
< 自己紹介 「7つの習慣と教師とわたし」>
<教員が学校教育で悩んでいること、アレコレ>
<2021年4月現在、特にスキをしてもらった記事たち>
✅スタートラインは「わたしが教育すれば変わる」と思わないこと。
✅スタンフォードが中高生に教えていること
サポートは美味しいおやつとコーヒーで心をみたすことに使わせていただきます☕️
