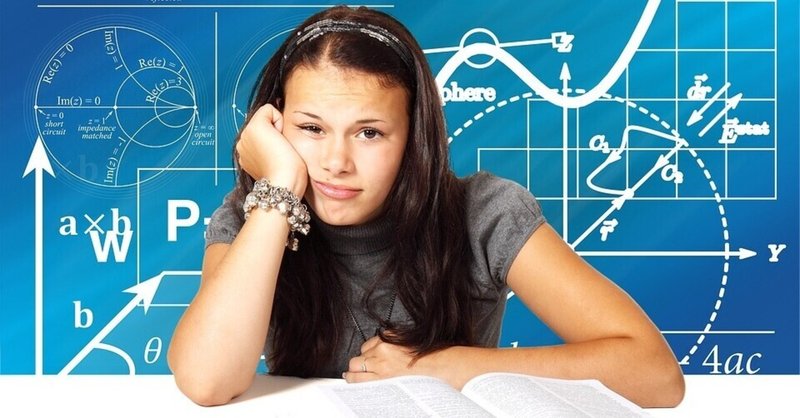
「知識」が「知式」になっていませんか?
はじめに断っておきますが「知式」は造語です( ̄▽ ̄;)。
漢字には、それぞれに意味がありますよね。
「知識」は、たった二つの文字から成る熟語ですが、よくよく考えてみると、その本質を見過ごしがちな言葉ではないかと感じています。
ということで、今回は簡単な言葉遊びをしてみようと思います。
余談ですが、造語を考えるって頭の体操になります(*'▽')。
そういう意味では、新語(造語)が若い世代から発せられるのも、思考の柔軟性があるからではないでしょうか?
「自由な発想」という言葉はよく聞きますが、歳を重ねるごとに無自覚に価値観が凝り固まっているのだなと、言葉遊びを考えるたびに痛感します。
それでは本文に戻りますので、最後までお付き合いいただけると幸いです。
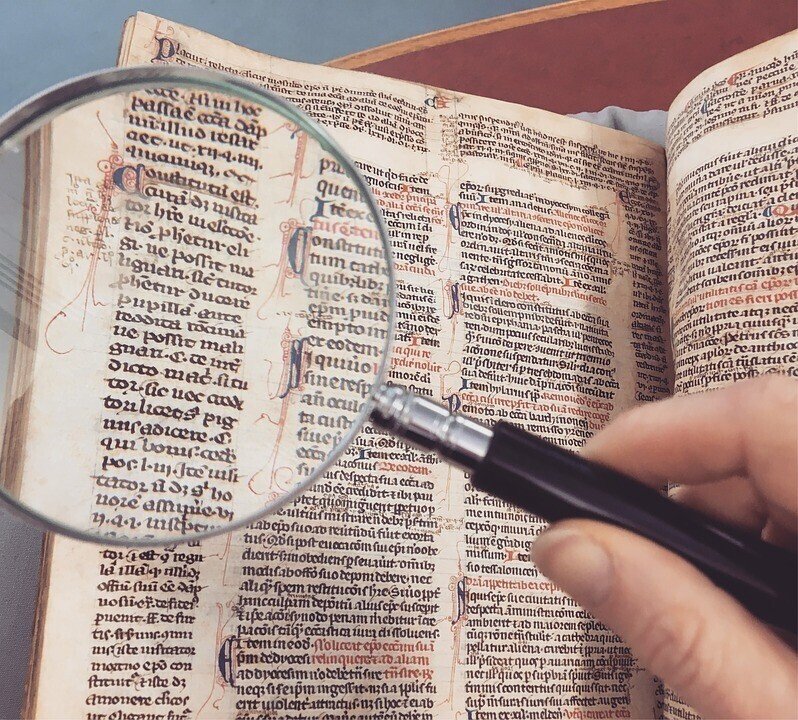
ーーーーーーーーーー
まずは「知識」の意味について、改めて確認しておきましょう。
【知識】
1 知ること。認識・理解すること。また、ある事柄などについて、知っている内容。
2 考える働き。知恵。
(デジタル大辞泉より抜粋)
…知ることと理解することには大きな差がある気もしますが、要するに「インプットした情報を保存・記憶処理すること」とします。
人間の脳は、顕在意識から潜在意識・無意識に至るまで、さまざまな情報が集積されています。
ですから、記憶するということは、必然的に何らかの類似あるいは連想する言葉と紐づけられて蓄えられるということです。
私が述べたいのは、「何と紐づいているか?」ということです。
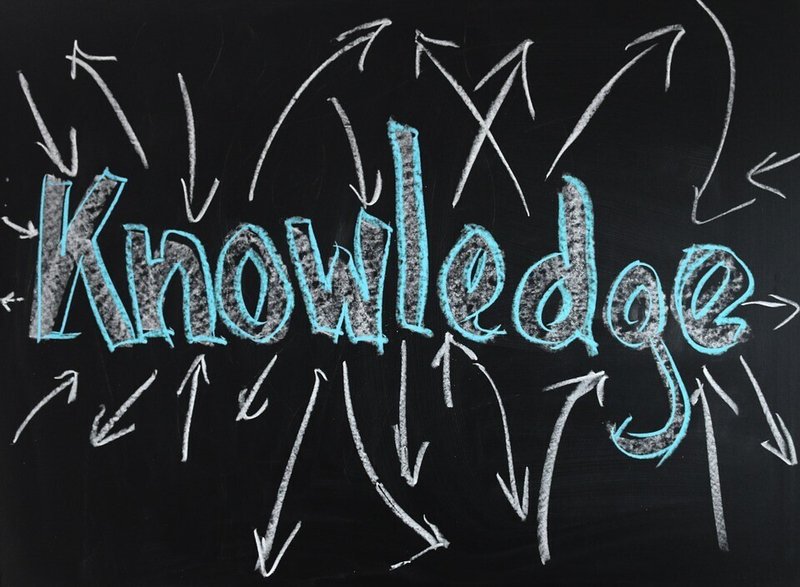
ーーーーーーーーーー
「識」とは、「物事の道理を知ること。また、見識があること」とされています。(出典:デジタル大辞泉)
「式」とは、「 ある定まったやり方やかたち。方式。形式。型」となっています。(出典:デジタル大辞泉)
個人的な解釈ですが、「知る」という行為との向き合い方は「付け加える」と「当てはめる」に大別できると感じています。
「付け加える=枠の外」
「当てはめる=枠の内」
…このようなイメージです。
新たな知識を得たとき、あなたはどのように考えるでしょうか?
辞典や辞書が好例となりますが、言葉には新語(造語)の他に意味合いが変化するモノも多くあります。
例えば「絶対」の本来の意味は「他に比較するものや対立するものがないこと」です(出典:デジタル大辞泉)
ですが、今では「打ち消し」や「強調」といった副詞的用法が主な用いられ方ではないでしょうか?
「絶対は絶対だ」という少し不思議に感じられる日本語は、言葉を既存の意味合いの内に押し込めようとするから違和感を感じるのではないかと思うのです。
「絶対の絶対だ」を、「他に比較するものや対立するものがないこと」ではなく「強調」を表している言葉だと認識できるのは、本来の意味合いとは違う用法だと付け加えているから、という論理になります。

ーーーーーーーーーー
知識を得ることは、成長とイコールだと考えるかもしれません。
しかし、自分の固定観念という枠のどこに新たな「知」を置くのか?という意識を持っておかないと、「自分は間違っていない」という間違った信念を「絶対だ」と裏付ける道具に過ぎなくなってしまうのではないでしょうか?
書籍を購入するとき、無意識に選書が偏っているかもしれないと感じることはありませんか?
不意に誰かに良書を紹介されたくなりませんか?
それは、もしかしたら「知識」が「知式」に変容している警鐘なのかもしれませんね。
どこまでも広く、思考の枠を広げていきたいものです。
ーーーーーーーーーー
ということで、最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の投稿は以上です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
