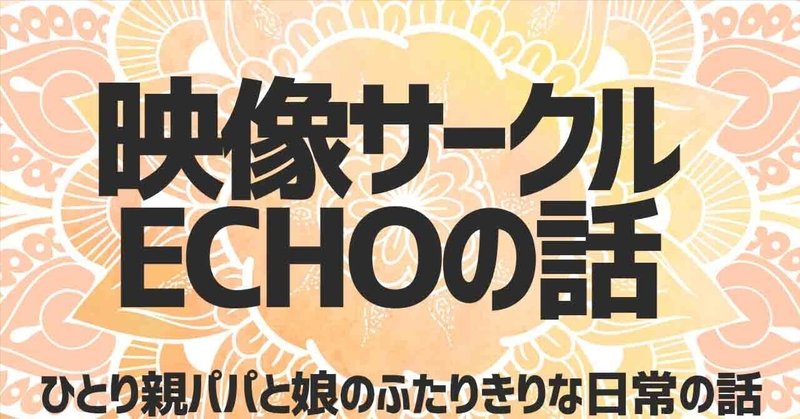
ひとり親パパと娘のふたりきりな日常の話 その11
こんちわ。
東京で映像クリエイターをしている
1児のシングルファーザーのKENと申します。
シングルファーザーになるまでのお話はこちらから
元妻が俗世を捨てて出ていってから半年が過ぎようとしていた。
毎日の幼稚園への送り迎え、毎朝のお弁当作りも慣れてきて同時に仕事もなんとかこなしてきた。
それでも離婚によるショックで怒りとやるせなさ、プレッシャーに潰れそうになる。
いつもモヤモヤしており、元嫁の言動がフラッシュバックして怒り狂ってしまう。
自治体が提供するカウンセリングもまったく役に立たない。
なのでnoteに書くことで自己流の認知行動療法を始めていた。
そんなある日、僕はとある映像サークルに参加することにした。
映像を作るということ
僕にとって映像というのは見るだけのものではなく、作るものでもある。
学生時代から映画研究部に所属し、カメラを持って自主制作していたし、友人の映像を編集で手助けすることも多かった。
この経験から僕は就職でも映像業界を選んだ。
当時は就職超氷河期でとてもとても大変だったが、運良く一社だけ都内のポストプロダクション(映像編集の専門会社)に入社できることになった。
大学の卒業式の日に内定の電話がかかってきたのを覚えている。
(つまりそれまで一つも内定をもらえてなかったというわけだ)
その後会社員として7年ほど働いた後にフリーランスとして独立し、現在まで続いているわけだけど、仕事以外にも趣味として映像を作っていた。
チームを組んでショートフィルムやMV、演劇用の映像、他にはちょっとしたドキュメンタリー、Vログ?的なものやアニメーションなど。
完成しなかった作品や、企画時点で頓挫した企画も多かったけど趣味として作っていたし、とても楽しい趣味だった。
それも僕が結婚し、娘が生まれてからは
趣味で映像を作ることはほとんど無くなった。
強いて言えば元嫁の参加していた某スピリチュアル系団体のイベント用映像を作ったくらいだろうか。
とはいえ、家庭の維持を優先すべきなので映像を作るのは我慢して仕事と家庭に注力していた。
実際、映像作品を作るのってとてもお金も労力もかかるので難しかったと思う。
結果、僕は欲求不満が溜まっていたが、それも仕方のないことだと思うようにしていた。
でも今思えば映像を作る…というか何かを作る・表現するという行為はこのnoteに認知行動療法として記事を書いているのと同じく心の安定をもたらすものだったんじゃないかと思う。
家庭と趣味
そんなわけでモヤモヤしながらも映像の自主制作を自重していたわけだけど、ここにきて元妻が出家してしまい、僕は娘と二人きりの生活になった。
コロナが少しづつ落ち着き始めている間、僕は悲しむ娘を慰め、生活を維持する方法に悩み、ことあるごとに元嫁に対する怒りがフラッシュバックし、我を失う。
こんな事を延々と繰り返しながら毎日神経をすり減らしていた。
前に書いた通り、頼みの綱だった行政サービスも全然マッチできず八方塞がりだった。(その話はこちらを参照↓)
たぶん、うつ病の一歩手前だったんじゃないかと思う。
なにか…なんでもいいからまずは精神的な部分から立て直しを図らなければ。
そこで僕がやった事がこのnoteを書く事と、
映像を作る趣味を再開することだった。
しかしもう何年も作っておらず、時代も変わり撮影周りの機材環境もすっかり変わってしまった。
また、自主制作をしていた時の友人達はすっかり遠くに離れてしまったり、すっかり疎遠にもなっていた。
そこで、まずは映像を作る人たちのコミュニティに参加することにした。
どこに参加するか?
僕は自分からどこかのサークルに入るという事をしたことがなくて、最初はどうしたら良いのかよくわからなかった。
とりあえずスタッフを募集できるサイトの「シネマプランナーズ」を見てみた。
色々な団体がスタッフを募集しているが、大体音声やカメラ、演者などの募集がほとんどで、監督や編集の募集が無い。
なぜか?
それはほとんどのケースで「自分の映像を作りたい人」=監督をしたい人が作品のスタッフを募集しているからだ。
そして編集は監督が自らじっくりとやりたいのだから当然編集者の募集も無いのである。
僕のような技術者としての編集者はせいぜい特殊効果や合成くらいでしかお呼びじゃ無いのである。
まれに演者自身が自分を主演にした映画を作りたくて監督を募集しているケースがあるが、正直言ってあまり食指が動かなかった。
やはり監督を募集と言っても自分自身をかっこよく撮ってもらいたいという思考が透けて見えるからだ。
じゃあ自分で募集すれば?とも思ったが、この時はまだ自分で脚本を書き、自分で制作資金を捻出し、自分で撮影現場に出る…なんて余裕はまったく無かったのだ。
自分の精神状態と崩壊寸前の家庭の立て直しを図るために家庭を犠牲にするのでは本末転倒なのである。
結局のところ、現状で映像を作るためには
一人で作れる規模
お金がかからない
時間の融通がきく
こういった前提条件が必要なのである。
じゃあ自分一人でやればいいじゃんって話になるのだけど、そうなるとどうしても孤独な戦いを強いられてしまう。
変な話だけど、一人で映像を作るにしても、一人ではモチベーションが続かないのだ。
どうしても先立つ物が必要になる。
それが何かというと、
作った作品を見てくれる人、そして同じように映像を作っている人たちがいる、という実感なのだ。
Twitter(いまは「X」に名前変わったけど全然慣れない)では映像を作っている人たちがいっぱいいるし、そういう人たちと絡めばいいのか?とも思ったけど、なんとなく求めている距離感とは違うし、そもそも「動画編集」界隈の人たちの話題って副業とか単価とか時短とか案件がどうのなんて話題ばかりでまるで違う世界の人たちに見えてしまう。
そりゃお金は大事だけどクリエイティブな話はしないの?面白い表現の話題とかしないの?そもそもそれやってて楽しいの?って思ってしまう。
自分でイチから映像制作チームを作る体力は無く、
TwitterなどのSNSで絡むにも求めている距離感が違う。
そんな折、僕はECHOという映像サークルに目が止まった。
映像サークル【ECHO】
ECHO(エコーと読む)は映像クリエイターでチュートリアル系YouTuberでもある「サンゼ」さんが主催する映像制作を楽しむ人たちのサークルだ。
学生・主婦・フリーランスなど、プロもアマチュアも参加している交流サークルで、サークル内Slackでの情報交換やさまざまなイベントも行っている。
たとえば、
サークル内勉強会
ハッカソン(制限時間内で映像を作る小イベント)
エコツム(少人数グループで行う短期のチャレンジ)
バーチャル空間でのリアルタイム作業部屋
飲み会(笑)
ゲーム会
そして最大のイベントとして年に一度の「ECHO映像大会」という発表会もある。
当時はあまり詳しく調べていなかったが、もう限界を感じてる精神状態のなかで僕は「入会ボタン」を押した。
たぶん白目むいてた。

広がっていく世界
ECHOに入会すると、そこにはいろんな人たちがいた。
学生で自主的に映像を学んでいる人や主婦業の傍ら映像を作っている人、プロとして第一線でバリバリ映像を作っている人、副業で映像を始めたばかりの人など。本当に様々だ。
専用のSlack スペースが用意されており、Twitterのように毎日の他愛もない事を書いたりバーチャル作業部屋への待ち合わせをしたり、おすすめの音楽を紹介したり、ゲーム会を企画していたり。僕のように子どもを育てる親御さんのチャンネルもある。CGやAIなど新しい技術について議論していたり、新しい情報を教えてくれたり、わからない事を教えあったり。
さまざまな事情を持つ人たち全員が、自分の作品を作っている。
これはすごいぞ。
僕はとても感動してその輪の中に入っていった。
最初は主催のサンゼさんも交えながら新メンバーの歓迎会も開いてくれた。
僕はだいぶ舞い上がっていたし、その時の精神状態からいって相当におかしなテンションだったと思う。
それからハッカソンに参加したり、パパママ向けチャンネルに投稿したりと少しづつ孤独から解放されていったと思う。
入会してからすぐに映像大会が開催されたのでこれにも参加した。
タイトルは「Push Funk Pop」だ。
急ごしらえではあったけれど、娘が遊ぶプッシュポップを利用して映像作品を作った。
(↓こちらのリンクから見れます)
映像大会はYouTube上だけでなく、某映画館を貸切でリアルイベントとしても開催され、全国からECHOメンバー(通称エコメン)が集結し、みんなで鑑賞した。
さらに打ち上げとしてBBQにも参加させてもらった。
娘も連れてきていたのだけど、すっかりエコメンの皆さんと仲良くなっていた。というより僕よりもモテてた。
まあ娘は人見知りしないし可愛いから仕方がない。うん。
また、僕は毎朝の娘のお弁当の写真をアップすることにした。
毎日続けるということ、そして誰かに見てもらうということ。
毎朝お弁当の写真に「おはようございます」とコメントを添えて投稿する。
これがお弁当作りに手を抜いたりしないためのモチベーションに繋がった。
相変わらず仕事はピンチだし、家事も育児も大変だ。
元嫁に対する怒りやカルトに対する怒りが収まったわけでもない。
そして誰かが僕を助けてくれるというわけでもない。
けれどECHOに参加して僕はどこか救われた気がした。
映像大会で作った作品に、特別なテーマや主張したい事を入れたわけではないのだけど、それでも僕が手作りで作った作品が、まぎれもなく僕という個人が作った作品が誰かに存在を認めてもらえた事にとても感謝できた。
この時になって初めて、僕はちょっとだけ前を向けるようになったのだ。
今回のお話は2022年での出来事だけど、ECHOには現在も在籍してます。
次回は今年、2023年のECHO映像大会について書こうと思います。
本当はその前に卒園とか引っ越しとか入学とか色々あるのだけど、いったんそれらをすっ飛ばします。
まだその余韻が残っている間に書いておきたいと思ったので。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
