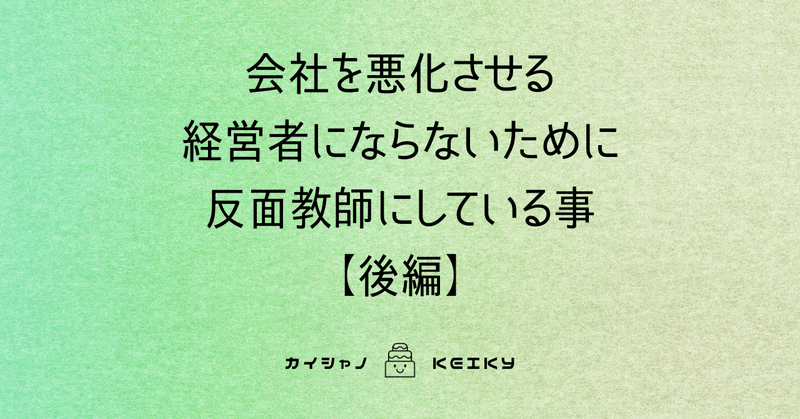
会社を悪化させる経営者にならないために反面教師にしている事【後編】
ときどきいろいろな会社の役員の方にお会いしたり、経営企画部門の異業種交流会に年に1,2回出ることがあって経営に関する悩みについて話すことがある。
志をもって比較的大きな上場企業で働いているサラリーマンとしては悩みの種はだいたい経営者であったりするし、うまく誘導できないことも多い。取締役や執行役員を含めた経営クラスもみんながみんな優秀なわけではないし、評価は透明性は全くないのでいろいろと反面教師にすべきことに出くわすことが多い。
そんなぼくが書き留めた会社を悪化される経営者の兆候からの教訓について後編を書かせていただいた。
前編に続いて残り5つの反面教師にしたいこと。
■ 責任転嫁ではない権限移譲を積極的にやろう
権限を”あえて”自分に集中させている経営者は多い。そういう経営者に限って「それぞれが自主自立の精神でやってほしい」ということをよく口にしたり、「なんでもかんでも相談してこないで自分で判断しろ」と叱責したりする。
ぼくはこれには懐疑的で、そういったことを言う人に限って、自分で判断したいと思っているし、人に権限を渡す気はそうそうないのだ。自分に権限がある状態を固持しているケースがほとんどである。
保守的で先送り思考が強いサラリーマン経営者がもっともやりやすいのは「権限は自分で、責任はとらせる」という状態を保つことである。そういった思考に陥っている経営者は非常に多く、だいたい上場会社で長期政権を保っている会社はそういう面が割と強いということが想像がつく。
本来権限移譲は現場での意思決定スピードをあげて市場の成長スピードに負けないようについていくことや、競合に対して優位になるためとにかく先手を打つためにとても重要なことであるから権限を現場に与えるという目的がある。
もう一つの重要な目的として経営者がもっと違うことに時間を使うために権限移譲をするという目的がある。
現場のビジネスの戦いがあまりに熾烈で、経営者がその戦いにずっと集中せざるを得ないと、中長期の方向性付けや、あらたな将来に対してアンテナをはることができないという不測の事態に陥ってしまう。
そうならないために、ビジネスの戦いは現場で判断できるようにして自分はネットワークの構築や現場のラインでは入ってこない情報をとりにいったり会社の将来を考える活動をするために移譲する場合がある。ダメな経営者は「自分が楽をするために」と考えている場合もあるのでそのあたりは反面教師にする必要がある。
また、日本企業の問題は責任の取り方だ。伝統的な日本企業は責任を分散させみんなで取るという家的な発想があるし、だいたいスケープゴートにされて責任を部下がとらされるケースがあるがまれである。
「権限と責任はセット」ということを言う人があるが、厳密には間違っている。本当の経営者であれば「権限は渡して責任は自分がとる」くらいのことを言ってほしいものだが、そういったことを言ってくれる役員や経営者は稀である。
自分はすくなくともビジネスを中心に考え、とにかく事業の成長だけを考えてベストな判断ができるようにしたいし、部下のために責任を常に取り続ける人でありたいと思う。
■社内や業者とだけ接して仕事を作らない経営者にならないように気を付けよう
内向きな経営者というのは結構いるもので、社外に出ない。知っている者にしか話さないという経営者は多い。
また、自分が強い立場で入れる相手としか付き合わないケースは多い。例えばメーカーに対して商社は”表面的には”へりくだってくれるので気持ちいいと感じる役員は多い。
ところが彼らはオオカミなので、利益をごっそりもっていくビジネスを作ってメーカーがただのサプライヤーにさせられるということを分かっていない。
そんな会社の経営者はなぜ自社の営業マンが商社マンのようにできないのか・・・と嘆いたりしているがとんだ勘違いであって、その経営者の能力が低いだけとした言えない。そういう商社は猛獣であることを認識したうえで、協業したり、つばぜり合いをしながら自社も利益を増やしていくしたたかさがないといけない。
社内でも知っている昔からつかえている人としか話さない経営者は多い。自分が年を取ってくると若い人のアップデートがさらないし、自分が若いと思っていた部下がすでに50だったりして、すでに若手ではないのに若手のように接して、おだてられて気持ちよくなっている経営者というのは結構いるものだ。
また、特定の部下からの話しか聞かず、そういった部下も会社の上層部の人間であるから「実は人からまた聞きした間接的な情報」しかもっていない場合が多く、とても不確かな情報だったり誰かが着色した情報だったりするので経営者がミスリードする場合がよく起きる。
そういった情報をもとに勘違いをする経営者も経営者だが、誤った情報やバイアスがかかった情報をうのみにして経営者に情報をあげる幹部や役員もたいがいだと思うことが多い(経営企画部門ではそういったねじ曲がった認識をなおしにいかなければならないことがなんと多いことか・・・)。
経営者としては自分が下に出なければならない嫌な相手やお客様とも接しなければならないし、若い世代にもアンテナを張ることも大切。常に社内の人たちの情報もアップデートして、子飼いの部下からだけではなく、嫌いな部下や全然違う人に同じ質問をして多面的に意見を聞くことなどを心掛けなければならない。そういったことを忘れない経営者になりたい。
■人を見る目が不足してるかどうか周りの人から点検してもらえるように聞く耳をもとう
経営者は次の後継者や、会社の事業をリードする人を任命して自分の代わりに具体的に事業を進める人を決める。
自分では見る目があると思っていたり、どうしてもかわいい部下を自分への貢献と引き換えに引き上げようとする傾向がある。
実力も伴っていて会社からも人望がある人であれば良いが、必ずしもそうではないので、経営者が任命したリーダーと現場が必要としているリーダーは異なる場合はかなりあって、事業が痛んでいく場合ことがあり、社長が決めた以上は誰も口出しをできないので誰も何も言えないのでいったん間違うと病原菌のように会社を蝕んでいく。
マネジメントとリーダーシップの違いについて以前記事を書かせていただいたが、マネジメント、つまり管理思考がつよい人ばかり上に上げてしまうと官僚主義が強まってしまう。こういったタイプは一定数必要だが、程度問題であまりにも官僚主義が強まるとYESマンばかり引き上げられて、部下に支持する伝言ゲーム状態になる危険性が高い。
ちゃんとリードできる人材、自分がかわいいとおもって買っている人間だけでなくて周り、同列や下の社員からどうその人物が思われているかまで考慮して考えるように気をつけたい。
■会長、各部門の先輩やOBなどに気を遣ってなにも言わないのはなさけないからやめよう
会社の社長と聞くとなんでも自由になるイメージが一般的にはあるが、オーナー社長でもない限り、実はあまり自由が効かないことで悩んでいる社長が多い。
いや、もう少し正確にいうと、顕現的には自由はできるのだが、角が立ったり恨みをかうのを嫌がってあえて我慢する社長は多い。
社長には前任、会長や顧問がいる場合がある。また自分が最年長とは限らないので先輩の部下たちもさまざまな子会社などを運営していたりするものだ。
本来的には自分が代表権のある取締役社長であれば独裁体制を構築してこういった目の上のタンコブたちを排除することはできる。ところがどういうわけか、会長に気を使ったり現場の先輩にはきつい指示を出せなかったりする。
これは自分が嫌われたくないとか、いざかいをやりたいときに前任を追い出すような嫌がらせをしたら自分もそうされるという恐怖感からくる場合が多い。
経営者として会社の事業だけを考えて未来に向けて経営を責任を持ってやってほしいと願うばかりだが、当の本人は孤独だとかどうしようもないことばかりに気を取られているような社長にはならないように気をつけたい。
■非難されていると感じたら自分が年だと考えて引退するか非難を受け入れよう
現場から自分の指示とちがう意見があがってくるときの対応というのはその経営者をはかる一つのバロメーターとぼくは思う。
構造改革という名のプロジェクトを社内で立ち上げ、経営に対して中長期的な経営課題や、自社が成長するために必要な変革について検討させることがどこの会社でもあると思う。検討させる相手が若手だったり、幹部だったり、役員だったりするが、そういった検討会はどこでもあるものだ。
すべて中間管理職が自分が怒られることを恐れるあまり忖度して気持ちのいい事ばかりを提案させる会社は論外として、結構聞く耳があるから自由に提案をするようにという雰囲気を出しながら、実際そういうものが上がってきたときのあなたの会社の経営陣の反応をよくみておくことだ。
だいたいみんな社員もバカではないのでどんな提案もある程度的を得ていることが多いはずだ。そして勇気を出して会社のことを思って提案している。
それを「おもしろい」としてどんどん採用するなら、深掘りされるような経営者なら最高だが、「自分を非難されている気分になる」とか、「君たちはおれよ の苦労を何もわかっていない」という経営者がいる。
自分が常に上の立場なので、アドバイスやコメントをすればいいとおもっていて、実際には会社をどう良くするか!という提案をしていて経営者の批判はしていないのに、「俺がやっていることに対する批判」と捉える経営者がいかに多いことか。
こういった意見はさまざまな会社できくのである特定の会社だけではなく、長期的に政権を独裁的に運営している経営者にはよくある話だ。
そこでキレてしまって叱責をした日にはもう誰にもあなたに意見をいうものはいなくなる。みんな受け身の仕事しかしなくなり、だれも考えなくなる。「社長はなんていっているか」しか興味がなくなり、創造的なエース級の社員から会社を去っていく。
その経営者がいるうちはなんとかフリーライドして会社がたもててしまうのが納得いないところだが、去った後にメタメタになった会社で仕事をすることになって割りを食うのは若手社員たちだ。
少なくとも金もたくさんもらっているのだからサッサと任期をルールとして決めて数年で去るべきである。そのタイミングの一つとして、「自分が非難されている」と感じたときというのは一つの経営者のバロメーターとして考えてはどうかとぼくは思う。
以上、二回に渡って経営者として反面教師にすべき点を書いた。
これらの点は自分が経営者にならなくても、誰かの人の上にたつ人がすべて反面教師として考えもいいことのようにも思える。
自分がいかにその会社のビジネスのことを四六時中考えて行動して社員のためにもひたすら前向きに進めるかということを考えて仕事をこれからもしていきたいと思う。
前編は以下からご覧ください。
keiky.
いただいたサポートは、今後のnoteの記事作成に活かさせていただきます。ますます良い記事を書いて、いただいた暖かいお気持ちにお返ししていきたいと思います☆
