
もしかしたら宿命解説【源頼朝編】⑬
【源頼朝編その13】
こんにちは。
もしかしたら宿命解説、13回目は頼朝公の死後の世界です。

算命学では、当事者がこの世を去ってもその人の気は残る。と考えられています。現在でいうならば、中国共産党の初代主席毛沢東や、パナソニック(松下電器産業)創業者松下幸之助などもその死後影響を与えていると考えられています。
人の気は残る。
人の気はどんな人でもその気は残ります。ですからあなたの大切な人の気もその死後最低10年は(大体次の大運が終わるくらいまでは)残ると言われています。その人がどの位のものを成し遂げたのかでその影響力は長く残ると考えられております。
さて、そこでこのシリーズで取り上げた【源頼朝】ですが、日本の歴史上はじめて武家政権を樹立した初代の将軍です。この人の気が残らないはずがない。
ということで無理やりこじつけて解説してみようと思います。
この解説も秘伝を使う部分があるので算出方法は伏せさせてください。
頼朝の大運の抜粋
43歳・庚子(1190年/文治6年・建久元年)~1199年(己未年)没
53歳・己亥(1200年/正治2年)~
63歳・戊戌(1210年/承元4年)~
73歳・丁酉(1220年/承久2年)~1221年、承久の乱勃発。
1200年より、頼朝公から見た世界は、自分の子ども(頼家・実朝)が主役となる20年間がスタートします。
また、1200年からは頼朝の部下たちが台頭し、

1210年からは、その活躍の舞台に自分の妻と兄弟(友人・仲間)が目立ってきます。

頼朝の妻は北条政子。1210年時点では頼朝の兄弟は全員亡くなってますから、兄弟であり友人・仲間でもあると言えば、政子の弟、頼朝にとっての義弟となる、北条義時ではないでしょうか。
頼朝死後20年間は、頼家・実朝を主人公に頼朝の部下や妻・義時がその回りを彩っていく時期となると書いてあります。
実際の歴史の流れ
次の通りです。
頼家の在位は(1199年~1203年)実朝は(1203年~1219年)となります。
1200年(正治2年) 十三人の合議制開始。梶原景時の変

1203年(建仁3年) 比企能員の変
1204年(元久元年) 頼家暗殺

1205年(元久2年) 畠山重忠の乱、牧氏事件


1213年(建暦3年) 和田合戦
1219年(建保7年) 実朝、公暁に暗殺される

以上主だった出来事です。
すべて頼朝の後継者(息子たち)が主軸となって周りが騒いでいます。
まさに、頼朝の宿命通りに動いていますね。
そして1220年から、頼朝から見たメインは妻・尼御台政子。
その脇を固めるのは義弟・北条義時となります。

1221年・辛巳年(承久3年) 承久の乱。
1224年・甲申年(元仁元年) 伊賀氏の変。
以上の事柄が勃発しました。
1221年(辛巳)は頼朝にとって年天中殺です。
辛は、頼朝にとって兄弟の意味ですから、これは義時にあたると考えます。
そして、その義時が座っている巳が中殺されている年になりますので、義時にとって不自然な、枠の外れた天中殺現象が表れます。この年に、後鳥羽上皇から義時追討の院宣が出されます。そして巳の中には「戊・庚・丙」がありますから、妻・政子も中殺されます。
政子が主役
1220年から主役である政子はここで後世に名を遺すあの大演説をします。
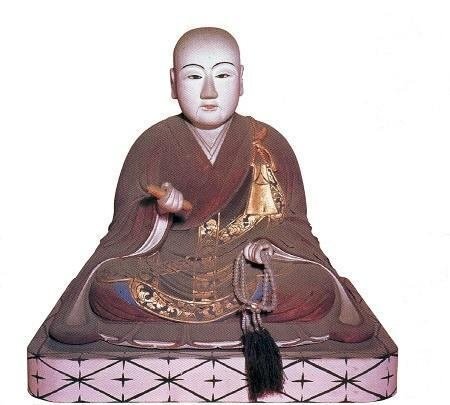
この演説でこの日本という国は幕府を中心に社会が動いていくことが決まったと言っても過言ではありません。つまり、頼朝の宿命の中に、「妻政子によって武家政権の確立が決定づけられる」と書いてある。のです。
中殺を受けている義時ですが、メインのキャストでもあります。ですから、あり得ない不自然なことを体験がこのタイミングで起こった。とみることができます。

すべて頼朝の宿命に書いてあった!
逆を言えば、この「承久の乱」が起こらなかったら、朝廷に頭の上がらない武家政権がこれからもずっと続いた。むしろ、武家政権は続かなかったかもしれない。それくらい一大事となる出来事の主軸は、頼朝の妻と兄弟である、政子と義時が主役と準主役として演じてもらいますよ。と頼朝の宿命に書いてあったのです。
合わせて、伊賀氏の変は、義時の死後の北条家のお家騒動ですが、これを見事に収めたのが政子です。これにより、義時の後継者は北条泰時(以降得宗家として、足利尊氏が登場するまでその権力は続く)となり、御成敗式目を制定しこれは、明治憲法が成立するまでその影響が続くことになります。

日本ではじめて武家政権を樹立することに成功した頼朝公のその意志は、頼朝死後も続いていった。という裏付けの部分を記してみました。
頼朝不人気は宿命のせい?!
ちなみに、源頼朝が、徳川家康などに比べて圧倒的に不人気なのは、死期となるタイミングで、忌神となる「己」が関わっているからと読み取ることも出来ます。頼朝の残した気(波動)は、忌神の力によって後世にはあまりよい姿ではない形で伝わったのかもしれませんね。
時代のトップランカーはみんな同じことを言う!
最後に。
こういう宿命の人が将軍になったから武家政権はこうなった。
と考えるのではなく、当時、この日本という国に暮らしていた人々が、そして国家が、そういう体験が必要だったので、それに見合う人物が選ばれた。とみなしていきます。
だから頼朝公のせいでこうなったのではなく、日本で暮らす人々と国家が、源頼朝を欲したと考えてください。
そう考えてみると、「時代が自分に味方している。」「自分は時代に生かされている。」という言葉を、世の中を動かしているように見える人たちは口々に仰りますが、なんだか妙にしっくりハマりますね。
以上で【源頼朝】編は終了となります。
お付き合い、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
