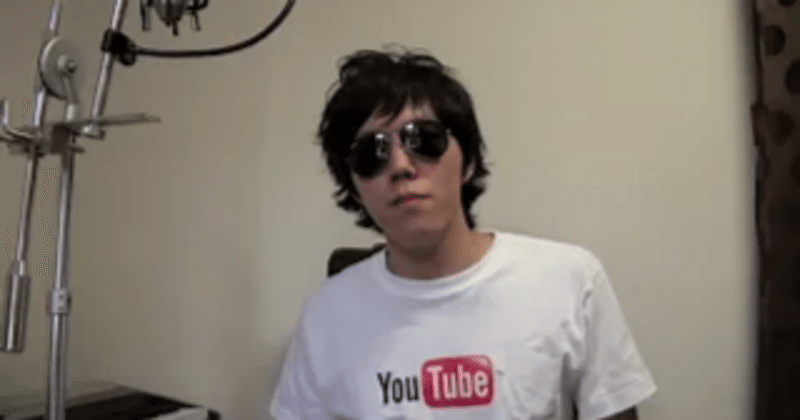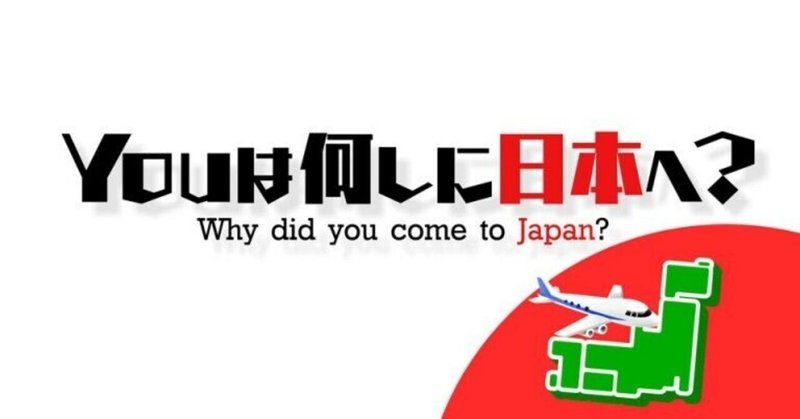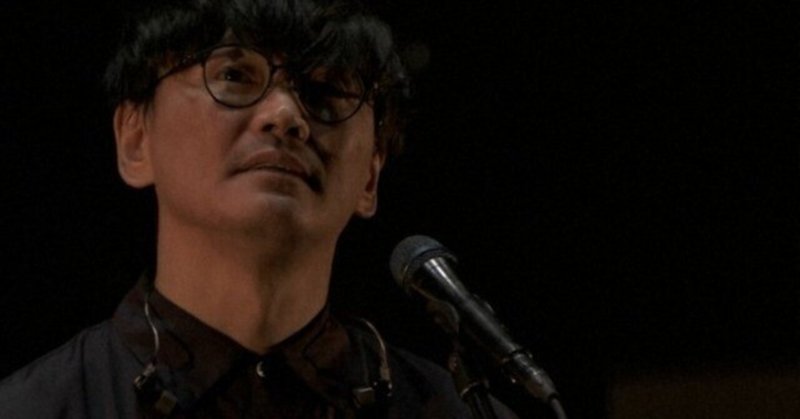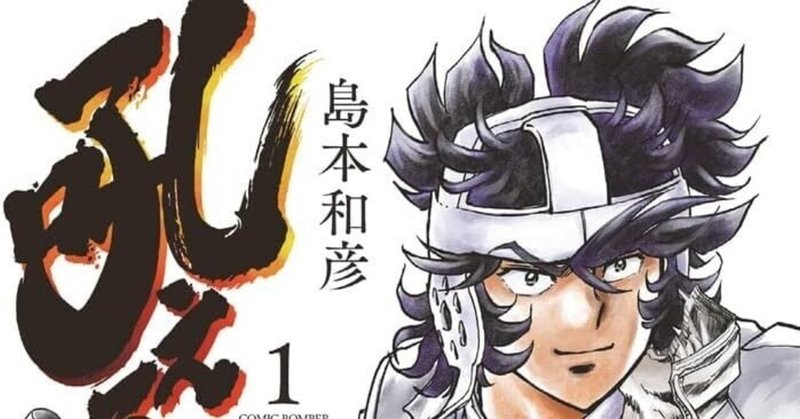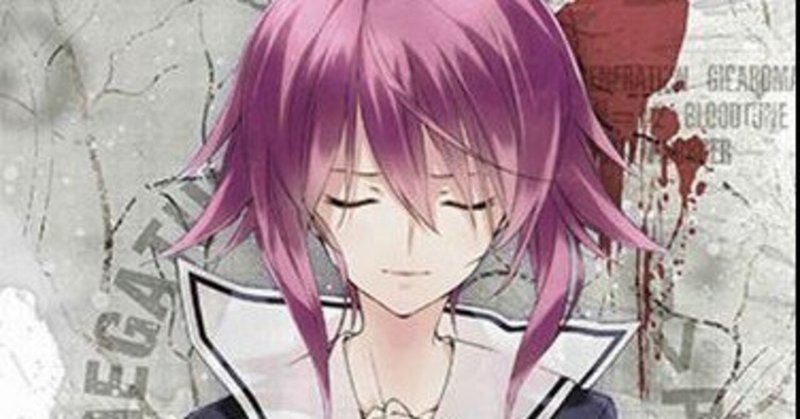最近の記事

映画で悪役や主人公がバイクを奪って一般人が「あ、俺のバイク!」ってなるシーンでバイクを奪われた人の気持ちを15分ずっと考えて映画の内容を忘れてる
映画とかで、主人公や悪役がバイクとかに乗って「あ、俺のバイク!」ってなるシーンあるじゃないですか。 主人公や悪役が逃げたり追いかける時に、他人の乗り物を勝手に奪うあのシーンです。 特にこのシーンがよくあったのが1980年代のハリウッド映画。この時期は本当にかわいそうなシーンが多くて、当時の警察官モノは「警察だ!」って言って手帳を見せて車を奪うシーン→車がオシャカになる展開が本当に多かった。 僕はこのシーンに結構引っかかる。 そこまでして執行する正義に意味があるのか。そ