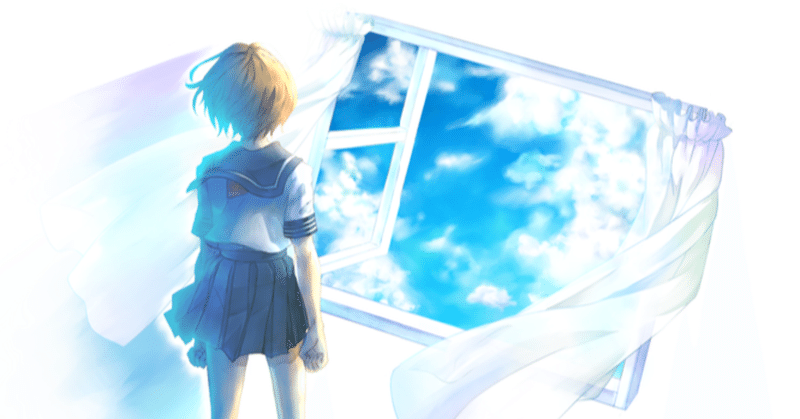
空のそら|第3章|長編小説
第3章…01
二学年になり、北校舎へと移ったわたしたち。本校舎とのあいだに中庭をはさんでいるこの校舎は、四階建てのおおきな建物だ。その三階と四階が、二学年が使用するおもなスペースとなっている。
新校舎といわれるだけあって、建物自体はとてもきれいで広々としている。ただ悲しいことにこの校舎には、屋上へつづく階段というものがないのだ。
一年の校舎へいくわけにもいかず、しかたなく毎日を教室ですごしていた。一学年で勉強の基礎たるものを、まともに学ぼうとしていなかったわたしたち。
いまさら授業にでたところで、まともについて行けるはずもない。徐々にクラスのみんなとの間に、みずから隔たりをつくっていく。
勉強がわからないことが恥ずかしいのではない。引け目を感じているということを、みんなに知られるのが嫌だった。
そんな気持ちが態度にあらわれるようになっていき、「わかるわけねえじゃん」と開き直るようになっていく。いつしか校内では、不良と位置づけされていた。
「椎名さん、ちょっと待ちなさい!」
「は? なに……」
「ちょっとこっちに来てみなさい。んん? 椎名さん、その髪は……パーマしとるよな」
廊下ですれちがった教員に呼びとめられた。通称オールドミスの、英語教師の竹上だ。近づいてきた彼女は、わたしの髪をなめるようにみる。
いったいわたしのまわりを何周すれば気が済むのだろうか。ときおり髪をすくってみては、にらむように顔をちかづける。髪の毛が返事をするとでも思っているのだろうか。
「……これ、天然なんやけど」
「こんな都合のいい天然が、あるわけないよなぁ」
「都合って……」
「今週中に、もとの髪にもどしてきなさい」
「もどせとか言われても。……これが元々やに」
めがねの奥の瞳を、ぎょろりとわたしに向ける。まったく信じていない、という目つきだ。しかしどんなに睨まれようが、本当なのだからどうしようもない。
竹上との言い合いは、しばらくつづいた。しまいにはどうしてこうも反抗的なのだと、ヒステリックに声をあらげはじめる。
ポケットに手をいれた竹上は、おもむろにハサミを取りだした。どうしてそんなところから、そんなものが出てくるのだろうか。
竹上の左手が、すっとわたしの髪にむかってのばされる。切るつもりだ、そう思った。とっさにわたしは背をむけて、その場から走ってにげる。
「待ちなさい! とまりなさい! もとに戻さないなら、ここで切ってしまいなさい!」
叫びながら追いかけてくる竹上に、恐怖を感じずにはいられない。これは脅しではない、彼女は本気で切るつもりだ。
こんなところで掴まってしまえば、きっとわたしの頭は悲惨なことになってしまう。助けだ、だれでもいいから助けを求めなければ。
しかし今この瞬時に、それをみつけることは不可能。とにかく人、そうだひとの多いところに逃げるしかない。
目のまえの教室にとびこむ。いったいここが何組なのか、そんなことを考える余裕などなかった。教室のなかでもとくに人のかたまっている場所をめざして、わたしはその中心へともぐりこんだ。
「椎名さん! こっちに出てきなさい!」
「……あーちゃん? どしたんな、なにしたん」
「オールドミスにパーマって言われて、切るっちゅうんやが」
幼少期から姉妹のように育っていた、そんな彼女がこの教室にいた。優等生としてここで生活している彼女に、迷惑はかけたくないと幼馴染であることはふせていた。
しかし、いまはそんなことを言っている場合ではない。彼女なら、きっといまのわたしを救うことができる。周りにいる生徒は、わたしの校則違反をうたがっているようだ。
「みんなどきなさい! 椎名さんを、こっちに出しなさい! かばうなら、あんたたちも同罪になるからね」
面倒なことにまきこまれたくはないのだろう、生徒のかたまりがじわじわと崩れはじめる。まずい、このままでは剥き出しになってしまう。
すっと幼馴染の子が、わたしのまえに歩みでた。わたしを背中にかばうように、彼女は両手をひろげ盾になる。それをみた数名の生徒が、ふたたび中心へと集まりはじめる。
みればその顔は、半信半疑でふあんそうだ。しかしありがたい、信じてくれ裏切らないと心のなかでさけぶ。
「先生! あーちゃんの髪は、天然です」
「そ、そんな都合のいい天然があるわけ……」
「おばちゃんに訊いてください。兄ちゃんも天然です! うちの親に電話して訊いてくれてもわかります。うちに三歳からの、あーちゃんの写真あります。持ってきましょうか?」
さすがの竹上も、なにも言い返せなかった。もつべきものは優等生の幼馴染、わたしは運がよかった。たまらず飛びこんだ教室が、この教室で本当によかった。
隼斗のことがあり目をつけられているのではないかと、幼馴染はわたしにいった。どうしてそんなふうに考えるのだろうか。
これはわたしの生活態度の問題であって、隼斗はまったく関係ない。ましてやここに居ない人間のせいにするなんて、筋違いにもほどがある。
しかしわたしを心配してくれているという気持ちは、やはりとてもありがたく感じる。助けてくれたことに対してとその気持ちにたいして、感謝のきもちをつたえ教室をでた。
「なあ……、おばちゃん聞いてよぉ。今日な、学校でオールドミスにハサミ持って、追いかけまわされたんでぇ……」
「なんな、その……オールドミスっちゃ」
放課後、いつものようにわたしたちは隼斗の家にいっていた。茅野と皐月には、すでに竹上事件は愚痴ってある。
まだまだ気持ちが治まらないわたしは、隼斗のへやをでて彼の母親のいる部屋までおしかけた。わがもの顔でくつろぐ、タクシーの運転手。
このひとが隼斗の母親の彼氏だということくらい、だれが何をいわなくてもわたしたちは気づいている。寝ころがってテレビを観ていたおいちゃんが、ちらっとわたしの方をみた。
ふたりのまえにぺたんと座り、竹上の通称の由来をはなした。それからハサミ事件を存分にぐちり、隼斗の母親をわらわせた。
いや、笑わせるつもりなど、毛頭なかった。しかしあまりの興奮ぶりがおかしかったのか、ふたりはけたけたと笑ったのだ。
「そん、オールドミスとかいう先生よ。おまえらん若さが妬ましいんじゃわい」
「は? ……なんそれ」
「いい歳こいて相手もおらんで、欲求不満でヒステリックんなっちょんのじゃわい」
「ちょっと、あんた子供んまえで、なんバカなこと言いよんのな」
支えていた腕を隼斗の母親にはらわれて、がくんと頭をおとしたおいちゃんは笑いながら身体をおこした。あぐらをくんで座り直すと、いたずらっこのように舌をだす。
すっと母親の手がのびて、わたしの髪をすくう。やさしく髪をすべらせながら、このふわふわの黒髪が可愛いのだと微笑んだ。
自分もそう思うと言って、おいちゃんは何度もうなづく。何度も念をおすように、絶対に染めてはいけないと隼斗の母親はいった。
「兄ちゃん、いま……いい?」
「どしたん、なんかあったんか」
部屋をのぞくと、光羅はベースを弾いていた。ベッドを背もたれにしたまま、膝のベースをよこにたてかける。くんでいたあぐらをほどき、膝をたてて足をひろげた。
光羅の瞳は、はなしを聞くよといっている。ここへ座れというように、彼の右手が膝のあいだで手招きをする。そこへ向かい合って座ろうとすると、くるりと後ろをむかされた。
いまから話をしようというのに、背をむけるというのはどうなのだろうか。しかし少々話しづらいことではあるので、こちらのほうが都合がいいかもしれない。
「……なあ、兄ちゃん。ストレートパーマって、高い?」
「は? ……なんし、そんなん訊くんな」
「ストレート……しょうかなって……」
「いけんよ」
「……だって」
「だってじゃねえやん。朱里は、この髪がすかんの?」
あきらかに不機嫌な、ひくい声がかえってきた。なぜ急にそんなことを言いだしたのかと問われ、学校での竹上のできごとを説明する。
光羅が中学のころも、竹上はよく同じようなことをやっていたという。彼女のストレス発散だから、気にすることはないといった。
うしろから髪をすくっては、さらさらとすべらせていた光羅。手ぐしでかるく梳かしながら、「兄ちゃんは好きなんやけどな」とつぶやいた。
兄は好きだといってくれるが、わたしは自分の髪が好きではなかった。母方に似てしまったわたしの髪は、兄とちがって真っ黒なのだ。
「うん、好かん。せめて、兄ちゃんみたいに茶色やったら」
「なんな、兄ちゃんの真似して茶色にしてえんな。……けど、したらいけんよ」
「けどさぁ……」
「けどじゃねえやん、絶対に髪はいじったらいけん。そげないらんことばっかり考えちょらんで、なんか趣味みつけらな」
「趣味とかいわれたって……」
「兄ちゃんの真似してえんなら、ベース教えちゃるで。担任が、軽音部つくったろ?」
この春、たしかに学校に軽音部ができた。それを立ち上げたのは、わたしの担任だ。彼はわたしを演劇部にさそってきたが、わたしはそれを断った。
そうすると何をおもったのか、軽音部なるものを立ち上げたのだ。そしてこれならば椎名もやってみようと思わないかと、ふたたび声をかけてきたのだ。
なぜ光羅がそのことを知っているのだろうか。さらに担任からのさそいを無視し、彼をさけて歩いていることまで指摘される。
「なんで入らんの? 兄ちゃんたちのとき、どげえ頼んでもつくってもらえんかったんで」
「ええ……、作ってくれとか頼んでねえし。楽器しきらんし、持ってねえし」
「じゃけん、教えちゃるっていいよんやん。朱里がするんなら、兄ちゃんがベース買っちゃんけん」
自分の趣味のために、必死にバイトをしている光羅。その大切なお金を、わたしのベースに使ってくれるというのだ。
練習用の楽譜もくれる、アンプも自分のをくれるという。他のメンバーが初心者ならば、全員の指導もじぶんが引き受けるというのだ。
そんなことはさせられないと首をふれば、意味のあるお金と時間の使い方だから気にすることはないという。このひとに人が集まってくる理由が、なんとなくわかったような気がした。
第3章…02
この部屋で過ごす、二年目の夏。ぬしである隼斗のすがたは無いが、いつだってそこに彼が座っているように感じてしまうのは何故だろうか。
また今年の夏は、あたらしい笑顔も仲間入りしていた。どういういきさつで加わったのか、よく覚えてはいない。ただあの事件が関係している、それは確かなことだった。
「なあなあ、椎名ってさ、ほんとうにベースとか初心者なん?」
「うん、そうで。……なんでな」
「いや……、あの指さばきは……。ある意味、ひわいというか」
「ひわいって、……なんな。兄ちゃんに教えてもらったけん」
「え、兄ちゃんとか言われると。ますます……。あ! っていうかさ、椎名の兄貴よ! あんときゃ、まじ殺されるかと思ったけんな」
石川のことばに、皐月は気まずそうに視線をそらした。増田も彼のことばに反応し、おおげさにうなづき前のめりになった。
そう、年末の和泉の事件だ。ふたりの話によると、犠牲になったのは、三年生だけだったらしい。
ただ石川にしてみれば、意味もわからず目のまえで兄が殴られたのだ。理解しがたいできごとであったに違いない。
そしてそうなるように仕向けてしまったのは、他でもない皐月の告げぐちなのだ。彼女からすればその話題は、耳が痛いにきまっている。
とうぜん、このわたしも心苦しい。もとはといえば、わたしの存在そのものが事をおこす原因となっているのだから。
「俺の兄貴はな、なんか椎名の兄貴のうわさ、知っちょったらしいで。和泉のせいで、とばっちりじゃってぶち切れちょったわ」
「あ、ああ……そうなんや……。なんちゅうか、わりかったな」
「んじゃけんど、なんで久我だけは……やられんのじゃろ」
たしかに、そう言われると不思議ではあった。茅野いわく、隼斗は変わったという。いや、変わろうとしていたと目をほそめた。
隼斗の過去のおこないは光羅から聞かされてはいたが、正直なところいまいちピンとはきていなかった。
知り合ってからの彼のことしかわからない私には、おそらく理解できていない部分がおおいのだろうと感じる。
「おーい、朱里。おくでババアが呼びよんで」
「おばちゃんが? なんで?」
「知らんけんど、行きゃわかるんじゃねんか。行ってみ」
おくから北斗がやってきた。ふすまを開けるなり、おくの部屋にいけという。隼斗の母親が、わたしになんの用事だろうか。
北斗が姿をみせたことにより、皐月の表情が活気づく。彼の行動のほんの一瞬すらも、見逃してなるものかと瞳をかがやかしている。
それを知ってかどうかはわからないが、北斗も皐月に意識的にはなしかける。わたしは立ちあがり言われたとおり、おくの部屋へとむかった。
「おばちゃん、呼んだ?」
「ああ、朱里。ちょっと話があるけん、こっちきて座りよ」
みればいつものように、おいちゃんの姿がそこにある。とくに変わったようすはなく、おいちゃんは畳に寝ころがっていた。
おばちゃんは手招きをしたあと、自分のまえを指さして座れといった。いつもと同じ光景なのに、なにか違うものを感じる。
よくないことを言われるのだろうかと、心なしか緊張をかんじてしまった。それが顔にでていたのだろうか、そんなに怖がらなくていいとおばちゃんが笑う。
「あんな、今からおばちゃんが話すこと、誰にも言わんって約束できるか?」
「え、……うん。約束……する」
「向こうの部屋のみんなにも、絶対にいったらいけんので」
「皐月たちにも? ……うん、わかった。絶対にいわん」
茅野たちにも言ってはいけないはなしとは、いったいどれほどの重い内容なのだろうか。聞かないほうが無難なのではないだろうか、どのていどの心構えであれば平気だろうか。
なんとなく、身体にちからが入らない。震えまではいかないが、それに近い感覚をおぼえる。いやがおうにも姿勢をただし、身構えてしまう。
「あんな、隼斗の夏の帰省の日にちがな、きまったんじゃわ」
悪いはなしを想定していたわたしは、あまりの嬉しい報告に声をあげそうになった。だがしかし声をあげるまえに、素早く隼斗の母親の手がうごいた。
叩いてかぶってのゲームをすれば、おばちゃんは誰よりも強いであろうと思わせる速さで、わたしの頭は弾かれていた。おいちゃんが横でわらっている。
基本的には、外部との接触には制限があるという。もしも帰省のことが外に知れ、なにかあっては困るからと彼女はいった。
「そんでな、三日後……迎えにいくんじゃけど。あんたも、一緒にいくか」
「えっ……、行ってもいいん」
「ほんとはいけんので! じゃけんど、連れていっちゃりてえなって、おばちゃん……考えちょんのよ」
おまえの健気なところが、見ていて切ないとおいちゃんがいった。そしてきっと隼斗も喜ぶだろうと、彼の母親も目をほそめた。
ただし部外者の同伴は、原則として許されてはいない。それを聞いたわたしは、どうしようもなく不安になってしまう。そんなわたしの表情をみて、おいちゃんはにやりと笑った。
ふたりで作戦をねったと、隼斗の母親は口角をあげる。それは行きの車のなかで説明をするから、とにかくお前は誰にもいわずここへ来いという。
誰とも共有できず、ひとりこの日を待つのはつらかった。そして、とても長く感じてしまった。昨夜は興奮のあまり、まともに眠ることすらできなかった。
「おせえが! ……誰にも言うちょらんじゃろうね」
いわれた時間より早すぎるのもどうかと、あえてちょうどに着けるように調整したら叱られた。今日のおばちゃんは、いつもと違いそわそわとしてみえる。
すでにエンジンをかけ待機している、おいちゃんのタクシー。うしろに乗れと手招きをすると、おばちゃんは助手席へと乗りこんだ。
町をぬけ峠へとさしかかり、車は県北へむけてひた走る。みどりの茂った山々をみて、きもちいいなどと感じたのは初めてかもしれない。
あとどのくらい走れば、隼斗のいる施設につくのだろうか。とちゅういくつかの集落があり、その度にここだろうか次だろうかと気持ちがはやる。
「ちょっと、朱里。あんた、ちゃんと聞きよんのか」
「ん? うん、聞きよるよ」
「本当じゃろうかな、こん子は……。ほら、あの川よ……あっこを渡ったら、もうそげえ遠くねえんじゃけんね」
「うん、わかった」
「……しゃあねえんじゃろうか。おばちゃんが声かけたら、ちゃんと言ったとおりにするんで」
峠をはしっている道中、おばちゃんは計画の説明をしてくれていた。わたしとて不安があるので、それはしっかりと聞いてはいた。
しかし内容を聞いて感じたことは、わたしの役目は単純なこと。大変なのはきっと隼斗の母親、彼女の演技力にかかっているのだ。
峠道がおわり、すこしおおきめの交差点で停止する。おいちゃんは、ウインカーを左にだした。かちかちという音が、カウントダウンのように心にしみる。
いままでは何気なくながめていた、この国道沿いの景色。この向こうがわの地区に、豊徳学園があるというのだ。
橋をわたり、しばらく川沿いをはしった。ひだりに小高い丘を確認すると、おばちゃんが準備をしろと声をかける。その声をきき、わたしはシートによこたわった。
「……久我隼斗の母です」
「お迎えで……ん? うしろ、……は」
「ああ、姪っ子なんですけどね。この子の母親が忙しくて、わたしが代わりに病院に……」
「……代わりに病院、ですか? はあ、具合がねぇ……」
そう、わたしは病人なのだ。ただ、どんな病気なのかは聞かされていない。どう具合のわるさを表現すればいいのか、そこまで考えていなかった。
男性のこえは、あきらかに疑いの声色だ。焦ったわたしは、とりあえず苦しそうに荒くいきをしてみせる。
おばちゃんがいろいろな言葉でごまかそうとしているが、顔を伏せているわたしには状況がつかめない。沈黙がつづき、わたしの不安をかきたててくる。
なぜ病院にさきに連れていかなかったのかと問われ、隼斗の母親もすこしだけ言葉につまった。しかしなんとか言い返し、こんどは男性がだまってしまう。
この威圧的な空気はなんなのだろうか、いったいいまどんな状況になっているのだろうか。男性はそばにいるのだろうか。わたしのことを見ているのだろうか。
「あ、まあ……あれですね。……こんかいだけは、おおめにみますけど。次からは気をつけて下さいね」
「そりゃもちろんですよ、そんなしょっちゅう具合がわるくなられても困りますしね」
「じゃあ、お母さんは受付のほうに……」
隼斗の母親が車からおり、おいちゃんはほっとしたようにギアをいれる。どうやら成功したようだ、変わらず様子はみれないが安堵した。
これで一安心だ、あとは隼斗がくるのを待つのみ。しかしわたしはいったいいつまで、こうして伏せていればいいのだろうか。
くるまがゆっくりと前進をしようとした、そのときだった。車をおりたおばちゃんに向かって、男性がぼそりと呟いた。
「……手紙の、女の子とかじゃ……ないですよね」
「え、手紙って……なんのこ……」
「…………あ、」
おばちゃんが男性に訊きかえすまえに、わたしは男性と目があってしまった。そう、緊張がピークに達してしまっていたわたしは、身体をおこしてしまったのだ。
元気そうですねと苦笑いした男性のうしろで、おばちゃんが苦虫を噛んだような顔をする。声にはださずともそのくちは、バカタレと動いていた。
「それでは、お母さん。……すこし長くなると思いますけど、あちらの部屋のほうにおねがいしましょうか」
「……あ、……はい」
大失敗におわってしまったのだと、うなだれるわたしをおいちゃんが笑う。「おしかったのぉ」なんてのん気な笑い声に、わたしは苦笑いすらもできなかった。
門のうちがわに移動されたタクシーは、そのまま隅により停車した。車のそばにはだれもおらず、気まずい空気にしたをむく。
「よい、朱里よう。……手紙っちゃ、なんか」
「え? ……ああ、矢野がな……」
それは、矢野の提案だった。面会のときの隼斗のようすをみて、わたしとの接点が彼のささえになるのではないか。
そう感じた矢野は、施設の職員にかけあった。規則としては許されないことではあるが、施設内での担任の協力によりそれが実現された。
もちろん内容はすべて職員が目をとおし、クリアしたものだけしか本人には渡らない。口外はかたく禁じられており、とうぜん隼斗の母親もしらない。
これは矢野とわたしと隼斗、そして極一部の施設職員しかしらないことだった。
そこまで職員が配慮をしてくれているのなら、今回のこともおおごとにはならないだろうというが、わたしは不安でしかたがない。
ここまで来ておきながら、帰省がとりけしなどになったらどうしよう。わたしの失敗で、隼斗を悲しませることになるかもしれない。
そんなことを思うと、申し訳なくて泣きそうになってしまう。おばちゃんの戻りをまつ時間が、あまりにも長すぎて気持ちがわるくなってきた。
第3章…03
帰省が決まったとしらされたその日から、どうにも気持ちが落ちつかなかった。昨夜にかぎっては、ほぼ一睡もできていないのではないかというくらいだ。
ここで待てといわれた部屋から、正門のようすがよくみえる。座っていろといいつけられてはいたが、じっと座ってなんていられるはずがない。
つくえのうえにかばんを座らせ、じぶんは何度も立ちあがり窓ぎわへいく。見知ったタクシーを視界にとらえ、おれは急いでかばんをかかえた。
前回の経験からすれば到着から呼びにくるまで、さほど時間はかからないはず。しかし正門のまえのタクシーは、なかなか中へ入ろうとはしなかった。
おかしい、まえとは違う。おれはかばんを抱えたまま、じっとタクシーをみつめていた。母親がくるまから降りるのがみえ、いよいよだと胸をはずませる。
「……なんしよんのじゃろ」
だれも居ない部屋で、おれは思わずひとりごちた。くるまをおりた母親は、その場から動こうとしないのだ。いや動こうとしないというよりは、うごけずにいるという印象だ。
車のなかを気にする職員のようすに、みょうに違和感をかんじる。いったいなにがあったのだろうか、だれかに問いたいが訊く相手がいない。
この数日のあいだに、おれはなにかやらかしてしまったか。思い返してみるも、心当たりなどはなかった。
母親がうごきをみせ、タクシーは正門のうちがわへと移動した。しかしこちらまでは入ってこずに、すぐのところに停車をしてしまう。
ひょっとして、帰省は取り消しになったのだろうか。原因となるものがみつからず、根拠のない不安だけがおしよせてくる。
扉をあけて、だれか職員をよんでみようか。不安はふくらみつづけ、檻のなかの動物のように室内をうろうろと動きまわった。
「おーい、久我。迎えがきたけん、荷物もっていくぞ」
「あ、はい!」
「なんか、おまえ。えらい張り切っちょんの」
「あ、いや……」
「うれしいんはわかるけんどの。……じゃけんど、ルールを守らんのはどうかと思うぞ。まあ、みんなの気持ちもわからんではないけどの……」
意味深なことばを吐きすてながら、職員はおれのまえを歩いていく。おれは何かルールをやぶるようなことを、してしまったのだろうか。
それを訊ねることはできず、また職員もふかくは話てくれなかった。もやもやとしながら後をついてあるき、母親の待つ部屋へとたどりついた。
おれの姿をみるなり、ババアはバツがわるそうな表情をした。一瞬ではあったが、おれはそれを見逃さなかった。職員になにか、言われたのだろうか。
もういちど思い返してみるが、やはり告げぐちされるようなやましい行動はしていない。職員の注意事項に、母親はおおげさにあいづちをうつ。
「それじゃ、行きましょうか」
「あ、はい。すみません……」
「……それでは、お母さん。くれぐれも注意して……久我、問題おこすなよ」
「はい、いってきます」
「家族と……、うん。ご家族と、ゆっくりな」
タクシーの手前で立ち止まった職員は、もういちど注意事項をくりかえした。ついいましがた部屋できいたばかり、それをなぜまたここで繰り返すのだろうか。
それを聞く母親の態度も、なんとなく気にかかる。まるで叱られている子供のように、すなおに返事をかえしているのだ。
最後の見送りのことばに引っかかりながら、おれはタクシーのほうへと振りかえった。そこにある光景をみて、一瞬だけ動きをとめてしまう。
なるほど、こういうことだったのか。姪っ子さんを病院につれていくらしいぞ、という含みのある職員のことばに母親は顔をゆがめる。
おそらく、いや確実にこれは職員にばれてしまったのだ。それでいてあえて、その設定を貫きとおしてくれているのだと感じた。
「それじゃ、先生……失礼します。隼斗なんしよん、はよ乗らんな」
「え、あ……ああ」
後部座席のドアをあけ、足もとに荷物をおいた。ぎこちなく横たわっている朱里のあたまを抱えあげ、そっとひざのうえに乗せて座る。
なんとなく恥ずかしくて、おれは職員の顔をみることができなくなった。ババアとジジイが頭をさげているところをみると、職員はこちらをみているのだろう。
ひざのうえの朱里のあたまが、緊張を物語っている。伏せるように下を向いている頬が、熱をおびているのが伝わってくる。
「……なあ、あたま……あげていい?」
「なんで? こんまましちょきゃいいやん」
「だって……」
くるまが動きだしたのを確認すると、朱里はあたまをあげようとした。おれはそんな彼女のあたまに手をそえた。
「ほんっと……。ばかたれのせいで、わたしゃ疲れたわ」
「なん、朱里がなんかやらかしたんな」
「病人役のくせに、元気に起きあがったんよ、こん子は。もうちっと辛抱しときゃいいもんを」
「まじか、朱里らしいやんな。……我慢、できんやったん?」
彼女の顔にかかった髪をすくい、覗き込んできいてみた。目があった朱里は、びくっとしたように耳まで真っ赤にして顔をかくす。
なにも答えない彼女のかおを、もういちど深くのぞきこんだ。これ以上はかおを背けられないとふんだのか、彼女は片手で顔をおおうように隠す。
照れている朱里をみて、どうしようもなく可愛いと感じてしまった。おもわず幼いこどもをあやすように、とんとんと肩をたたいてしまう。
ふと視線をかんじ、ルームミラーをみた。おれと目があったジジイは、にやりと笑って視線をそらす。見られていたということに、おれの顔は熱をもった。
「こら、あんたら起きんかえ! 着いたで」
「……んん、……なん」
「なんじゃねえが、着いたっていいよんのよ。はよ、降りんかよ」
かたまった身体をのばすようにして、そとの景色に目をやった。ついさっき施設をでたような気がしているが、タクシーは確かに団地のしたにいる。
おれの膝にはかわりなく、朱里のあたまが乗っている。肩をひいて覗いてみると、彼女は気持ちよさげに眠っていた。
声をかけるが反応はなく、おれは彼女の肩をゆする。ゆっくりと覚醒していく朱里のようすが、またなんとも子供のようでかわいかった。
荷物をかかえタクシーを降りると、彼女もふらふらとしながらついてくる。寝ぼけているようすの彼女をみて、おもわずくすりと笑ってしまった。
じぶんが笑われたのだと気づいた朱里は、照れくさそうにへらっと笑う。階段を踏み外されでもしたらおおごとだと、おれは彼女の手をとった。
「なんか、ノートがそうとう増えちょんな」
「ん? だって、毎日きちょんけな……。茅野も書きよんし、人数もふえたしな」
ふたりきりの部屋のなか、ふと気まずさを感じてしまう。ついさっきまで密着していた、そんな考えがおれに緊張をあたえた。
気をそらさなければと意識をちらすべく、部屋の落書帳に手をのばす。毎日のように通っているという彼女たちの日常が、このノートのなかにはぎっしりと記されていた。
おおくの落書のなかから、朱里の筆跡だけをぬきとって読んだ。どうやら彼女は、ちゃんと学校に通っているようだ。
「なん、この……オールドミスぶっ殺す……って」
「あ、それな! 通称オールドミスっちゅうババアがおんのよ。そいつに追いかけられてからさぁ……」
朱里はおれの質問に、ころころと表情ゆたかに答えてくれる。落書帳のかきこみに解説がくわわり、おれのなかの空白の彼女にどんどん色が添えられていく。
なによりも安心したのは、愚痴もあるにしたとしても、彼女の毎日が充実しているのだと感じたこと。しっかりと今に向きあっているんだ、そう感じることができたことだ。
そこに自分のすがたが無いことは、かなしくて悔しくもある。しかしそれは自分のまねいたことで、恨むならじぶんのあやまちだと承知している。
はやくここに戻りたい。おれも朱里の思い出のなかに、しっかりと姿かたちとして残りたい。強くそう感じながらページをめくり、どくっと心臓が跳ねあがる。
『隼斗に、会いたい。……by 久我朱里』
身体中の血液が、いっきに逆流をはじめた気がした。その熱いものがどこへいこうとしているのか、なにをしようとしているのかわからない。
とにかく身体のなかがさわがしくなり、あたまは真っ白になっているような感じがした。
おどけたように首をかしげ、手もとの落書帳をのぞこうとする彼女。「どしたん?」という朱里の問いにさえ、なにも返すことばがうかばなかった。
おれは喜びを声にして叫びたいのだろうか、それとも朱里を抱きしめたいのだろうか。そのどちらをすることもできず、ただ熱いこころでじっと彼女のことをみていた。
第3章…04
起きあがることは許されず、隼斗の膝枕でゆられる道中。緊張をさとられることが恥ずかしく、自由の残っている片手で顔をおおった。
隼斗の視線がじぶんにあることは感じてはいるが、じぶんの視界をさえぎることでなんとか気持ちをやりすごす。
多くはない会話と適度なゆれ。昨夜あまり眠れていなかったこともあり、徐々に意識はとおのいていった。
車のそれとは違うゆれに、意識がすこしずつ呼びもどされていく。肩にふれた誰かの感触と、聞こえてくる声がひとつになっていった。
「朱里、ついたで」
「……ん、……んん」
「起きれる? ……ほら、降りるで」
ぼんやりとした意識のなかでも、目覚めたそこが隼斗のひざのうえだということは理解できた。自分のなかの精一杯で、素早く身体をおこす。
着いた、降りる。隼斗のことばを、必死に理解しようと頭のなかでくりかえす。ふと気づくと、彼はすでに車からおりていた。
あとを追うように車から降り、彼の背中をおいかける。何度も振りかえる彼に、ちゃんと起きてるよという気持ちをこめて笑顔をかえした。
「ノートがそうとう増えちょんな」
「え、あ……うん。毎日きちょんけんな」
「そっか、毎日……」
「うん、それにな。最近は、石川とか増田とかな……人数もふえたけん」
こちらを見ていた隼斗は、ふっと微笑んで落書帳に視線をおとす。ページをめくるたびに、彼の表情もあたらしくなる。
いまどの落書きをみて、そんな顔になっているのだろうか。ころころと変わる彼の表情をみているだけで、わたしまで楽しくなってしまう。
これはどういう状況なのか、これは誰のことをいっているのか。隼斗のそんな質問が、わたしへの興味なんだとうれしく感じた。
もっと話したい、もっとわたしを知ってほしい。もっと喜ばせたい、もっと笑ってほしい。彼が問うてくる落書きのないようを、わたしは全力でつたえていく。
「あの、さあ……。ぶり返すつもりじゃねえけん、気をわるくせんじょってな」
「え、なん?」
「和泉んことなんやけど……」
「あ、あの……あれは……」
あの日の荒れたへやが、脳裏によみがえった。隼斗の視線は落書帳にむけられたままで、こころの内側がつかみづらい。
気をわるくするなと彼はいったが、気をわるくしているのは彼自身なのではないだろうか。心細さににたような、そんな不安がおそってくる。
おもしろくはないはずだ、腹がたって暴れてしまうのは当然のこと。あきらかにあれはわたしが悪かった、わたしの行動が軽率すぎた。
謝らなければ、そう思った。いちどは下をむいてしまったわたしだが、しっかりと顔をあげ隼斗をみた。
「……ごめんな」
「いや、おれのせいやけん」
「え? なんで……」
「おれが、こげんことになったけん。ちゃんと話もせんで、……行ってしまったけん」
なんの説明もなしに、とつぜん居なくなったじぶんが悪い。伝えたかった感情も、ことばにすることを戸惑った自分がいたという。正直なところ、いまでもじぶんの気持ちと闘っているとつづけた。
待っているという伝言をきいたとき、ほんとうに嬉しくてたまらなかった。それと同時に、じぶんなんかが待っていてほしいなどと思っていいのだろうかと不安になったとはなす。
かといって別れたくないという気持ちがつよく、だれにも取られたくないとも思ってしまうという。わたしの気持ちが和泉に向いてしまったらと思うと、暴れずにはいられなかったと情けなくわらった。
「和泉んことは、光羅兄が片付けてくれたけん、もう心配とかしちょらんけんな」
「……な、なんで知っちょんの」
「ん? 兄貴からきいたけん」
「あ、ああ……。そうなんや」
「おれな、光羅兄には感謝しかねえっちゃ……。こげんことになったに、切り捨てんで見ちょってくれて……申し訳ねえわ、まじで」
石川がいっていた疑問のことばが、ふっとわたしの脳裏によぎる。いったい光羅と隼斗のあいだには、どんな繋がりがあるのだろうか。
隼斗とのかかわりを反対していた兄が、一夜にして気持ちをかえた理由はなんなのだろうか。隼斗は感謝だというが、わたしには疑問でしかなかった。
じぶんだけが光羅から殴られていないと、得意気にあごを突きだす。複雑な気持ちで、わたしは苦笑いをかえした。
めくったページの一点をみつめ、ふいに隼斗の動きがとまった。落書きの状況を問うてくることもなく、ただずっと同じところをみている。
訊くことすらも忘れるほどの、そんな意味不明な落書きをしただろうか。気になったわたしは、そばへ寄り手もとのノートを覗きこんだ。
そこにある落書に焦ったわたしは、おもわずノートをうばいとる。はっとしたように手をのばす隼斗に、渡してなるかと背中にかくした。
「…………く、が……あ」
「なんな、うるさい。ほかのノート見よ」
「え、なんでな。いまの……もいっかい見せてよ」
「いやだ! ほかの見よな、なんぼでもノートあるやん」
正面からのばされた彼の手が、わたしの背中にあるノートに触れる。なかば取り返されることを覚悟したわたしは、それ以上の抵抗はしなかった。
近すぎる隼斗と、わたしの視線がぶつかった。なにを言われたわけでもないのに、動くことができなくなる。
なにかを言いたそうな顔をしては、そのことばは音とならず呑みこまれている。うばう気ならばたやすく奪えるはずのノートも、いまだわたしの手のなかにある。
どうしたのだと問うことは簡単だが、なぜかそれをくちにできなかった。なんとなく、なんとなくだけれど喋ってはいけない、そんな気がしてしまう。
「……はじめて、……なんでな?」
なにが、起きたのだろうか。隼斗の声に我に返ったわたしは、じぶんが畳のうえに倒れていることを知った。くちびるに残っている、やわらかく温かい感触。
首のうしろにまわされた彼のうでと、異常なほどにちかい彼のかお。冷静さと大騒ぎが、わたしのなかでせめぎあう。それはどさくさのなかの、わたしのファーストキスだった。
隼斗の問いにこたえるべく、瞳だけを彼にむけた。こくりと小さくうなづけば、かれは微かに笑みをうかべる。
ふたたび触れようとするくちびるに、おもわず胸をおしてしまった。あまりにも意識がはっきりとしすぎていて、戸惑いをかくすことができずにいる。
「……嫌だ?」
「そ、そういうんじゃ……なくて……」
そう、嫌とかそんなことではない。隼斗のくちびるが触れた瞬間、わたしは息をとめてしまう。緊張をしているいまの状態では、無呼吸がどこまで続くか不安になった。
正直、キスに集中なんてできない。温かい、やわらかい、どうしよう苦しくなってきた。けれどくちは塞がれている、鼻で息なんてとんでもない。
くちびるが緩んだそのとき、口内にじぶんのものではない温もりをかんじた。逃がせば追いかけてくる熱いものを意識してしまい、じぶんの体温もあがっていく。
「……大丈夫?」
「う、うん……」
「嫌じゃ、……ねえ?」
「うん……」
そう問う隼斗のくちびるは、頬をよせわたしの耳元にあった。シャツを掴んでいる手に、ぎゅっと力がはいってしまう。
まわされている彼のうでにも、こころなしか力が加わった気がした。隼斗の存在を、重みとして身体でかんじる。
みたび重なったくちびる、追いかけてくる舌が荒くなり、抱きしめる彼のうでの力はさらにつよくなっていく。もしもこのまま死ぬとしても、それならそれでかまわない。
どうなってもいい、このひととこのまま一緒ならば。身体のちからが抜けていく、すべてこのひとに任せようと思った。この感覚が、幸せというものなのだろうか。
「……で、こいつら何しよんのじゃろうか」
突然のこえに、わたしたちは飛び起きた。その速さときたら、現役のアスリート並みだと感じる。素早くおきあがったわたしたちは、すでに正座をしていた。
みれば北斗は部屋のなかにおり、腕をくんだ状態で壁に背をたくしている。どうみても、いましがた来たばかりとは思えない。
言いあらわしようのない気まずさと、恥ずかしさがこみあげてくる。北斗のことを直視できず、わたしはずっと下をむいていた。
「いや、……これは……その」
「うんうん、わかるよ、わかる。おれも男やし、わかりはするよ」
「そ、そげなんじゃねえし。……ばかやん」
「そげなんじゃろうが、いまのは絶対に。じゃけんど、おまえあれやぞ、さすがにそれ以上はやめちょけよ。……椎名、ぶち切れるけんの」
ばつがわるそうに視線をそらした隼斗は、真っ赤な顔をしている。さりげなくちらりと北斗の様子をみれば、彼はにやにやと笑っていた。
ガキのくせに色気だけは一人前だと茶化す北斗に、隼斗は「うるせえ!」といって背をむけた。
第3章…05
この夏の帰省期間は、五日間だときいている。初日こそ隼斗とふたりきりだったが、翌日からは茅野たちもあつまっていた。
石川たちの好奇心は、ようしゃなく隼斗にむけられていた。しかし嫌みな感じはみうけられず、隼斗自身もそう受けとめるようすはない。
やはりみんなが思うのは、施設というだけあり閉鎖的なのではないかというところだった。そんな感じではないという隼斗の言葉に、皐月はわたしの顔をみる。
そう、わたしが迎えに同行したということを、翌日ここに来るときにはなしたからだ。その目はほんとうにそんな雰囲気ではなかったのか、と問うている。
正直なところ、あの日のわたしはテンパっていた。じっくりと建物を観察するよゆうなど、あの状況であるわけがない。それでもなんとなくは感じることができた。
たしかにへんな威圧感はなく、ふつうの学校とあまり変わらないようにみえた。隼斗のいうとおりだと、わたしは皐月にうなづいてみせる。
「……そんでな、面倒くせえんが、あさのランニングなんよ」
「は? なん、……はしるん?」
「そうっちゃ。施設をでてな、川沿いのみち走って丘をこえて、畑だらけの田舎はしって……とにかく、なげえんじゃが」
「外、走るん? え、うそやろ。職員とか、がっちがちに囲んで?」
「いんや、職員とか数人しかおらんので」
「うそや……、ゆるくね?」
そんな状態ならば、逃走するのはたやすいのではないかと増田がくちにする。そのことばを聞いた瞬間、わたしたち三人は顔をひきつらせた。
そうなのだ、ゆるいのだ。施設側としては、なにか考えがあってのことかもしれない。しかしそのゆるさゆえに、隼斗は二学年もそこで過ごすことになってしまったのだ。
隼斗にしてみても、そこは触れたくはない場面であろう。きっと動揺してしまうにちがいないと、不安におもい目をそむけた。
「そうっちゃ、簡単に列からはみだせるんやが」
「そうでな、逃げれるでな」
「じゃけんど、どうせ戻ることになるんやし。やるだけ損っちゃ」
「え、そんなもん? うまく逃げ切ることってできんもんなんかや」
「ばかやん、ずっと逃亡生活するわけにゃいかんじゃろうもん。地元にかえりゃすぐに見つかるし……時間の無駄よ」
たしかに冷静な判断だと、石川たちはうなづいた。たったいちどの気のまよいで、入園期間が延長になるのはばからしい。
そうくちにした隼斗のかおは、すこしだけ後悔をしているようにみえた。このいちねんの間に彼は、なんだかおとなになったように感じる。
なにも知らない石川たちは、ちゃかすように拍手をしてみせる。事情をしっているわたしたちは、ほんのちょっぴり胸が痛んだ。
「あ、そうそう。おれな、最初は小学校の勉強からやらされたんじゃが」
「なんか、それ。え、なに……ばかにされちょんの?」
「ばかにされたっちゅうか、おれがバカやったみたいやで」
入園してすぐにおこなわれたのは、簡単な学力テストだったらしい。結果、小学校高学年の勉強から、復習授業をうけることになったそうだ。
小学校のころからまともに学校には行っていなかったせいだと隼斗は苦笑った。それならばまともに行っていたにもかかわらずのわたしは、どうすればいいのだろうか。
ふいに視線があった皐月や茅野たち。彼女たちもわたしと同じように、にがい笑みをうかべている。
「なあ、勉強ってどんなとこでするん」
「学校でするに、決まっちょんやん」
「え、学校って……近くの?」
「近く? ……ああ、そとの学校じゃねえよ。おなじ敷地にあるんで」
「そうなんや? え、それってどんなん? 普通の学校みたいなかんじなん?」
石川の質問に、わたしは疑問をいだく。ふつうの学校ではない学校とは、いったいどんなものが頭にうかんでいるのだろうか。
隼斗も質問の意味が理解できなかったようすで、すぐには返事をしなかった。しかしそう時間はかからずに、彼のくちから女もいるとつげられる。
なぜかその返答をきいた瞬間、胸のあたりがずきっと痛くかんじた。そうだ更生すべき生徒が男だけとはかぎらないのだ。このときはじめて、そのことに気がついた。
ここまでのわたしは隼斗が施設にいってしまった、離ればなれになってしまった、そのことばかりでいっぱいだった。
彼のくちから異性の存在を聞かされ、えたいの知れないもやもやがわきおこる。そんなわたしとは裏腹に、おとこ三人は瞳をかがやかせ身体をのりだした。
ちらっとこちらを気にする隼斗。そんな彼のしぐさに、茅野たちもこちらをみた。へんなプライドがはたらいて、わたしは素っ気なくあごをつきだす。
「授業はな、ふつうに共学で教室もいっしょなんで」
「え、え、そんならさ。……生活、するとこは?」
「生活……、ああ。寮で生活すんのじゃけんど、さすがにそれは別々で」
「……なーんか、べつなんか」
「あたりまえやん。けどな、行き来するんは意外と簡単なんじゃが」
興味などないふりをしながらも、わたしの耳はダンボになっていた。共学と聞きちょっぴりおちこみ、寮がべつと聞いてほっとして、行き来ができると知りどきっとする。
なんだかとても、わたしの心がいそがしい。そんなわたしとは真逆の反応をしている三人は、行き来できるという情報にとびついた。
部屋はひとり部屋なのか、女子はなにをしにくるのか。ひとり部屋など贅沢なわけがないと笑い、女子は彼氏に会いにくると隼斗はこたえる。
「じゃけんな、最悪よ。目ぇあけちょか見えてしまうし、寝たふりしちょってん聞こえてしまうしな」
「……やば」
「やべえどころん話じゃねえっちゃ。地獄やが、じごく」
隼斗の同室のおとこは、園内の女子と恋愛をしているらしい。男子寮よりも女子寮のほうが抜け出しやすいためか、おんなが来ることのほうが多いのだという。
ふたりは自分がいようが居まいがおかまいなしで、性行為を繰り返しているのだと話す。隼斗のはなしを、三人は前のめりで聞いていた。
わたしと皐月はいたたまれなくなり、近くにあった落書帳を手にとり顔のまえでひろげた。
「え、え、声とかでるじゃろ! みつからんの」
「んん、俺が入園してからは……まだ、だれも見つかっちょらんみたいやけど」
「見つかったら、どげえなるんじゃろうか」
おなじ空間に異性がいると知っただけでも不安なうえに、たやすく接触ができるという事実。会えない彼女よりも、会える異性のほうが強いのではないだろうか。
もしかしたら素敵な女の子がいるかもしれない、そうすれば隼斗の気持ちも向くかもしれない。つなぎとめておけるだけの自信が、わたしには無い。
「な、なあ……。つぎってさ、いつ帰ってこれるん」
「ん? ……多分、正月じゃねえかや」
ふあんを掻き消すごとく、はなしをさえぎり隼斗に問うてみた。かえってくる答えなど、はじめからわかっていた。この話題からはなれたい、ただそれだけのことだった。
あらためて訊ねてのしかかる、四ヶ月という月日のながさ。話題をかき消してもなお、わたしのなかの不安はきえることはなかった。
興味深いはなしを中断された石川たちの、やるせない視線がようしゃなくふりそそがれる。
「え、なん……。いじけちょんの?」
「は? なんそれ、いじけちょらんし!」
「えー、ほんとうかや。寂しゅうてたまらんって、思っちょんのじゃねんな」
「ばかやん、そんな四ヶ月くらい……」
よどみそうになった空気を、隼斗のおどけた声がかきちらす。「なげえな……」と言葉をそえたのは、意外にも石川だった。
それこそ四ヶ月なんてあっという間だと、隼斗は口角をあげてみせる。しかしその瞳が笑っていないことに、ここにいるだれもが気づいていた。
「よう、久我。あした、何時なん」
「ん? ここ出る時間のこと?」
「うん、明日かえるんじゃろ。みんなで見送りするけん」
「まだ決まっちょらんのやけど。……やめてや、見送りとか」
明日、隼斗は学園にかえってしまう。つぎに会えるのは、四ヶ月後。ほんのすこしの時間でも、ともに過ごしたいという茅野の想い。
隼斗は、まだ時間はきめていないと答えた。しかしそうくちにしたときの彼の瞳は、この場にいるだれのこともとらえていなかった。
きっと嘘だ、ほんとうは出発のじかんはきまっている。そう感じたのは、わたしだけではなかった。
うそを言うなと問い詰める茅野に、隼斗はちからなく笑ってみせる。しかしそのくちは、けっして時刻をつげようとはしない。
「なんか久我-、おしえれの。またいっとき会えんなんのじゃけん、見送りぐらいさせれの」
「……じゃけん、嫌なんっちゃ」
しばらく会えなくなる、さみしくなる。そんな彼らのことばに、隼斗の表情がくもった。三人とまともに視線をあわそうとしない。
ふいにこちらを見た隼斗の視線と、わたしの視線がぶつかった。ふにゃっとした笑みをみせた彼のひとみは、こころなしかうるんでいるようにおもえた。
第3章…06
かじかむ手をこすりながら、じっとまがり角をにらみすえていた。どんなに太陽ががんばってくれても、吹きぬける風にくじけてしまいそうだ。
おもわずその場にしゃがみこみ、ひざごとじぶんを抱きしめる。団地の階段へと逃げこんだならば、この寒さもすこしはしのげるかもしれない。
しかしそうしてしまったら、その到着に気づくのが遅れてしまう。一秒でもはやくタクシーに気づき、隼斗の姿をこの目にとらえたい。
いまか今かと、はやる気持ち。道行く関係のないくるまのエンジン音が、じゃまになって仕方がない。
「来た!」
あまりにも待ち焦がれすぎ、おもわず声にだしてしまう。しかし、なにも恥ずかしいことなんてない。なぜならわたしには他のなにも、そしてだれのことも見えてはいないのだから。
角をまがってきたタクシーは、ゆるやかに焦らすようにすべりこんでくる。そわそわと身体を上下にゆらすわたしを、まるで面白がっているかのように。
まさかそんなことがあるわけがない、くるまに意思などあるはずもない。ひかりの加減でみえた、おいちゃんの顔。あきらかに面白がっているかのような、わるい笑みをうかべていた。
「なーんな、朱里。もう来ちょったんな! あんた、誰にも言うちょらんじゃろうね」
「ああ、言ってねえいってねえ」
「なんかね、その適当な返事は……」
「いいけん、おばちゃん……隼斗は!」
「んまぁ……腹たつこじゃな」
さきに降りてきた隼斗の母親と、ろくに視線もあわさずに返答をした。図太くなったなと笑うおいちゃんの姿すら、まともに視界にはいれていない。
けたけたと笑いながら、後部座席から隼斗がおりてきた。その手にある荷物を受け取ろうとしたが、すばやくそれはうしろに退かれた。
「バカみたいに、にやにやと笑いおうちょらんで、さっさと家にはいりよや」
「うるせーな、くそババア。わかっちょんわ」
「うるせえじゃねえわ、ひとめについたら品がわりいじゃろうがね。面倒なことになったら、どげえすんのな」
ふたりをおろしたタクシーは、ゆっくりと駐車場へといどうした。尻からおわれるようにしながら、わたしたちは階段をのぼっていく。
ごめんなと謝る隼斗に、微笑んでくびをふる。いまが大切な時期、それはわたしでも理解ができている。この帰省で問題をおこすわけにはいかない。
こんかいは誰のことも呼ぶなと、おばちゃんは真剣なかおでいう。もうこれ以上の面倒はこりごりだ、と眉間にしわをよせた。
あとから追いついてきたおいちゃんが、そんなに小言をいうなと笑った。いいかげん隼斗もわかっている、いや誰よりも本人がわかっているという。
「わりいな、ババア……なんか、苛々しちょって」
「いいや、仕方ねえっちゃ。大事なときなんじゃろ?」
「んん、まあな……」
「むこう、……いつ帰るん」
「あさって、……たぶん午前中には、こっち出るとおもう」
いくら大切な時期だとはいえ、ふつかほどの滞在とは短すぎる。神経質になっているのは、隼斗の母親だけではない。
関わるすべてのひとがぴりぴりしているし、とうぜん隼斗ほんにんも気を張っている。すべてがこの三学期にかかっているからなのだ。
四ヶ月ぶりの帰省なのだ、ほんとうなら彼もみんなに会いたいだろう。しかしいつもより慎重にならざるを得ない今だから、あえて誰にも連絡はしなかった。
「あ、そうや。てがみ、ありがとな」
「うん、けどさ……あれって、ほんとうに施設のひとが読みよんの」
「そうっちゃ、あれまじで読みよんので。いっつも封筒が開いとるけんな。恥ずかしいんじゃけんど、あれがあるけん頑張ろうっておもえるけんな」
「恥ずかしいって……、それこっちのセリフやけんな」
手紙をわたされるとき、だいたいは職員からひやかされるという。そんな原因になるような内容は、いくらわたしでも書きはしない。応援とはげまし、それだけを意識して書いている。
あまりにも気をつかいすぎて書くものだから、まいかいそれほど変わりばえのない内容になりがちだ。しかし職員は健気だといって、隼斗をちゃかしてくるのだという。
あらためて言われると、どうにも照れてむずがゆい。しかし矢野からの報告で彼の頑張りをきいていたわたしは、それが自分のおかげだと言われることが嬉しくもある。
「なあ、こっちに帰ったらさ。矢野のクラスって決まっちょるって本当なん?」
「ん? うん、施設に行ったときの担任のままじゃって聞いたで」
「そうなんや……。矢野か……」
「なんな、どしたん」
「いや、矢野ってちょっとだけ、うざくね? けど、同じクラスになれるんなら……」
「え、おれは嫌やけん」
わたしなりに思い描いていた、あこがれの場面。それは最初は屋上から、少しずつと考えていたことだった。しかしそれは叶わず、遠くはなれてしまうこととなった。
会えないことに耐えぬいた、そしてめぐってきたこのチャンス。おなじときを過ごすことができるかもしれない。もしもおなじ教室になれたならば、どんなに楽しいだろうか。
そんなありきたりな恋の願望は、隼斗のひとことで打ち砕かれた。彼はわたしが近くにいることを、そこまで望んではいないのだろうか。
「なんで、嫌とかいうんな……」
壁にもたれた、たがいの背中。かすかに触れる肩のぬくもりすら、心もとなくうつむいた。やばい泣きそうだと思ったとき、隼斗の腕がぴくりとうごいた。
「だって、……はずかしいじゃん」
そうくちにした隼斗の表情は、ほんの一瞬しかこの瞳にとらえられなかった。近すぎる顔と、ふれあったくちびる。そのまま畳のうえに倒れこんでしまう。
慣れてはいないくちづけなのに、腕は自然とたがいを抱きしめあっていく。のしかかってくる隼斗の重みが、とても心地よくこのまま居たいと感じる。
ふいにはなされた彼のくちびるが、わたしと頬をよせ耳元でなまえを呼んだ。ことばなのか吐息なのか、はっきりとしない音にどきっとする。
これはひょっとすると、そういうことなのかもしれない。たよりない思考のなかで感じたとき、彼の身体の変化に気づいてしまった。
「……ごめん。……ごめんな、すこしだけ……こんまま。……ほんと、ごめん」
そうつぶやく隼斗の身体は、こころなしか震えているようにかんじる。ときおり呼吸をとめては、おおきく息をすって吐く。
わたしは動いてはいけない、なんとなくそう感じた。なのに強く抱きしめてしまう。そのたびに隼斗は苦しそうに、まわしている腕にちからを込めていた。
「あ、……ごめん」
「いや、朱里は……なんも。……ごめん」
「あんたら、ごめんごめん言うちょらんで、さっさと離れんかよ!」
はなれるタイミングを失っていたわたしたちは、隼斗の母親の一喝でとびおきた。「隼斗!」というみじかい母の叫びに、「わかっちょる!」とかえす。
苛立ちにも気まずさにもみてとれる表情で、隼斗はおばちゃんに背をむけあぐらをくんだ。あいだにいるわたしは何もできず、畳のめをみつめていた。
「朱里……ちょっと話があるけん、あっちの部屋についてきよ」
「……え、はなし」
そのことばに反応した隼斗は、すこしだけ母親を視界にいれ舌打ちをする。
「ババア! 朱里に、いらんこと言うな! ……俺だって、考えちょんのじゃけん。朱里、行かんでいいで」
「しゃーしい! あんたの考えなんか、あてになるもんかよ! ほら、はよ立って……こっちきなさいって」
行くなと来いで、わたしの両腕はふさがっていた。この場合、わたしはどちらの言うことをきくべきなのだろうか。にらみあった親子のあいだで、なすすべなく途方にくれる。
どうあっても母親はひきさがるつもりはないようで、対する隼斗もまったく怯んだようすは見せてはいない。
なんとなく隼斗の母親のいいつけを、無下にするわけにはいかないと思ってしまう。立ちあがってしまったわたしをみて、彼はしぶい顔をしてさらに母親をにらむ。
なんども振りかえり彼をみたが、そのひとみは最後までおばちゃんを睨みすえていた。
「朱里、あんたな……。あげなバカタレ……いや、あん子じゃねえでもじゃけんど。いいか、あのな……男に、ながされたらいけんで」
「流される……って……」
「いいか、よう聞きなさいよ。おとこっちゅうんはな、やりてえが先にたつ、単純ないきもんなんじゃけんな」
「……え、」
「簡単に、じぶんを差し出したらいけんので。損するんは、おんなのほうなんじゃけんな」
「損するって、……なんで?」
「そげなんは、いま知らんでもいいけん。とにかく、じぶんのことは自分でまもらないけん。だいじにせんといけんので……わかったか?」
正直なところ、わからなかった。差しだすの意味することは、いくらわたしでも理解はできた。そうなる段階のなかに、お互いをもとめる気持ちがあること。
それを否定するかのような、おばちゃんの最初の発言がわからない。損をする、そのことばの意味もわからない。好きあってそうなることに生じる、損という概念がおもいうかばない。
はじめてだから、そういうことなのだろうか。最初のひとは慎重に、おばちゃんはそう言いたいのだろうか。至ってまじめな表情の母親にむかい、そんな質問はなげられるはずもない。
あたまのなかをぐるぐると駆けめぐる疑問をさとったのか、おばちゃんは呆れたように肩をおとした。「こん、ばか娘が……」そういいながら、わたしの頭をかるく平手でたたく。
第3章…07
何ヶ月かのときをかけ、施設や児童相談所などとのやりとりが交わされていたはず。桃の節句とかいうものもおわり、そろそろ俺の今後がみえていてもおかしくはない。
検討の材料となる、ここでの生活や帰省時でのたいど。俺はじゅうぶんに気をつけて、不利になるような軽率な行動はおこしてはいない。
今後の交友関係の把握や、受け入れがわの学校の態勢。それは俺があがいたところで、どうにもできることではない。ただひたすら、問題がないことを祈るしかない。
「なあ、おまえってさ。なんで、そげえ帰りてえとかって思うんな」
「なんでって……。おまえは、帰りてえとか思わんの?」
消灯になった部屋のなか、もぐりこんだ布団のなかから男が問うてきた。たがいの顔などみることなく、気のない会話がつづいた。
めだった楽しみもないかわりに、それほどの不自由も感じないだろうと男はいう。たしかに慣れてしまえば、ここでの生活もそんなにつらいものではない。
あらためて考えさせられる問いだ、なんとなくそう感じた。もしも朱里と知り合うまえに、ここに来るようなことになっていたならば。
すでに付き合いを絶っている、過去のなかまをおもいうかべる。たしかにあの頃は、あれで楽しかった。しかしいまの俺に、なっていただろうか。
おそらく頑張るなどという考えにはいたらず、帰省のたびに楽しさにかまけて問題をおこしていただろう。
「おまえってさ、……地元に大切なやつとか、そんなんっておらんわけ?」
「なん、大切って。……あれか、彼女とかそんなんのことか」
「んん、まあ。そんな感じかや」
「めんどくせえやん、そんなん。女とか、ちょっと格好いいおとこに告られたら、簡単に乗りかえるし……彼女とかつくらんが楽じゃが」
「そうかやぁ……」
例の彼女とはうまくいっているのか、と男が問う。いろいろとすれ違いはおおかった、けっして好ましいとは言えない遠距離の関係。
じゆうに会うことは叶わないが、じぶんの心のささえになっていることは確かだ。だまって待ってくれている彼女のもとへ、いちにちでも早くもどりたい。
「ふーん……」と、素っ気なくかえされたことば。しかし最後に消え入るような声で、「……すげぇな」とつぶやいた男のこえを、おれは聞きのがしてはいない。
おそらくこいつは、地元に彼女がいたのだろう。そして望んでいたのとは異なるほうこうに、ことは進んでしまったのだろう。
ここでの男の恋愛事情、それもしっかりと定まってはいなかった。この一年半ほどのあいだに、こいつは数人と関係をもっている。
とっかえひっかえとまではいかないが、相手にのめり込むようすも見せてはいなかった。向かいのベッドに横たわるおとこは、その後なにもはなすことなく静かに闇にとけていった。
「おーい、久我。登校のまえに、ちょっと話があるけん。朝食すませたら部屋によってくれ」
「……あ、はい」
朝のランニングからかえり、正門をぬけたところで声をかけられた。声をかけてきた職員の表情は無、そこからは内容の想像は難しい。
寮にもどり朝食へ向かうも、それが気になって食べた気がしない。あごを動かす回数だけ、過去のおこないをふりかえる。思いあたるふしがない、なんのはなしなのだろうか。
「失礼します、久我です! 入ってもよろしいでしょうか」
「おお、来たか。はいりなさい。……かたいな」
職員からのよびだしで、ろくな話をされるやつはいない。そうおもい身構えているのだろうと、職員はふくむように笑う。あたっているだけに、反応にこまってしまう。
扉のまえで直立するおれに、職員は手招きをした。いっぽまえに出たおれに、もっと近寄れとふたたび手をまねく。
この春、地元復帰のせんがつよまった。担任と親御さんには、このあと連絡をいれておく。のこりの期間さらに気をひきしめ、これまでどおり頑張りなさい。
「……久我? 聞きよるんか」
「え、あ、はい。……え、帰れる……ん、ですか?」
ずっと聞きたかった、地元復帰のことば。ずっとずっと願い頑張ってきた、そのことだけを心のささえに。聞こえているのに、あたまがついていけない。
実感がわかないとは、こういうことを言うのだろうか。職員のへやをでて、自室にもどる。荷物をかかえて、学校へとむかう。いつものように過ごしながら、ゆっくりとよろこびを感じていく。
数日がたち、矢野が面会へとやってきた。いつだって病弱そうにみえる矢野のかおが、きょうはやけに血色よくかんじる。
「久我! がんばった、えらい! よく頑張った」
「なあ、……朱里は知っちょんの」
「いや、……まだ」
施設のほうから、口外はかたく禁じられているという。しらせてあげれば、どんなに彼女がよろこぶだろう。おそらく泣いてよろこぶに決まっていると、矢野は目尻をさげた。
つたえたい、伝えてあげたい。待ち遠しい、その日がくるのが待ち遠しくてたまらない。
めがねの奥のそのひとみに、なみだをいっぱいに溜めていう。そんな矢野のすがたをみて、やっとおれは実感という感覚をしる。
「久我ってさ、……退園、きまったんじゃろ」
「は? なんで……」
矢野との面会をおえ、おれは自室にもどった。ベッドにくつろいでいた男は、こちらを見ないままにそういった。なぜ気づかれてしまったのだろうか。
おとこに言わせれば、おれはわかりやすいという。ここ数日のおれのようすにも違和感はあったが、今日の面会の人物のようすで確信したというのだ。
「あれやんな、その待っちょるっちゅう彼女? よろこぶじゃろうな」
「……あ、ああ」
「なん? いまさら隠さんでいいで。あれじゃ、……よかったやん」
「んん、……なんか。……ありがと」
気のないそぶりではあるが、なんだかうれしく感じてしまった。あまり馬が合っていたとはいえない男だが、いざこうして別れるとおもうと寂しくもかんじる。
会話がなくなり静まり返ったとき、部屋のまどがノックされた。おれは窓をあけにはいかない。なぜならその音は、おとこの彼女がきたという合図だからだ。
しかしそこに見えたのは彼女ではなく、そのともだちのすがただった。そのおんなから伝言をうけたおとこは、なにも言わずにその窓からでていった。
めずらしいこともあるものだ、男のほうから出向いていくなんて。ひょっとしたらあいつは、いまの彼女には本気になっているのではないだろうか。
「久我、緊急のようじだ。……いますぐ、職員室にこい」
午前の授業がおわったタイミングで、職員からのよびだしを受けた。放送でいえばいいものを、わざわざ教室までやってきた職員。
その表情は穏やかではなく、よき話ではないことは予想できる。しかし心当たりのようなものはなく、ただ言われるままに教室をでた。
職員室のおく、応接スペースに誘導される。間仕切りの壁をこえたところに、ふたりの人物のすがたをとらえた。なぜここにこいつが居るのだろうか。
そこにあるソファーに浅くこしかけていたのは、おなじ部屋のおとこと付きあっている女だった。そしてそのよこに渋い表情ですわる、女子寮の職員のすがたがあった。
「久我。そこに座りなさい」
「え? ……あ、はい」
すわるようにと示されたのは、おんなの真向かいになるソファーだった。正面にすわろうとしている俺のことを、ただのいちども見ようとしない彼女。
おれがここへ呼ばれてきたことに、なんの不思議もかんじないのだろうか。まるで俺がくることを知っていたかのように、不自然なほどにこちらをみない。
そしてこわいくらいに俺をみている、彼女のよこの職員もきになる。その瞳はなにかを言いたげでもあり、あきれているようにも感じられる。
着席をかくにんした職員は、ひとつおおきな咳ばらいをした。そしてつぎにくちにしたのは、彼女の妊娠というしらせだった。なぜそんな話を、この俺にしてくるのだろう。
そんな疑問をぶつけようと、かおをあげた瞬間だった。おれは、自分の耳をうたがってしまう。
「なあ、久我。あいては、……おまえらしいの」
「…………は? ……え、ちょっと待って。……こいつって、おなじ部屋……」
「なんでな! なんでそんなこと言うんな! 退園がきまったけんって、……わたしのことなんか……」
おれの話は、おんなによってさえぎられた。なんとかして続きをはなそうとするが、そのたびに女はおおごえをだし遮ってくる。
ここはどうあっても真実をつたえなければ、そう思ったおれはことばを止めずに言い切った。おれではない、おなじ部屋のおとこの彼女だ。
どんなに訴えても、職員はしぶい顔のままなにもいわない。おそらくおんなも必死なのだろう、しまいには泣きだしてしまう。久我くんに裏切られた、泣きながらそういいつづける。
おれと彼女の逢瀬を黙認していたと、同室のおとこが職員にいったらしい。
あのとき、そう女のともだちが呼びにきたときだ。退園をいわってくれた、それは俺の平和な勘違いだった。おれはめでたく裏切られた、もうどう足掻いてもむだだろう。
「とりあえず、地元のはなしは……」
「ああ、……もう……いいです」
「親御さんには、連絡をしとくけん……」
「あ、矢野……。担任には……まだ、言わないでください」
ざんねんだとか、くやしいだとか、もうそんな感情すら失っていた。あたまに浮かぶことば、それは二文字。絶望、ただそれだけだった。
すぐそこに見えていた、さくら色の希望という文字。たった一夜にして散り落ちた、はかなすぎる夢の花だった。
朱里とのやくそく、それはもう果たすことはできないだろう。せめて最後のいちねんだけでも、朱里の願いをかなえてあげたかった。
第3章…08
隼斗の今後について、めだった情報のないまま三学期がおわる。この三ヶ月間は、とくに意識してはげましの言葉だけを手紙でつたえていた。
矢野は、最低でも月に二回は面会にいっていたはず。それでも持ち帰ってくる情報といえば、施設でどのように頑張っているかの報告だけ。
「おーい、おい椎名! ちょっとまて、椎名、椎名、しいな!」
「……うるさ。……なに、そげえ何回もよばんでも聞こえちょん」
くつばこの手前で足をとめ、声のほうをふりかえる。体育の教師のくせに息をきらし走る、矢野のすがたをとらえた。
ひざに手をつき、「間に合った……」と肩をゆらす。間に合うだろうとも、なぜならわたしは止まっている。よほど全力ではしったのだろうか、呼吸はととのわず右手だけが焦っている。
おそらくその右手のしぐさは、ちょっと待ってくれと言いたいのだろう。そうこうしている間に、皐月がくつばこへやってきた。
「……なんしよんの」
「……さあ?」
わたしと矢野のすがたを見て、不思議におもうのは皐月だけではない。やってくる生徒のほとんどが、わたしたちをみては首を傾げてさっていく。
それでなくとも荷物のおおい学年おわり。せまいくつばこスペースで、わたしたちはじゃまな障害物でしかない。それに気づいたか、矢野がいどうをはじめた。
ついてこいと手招きをされ、廊下のすみへとついていく。すこし息がととのったのだろうか、身体をまっすぐにおこした矢野。
やっとのことで用件がきけるそう思ったつぎの瞬間、矢野がうれしそうに破顔した。
「え、なに……。きもちわりいんやけど」
「なんが気持ちわりいか。あんの、あんの椎名。……帰ってくるんよ!」
「……なにが」
「なにがじゃねえ、久我よ! 四月から、この学校に通うことになったんよ!」
矢野のこえは聞こえている、そのことばの意味もりかいできる。なのに気持ちがおいつかない。脳からの指令が、おりてこない。
反応のわるいわたしをみて、矢野は眉をひそめた。「どうしたんか、椎名」、自分がどうなっているのかわからない。
「嬉しくねえんか」、うれしいに決まっている。帰ってくるのだ、一緒にここに通うのだ。矢野はわたしの肩をつかみ、はげしく前後にゆさぶった。
「……え、施設。……でるって、こと……なんでな」
「そうよ! 施設をでて、この学校にかえってくるんよ!」
ぼうっとしているわたしの腕を、皐月がつかんでひっぱる。うるんだ瞳の彼女は、わたしに何度もうなづいてみせた。
かえってくる、隼斗がかえってくる。皐月に抱きつき、ひとめも気にせずおおごえで泣いた。
施設からのくちどめで、教えてあげられなかったと矢野がいう。明日からは春休み、もうわたしに教えてもいいだろうと判断したと。
みれば矢野のめには、涙があふれそうになっている。おれは久我の担任だうらやましいだろうと、すこし意地悪な笑みをみせた。
「おばちゃーん! おばちゃん、おばちゃん。いつ迎えにいくん!」
「な、なんか……朱里。なにをそげえ興奮しちょんのな」
「隼斗よ! 帰ってくるんじゃろ、いつなん? いつ迎えにいくんな」
かぎが開いていることをしっているわたしは、いきおいよく玄関のとびらをあけた。おおごえで叫びながら、雑にくつを脱ぎすておくの部屋へとかけこんだ。
「おいちゃんのタクシー? おばちゃんしか行かれんの? いついくん? なあ、いつ迎えにいくんな」
「ちょ、ちょっと朱里……とりあえず、いっかい落ちつきよ。あんた、隼斗がかえるって、だれから聞いたんな」
ここにくる直前に、学校で矢野から聞いたとはなす。それをきいた隼斗の母親は、わかりやすく困惑のかおをした。
ふと施設からのくちどめのことを思い出し、明日から春休みだから問題ないとつけくわえた。心配しているようなことにならないよう、わたしも決して口外はしないと誓う。
おばちゃんは困ったかおをして、わたしの腕をゆっくりとつかむ。そのうでをそっと自分にひきよせ、そのまま畳へとしゃがみこむ。
向かい合ったおばちゃんのうしろに、おいちゃんの姿がみえた。いつだってわたしをみると微笑んでくれる、そんなおいちゃんが笑わない。
「あんな、落ちついてきくんで。……隼斗じゃけんどな、帰ってこられんなったんじゃわ」
「……なん言いよんの? またまた、うそばっかり」
「ばかたれ、……おばちゃんが、こげな嘘つくもんかよ」
わるいいたずらだと思った、いやそう思いたかった。いや、まだ冗談だと思っているし、そうでなければつじつまが合わないと思った。
つい今しがた、矢野から聞いたばかりなのだ。ここへくる数十分のあいだに、じたいが急変などするはずがない。苦笑いでおいちゃんをみるが、おいちゃんは笑い返してはくれない。
「……え、うそなんやろ?」
「じゃけん、うそじゃねえって言いよろうがね。……あんな、……少年院にな、いくことになったんじゃわ」
「少年院……。なんで……、意味わからんのじゃけんど……」
どうしてだといくら問うても、ことのいきさつは教えてはもらえない。ただ隼斗の母親がくりかえすのは、もうここには来るなというセリフ。
中学三年という、たいせつな時期になるという。今後の進路に、おおきくかかわってくる時期だという。それぞれの道をあるくため、隼斗を忘れろという。
ふりだしに戻された気持ちになった。二年前の、あのときと同じ虚無を感じる。
さすがの隼斗も二度とここへは戻れないと、別れるかくごはできただろうという。もうここへは来るな、今後かぎを開けておくことはしない。
施錠のおとに我にかえり、急いでドアノブを掴みまわした。放心したまま外にだされ、すべての終わりを告げられたと実感する。
「朱里! ……久我はいつ……。え、どしたん……」
「……皐月。……なんか、もう……なんもかんも、嫌や……」
しばらくまで 隼斗の家のまえでねばってみたが、おばちゃんが応答してくれることはなかった。行き場をなくしたわたしの心と身体は、よろよろと皐月のもとへとたどりつく。
市営の団地からそう遠くはない、彼女の母親の借りているアパート。そこへあがりこみ、嫌になったといういきさつを説明する。
よい報告がまっていると信じて疑わなかった皐月も、はなしの急展開に気持ちがついていかない様子だった。
「……全部さ、忘れてしまって。……最初っから、なんもなかったことに……ならんのかやぁ……」
わたしの、そのひとことがきっかけになった。おもむろに立ちあがった皐月は、まようことなく台所へとすすむ。冷蔵庫をあけ、なにかをつかみ戻ってくる。
両手でかかえるようにして運ばれたもの、それは大量の缶ビールだった。それをわたしのまえに、ならべていく。
「……なん、これ」
「うちのおかんも、嫌なことがあったとき……こげんしよんけん」
飲んでわすれる、そう皐月の母親がいっていた。だから飲もう、飲んでわすれようというのだ。
はじめてのビール、それは苦いだけの飲み物だという印象だ。しかし嫌なことが忘れられるというのならば、どんなに不味くとも飲むしかないと思った。
たったいちにちで、しかもものの数十分のあいだに、天国と地獄をあじわってしまった。そんなことってあるのだろうか、いや実際にあったのだから笑えない。
「……なあ、それって……おばちゃんの?」
「なん? ……あ、このたばこ? いんや、うちのおかんは吸わんけん……くそ男のやろうな」
カラーボックスのうえに忘れおかれた、皐月の母親の彼氏のたばこ。光羅から、いけないといわれているもの。
しかし真似をするなと止められていた飲酒には、すでに手をだしたあと。いまさらたばこだけは、などと調子がよすぎるきもする。
いや、そうではないかもしれない。飲酒のせいで気がおおきくなり、もういいかと開きなおりの気持ちがつよい。誰がみているわけでもない、話さなければばれはしない。
吸い方など知らないわたしたちは、なんとなくのみんなの真似で火をつける。そのまま思いきりそれに吸いつき、深呼吸のごとく煙を肺へとおくりこんだ。
痛いどころの話ではない、このまま死ぬかのように咳こんだ。あふれる涙をぬぐう余裕すらなく、ころがりしばらく苦しみもがく。
「……なあ、皐月。……少年院ってさ、どんなとこやとおもう」
「げほっ……。どんなんやろ、……刑務所、みたいなんかや」
豊徳学園の存在も所在も、ほんの少しまえに知ったばかり。少年院というものがあることくらいは知っていた。ただ、どこにどうあるのか知りはしない。
あんなに頑張っていた隼斗に、いったいなにがあったのだろうか。また理由もわからないままに引き離され、こんどこそもう二度とはあえなくなるのだろうか。
峠のみどりをながめ、学園へむかった日の胸のたかなりがよみがえる。おなじクラスは嫌だと照れわらい、かさねたくちびるの温もり。最後にあった日の、あの隼斗の笑顔がとおくなっていく。
「会えんくなる!」
「な、なん……びっくりするやん。……朱里?」
とつぜん立ちあがったわたしに、顔をあかくした皐月がめをまるくする。隼斗が学園にいるうちに、いまのうちに会っておかなければ。
時計をかくにんすれば、すでに門限をすぎている。いつ光羅が来ても、おかしくない時間だとあせりがでる。おもわず皐月の腕をつかみ、強引に玄関へとつれだした。
「ちょ、ちょっと……。朱里、どしたんな」
「……隼斗に、会いてえ」
「うん、それはわかるんやけど……どうやって……」
「なんとなくなんやけど、……学園のあるとこ、わかるかもしれんけん」
なんとなくでも行けるかもしれない、本気でそう思ってしまった。峠までのみちは、かんぺきにわかっている。あとはその峠をひたはしるだけ。
きっとわかる、あの橋のちかくまで行けばきっとわかるはず。根拠のない自信が、わたしを突き動かしていた。
ポケットのなかに手をつっこみ、自分の所持金をみせる皐月。わたしもおなじように、ポケットのなかみを彼女のまえに差しだした。
ふたりのを合わせてみても、それは二百三十円にしかならない。わたしたちの交通手段は、皐月の家にある自転車のみ。
「……わかった、朱里。行けるとこまで、いってみろうや」
冷静にかんがえたなら、むぼうすぎることだと誰でもわかる。それでも彼女は、きりっとした笑顔でやろうと言ってくれた。だれにも何もつげることなく、わたしたちは県北をめざしてはしりだした。
第3章…09
灯りはじめる街のあかりに、わたしたちは自由をかんじた。峠がちかくなるにつれ、行き交うひとも車もすくなくなっていく。それでも、寂しいなどとは感じなかった。
街灯がまばらになっていき、建物もひとの住むものではなくなっていく。ゆるやかな登りにさしかかり、峠のはじまりなのだと理解した。
平坦なみちであればなんてことない二人乗りも、のぼりになるとさすがにきびしい。自転車を降りふたりならんで、ただひたすら先をめざす。
「なあ、このみちをずっと進んでいけばいいんでな」
「うん、国道からそれんで……橋がみえるとこまで、ずっとずっと行けばいいはず」
ひとつめの峠をのぼりきったところで、わたしは自転車にまたがった。最初にめざすはみどりの橋だと、皐月をうしろに乗せて峠をくだる。
全身でかんじる風に、さらに自由をかんじてしまう。鳥かごから飛び出した鳥のように、どこへでも行けるような気持ちになった。
田舎の峠みち、国道といえど交通量はすくなく暗い。それでも、怖いという感情をいだくことはなかった。ときにはお喋り、ときには鼻歌、ただ前へとすすんでいく。
この峠のさきにある学園にいきつく、隼斗にあえると信じてうたがうことなどしない。
「なあなあ、朱里の兄ちゃん……さがしよんじゃろうな……」
ふたつめの峠の登りみち、皐月がぽつりとつぶやいた。そのことばにちくりと胸がいたみ、それまでいちども振りかえらなかった道をふりかえる。
くらい闇につつまれたそこは、いまきた道すら確認がむずかしかった。こんなくらいところを進んできたのか、はじめて峠のさみしさを感じた。
ふりかえるたびに、なんとなく心細くなっていく。最初のころにくらべ、すれちがうトラックのかずも減っていることに気づいた。心のどこかで光羅にみつけて欲しいと、ほんのすこしだけ弱気になってしまう。
前方から車のライトが近づいてきて、こころなしかほっとする。一瞬のすれちがいだとしても、ひとの気配がこれほど嬉しいと感じたことはなかった。
「こんな時間でも、くるま通ることあるんやな……」
「うん、ちょっとうれしいな……トラックも、あんま通らんけん。さすがに、静かすぎやんな……」
「なあ、ちょっとだけ休憩せん?」
ちいさな集落のちいさな商店。そのまえにくたびれたベンチがあった。自転車をとめてそこへすわり、ちらちらと辺りをみまわす。
どの家のあかりも消えており、ゆいいつの灯りはちいさな自動販売機。さすがに喉もかわいていたが、所持金をおもうとここでつかうわけにはいかない。
みつめてしまうのはこれから進むべき方向ではなく、ここまでやってきた暗いみちのり。微かな後悔をかきけすように、ふたたびわたしたちは立ちあがった。
「なあなあ。……あんたらってさ、こんなとこでなんしよんの?」
とつぜんの声にふりむくと、さきほどすれ違ったくるまだった。助手席のまどがあけられ、茶髪のおとこが笑顔でこちらをみていた。
まずいことになった。いくら世間知らずのわたしたちだとしても、これが危険な状況だということは察知できる。とっさにあたりを確認するが、助けをもとめる相手などいるはずもない。
「なあ、無視せんでよ。聞こえちょんのやろ? ふたりって友達? ……あ、それとも姉妹かな。夜遊びなら一緒あそぶ? それか、帰りよんのなら送っていっちゃんで」
ここは関わらずにすみやかに逃げるべし。とにかくすこしでも移動をして、どこか逃げ込める場所をさがさなくては。
皐月を自転車のうしろにのせ、わたしは必死でペダルをこいだ。なにもいわないけれど、背中にしがみついている彼女は怯えている。
わたしのせいだ、わたしがこんなわがままをしたから。なんの関係もなかった皐月に、こんな怖いおもいをさせてしまった。
どうにかしなければならない、せめて彼女だけでも守らなければいけない。わたしだって怖くないわけではないが、こんなことになった責任をかんじてしまった。
「ちょっと待ってっちゃ! こんな時間に、女の子ふたりってあぶないよ? 送っていっちゃるって」
「やめて下さい! い、いもうとが……怖がってます……」
「じゃけん、怖くないように俺らが送っていっちゃるって」
「家は! ……そこですから」
まえにまわされた車によって、行く手をはばまれてしまう。助手席のおとこが降りてきて、わたしたちに向かって手をのばしてきた。
逃げられない、そう思ったわたしは目のまえの家を指さした。もちろん知らないひとの家であり、灯りなんてものはついていない。
そんな嘘は通用しないと、茶髪のおとこはうすら笑う。運転席のおとこも、あきれたように鼻でわらった。ここで終わってしまうのか、皐月の泣きそうな顔がみえた。
おもわず皐月のうでをつかんで、自転車を放りだして民家にかけよった。
「ただいま! おかーさん遅くなった、ごめん! あけて!」
「う、うそやろ……やばっ……」
おとこは慌てたようにくるまに乗りこんでいく。ここが自宅だとだませたわけではないのかもしれないが、危険は回避できたのだと安堵した。
知らない家の庭さきにすわりこみ、くるまの走り去るすがたを確認した。すっかりみえなくなってしまってもなお、そこから動くことができなくなっていた。
「……ごめんな、皐月」
「い、いや……大丈夫やけど……。朱里、すげえな……」
「な、なんが……」
「いや、こんなこと……よう思いついたなと、……おもって」
じぶんでも、すごいと思った。けっして余裕があったわけではないと、この身体のふるえがものがたっている。なにも考えることなどできなかった、気づいたらそうしていた。
とにかく危機はのりこえた、きっとこれでよかったのだ。しかし動くことができない、くるまが戻ってくるのではないかと不安でしかたない。
かといっていつまでも、ここにこうしている訳にもいかないということはわかっている。すすむべきなのか、もどるべきなのか。
学園にたどりつけると信じて疑っていなかった、あの自信はどこへいってしまったのだろうか。おそるおそる立ちあがり、そっと道路にでてようすをうかがう。
「……どうする? あのひとたち、もどって来よらん? ……もう大丈夫かな」
「きみたち、こんな時間に……なにしてる?」
さっきのくるまが去っていったほうに気をとられ、背後のくるまに気がつかなかった。とつぜんの声に身体をこわばらせ、おそるおそる振りかえる。
そこに停まっていたのは、白と黒のツートンカラーのくるまだった。降りてきたのはもちろん、警察官。さっきとは違う緊張がはしる。
さきほどのような状況の想定もしてはいなかったが、こういう状況の想定もまったくもって皆無だった。あたまが真っ白になってしまう。
「……家出?」
ことばにならず、ふるふると小さく首をふる。おかしいよねこんな時間にといわれ、もっともだと視線をおとす。運転席の警察官が、懐中電灯を片手におりてきた。
たおれていた自転車をおこし、それを懐中電灯でてらして確認している。なにをみているのか、隅からすみまで念入りにてらし顔をあげた。
「これ、だれの自転車?」
「……わ、わたしの……です」
こえをだした皐月に歩みより、懐中電灯でかおをてらした。「きみの? 名前は?」そんな質問に、皐月は下をむいてくちを閉ざした。
素直にこたえるはずなどないと、知っていたかのように鼻でわらう。その警察官によって自転車はすみによせられ、わたしたちはパトカーへと誘導された。
「……で、なにしてた? 中学生、くらいかな。姉妹……じゃないか、似てないもんね」
「…………」
「答えられないってことは、ふつうの外出じゃないってことだよね」
「遅くなって……家にかえる途中で……もう近くで……」
さきほどの連中のときと似たような嘘で、なんとかこの場をのがれようとこころみる。どの家かときかれ、返事にこまる。警察官のようすからして、行くき満々だとかんじたからだ。
「……うそは、よくないな。こんなとこに放っておくわけにいかないんだよね……、一緒に街にもどってもらおうかな」
「あ! ……自転車があるし」
「うん、自転車はこっちで運ぶから。あしたにでもちゃんと返してあげるから、大丈夫」
さすがに警察相手で、わたしたちが逃げきれるはずもない。せっかくの思いでここまできたが、あっけなく計画は中止となった。
自転車で何時間もかけてはしってきた道のりを、パトカーにゆられもどっていく。このあとのことが不安で、わたしたちは何度もかおをみあわせた。
ぜったいに隼斗のなまえも、学園のなまえもくちにしてはいけない。自分たちがなにものなのか、それすらも明かしてなるものかと瞳で誓う。
「あーっと、……おなじ部屋は、あれだから。どうしよっかな、……きみ、あっちの部屋にいこうか」
そとからは何度もながめたことのある、地元のまちの警察署。なぜか裏口からなかへと誘導され、せまくるしい階段をあがっていった。
皐月が連れられた部屋に、わたしも迷いなくついてはいる。うす暗いへやの雰囲気は、テレビでみる取調室そのものだった。
ふたり同室ではあれだからと言い、わたしは部屋をつれだされた。すこし悩んだように立ち止まり、ここでいいかと道路沿いの部屋のとびらを開ける。
おおきな窓のあるその部屋は、さきほどの場所とは違って開放的だった。ビジネスデスクのようなものの横に、ちいさな冷蔵庫までおいてある。
「……コーヒーでも、のむ?」
「あ、いえ……」
「そう? ……じゃ、すこし話そっか。……名前、おしえてもらえるかな。……それじゃ、家のでんわは? ……言いたくないか、……学校の担任でも、いいけど」
終始無言をつらぬきとおす、それでも警察官は笑顔でゆっくりと何度でもきいてくる。はなれた部屋から、おおきな物音がした。
わたしのまえに座っていた警察官は、「ちょっとごめんね」と言い退席する。ひとりになったことで少しだけ緊張がほぐれ、やっと呼吸がしやすくなった気がした。
「……椎名さんだって? お友達がね、教えてくれたみたいだから……家に連絡しとくから」
「……え、」
「お友達、こっち呼ぶ? 特にあれ……だから、迎えくるまで一緒にいてもかまわないし」
一緒はあれで駄目だといった次は、とくにあれだから一緒でいいと。すっきりしないが、帰れるならばそれでいい。しかし部屋にやってきた皐月の顔をみて、そんなのん気は吹き飛んだ。
片方の頬をあかくした皐月が、ひとみに涙をため入ってきたのだ。ひとめ見ただけで、その頬は叩かれたものだとわかった。
不機嫌な警察官が、とびらのまえを横切った。あいつだ、さっき彼女と部屋にはいった警察官だ。あいつが皐月に、手をあげたにちがいない。
しゃべってしまってごめんと謝る皐月に、申し訳なくて涙がこみあげる。わたしのせいなのだ、謝るべきはわたしのほうなのだ。
「椎名さんのほうは、家のひとと連絡がついたんだけどね。……七瀬さんとこ、電話でないんだよな」
「……あ、うちでよかったら一緒につれて帰りますけど」
「椎名さんの家のかた?」
「……はい」
すがたを現したのは、親ではなく光羅だった。皐月の母親はひるも夜もはたらいていて、まだ帰宅はしていなかったようだ。
今後このようなことがないようにという締めくくりの注意で、わたしたちは帰ることをゆるされた。
警察署をでると、そこには北斗のすがたもある。おそらく光羅とふたりして、わたしたちを探してくれていたのだろう。
わたしたちの顔をみるなり、なさけない笑みをみせた北斗。なにか言いたそうではあったが、なにもいわずに肩をだいてきた。
「久我、わりいけんど皐月ちゃん、送っちゃってくれんかや」
皐月をのせた北斗のバイクが、駐車場からでていくのを見送る。わたしを乗せた光羅のバイクは、自宅とは逆のほうこうへと走りだした。
真っ暗な堤防で、光羅はバイクを停めあるきだす。波のおとを聞きながら、わたしは兄のあとをついてあるいた。
「なあ、朱里。なんで、峠なんかにおったん?」
「……隼斗」
「隼斗? ……え、お前まさか……施設に行こうとしよったとか」
「……うん」
ふたりして海のほうをむいて座っていた。光羅はおもむろに立ちあがり、わたしのうしろに座りなおす。両足をひらいたそれは、部屋でのいつもの定位置だ。
うしろからまわされた腕が、ぐっとつよく引きよせた。「隼斗をわすれろ」という彼のことばに、わたしは何度もくびをふる。
隼斗は、もうかえらない。それは彼の母親からも、なんども聞かされたことば。別れろ忘れろとくりかえす光羅に、わたしは嫌だとこたえつづけた。
「ようすなんか……見らなよかった。……最初っから、反対しちょきゃ……こげんことに……」
「なんで、……兄ちゃん、なんでそんなこと言うん……隼斗は……」
「朱里! ……たのむけん、頼むけんしっかりしてくれえの……。おまえが、こんなんじゃったら……安心して行かれんやんか」
うっすらと東のそらが白けはじめ、水平線がすがたをみせはじめる。その水面はとても穏やかで、もったいないような美しさだ。
こんな状況でさえなければ、この海に感動をしていただろう。背中で光羅が泣いている。声をころして、苦しそうに泣いている。
ごめんなさい、兄ちゃん。どんなに忘れろといわれても、わたしは隼斗を忘れられない。なかったことになんて、できるはずがないよ。
第3章…10
豊徳学園、退園の前日。あきれかえった表情の北斗が、おれの前にすわったままくちをひらかない。
なにか言いたそうなのは、いやというほど伝わってくる。おれのほうだって、どんな罵倒もだまってうけるこころづもりはできている。
なにか言いだしづらいことでもあるのだろうか、それともこんなおれと話すことも面倒なのだろうか。わざわざ面会に出向いてきた理由、それはいったいなんなのだろうか。
おれがここを離れれば、もうおれに会いにくることもない。最後に顔だけでもみておこう、そんなつもりの来園なのだろうか。
「なあ、兄貴。……いろいろ、ごめんな」
「……あやまるんか、おれに。おまえ、相手を間違ごうちょらせんか」
「……え、」
「謝らないけんのは、おれじゃなかろうもん」
北斗のいいたいことは、痛いほどよくわかる。おれだってそうだ、まず朱里にあやまりたい。彼女はおれが帰れなくなったことを、すでに知っているのだろうか。
知ってしまったとき、どんなに悲しむのだろうか。それを考えると、いたたまれなくなる。おれはうつむき、膝のうえでこぶしをにぎった。
「兄貴……。朱里は、年少のこと……」
「おう、知ったんよ。……くそ矢野んせいで、おおごとじゃったわ」
「……え?」
「言うたんよ、あんバカが。おまえが帰ってくるって。そんあと年少のこと知って、……警察に補導されたわ」
「え、警察……。なんそれ、どういう……」
朱里がおおごとになったとは、いったいどういうことなのだろうか。矢野のせいとは、警察とは、補導とはいったい何があったのだろう。
光羅と警察にいき、朱里と七瀬を連れ帰ったという。そのときに七瀬から事情をきいたというが、おれにはさっぱり意味がわからない。
「え、ちょ……ごめん、兄貴。なにが……あったん」
「んああ? もとはっちゅうたら、おまえが悪りいんじゃろうが!」
よほどあたまに血がのぼっているのか、ことの重要部分をはなさず伝わってこない。そう、おれのせいなのだ。すべては二年前、いやおれの過去のすべてが悪い。
なにもかも忘れたいと泣いた朱里、そんな彼女と七瀬は酒をのんだという。そのままの勢いで、たばこにも手をだした。
それを聞いたおれは、じぶんが情けなくかんじた。光羅も心配をしていた悪影響、おれはそれを与えてしまっていたのだと痛感する。
おれが彼女たちのまえでそんな姿をみせていなければ、ふたりもそんな真似はしなかったかもしれない。
「……峠で、補導されたらしいんじゃが」
「とう……げ……?」
「おうよ、ここに来るっちゅうて……峠、越えろうとしたっちゅうんよ」
「……なんで」
「なんでじゃねかろうが! おまえがここに居るあいだじゃねえと、会えんなるって思うたけんじゃろうが!」
おれに会いたくて峠をこえようと、自転車での山越えなどという無謀なことをしたという。
愛おしくてたまらなくなったおれは、「会いてえ」とつぶやいてしまう。そんな身勝手な発言に、北斗は目をみひらいた。
なにが会いたいだ、のん気なことをいうな。深夜の二時過ぎに、おんながふたりで峠にいたのだと。なにかあってもおかしくない、現実におとこに絡まれたのだという。
いまにも掴みかかってきそうな勢いで、北斗はまくしたてた。そのようすをみて、おれはあたまが真っ白になる。
「……まさ……か……。兄貴……」
「…………まさか? ……そん、まさかがあっちょったら、椎名の代わりに、おれがここでおまえを殺るわ」
「…………よか、っ……た」
「よくねえ! どんだけ怖かったと思うちょんのか!」
朱里のとっさの判断で、なんとかおとこからは逃れたという。警察の巡回にあわなければ、おそらく被害にあっていただろうと。
たまたま運がよかっただけで、おれがふたりを危険においこんだことに変わりはないのだと。確かにそうだ、おれはふたりに大変なことをさせてしまった。
もしもほんとうになにかあった後だったとしたら、どんなに謝ってもあやまりきれないことなのだ。
「朱里が、こげえまでおまえんこと思うて……。じゃのに、おまえはどげえしよんのかよ。なんが妊娠か、……ふざけちょんなよ」
「ちがう! おれじゃねえんやけん」
「そんぐれえ、わかっちょんわ。じゃけん、隙みせちょんなっち言いよんのじゃ……くそぼけが!」
おれが隙をみせた。たしかになにも言い返せない。じぶんが帰れるとわかり、うれしさのあまり浮かれていたかもしれない。
残される者のきもち、それはよく知っていたはず。気がゆるんでいた、配慮が足りていなかった。自業自得といわれれば、おれはなにも言い返せはしない。
「なあ、……朱里は、そのはなし」
「言えるか、ばかたれ。年少っちゅうだけで、あのさわぎなんぞ。……おまえ、妊娠やら言うたら……あいつ壊れるわ」
「……言わんでな、朱里には。へんな誤解されとうねえけん」
「言うもなんも、もう会うこともねえかんしれんし……」
いくら待っても無駄だ隼斗は二度ともどらないと、母親が朱里をつきはなしたという。もちろん、家への出入りもぜんいん禁止していると。
母親は、別れろとはっきり言い切ったらしい。朱里がどう思っているかは本人にしかわからないが、おまえもその心づもりはしておけという。
北斗自身も、どうするのが朱里のためにいいのかわからないという。どちらにせよ今後は、自分もあまり関りをもたないようにしようと考えているといった。
去っていく北斗のすがたに、なにもかもが遠くなっていくような感覚をおぼえる。どうしてこんなことになってしまったのだろう、悔しくてたまらない。
ぼんやりとみつめる、自室の天井。怒り、後悔、時間をもどすことができたとしたなら。不可能なことをおもっては、虚しさにふるえる。胎児のようにまるくなり、眠れぬ夜をすごした。
「向こうにいっても、ここと同じように真面目に頑張れよ」
「……はい。お世話になりました」
目のまえの職員に、感情のないあいさつをかえす。停められているワゴン車に乗りこみ、ぼんやりと空をみつめた。頑張るということの意味も、必要性すらも見いだせない。
真面目に頑張るということばが、どうにもしっくりと入ってこない。これから向かうさきで、おれはどう過ごしていけばいいのだろうか。
走りだした車は、ほどなく橋へとさしかかる。おだやかに流れる川が、きらきらと光りをはねかえしていた。めを細めたおれは、橋のさきの交差点に視線をうつす。
ここを右折したずっとさきで、朱里が待っている。いまかいまかと身体をゆらし、おれの帰りをまっているのだ。
かちかちと点滅するウインカーの車内表示が、おれを現実の世界へと呼びもどす。おれの気持ちをそこに残したまま、くるまは北へと向きをかえた。
「……もう、あえんのやろうな」
「ん? どうした」
「あ、いえ。……なんでも、ありません」
県の北西端にいちする学院をみあげ、ため息をついてひとりごちた。とおくはなれたこの場所が、これからおれが暮らしていくばしょ。
塀をこえたその時点で、おれと朱里の縁はつきてしまった。そうだもう二度とあうことはない、それは決してゆるされることではないのだ。
いいかげんに諦めろと、じぶんで自分にいいきかす。そうしながらもまだ、こころのどこかで望んでしまう。なあ朱里、おれのことを待っていてはくれないだろうか。
第3章…11
光羅が、家をでていく日がきてしまった。ずっと音楽にたずさわっていたい、それが彼のつよい想いだった。
きまった就職先にさだめられた、二年間の養成研修。たとえそれが終わったとしても、光羅がこのまちに帰ってくることはない。
兄であり、親代わりのようなものだった光羅。いつだってそばにその姿はあり、ずっと頼ってきた存在だった。その関係が、今日でおわりになってしまう。
「朱里、兄ちゃん……行くけど……おまえ、大丈夫か」
「……うん」
大丈夫なわけがない。しかし行かないでくれなどと、そんなことは言ってはいけないと知っている。余計な心配をかけてはいけない、そんなこともわかっている。
うそだとしても、大丈夫だとこたえなければならない。心配かけるようなことはするなと言われれば、わかったと答えるしかないのだ。
見送りになんて、こなければよかった。つぎはいつ会えるかもわからないうしろ姿をみつめるのが、こんなにも苦しいことだなんて知らなかった。
「…………最悪」
望まずともむかえることとなる、あたらしい学年の最初の日。重いあしどりで三学年のくつばこへ向かい、クラス分けの貼り紙をかくにんする。
おもいのほかじぶんの名前をはやくにみつけてしまい、書かれてある文字に絶句した。三年一組、担任の氏名は矢野。
よりによって、なぜ矢野のクラスなのだろうか。したくちびるを噛む、まさしく最悪の二文字しかおもいつきはしない展開だ。
これはわたしの身勝手な、逆恨みというものだということはわかっている。しかし故意にしくまれたことなのではないかと、そんな勘ぐりまでしてしまう心境なのだ。
あいつが待ち受けている教室になど、できることなら入りたくはない。あいたくない顔をみたくない、卒業まで矢野とは関わりたくなかった。
「一年間、担任をします矢野です。中学校生活さいごの一年、思い出をつくりつつも……」
うざい、むかつく。ありきたりすぎて適当に聞きながせるようなセリフも、無性に耳についていらいらする。顔をそむけていたとしても、はっきりと顔がうかんでくるから尚のことはらがたつ。
点呼がてらなまえを呼ぶので、簡単な自己紹介をしろという。すでに二年間というときを、クラスは違えど共にすごしてきた同級生。いまさら何をアピールしろというのだろうか。
教室のなかが、ざわざわとした雰囲気になる。みんなの視線が、わたしに注がれていることくらい感じている。そして矢野のくちから、わたしの名前が幾度となくよばれていることもわかっていた。
「……椎名? 自己紹介がいやなら、返事だけでも」
もちろん、自己紹介などという面倒なことはごめんだ。しかし、それだけではなかった。矢野のくちから、矢野のこえでわたしの名前がよばれる。
その事実だけで、なんともいえない感情がこみあげる。うるさい黙れ、こころのなかで悪態つく。視線はずっと教室のそと、聞こえないふりをつらぬいた。
中庭のずっとさきに、ひとの気配をかんじる。新学期早々に、遅刻をしたものがいるのだろうか。ひとかげはくつばこへ行くようすはなく、中庭へとやってくる。
学生ではなさそうだが、どうやら教員ともおもえない雰囲気だった。近づいてくるその人物が、見知ったものだと確認ができる距離にきた。
「北斗兄!」
「おう、朱里か。ちょうどよかった」
それが北斗であるとわかった瞬間、わたしはその窓から中庭へと飛びだした。スリッパのまま彼のもとへと駆けより、その腕にからみつく。
こんな時間にこんな場所へ、いったいなんの用事があるのだろうか。見あげればいつものやさしい笑みで、くしゃりとわたしのあたまを掻いた。
「どしたん? なんで、学校にきたん?」
「ん? いや、ちょっと……。あ、そうや朱里、矢野っていまどこにおるか……知らんわの」
「え、矢野? ……あいつなら」
わたしは、今しがたじぶんが飛びだした教室のほうをみた。思ったとおりその窓からは、矢野と生徒たちがこちらをみていた。
わたしの視線をおうように、北斗もそちらをみやる。やさしかった北斗のひとみが、いっきにするどく尖った。
からめていたわたしの腕をふりほどき、わたり廊下の開放された扉へとむかう北斗。廊下へむかうのだと知ってか、矢野は窓のそばをはなれた。
はなしがあるのなら窓越しでもいいものを、わざわざ教室へとでむくつもりなのだろうか。あわてて北斗のあとを追い、扉のなかへと駆けこんだ。
「北斗兄、どした……」
遅れをとって教室にたどりつき、とびらのまえで固まった。はげしく教台が移動する音に、生徒たちの悲鳴がかさなっていた。
視界のなかでなにかがおおきく移動したのを感じ、それが矢野だと理解するのにも時間はようさなかった。
ボードのまえに倒れ、くちびるから血をながしている矢野。それを見てもことの把握には、もうすこし時間が必要かもしれないと感じた。
理解はできずとも、状況に足はすくむ。倒れている矢野の胸ぐらをつかみ、引きおこしては殴る。何度もそれをくりかえす北斗を、ただ見届けるしかすべがない。
「朱里!」
顔だけこちらを振りかえった北斗が、わたしの姿をとらえるなり叫んだ。おもわず背筋をのばし、表情だけで返事をする。
こっちへ来いとの彼のことばに、わたしはひるまずにはいられなかった。なにごとかと興味をあらわにした、クラス内の視線がいたすぎる。
北斗の関係者だということは、さきの中庭での行動で知れている。ただ衝撃的な状況ゆえに、呼ばれてすぐに動ける余裕がなかった。
「なんしよんのか、朱里。……こっち来いっちゃ!」
「え、あ……。え、……なんで」
「なんでじゃねえ、ここに来いっていいよんのよ」
クラスの視線が、はやく言われたとおりにしろという視線にかわる。わたしの対応のにぶさに比例して、北斗の口調が荒くなっていったからだ。
正直なところ、彼のこんな姿をみたのは初めてだった。中庭での眼光のことにしてもこの行為にしても、わたしからすれば意外すぎて処理がおいつかない。
「おいこら、矢野! ……おまえんせいで、めちゃくちゃになったん知っちょんのか!」
「え、あの……めちゃくちゃとは……」
「朱里が! あかりが……、どんだけ傷ついたか……」
北斗の行動の意味がわかり、わたしのなかの何かが解放された気がした。身体中のちからがぬけ、その場にすわりこみ号泣する。
ここは中学校の教室、ほかの生徒たちがみている場所。そんなことはすべて、一瞬のうちに頭のなかから消え去っていた。
朱里の精神を追い込み、隼斗まで追いやってしまうつもりかとまくしたてる。意味のわからない生徒たちは、ただ黙ってみとどけていた。
北斗に腕をつかまれ、ボードのまえにころがる矢野のまえに立たされた。飛ばされためがねを拾い、それをかけながら矢野は起きあがる。
「謝れ……、朱里にあやまれ」
北斗のことばに、矢野はわたしの顔をみた。わたしはこいつに謝ってもらおうなんて、ほんのすこしでも思ったことはない。
矢野から目をそらし背をむけようとしたが、うしろから北斗に抑えられ向きあわされる。両のあしをそろえ膝を折る矢野。
教室のつめたい床に、矢野のひたいがくっついた。自分の不注意でつらい思いをさせてすまなかった。すまない、申し訳ないと何度もくちにする。
「……こいつも、こげん言いよんけん。朱里、もうゆるしちゃれよ」
「ゆるす、とか……」
「あんな、朱里。これがおまえら二人んために、俺がしちゃれる最後のことじゃけんの」
「……え、どういう意味なん」
「こんクラスで、……矢野んクラスで、しゃんとやって行かな……やぞ。わかったか? ……しっかりせーよ、朱里」
「北斗兄……」
この彼も、わたしのまえから消えるのだとかんじた。すがるように見あげれば、北斗は困ったように微笑む。どうすれば彼が安心するか、わたしにはわかっている。
こみあげそうになった涙をこらえ、力強くうなづいてみせた。むりやりの表情だとさとったように、北斗はふっと息をもらし笑った。
こどもをほめるようにわたしの頭をなでると、矢野にむかい「隼斗にも謝ってこい」と言葉をのこし教室からでていってしまった。
張りつめたようすだった教室の空気が、いっきにいつもの状態にもどる。ざわざわとした音のなかで、わたしは扉をながめていた。
追いかけたい衝動にかられるが、それをしたところでどうにもならない。じぶんのなかに冷静な、もうひとりの自分がいる。そんなことがおかしくなり席へもどった。
◇空のそら|第4章へ…つづく↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
