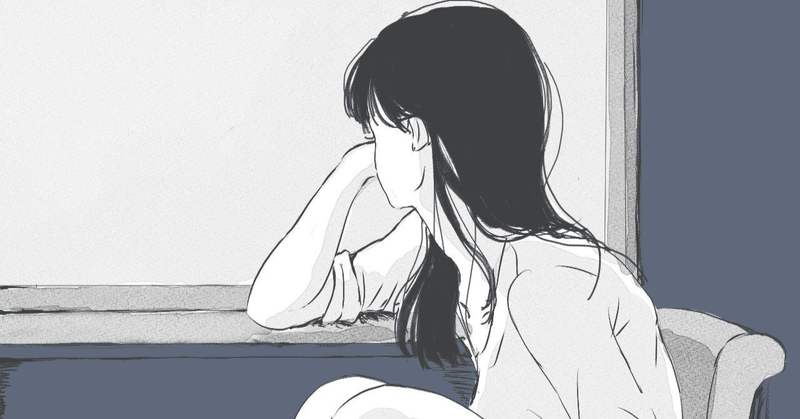
「小中学生時代のことが思い出せない」理由が分かった気がする
学生時代のことが思い出せないことって、ありませんか?
今回は、わたしのように
幼少期や小中学生時代のことが
思い出せない人へ向けたお話しです。
3年前、自己分析を始めたわたし
3年前に転職をしようと思い自己分析をすることにしました。
自己分析に関する本に、
必ずといっていいほど出てくる「自分年表」とか「人生年表」。
小学生時代は○○が得意で・・・
中学生時代は○○が好きだった
とかいうやつです。
自分の記憶を遡っていくと
わたしは幼少期~中学生時代のことが
思い出せなかったんです。

過去を思い出せず、モヤモヤ
アルバムに残っている
入学式や修学旅行の写真を見ると
「こういう出来事があったなぁ」と
断片的に思い出すことはできても、
毎日どういう思いで過ごしていたのか
何が好きで 何が楽しかったのか
友達とどう過ごしていたか
など
全然思い出すことができなくて、、、
なんでだろう? みんなそんなものかな?
と思っていました。
ところが、ちょうどその頃
幼馴染の友達と会う機会があり
話していると、その子は
「小学生の頃、Aちゃんにノロマって言われてたんだよね」
「さくらちゃん(自分)とkちゃんと私の3人で
よくブランコで遊んでたよね」
と昔のことをよく覚えていたんです。
やっぱり、わたしがおかしいんだろうか。
でも、事故にあったり記憶障害と言われたこともないし...
とモヤモヤしていました。
原因が分かった!
そして半年後、ある本に出会ったことで
原因がわかった気がしたのです。
それがこちらの本です↓
「生きる力を育む愛着の子育て」(ダニエル・J・シーゲル、ティナ・ペイン・ブライソン著)

結論から言うと、
「子ども時代のことが思い出せないのは
幼少期に回避型愛着を形成した可能性が高い」
とのことでした。
なぜなら、
回避型愛着を身につけた人は、
子ども時代において
「身体面の要求には応えてくれるけど
感情面での要求は無視する」親の元で育ち、
その結果
「目に見えない感情や情緒的な感覚に
気づかないような脳のしくみになった」
とのこと。
著書のなかで、
子どもの脳は「建築中の2階建ての家」にたとえられています。
1階の脳・・・感情と衝動をつかさどる大脳辺縁系があり、怒りや恐怖などの本能的なプロセスの出どころとなる
2階の脳・・・共感、想像や意思決定、自分の心を見る力などに関連した高度な思考をつかさどっている
学んだことから脳がどう作られるかというと
1階に存在する つながりを求める内面的な欲求が
回避型愛着のせいで満たされないので、
脳はその信号を遮断して
2階の脳に入れないようにする。
そうすると
つながろうとする合図を親に見逃されても
それほど苦痛には感じなくなる
つまり
自分を守るための自衛策として
1階の基本的な要求の信号が拒絶され、
2階の脳に届かなくなってしまうのです。

以上のように、
「子ども時代のことが思い出せないのは
回避型愛着を形成した可能性が高い」
という話でした。
回避型愛着についてもっと知りたい方はこちら↓
自分を誇れるようになった
このことを知ってから、
「小中学生時代のことを思い出せないのは
自分を守るための戦略だったんだ」と考えるようになり
守ることができた自分を
誇らしく思えました。
それからというもの、
過去のことを思い出せない自分を恥じることなく、
受け入れられるようになりました。
このような体験を通して、
子ども時代の記憶が無いことを
疑問に思っている人や
コンプレックスに思っている人に
「恥ずかしいことではなく、誇れることなんだよ」
と伝えていきたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました🥰
記事の感想など、コメントもお待ちしております。

よろしければサポートお願いします。いただいたサポートは参考資料となる書籍の購入や、仲間のサポートに使わせていただきます。
