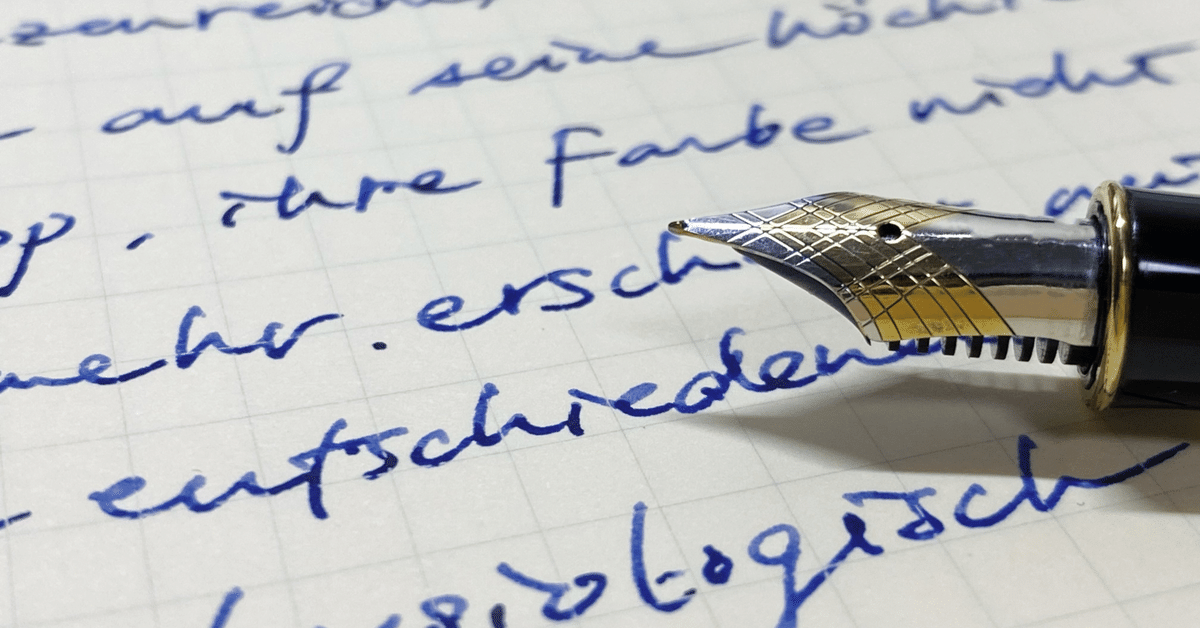
スピノザに言及する哲学者たち・その4エトムント・フッサール
現象学の提唱者、エトムント・フッサールは、スピノザと並べて語られることが、きわめて少ない哲学者の一人であろう。
論文単位では探せばあるのだろうが、著作として読めるのは、私の知る限り、『自然の現象学:時間・空間の論理』(中敬夫著)のみである。
タイトル通り、主要テーマは「現象学」そのものであるのだが、そのうちの一章として、スピノザとフッサールの比較が論じられている。
「自然」についての著者一連の現象学的研究のなかから、特に根源的な時間・空間経験の問題を出発点として、現代哲学のもろもろの有力な立場と対決しつつ、〈多における一〉〈一なき多〉の根底に、〈多なき一〉〈一における一〉の論理を析出する。
<目次>
●第一章 一にして不可分の空間(の)経験― スピノザ、フッサール、ビラン
●第二章 『物質と記憶』における緊張(tension)と伸張(extension)
●第三章 瞬間のなかの持続 フッサールとベルクソンの調停の試み
●第四章 〈一なき多〉の場の自己経験としての〈多なき一〉― レヴィナス多元論の批判の試み
フッサールについては以下に記しておく。
[1859~1938]ドイツの哲学者。現象学の創始者。数学の研究から出発し、心理主義を排して純粋論理学を提唱。のち厳密な学としての哲学を目指し、先験的意識の本質構造に基づいて対象をとらえようとする現象学に到達。ハイデッガー、サルトルらに強い影響を与えた。
現象学とは、フッサールの「事象そのものへ」という言葉にあるように、伝統的あるいは日常的な先入観や、哲学的独断にとらわれることなく事物や存在にアプローチし、われわれ人間の意識に現象として現れる意識体験のあり方を記述的に探究する哲学であり、その意味を問うことで、もろもろの学問を基礎づけようという方法である。
スピノザとフッサールは、どう違うのだろうか。実際、上記の書においても、スピノザとフッサールを論じることを「奇妙な取り合わせ」「対極的な哲学者」と著者自身が形容している。なぜゆえに「対極的な哲学者」とされているのであろうか。
まず、スピノザの認識論においては、「三つの認識」がある。
第1種の認識=表象知 臆見、表象、想像などによる認識
第2種の認識=理性知 共通概念、理性による認識
第3種の認識=直観知 本質の直観的な認識
この中でも「直観知」と呼ばれるものが、スピノザの思想を「力の存在論」、「生の哲学」として形容させるものであり、この直観知においては、世界の認識とは存在そのものの意であり、存在自体が認識と一致する、あるいは含む。
スピノザ哲学は、「我」から始めたデカルトや通例の哲学がそうするように「人間」「主体」から始まる哲学ではなく、何よりも神=世界からはじまるのであり、われわれ人間はその世界における有限なる個物の存在でしかない。
一方のフッサールは、上述したように、私という主観が持つ意識現象から、どのような構造で、私たちの「確信」が構成されていて、認識が成立しているかというアプローチである。
私たちは、通常、自分の目で実際に見えるものや、自分の感覚器官において経験できること、知覚できること、認識できるものが、この世界である、と考える。このことをフッサールは「自然的態度」と呼ぶ。
この自分が認識している世界は、きっと自分以外の他者にも当てはまるのであろうと推測し、実際の他者とのコミュニケーションにおける同意、確認により、自分の経験は他者も同じように経験しているのだということで、世界は客観的な実体として存在すると確信している。そのようにして、われわれは半ば無意識的に、日考日常生活を送っている。
デカルト以降の哲学は、超越的な主観により世界を把握しようとする。科学もこのような客観的視点によるもので基礎付けられているが、フッサールら現象学が試みたのは、このような超越的世界の先にくる現存在、生活体験によって知覚される世界にこそ、学術を基礎付けなければならないとした。
一見、両者の認識論には、存在(世界)が先か、私が先かという「起点」において、そもそもの隔たりがあり、相容れないものであるかのように思える。
もっとも、現象学自体が、真理とは何かや認識とは何かを問う哲学とは異なる。現象学はむしろ、その認識が真であると確信、確証されるのはなぜかを問う、探究するための「方法論」であり、扱っている領域が違うといえば違うであろう。
では、フッサール自身はどうなのだろうか。スピノザをどう捉えているのだろうか。
私が読んだフッサールの作品は、『内的時間意識の現象学』『デカルト的省察』『現象学の理念』『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』くらいなので、断言はできないが、フッサールがスピノザに関して言及することは、ほぼない。
理由は、上記に挙げたように、そもそも現象学は、哲学ではないということもそうなのだろう。
だが、哲学史的な流れの中で出てきたこの現象学という学問は、哲学とはむろん、無関係ではない。
フッサールが、おそらく唯一といっていいほどに、スピノザに触れている著作がある。
『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』がそれだ。
『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』は、フッサールがその最晩年、ナチスが台頭するなか、近代ヨーロッパ文化形成の歴史全体への批判として書き継いだとされる、いわばフッサールが語る「哲学史」あるいは「学問史」の総決算的なものとなっている。
「哲学は現在、懐疑や非合理主義や神秘主義に屈服しそうになっている」
というくだりから始まるこの書の中で、フッサールは、ヨーロッパの知の歴史形成、ガリレオから始まりデカルト、ロック、ヒューム、カントというお馴染みの西洋哲学史をなぞりながら、「ヨーロッパの諸学問が危機に陥っている」と主張する。
この「危機」とは「諸学問が自然科学を模範とした結果、人間の生を適切に扱うことができなくなってしまった」という、近代合理主義、科学主義的思考への痛烈な批判を行っている。
そのような危機を克服するためには、「自然科学的な思考をはじめる以前に私たちが生きている「生活世界」に立ち戻らなければならない」とフッサールは言う。
その語りの過程の中で、スピノザも登場するのである。そしてこれが、意外?なまでに、スピノザに対しては高評価を与えている(と思う)言及なのである。
新たな自然主義的合理主義がどのようにして体系的哲学――形而上学すなわち理性の問題についての学――を「幾何学的秩序で」創造しうると信じたか、われわれはその古典的な例証をスピノザの『倫理学(エチカ)』においてもっている。むろん、われわれは、スピノザをその歴史的意味において正しく理解せねばならない。もし人がスピノザを、彼の「幾何学的な」証明方法という表面に現れたものだけで解釈するなら、それは完全な誤解である・・・・・・こうしてはじめて、合理的な存在者の全体が現実的に思考可能だということが、(スピノザの)実行によって証明されたことになる・・・・・・スピノザにとっては、体系的一般者だけが問題だったのであり、彼の『倫理学(エチカ)』は、最初の普遍的存在論なのである。この存在論によってこそ、現実の自然科学も、またそれに並行するものとして同じように建設されるべき心理学も、体系としてのその真の意味を獲得しうるのであり、この体系であるという意味なしには、自然科学も心理学もわけのわからぬものに終わる、とスピノザは考えたのである。
フッサールは、学問の基礎付け、土台というものにものすごくこだわっていた。その土台が、科学においても哲学においてもグラグラだから、「ヨーロッパの諸学問が危機に陥っている」という文脈の中で、スピノザこそが、「最初の普遍的存在論」であり、自然科学も心理学も、のみならず、存在そのものを体系化させ、かつ、現実化させた人間なのだとしている。
フッサールのスピノザへの言及は、この部分しかなく、ほんのわずかなのだが、「倫理学(エチカ)」=自然科学および心理学、と触れている点で、かなり的確にスピノザを読んでおり、かつ哲学史的にも重要な位置付けにあるという評価をくだしているのではないだろうか。
今回は、詳しくは触れないが、じつは、フッサールがやろうとしていたことは、上述した、スピノザの第一種の認識=「表象知」における認識と、同じなのではないかという指摘がある。
そのことに最後、触れておきたいと思う。
『探究2』においてスピノザを論じていた柄谷行人は、『言葉と悲劇』において、フッサールとスピノザについて言及している。長くなるが、重要な箇所なので引用しておく。
われわれは身体を超えられないわけですから、スピノザから見れば、我々が考えていること、知覚していること、これらはすべて想像知にすぎません。しかし彼は、それとは別に真の知識(エピステーメー)がある、とは考えていない。ある意味では、後期フッサールみたいなことをスピノザは考えていると思います。というよりも、後期フッサールは、彼自身における前期からの転回が、デカルトからスピノザへの転回に似ていることを知らなかった、というべきです。たとえば、月は、われわれが(経験的に)見ているよりも実際はもっと大きい。そのときに、どちらが虚偽でどちらが真であるとは言えないわけですね。デカルト主義的な観点からすれば、天文学者がいう月の大きさが正しくて、われわれが見ている月の大きさは誤りになります。いわばフッサールが、『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』で書いたのは、われわれが知覚する月という体験を無視してしまったところに、近代的な精神の危機があるということでしょう。しかし、スピノザは最初からそう考えています。身体・知覚・情念・想像、この条件をわれわれは超えられない。それがスピノザの基本的な考えですね。
※強調引用者
先にあげた、スピノザの三つの認識、表象知、理性知、直観知は、表象知が「非十全な認識」で、理性知と直観知のみが「十全な認識」である、とスピノザが言っているため、人間の認識は、表象知→理性知→直観知と、段階的にレベルアップしていくもののにように誤解されがちだが、そうではない。
スピノザにおいては、人間の認識の条件、必然として表象知を挙げており、虚偽ゆえに乗り越えるべきもの、排除するもの、とは決して考えていない。
理性知や直観知と等号で結べるものではないが、知覚においては、いずれの認識も、人間は不可避的に持っているということなのであろう。
表象知=imaginatio=イマジナチオは、「迷信」「想像」「臆見」「妄想」「幻想」「夢」などがあげられており、マイナスな印象もあるのだが、人間の精神(主観)が曖昧に捉えてしまうものが、表象知であるならば、フッサールが学問を基礎づけようとした、主観による日常的な経験、意識もまた「表象知」であろう。フッサールはその表象知にこそ、積極的なものを見出そうとしていた。
この点からも、フッサールとスピノザはもっと、共に論じられてもいいような気が、個人的にはしている。
今日のわわれの社会が、ますます抽象度を増し、「臆見」や「憶測」、「迷信」や「虚構」といった、負の表象知にまみれていけばいくほど、この表象知自体を問うということの重要性は増していくであろう。
フッサールを読むことの重要性ももっと増していくように思うし、これら哲学の領域はもとより、文学や映画といった芸術の領域も、この表象知をめぐっての実践的な思考=活動ともいえる。
「表象世界において表象でもって戦う」という、積極的な表象知の位置づけ、実践が、今なおわれわれには求められている。
<関連記事>
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
