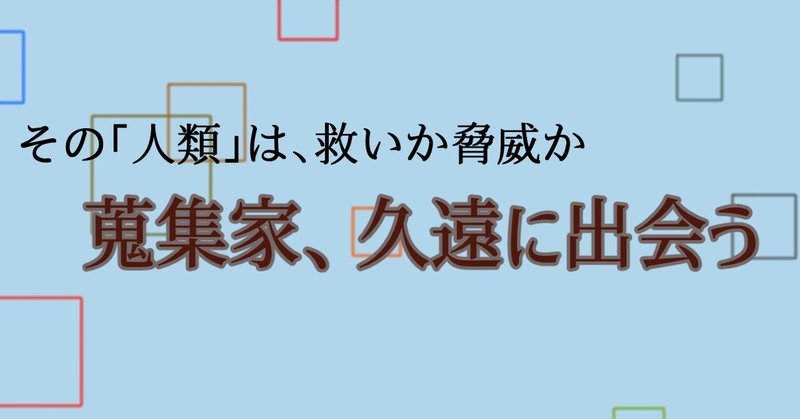
蒐集家、久遠に出会う 第一章 三、彦根直の発見
第一章一話へ
前の話へ
午後を回り、休憩時間ながら人通りの少ない廊下で、彦根直はかつての同僚に電話を掛けていた。窓から日差しの入り込む中、長く続く呼び出し音に痺れを切らす。ついに相手は出そうにないと分かって、端末を耳から離して乱暴に振り下ろした。この研究所をやめて以来、向こうは一度も連絡に応じてこない。きっと自分が懸念している計画を、誰にも黙って進めているのだろう。
やはり姫路好古の監視は、何を言われようと押し切るべきだったのだ。頭の中に所長の姿を思い浮かべ、彦根は奥歯を強く噛み締める。所長だけではない、一部の職員たちからも、退所した姫路に関わることはやめるよう求められた。彼はもう、組織の在り方に縛られるべきではない。久遠研究所は元職員を深追いしないとして、誰も姫路のやろうとすることを問い詰めなかった。
スマートフォンをポケットに仕舞って、彦根は廊下を歩きだす。足はいくらか重く、あまり同僚たちに会いたくない。解決すべき問題を放置している所長など、まっぴらだ。あの人はこことは違う機械文明の発達した世界の出身で、幼少期から当たり前のように科学を信奉してきたという。何もかもを機械に頼っている故に、文字さえまともに手で書けない。その世界では当たり前だという事象を思い出し、彦根は顔をしかめる。
所長の故郷では、人間はどのような存在として見做されているのだろう。既に多くの仕事で、人造人間である久遠への置き換えが進んでいると聞く。自らも久遠をこの世界に普及させたいと言う所長は、人間の問題などどうでも良いと思っているのか。
「……あ、彦根さん。また姫路さんに電話してたんですか?」
油断すれば聞き逃しかねない弱めの声がして、彦根は足を止めた。戸のない給湯室入り口から、林長時が顔を出している。久遠研究所所長の秘書にして夫である彼は、茶を淹れても良いか尋ねてきた。すかさず頷き、彦根は友がてきぱきと作業をするのを入り口から眺めた。
控えめが人の形をしたものが林という存在だと、彦根は度々思っている。いつも所長に従って何やかややっており、あまり目立つことはない。他の職員たちと話す姿も滅多に見ない。自分と親しいのは、この理系が多い組織の中で、たまたま文系として主に学んできた縁が結んだためだった。
「能鉾で大変なことになっているの、聞いてます?」
今は気を緩めても良い休憩時間中なのに、林は相変わらず丁寧な態度で茶を渡してくる。能鉾といえば所長の生まれた異世界の国だが、そこで何が起きているかなど彦根は全く関心がなかった。だが友人の話は、茶を飲もうとしていた彦根にしばらく思考を停止させた。
「正体のよくわからない女の人が、人類を滅ぼすとか言っていて……本気でそうなのかは、まだなんとも言えないけど……」
しばらく湯飲みから漂う湯気を眺め、彦根は不意に笑いを抑え切れなくなった。両手を叩きたくなって茶を零しそうになり、その場で正直な思いを口にする。
「人類滅亡なんて映画の中の話じゃあるまいし、そんなことする奴がいるはずないだろう!」
一体相手は何を思って、そんなとんちきな行いをしようというのか。そもそも人類を滅ぼすなど達成できるのか。絶対に無理だと言い捨てて、彦根は湯飲みの中を一気に呷った。
「笑いごとじゃありませんよ、彦根さん。実際に能鉾とかでは、各地で事件が起きているんですから」
林は眉を吊り下げ、スマートフォンの画面を彦根へ示してくる。自分がよく見るニュースアプリと似た体裁で、聞き覚えのない報道が多数表示されている。首謀者と思われる人間が殺人を見せ付けたなど、気分の悪くなりそうな情報は下まで続いていた。あるニュースを開き、彦根は久遠が人を殺したという点に顔をしかめる。通りすがりの人間を突然刺したなる内容は、すぐ忘れて良いものではない。こんな騒ぎが自分の知らない所で起きていたのかと、彦根は声を低めて林に問うた。
「わたしが直接向こうへ行ったわけではないから、確証は持てませんよ。でも『新世界ワイド』には、ちゃんと書いてある」
信頼できる報道機関だと、林はアプリの紹介画面を見せた。異世界の報道を伝えるべく数年前に発足された会社は、今やこの世界以外の事件を知る上で重要な存在となっている。それが彦根に知られていないのは、異世界の知識流入を阻む原則とやらがあるからだろう。限られた人しか使っていないそれを、林はダウンロードするよう勧めてきた。
「しかし久遠がああして事件を起こすとは――やはり久遠なんてものは、より警戒した方が良いんじゃないか? この世界で広めるのも――」
「そんなことを言ったら、また所長に怒られますよ? ここの職員としてふさわしくないって」
「全く、異世界の人間っていうのは……」
どうにもならない問答が途切れ、彦根は大きく息を吐き出した。初めて所長が異世界の出身だと知った時には、戸惑ったものだった。その突飛な価値観に呆れ、分かり合えないと思った時もある。それでもこの職場に留まるのには、理由があった。
「久遠と人間は、共存できるのかなぁ。彦根さんは、それを目指してここへ入ったんですよね?」
頷くも、彦根はその未来実現への思いが弱りかけていた。確かに入所時は意気込んでいたが、思っていたものと何か違う感じがする。姫路の思想と彼がやらんとしていることが、揺らがせてしまったのか。自分へ言い聞かせるように、彦根は呟く。
「人には、人にしか出来ないことがある。姫路は久遠を素晴らしいと見ているようだが、あいつには負けられない……!」
いつの間にか、湯飲みを持っていない方の拳が硬く握られていた。皮膚に爪が食い込んで痛むのも我関しない。久遠に人間の営みが奪われてはならない。人は人で、やるべきことをしっかり果たすのだ。そうしなければ、本当に人類が終わってしまう。
「でもこれからの時代に、人には何ができるっていうんですか?」
自分とは対照的な細い声で、林は問い掛ける。将来は多くの仕事がロボットや人工知能に置き換えられる、そんな未来を例に挙げて。
「きっと将来は、町に久遠があふれて、接客も案内も、わたしみたいな秘書業もみんな――」
「悲観的なことを言うな、林。あんたも仕事が奪われたら困るだろう? それをおれたちは止めないといけないんだ」
強めに林の肩を叩き、湯飲みを持って入り口と反対にあるシンクへ向かおうとする。しかしすかさず林に、洗っておくと言われて器を取られてしまった。言葉に甘えて微笑み、彦根は給湯室を出る。そのまま仕事場には向かわず、廊下の隅で「新世界ワイド」を素早く調べた。改めて、アプリに掲載されている情報の多さに驚く。林の言っていた久遠を信奉する者の件から、念願の博物館が崩壊したライニアのことも詳細に書かれている。
そうして画面を眺めていた中で、ニュースの間に挟まれていた一つの広告に引き付けられた。写真もない文字だけのシンプルなもので、困った人を助ける「早二野」なる組織が宣伝されていた。思わず指で触れ、新たに現れた画面で「早二野」が盗品を返す団体だと表記されているのを読む。特に「楽土蒐集会」に盗まれたものがある人は、ぜひ連絡してほしいそうだ。
好奇心と同時に彦根へ芽生えたのは、胡散臭さだった。彼らは本当に、盗品を返却しているのか。具体的な例はいくつか書かれていたものの、ほとんど個人が対象であまり大きな功績には思えない。しかし休憩を終えて仕事に取り掛かっている間も、彦根の頭から「早二野」が離れることはなかった。
別に大事なものが盗まれたというわけではない。ただ心に引っ掛かっていることがあるだけだ。もし「早二野」が人を助けるというのなら、自分のような人間の話も聞いてくれるだろうか。「新世界ワイド」に広告を出すほどだ。きっと異世界や久遠について説明しても、苦い顔はされないはずだろう。
就業を終えて暗い路地を進み、職場の最寄り駅に着いて彦根は心を決めた。広告に載っていた番号へ電話し、応答を待つ。やがて聞こえたのは、まだ若いとも思える男の声だった。
『蒐集団体『早二野』の白神だ。蒐集の依頼か?』
いきなり脅しに近い声色で言われても、彦根は怯まず返す。
「あんたたちが困った人を助けるというのは、本当なのか?」
『少なくとも長なら、喜んで受け入れるだろうな』
溜息に似た笑いを向こうから耳にし、彦根の心臓は騒ぎだす。ひとまず相談をと思って連絡したが、果たしてこの得体が知れない団体を頼って良かったのか。そもそも広告に事業者の名前と顔写真がなかった点からも、怪しむべきだったかもしれない。だが疑って何もしないままでは、今後が好転すると思えない。
組織のメンバーを把握したいと伝えると、相手はあっさりと受け入れた。そして話し合う場の予約を入れるとして、ある小料理屋の名が出されたのだった。
次の話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
