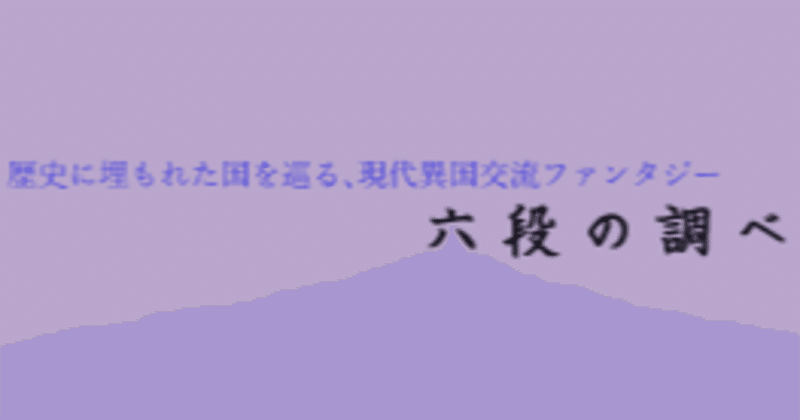
六段の調べ 序 三段 六、貴なる人
前の話へ
三段一話へ
序・初段一話へ
神器の焼失を伯母へ謝るシャシャテンの隣で、清隆の脳裏には繰り返し湖畔での出来事が再生されていた。四辻姫が託し、シャシャテンと五色姫が日本へ預けた巻物は、呆気なく燃えた。瑞香の姫たちだけでなく、巻物を預かっていた北の思いも灰と化したことに、清隆は歯を食い縛る。
加えて、宮部も死ぬ必要はなかったのではないかと浮かぶ。北だけでなく、宮部も止められなかった。しかも今回の場合、宮部は本当に死亡してしまった。前と何も変わりのない自分に、苛立ちが募る。
「申し訳ありません、四辻姫さま……」
信の声がして、シャシャテンの話が既に終わっていたと気付く。彼に続くように、清隆は四辻姫へ頭を下げて謝罪した。せっかく自分たちのために策を与えてくれた彼女に、罪悪感が募る。何しろ、神器を最も望んでいた者だ。彼女からどんな処罰があってもおかしくない。
「御二方、そなた達はそこまで我が国を思うてくれておるのか?」
元女王の言葉に、清隆は顔を上げる。彼女が怒っている様子はなく、むしろ不思議そうな表情をしている。
「ありがたきことじゃが……まずそなた達は、隣国・日本に住む一介の民に過ぎぬ。元は斯様な瑞香の重き事の様に関わる筈のない者じゃ。とはいえ、巻き込んだ私が悪いのじゃが」
神器はまだ鳳凰の箏があり、無銘「栄光」ももしかしたら出てくるかもしれない。瑞香は任せて、清隆たちは再び日本での日々に専念してほしい。四辻姫にそう言われても、清隆はすぐ受け入れられず口を噤んでいた。一方で信は、作戦失敗が自分のせいだのとぶつぶつ呟いている。それが清隆の耳にもはっきり届くようになると、突然衣擦れの音が聞こえた。帳台から下りた四辻姫が、袴に差していた扇子で信の肩を叩く。
「そなたもいつまで悩んでおる! かほどに思っておるのなら、この国に住むか?」
「それはお断りします!」
まだ学校などがあるからと、信が姿勢を正す。そして清隆の方を向くと、飛び付かんばかりに迫ってきた。
「清隆も、今日は日本へ帰ろう? ずっと瑞香のことで悩んでなんかいられないよ」
思えば、自分は少し前にも瑞香や『芽生書』を気にしていた。それを八重崎にも心配されたのだ。
まだ気掛かりな点はあるが、いつまでも瑞香を考えてはいられない。日本に帰ってからもやるべきことは多い。そう気付いて、そちらに意識を向けなければと心を改める。信の言葉をやむなく受け入れ、清隆は四辻姫に一礼した。応えて笑う元女王は、王位の剥奪や幽閉生活での苦労を微塵も感じさせなかった。窮地に陥った時でも、人を励ますほどの余裕を見せている。
感謝を覚えつつ、ふと清隆はその励ましが彼女の本心か引っ掛かった。好意でやっているのなら申し訳ないが、どうしても気になってしまう。彼女に何か裏があるのではないか、自分たちを油断させようとしているのではないかと。
四辻姫が女官に呼ばれ、帰りの際は見送ると言って部屋を出る。長髪を引きずって歩く彼女の後ろには、まだ髪が残っている。いつになったら毛先が出ていくのか観察するのも諦め、清隆はシャシャテンに四辻姫をどう思っているか尋ねる。
「無論、私の親代わりであり、師でもある方じゃ。あの方はいつも私を気に掛けてくださった。宮部の言い方と似ておるかもしれぬが、私も伯母上には強い恩義がある。じゃから」
小袖の膝辺りをぐっと掴み、シャシャテンは誰もいない正面へ厳しい目を向ける。
「伯母上から多くを奪った大友が許せぬ。私の母を殺したことと同じく、伯母上への仕打ちは憎むも当然よ」
シャシャテンが青柳湖で、大友を散々に言っていた様を思い返す。あの言い分は、彼女が完全に彼を敵と認識しているからだろう。世間自体は大友の治世をどう考えているのか。知りたいところだが、今日中の帰還は決まっている。せめてもう一度町へ行く時間が欲しかったと思いながら、清隆は部屋の奥にある丸い窓を眺めた。
初めは窮屈で仕方なかった女官装束も、宮仕えを続けるうちに慣れていった。それでも周りからは不格好に見えるらしく、度々謗りを耳にする。こんな自分だが、大友には頼りにされている方だと伊勢は自負していた。日が暮れた後、真っ先に王から呼び出されて彼の部屋へ向かう。帳台と向かい合うと、彼の威厳と心頼みはありありと伝わってくる。
まず聞かされたのは、宮部玄が青柳湖の畔で身を焼き果てたということだった。思いがけない友の死に、しばらく心が動かなくなる。彼とは同じ師匠のもとで学び、共に本意を果たそうと誓っていたのに。急な知らせに涙も出ず、伊勢は声を失っていた。
「そなたの心は分かる。私もあの者には目を掛けていた。命を奪われたのは惜しい。……だが、どうかあの者を恨むな」
巧みでないながらも励まそうとしている言葉を聞いた末に落ち着き、伊勢は気を取り直して他に用はないか問うた。廃されていた責め苦によって六段姫を殺害しようとした件を咎められたが、重く罰しはしないと言われた。王女にまつわる話に、思わず伊勢の口が動く。
「あの者は、陛下を確かに敵と見ています。早めに排すべきかと」
主はしばらく黙っていたが、突如激しい咳をした。前から何度かその姿が目立っていたが、これほどひどい様は初めてかもしれない。医者を呼ぼうか迷うも、しばらくして調子を取り戻した王に止められた。
「あやつを殺めるのは、国が昔に戻ってからで良かろう」
くぐもった低い声で、大友は述べる。その心を、伊勢はすぐに受け入れられなかった。王を脅かす者を、いつまでも放ってはおけない。そして大友が躊躇するのには訳があるはずだと見抜く。
「陛下、まだあの者を気にしておられますか? 恐れるお気持ちは分かりますが――」
「そなたも、あやつの指図に沿うたのだろう」
何も返せなかった。六段姫も、初めは彼女を気の毒に思って手を付ける気になれなかったのを、宮部から逆らわず従うべきと勧められたのだ。所詮自分も、あの者の言葉に左右されるがままなのか。
「そなたは私と違って、あやつから重く見られているまい」
大友の声に、伊勢はじっと耳を傾ける。国や臣下に関する件は、己が全て責を負えば良いと彼は言う。だから伊勢も自分に構わず、人の指図や周りの言い分など気にせず好きに生きてほしい。ここでの勤めをやめて、町で心安く暮らすことも許す。そんな大友の案を、伊勢はすかさず跳ね除けた。
彼は卑しい者たちを哀れみ、その扱いを良くしてくれた。特に伊勢へのそれは誰よりも大きかった。そんな恩義を、今さら捨てて生きるなど出来ない。
「……これ以上あやつに逆らえば、命はない。それでも良いか」
迷いなく頷いた伊勢に、次の指図が下された。それを受け入れて退室し、提灯を手に御所を出る。宮部と並ぶもう一人の友が住む屋敷へ行き、王から聞いた話を伝えた。友は自身の部屋へ伊勢を連れて行くと、昨夜宮部に受け取ったという箏爪と紙片を渡してくれた。なぜ自分には何も言ってくれなかったのか苦々しく思いながら、伊勢は畳に座り込む。
ここに住む友を自分に引き合わせてくれたのが、宮部であった。都の外れで政とも関わりのない暮らしをしながら、実はやんごとなき者と会うことは、拷問吏の身では考えられなかった。そんな貴なる人との縁を繋いでくれた宮部に、感謝といたたまれなさが募る。
「しばらく一人にしてあげますから、思う限りに泣いてください。先ほどからつらそうに見えてなりません」
友が部屋を出て襖を閉じ、伊勢は一人で残される。この屋敷に来てからずっと抑えていた思いを、ようやく吐き出せた。赤い単の袖が、さらに濃く染まっていく。声を塞いでいた袂をより強く噛み、伊勢は顔を上げる。宮部は思いを果たせず亡くなった。彼の無念を、何としても果たさなければならない。そして大友の願いも早く叶えねば。
吊り下げられながらも恐れを見せず、自分を睨んでいた女が目に浮かぶ。彼女こそ大友の敵だ。似たような道を辿ってしまったものの、敵味方と分かれている今は仕方がない。恩義のため、そしてある意味では彼女を救うためにも、伊勢は心を決めた。
次の話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
