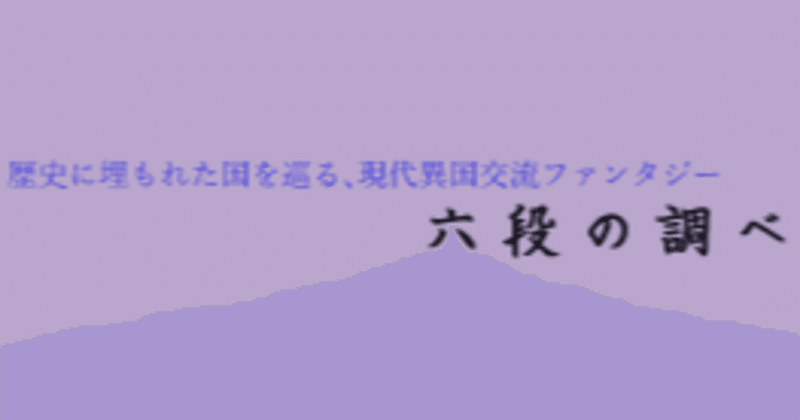
六段の調べ 破 四段 三、倉橋輪
前の話へ
四段一話へ
序・初段一話へ
座った清隆が視線とほぼ同じ高さで見る倉橋の顔には、隠し切れていない自信が溢れていた。人に聞かれることも気にせず瑞香の話をしようとするその人には、清隆が今までに会ったあの国を知る人物の中でも癖の強いものがあった。倉橋が亡父の遺志を継いで日本に瑞香を知らしめたいのなら、大声で話したくなるのも当然かもしれない。しかしそれでも、周りに多くの客がいる中で王家の事情を堂々と語ることには首を傾げたくなる。
「倉橋さん、それはどういうことですか」
清隆が問い掛けると、倉橋は小さく声を立てて笑った。
「やはり貴方は気になりますよね、清隆さん。詮索好きな方ですから」
「今はそれどころではなかろう。そなた、伯母上――四辻姫様に何を言った?」
険しい目をシャシャテンに向けられながら、倉橋は淡々と答える。
「私の知人が宮中で働いていましてね、そこで四辻姫が賢順とやり取りをしていると分かったんですよ」
僧坊の一室にあった封を、清隆は思い返す。一方でシャシャテンは目を丸くしていた。それも気にせず、倉橋は話を続ける。理由を直接四辻姫に尋ね、もし言わなければ彼女の計画を瑞香国民にばらすと脅したら殺されかけたので逃げだした。あれから二ヵ月ほど経った今も油断できず、大事な原稿を北に託したのもそれが原因だ。
「四辻姫は恐ろしい人です。貴方は知らないでしょうが――」
「伯母上は賢順に用心しておるのじゃ。懇意に文を交わすはずがない」
あっても布教を止めろなどといった、牽制を伝えていたのだろう。強く言い切ったシャシャテンに、倉橋は息をついて飲み物を口にした。
「あの人は賢順と親しくする振りをしながら、梧桐宗を滅ぼそうとしているのです。例えば八月にあった諸田寺での儀礼で、四辻姫は部下に火を付けさせました。そしてあの場に集った人々を、尽く処刑したのです」
清隆も、夏に寺へ行った面々も揃って息を呑んだ。山住が不審に思っていた失火の原因は、人の手によるものだったのか。それも四辻姫が命じて。だがなぜ倉橋が放火犯の正体まで知っているのか、すぐ清隆には疑問が湧いた。
そしてシャシャテンは、顔を引きつらせたかと思えば急に立ち上がった。テーブルに両手を突いて身を乗り出し、大声を張り上げる。
「嘘じゃ! 斯様なこと、誰ぞやの流布した悪名に決まっておろう!」
騒がしかった店内が一瞬だけ静かになり、清隆は周囲を見回した。客たちの視線は、やはりこちらに集中している。何やらこそこそと話している人もおり、急に清隆の胸は熱くなる。出来ればここからすぐ立ち去りたかったが、誘ってきた者がまだいる以上はそれも許されなかった。
清隆は同行者たちの顔をそれぞれ見、彼らが何も言わないつもりだろうと読み取った。諸田寺で事件があった後に山住から届いた連絡を、清隆はシャシャテンに黙りつつ信たちへ伝えていた。そして自分を含め一時捕らえられた件については、あの口止めがある。それは清隆たち自身のためでも、また伯母を純粋に良い人と信じるシャシャテンのためでもあるだろう。しかしはっきりと何も言えないことが、清隆には心苦しかった。
「シャシャテン、いったん座れ。それで倉橋さん、なぜ菅宗三の原稿を北道雄に託したんですか」
「昔から瑞香を知る人として、信頼していたんですけどね……」
シャシャテンが椅子に腰掛ける間、倉橋は零す。瑞香では公に知られていない王家の事実も書かれた原稿があると知れば、四辻姫は処分しかねない。亡父の遺産ともいえるそれを北には守ってもらいたかったが、失敗に終わってしまった。
「あの人は不注意でした。あれには、父が調べた不老不死になる方法も書かれていたのに……」
茶を飲み進めていた美央が、急に姿勢を伸ばした。シャシャテンも食い付くように、再び立ち上がりかけて周りを見、腰を下ろす。瑞香人が原稿を持ち去ったなら、梧桐宗に渡る可能性もなくはない。
「あやつらに知られてしまってはまずい。よし、ここは私が肝胆を砕いて、その原稿とやらを奪い返すとしよう!」
片手の拳を握り、シャシャテンは口角を上げている。突然の決断に、清隆たちは呆然とする。諫めるべきと思う一方、清隆は彼女に協力したいとも心に浮かび上がってきた。菅宗三なる男は、瑞香について一体何を遺したのか。王家が云々とも書いたのも本当なのか。とにかく詳しい内容が気になって仕方がない。
対して倉橋は、しばらく黙ってカップに口を付けてから顔を上げた。
「無鉄砲ですね、貴方は。清隆さんたちの手も借りるつもりでしょうが、その方たちに何かあったらどう責任を取ると言うのです?」
シャシャテンは目を瞬かせ、清隆や美央に請い願うような視線を向けた。その意味を何となく察し、清隆は頷く。答えに安堵したのか、シャシャテンは強気な声で言い放った。
「清隆たちを案ずることはない。何かあれば私が守る故な。ひとまずは家に戻り次第、伯母上に文を書くとしよう」
「ここでも四辻姫、ですか。貴方は伯母に頼り過ぎです。彼女に心酔していれば、いずれ裏切られますよ。……いえ、とっくに裏切られていますか」
倉橋の忠告を、清隆は疑い切れなかった。去年の秋、伊勢が似たような話をしていた。やはりあの言葉は本当なのか。そして当時と同じようにシャシャテンは反論する。伯母が自分を手ひどく扱うはずがないと。
「母代わりに育ててくれただけで、なぜそこまで四辻姫に入れ込むのでしょう? 本当に王家のことは、よく分かりません」
カップの中身を一気に飲み干し、倉橋は席を立った。そこで思い出したように清隆を見、吹奏楽をやっているか尋ねてきた。急な質問に戸惑うも、清隆は肯定する。
「もしかして、夏のコンクールにも来ていましたか。桜台高校っていう所で――」
「はい、見ていました。それで会った気がしたんですね。これもきっと運命でしょう。またの機会があった時のために、連絡先でも教えておきましょうか」
清隆が遠慮する暇もなく、倉橋は素早くスマートフォンを操作し、連絡先を伝えてきた。そしてシャシャテンを除く同行者にも同じようにする。思いがけぬ収穫に信と八重崎が喜ぶのと違い、美央は興味なさげに端末の画面を見るだけだった。そしてシャシャテンは、軽く頬を膨らませてそっぽを向いている。そんな彼女へ一度振り返り、意地が悪そうに微笑んだ後、倉橋は店の出入り口へ姿を消していった。
「何じゃ、あやつは! 私が疎ましいことがあからさまではないか! 私も奴なんぞ気に入らぬわ!」
声を荒げるシャシャテンに落ち着くよう言い聞かせつつ、清隆は彼女の盲目さを思った。伯母が自分に不都合なことを考えるはずがないと頑なに信じ続けているのは、やはりどうなのか。もし伊勢や倉橋の話が正しかったら、シャシャテンは心の整理をつけられるのか。しかし、そもそも二人の四辻姫評の根拠や具体的な女王の思惑も、まだ清隆は知らない。それを探るには、奪われた原稿を見るのが早いかもしれない。
シャシャテンが仏頂面で飲み物を口にし、清隆たちへ視線を順番に移していく。そして八重崎の方を見た瞬間、音を立ててカップを置いた。
「そうじゃ、八重崎殿には言っておらぬであろう! 私は――」
「ああ、ごめん。気にしなくていいよ。前に瑞香へ行った時に聞いちゃったんだよね」
詳しい経緯は明かさず、八重崎はシャシャテンの正体を知っていたと端的に伝える。それに安心したのか、シャシャテンは椅子の背もたれに寄り掛かった。遠くに向けられたその目は、どこか疲れているようであった。
次の話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
